本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第7話です。
前回の記事では、会社が従業員全員で一斉に有給休暇を取得する日を決める「計画的付与制度」について解説しました。
会社が主導するこの制度は、年休の取得率向上に役立つ便利な仕組みです。
前回の記事は👉年次有給休暇の計画的付与で損しないために|労働者が押さえる注意点【やさしく学ぶ年休シリーズ 第6回】
しかし、年次有給休暇は、本来は労働者自身が自由に取得日を決められるのが大原則です。
この「労働者の権利」こそが年休の本質であり、好きな時にリフレッシュできる最大のメリットと言えるでしょう。
もちろん、会社側も事業をスムーズに運営していく必要があります。
そのため、あなたが「この日に休みたいです」と申請した時、会社が「その日は困る」と主張するケースも少なからずあります。
では、会社はその申請を自由に拒否できるのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
会社が年休の申請を拒否したり、取得日を変更させたりする権利は、法律で厳しく制限されています。
それが今回解説する「時季変更権」です。
時季変更権とは?会社が年次有給休暇の申請日を変更できる条件と対応策
「この日に年休を取りたい」と申請した時、会社がやむを得ずその日を変更してほしいとお願いする権利。それが「時季変更権」です。
この権利は、労働基準法第39条第5項に以下のように定められています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
この条文からわかる重要なポイントは3つです。
- 時季変更権は法律(労働基準法)で認められた会社の権利
- 会社は勝手に年休の取得日を拒否しているのではなく、法律に基づいた手続きとして「時季変更権」を行使します。
- 「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使できる
- これが時季変更権が認められる唯一の条件です。
- 「なんとなく人が足りないから。」「気分が乗らないから。」といったあいまいな理由では認められません。
- この「事業の正常な運営を妨げる場合」が具体的にどのようなケースを指すのかは、後ほど詳しく解説します。
- あくまで「申請日の変更」を求める権利であり、「年休の取得自体を拒否する」権利ではない
- これが最も大切なポイントです。
- 会社が時季変更権を行使できるのは、あくまで「その日」をずらしてほしいとお願いすることまで。
- 最終的に年休を取得させないことは、法律上許されていません。
時季変更権は、会社が労働者の年休申請日を変更できる「限定的な権利」なのです。
この大前提を理解しておくことで、会社から時季変更を求められた際に、落ち着いて対応できるようになるでしょう。
時季変更権で「事業の正常な運営を妨げる場合」とは?年休取得に影響する具体例
先ほど「時季変更権」は「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使できると解説しました。
しかし、この言葉の解釈は非常に難しく、会社が都合よく「うちは事業の運営が妨げられるからダメだ」と主張するケースも少なくありません。
いったいどのような場合に、会社の主張(事業の正常な運営を妨げる、という主張)が正当なものとして認められるのでしょうか。
具体例を交えて見ていきましょう。
時季変更権が認められやすいケース|年休取得に影響する具体例と注意点
以下の例は、事業の運営に支障が出る可能性が高いため、時季変更権の行使が正当と判断されやすいケースです。
- 繁忙期に、同じ部署の多くの従業員が同時に年休を申請した場合
- 年末年始の書き入れ時や決算期など、特定の時期に業務量が激増する業種や部署では、一度に多くの人が休むと業務が滞ってしまう可能性があります。
- その日にしかできない重要な業務があり、代わりの人がいない場合
- たとえば、その人にしかできない特別な技術や知識を要する業務がある日や、重要な取引先との商談や打ち合わせがその日にしかない場合などです。
- ただし、会社は代替要員を確保する努力をする義務があります。
- 過去に取得日を話し合って合意したのに、直前になって変更を申し出た場合
- 一度合意した取得日を直前に変更すると、会社は人員配置などをやり直す必要が生じ、事業運営に支障をきたす可能性があると判断されることがあります。
時季変更権の濫用で無効になるケース|年休取得を不当に制限されたときの注意点
一方、以下のような理由で時季変更を求められた場合は、時季変更権の濫用とみなされ、会社側の主張が無効となる可能性が非常に高いです。
- 「ただ単に人が足りないから。」という漠然とした理由
- 慢性的な人員不足は会社の経営課題であり、労働者の年休取得を制限する正当な理由にはなりません。
- 会社は常に人員不足を解消するための努力をする義務があります。
- 会社が年休の取得自体に消極的な態度をとっている
- 「年休はできるだけ取るな。」「休んだら評価が下がる。」といった態度を会社がとっている場合、時季変更権の正当な行使とは言えず、単なる年休取得の妨害とみなされます。
- 年休の取得を理由に、嫌がらせや不利益な扱いをする
- 「休むなら給料を下げる。」「休んだら閑職に回す。」といった、不利益な扱いは絶対に許されません。これは労働基準法違反にあたります。
つまり、時季変更権は、会社が「業務が回らなくなるほどの深刻な事態」を客観的に証明できて初めて認められる、非常に限定的な権利なのです。単なる「不都合」を理由に年休を拒否することはできません。
時季変更権が行使されたときの対応方法|年休取得で困ったときの労働者向けガイド
「その日は休めません。」「休まないでくれ。」と会社に言われてしまうと、戸惑ってしまうかもしれません。
しかし、時季変更権の定義と条件を理解していれば、冷静に対応することができます。
ここでは、会社から時季変更権を行使された場合の労働者側の対応策を2つのケースに分けて解説します。
ケース1|会社が提示した別日で問題ない場合|スムーズに年休を取得する方法
もし会社が提示した代替日や、会社と話し合って決めた別の日程で問題がなければ、スムーズに年休を取得するのが一番です。
お互いが納得できる形で取得日を調整することで、良好な関係を保ちながら年休を消化できます。
ケース2|会社の提示日で困る場合|納得できないときの年休取得の対応策
たとえば、子どもの学校行事や病院の予約など、どうしてもその日に休む必要があり、日程をずらせない場合もあります。
そのような時は、会社に一方的に従う必要はありません。以下の対応策を試してみましょう。
- なぜその日に休む必要があるのか、具体的な理由を説明する
- 「どうしてもその日でなければならない理由」を会社に明確に伝えましょう。
- これにより、会社側も代替要員の手配や業務の調整をより真剣に検討してくれる可能性が高まります。
- ただし、必ずしも理由を伝える義務はありませんので、伝えられる範囲で構いません。
- 会社の代替案に対し、こちらも別の代替案を提示するなど、譲歩する姿勢を見せる
- 会社が「この日は人が足りない。」と言うなら、「では、この業務は事前に終わらせておきます。」「その日だけは別の部署のAさんに手伝ってもらえないでしょうか。」など、こちらからも解決策を提案してみましょう。
- お互いに譲り合う姿勢を見せることで、会社もあなたの希望を尊重してくれる可能性が高まります。
- 一人で抱え込まず、上司や会社の担当部署(人事など)に相談する
- 交渉がうまくいかない場合は、一人で悩まず、上司や人事担当者に相談するのも一つの手です。
- 会社の相談窓口や社内ユニオン(労働組合)に助けを求めることも有効です。
大切なのは、「年休は労働者の権利」であることを忘れず、諦めずに交渉を続けることです。
まとめ|時季変更権は万能ではない|年休取得時の注意点と労働者の権利
ここまで「時季変更権」について解説してきました。
年次有給休暇は、本来、労働者が自由に取得日を決められる貴重な権利です。
会社が時季変更権を行使できるのは、あくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」という限られた状況においてのみです。
「単に人が足りないから。」「なんとなく休まれると困るから。」といった理由で、あなたの年休申請を拒否することはできません。
時季変更権は、会社が自由に使える便利な権利ではないのです。
円満に年休を取得する方法|労働者ができる配慮と具体的ステップ
とはいえ、会社と対立するのは避けたいものです。
会社との良好な関係を保ちながら円滑に年休を取得するためには、労働者側からの配慮も大切です。
一社会人として、会社の状況にも気を配ることで、お互いにとってより良い結果を招くことができます。
なるべく早めに年休を申請する
- 休みたい日が決まったら、できるだけ早く会社に伝えましょう。
- これにより、会社は業務の調整や代替要員の手配をするための十分な時間を確保できます。
周囲の状況を把握しておく
- 同じ部署の他の人がすでに年休を申請していないか、繁忙期ではないかなど、周囲の状況をある程度把握した上で申請することも、トラブルを避けるための有効な手段です。
業務の引き継ぎをきちんと行う
- 休む前に、担当している業務について引き継ぎを行い、同僚や上司が困らないように最大限の努力をしましょう。
- これにより、会社も安心して年休を許可しやすくなります。
もし、これらの配慮をしてもなお、会社に不当な拒否をされたと感じたら、一人で悩まずに、最寄りの労働基準監督署や、弁護士、社会保険労務士といった専門家に相談することも一つの選択肢として頭に入れておきましょう。
年休はあなたの心と体を守るための大切な権利です。その権利を正しく理解し、賢く活用していくことが、より良い働き方につながります。
次回予告|退職時の有給休暇と円満退社のポイント
ここまで、年次有給休暇の取得をめぐる会社と労働者の権利について解説してきました。
ところで、もし会社を退職することになったら、残っている年休はどうなるのでしょうか?
「退職日までに全部消化したい」と考えるのが一般的ですが、最終出勤日の翌日からすぐに次の会社へ出勤する場合など、年休を消化する期間がないケースも少なくありません。
そんな時、残った年休を会社に買い取ってもらうことはできるのでしょうか?
次回は、多くの人が直面する「退職時の年休」というテーマに焦点を当てていきます。
退職前に年休を消化する際の注意点から、買い取りが可能なケース・不可能なケースまで、そのルールを詳しく解説します。
次回の記事は👉退職する時に有給休暇は全部使える?法律と円満退社のポイント【やさしく学ぶ年休シリーズ 第8回】
どうぞお楽しみに!

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
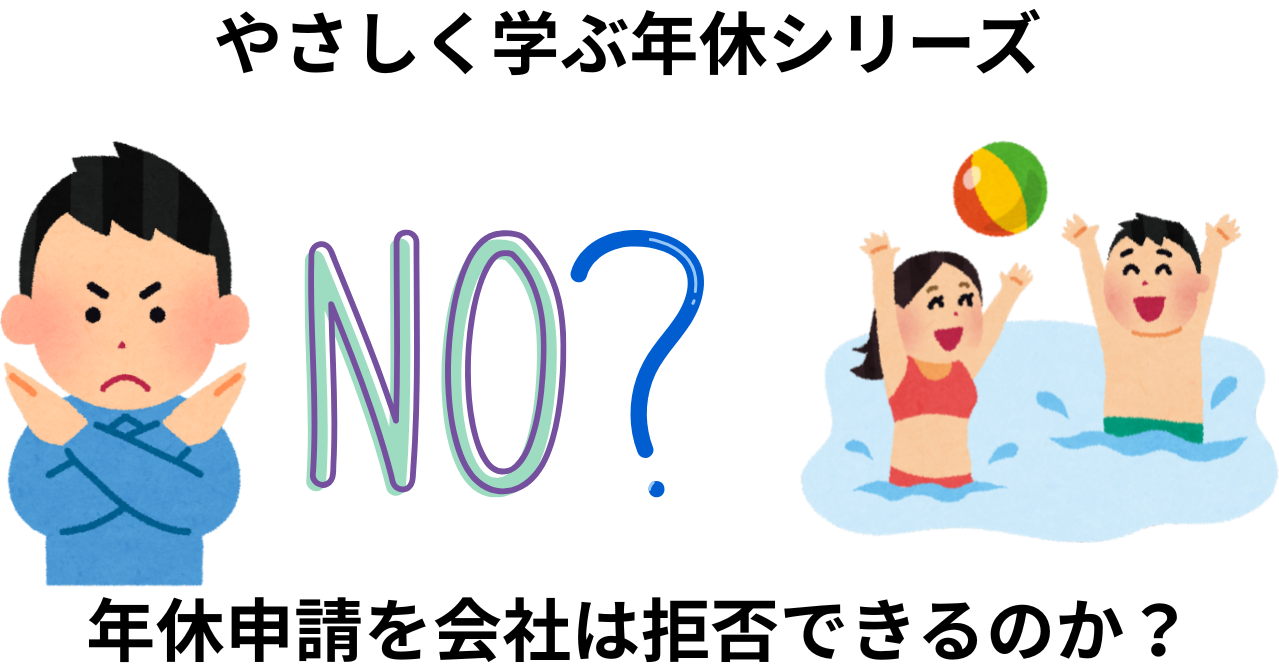
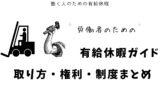
コメント