本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第4話です。
前回の記事では、「正社員だけじゃない!パートやアルバイトにも年休がある」というテーマで、非正規雇用の皆さんも含め、年次有給休暇(年休)が「いつ」「何日」もらえるのか、その付与要件や日数の計算方法について詳しく解説しました。
前回の記事は👉パート・アルバイト・非正規社員向け|有給休暇の付与条件と日数
年休が付与されると、それはもうあなたの「権利」です。
でも、権利があるだけでは、いざという時に使えなかったり、会社との間でトラブルになったりすることもありますよね。
せっかくの年休をスムーズに、そして気持ちよく取得するためには、その申請ルールや取る際の注意点をしっかり知っておくことがとても大切なんです。
今回は、付与された年休をどうやって使うのか、具体的な申請方法や、会社に伝える際のポイントについて見ていきましょう。
年休申請の基本的なルールと手順年休の取り方・申請手順をわかりやすく解説【正社員・非正規共通】
年次有給休暇は、法律で認められたあなたの権利です。しかし無条件でいつでも取れるわけではありません。
会社には、事業の正常な運営に支障が出ないよう、「いつ」「誰が」「どう」申請するのかという基本的なルールがあります。
年休の申請方法|誰に、いつまでに、どう連絡する?
年休を申請する際は、まずあなたの会社で最も相談しやすい窓口や情報源を確認するのが一番です。
多くの場合、以下のいずれかの方法で情報を得られます
- 総務・人事担当者に聞く
- 最も確実で、気軽に相談しやすい方法です。
- 担当者が具体的な申請方法や期限、必要な書類などを教えてくれます。プライバシーが守られやすい点でも安心です。
- 先輩社員に相談する
- 普段から年休を取得している信頼できる先輩社員に聞けば、会社のリアルな運用状況や「暗黙のルール」なども把握できます。
- 会社の就業規則を確認する
- 大企業など、就業規則が整備され、従業員がアクセスしやすい環境であれば、そこに具体的な申請手順が明記されていることが多いです。
- もし確認できるようであれば、一度目を通しておくと良いでしょう。
これらの方法で確認した上で、一般的なポイントは以下の通りです
- 誰に伝えるか?
- 通常は直属の上司や人事担当者に申請します。
- 会社の組織体制によって異なるので、確認しておきましょう。
- いつまでに伝えるか?
- 会社が「〇日前までに申請すること」と期限を定めている場合があります。
- 例えば「原則として取得希望日の3日前まで」といったルールです。
- これは、会社が業務の調整や代替要員の確保をするために必要な時間を与えるためです。
- 期限を過ぎての申請は、会社が時季変更権を行使する要因となる可能性があるので注意しましょう。
- どう伝えるか?
- 申請方法は会社によって様々です。
- 口頭
- 比較的短い期間の年休や、日ごろからコミュニケーションが密な職場であれば口頭で済ませるケースもありますが、後々のトラブルを避けるためには記録を残す方が安全です。
- 書面(申請書)
- 多くの企業では、専用の「年次有給休暇申請書」があります。
- 必要事項を記入し、上長に提出します。
- メールや社内システム
- 最近では、メールやグループウェア、勤怠管理システムを通じて申請する企業も増えています。
- 証拠が残りやすいので、おすすめです。
- 口頭
- 申請方法は会社によって様々です。
有給休暇の時季指定権とは?急な病欠でも使える?
年次有給休暇の取得において、労働者が持っている非常に重要な権利が「時季指定権(じきしていけん)」です。
これは、「いつ有給休暇を取りたいか」を労働者自身が指定できる権利のことです。
あなたが「この日に有給を取りたい」と会社に伝えた場合、原則として会社はそれを拒否できません。
労働基準法によってこの権利は保障されてます。会社は基本的に、労働者が指定した時季に有給休暇を与えなければならないとされています。
しかし、ここで多くの人が疑問に思うのが、「急な病気で休んだ場合、後からでも有給にできるの?」という点ではないでしょうか。
つまり「事後の時季指定」はOKなのか?という点ではないでしょうか。
さらに言えば「今まさに熱が出たので休むと連絡し、同時に有給にしてほしいと伝える。」というケースも、厳密にはこの「事後申請」の範疇に含まれると解釈できます。
原則は「事後申請NG」、その法的根拠は?
法律上の「時季指定権」は、あくまで「事前に」いつ休むかを指定することで成立します。
労働基準法第39条第5項は、会社が「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、労働者の請求した時季を「他の時季に変更」できる「時季変更権」を認めています。
しかし、すでに休んでしまった過去の時季に対しては、この「他の時季に変更する」という行為は物理的に不可能です。 会社は業務調整を行う機会を失ってしまいます。
このため、裁判例や行政通達においても、労働者の時季指定権は「事前に行われることを要する」という解釈が一般的です。
事後的な年休の指定は、原則として認められないという法的立場が明確に示されています。
多くの企業で「急な病欠」を有給として認める理由
しかし、現実には多くの企業で、急な病欠による欠勤を、後から有給休暇として処理することを認めているケースが非常に多いです。これはなぜでしょうか?
企業側にも、実は大きなメリットがあるからです。
- 年5日取得義務の達成を助ける
- 会社は、年10日以上年休が付与される従業員に、年間5日間の年休を確実に取得させる義務があります。
- 急な病欠を有給として処理することは、この義務の達成に貢献します。
- 労使関係の円滑化と従業員満足度向上
- 従業員が安心して休める環境は、会社への信頼感を高め、モチベーションや定着率の向上に繋がります。
- 無理をして体調の悪い従業員が出社し、周囲に影響を及ぼす事態も避けられます。
- 賃金控除の回避
- 従業員にとって、病欠による賃金控除がないのは大きな安心です。経済的な不安なく療養に専念できます。
このように、会社が柔軟な対応をすることで、企業側は法的義務の達成を助けらます。そして従業員側は安心して休めるという、まさに「WIN-WIN」の関係が築けるのです。
急な病欠時の現実的な対応策
万が一、急な体調不良で休むことになった場合は、まずは会社の連絡ルールに従って、できるだけ早く「今日は体調不良のため休みます」と連絡を入れるのが最優先です。
その際、「この日の欠勤を有給休暇として扱っていただけますでしょうか?」と、相談ベースで伝えると良いでしょう。
会社の就業規則に急病時の年休扱いの規定がないか、総務・人事担当者に確認することも大切です。
年休はあなたの大切な権利です。しかし、それを円滑に行使するためには、会社のルールを理解し、適切なコミュニケーションをとることが非常に重要です。
有給休暇の取得で避けるべきNG事例とトラブル回避のポイント
年次有給休暇は労働者の権利ですが、その行使の仕方によっては、会社との間で不必要なトラブルを招いたり、職場の人間関係に悪影響を与えたりする可能性もあります。
ここでは、年休取得時に避けるべき「NG事例」と、円滑な取得のための回避術をご紹介します。
NG事例1|無断欠勤と事後の有給申請はトラブルの元
「会社に何も連絡せず休んだ後で、有給にしておけばいいだろう。」――これは、正真正銘の「無断欠勤」であります。就業規則によっては懲戒処分の対象ともなる非常に重い行為です。
NG事例2|繁忙期に強引に有給申請するとトラブルに
「会社が忙しいのは知っているけれど、どうしてもこの日に休みたいから無理やり申請する。」――このような強引な申請は、会社が「時季変更権」を行使するきっかけになりやすいNG事例です。
- 時季変更権の行使につながりやすいケース
- 会社は、労働者の申請した時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、別の日に変更するよう求める「時季変更権」を行使できます。
- 例えば、以下のような状況が該当します。
- その日にしかできない重要な業務がある
- 他に休暇取得者が集中し、人員が極端に不足する
- 代替要員の確保が著しく困難である 繁忙期に複数の従業員が同時に休むと、会社の業務がストップしてしまう可能性があります。
- 会社への配慮も円滑な取得には重要
- 年休は権利ですが、職場はチームで動いています。
- 繁忙期にどうしても休みたい場合は、早めに相談し、業務の引き継ぎを完璧にする、代替案を提示するなど、会社への配慮を示すことで、時季変更権の行使を避け、円滑な取得につながる可能性が高まります。
NG事例3|年休理由の虚偽申告で起こるトラブルとリスク
「本当は遊びに行くけれど、体調不良と偽って年休を申請する。」――会社は年休の理由を原則として問えないものですが、虚偽の申告は避けるべきです。
- 会社は年休の理由を問えないのが原則
- 労働基準法上、年休の取得理由は問われません。
- 労働者は、私的な理由で自由に年休を取得できます。
- 虚偽申告のリスク
- しかし、虚偽の理由を申告し、それが発覚した場合、会社との信頼関係が損なわれるだけでなく、就業規則違反として懲戒処分の対象となる可能性もゼロではありません。
- 特に、業務に大きな支障が出た場合などは、より厳しく問われることもあります。正直に申請し、信頼関係を維持することが大切です。
年休取得のトラブル回避|円滑に取得するためのコミュニケーション術
これらのNG事例を避け、年休をスムーズに取得するためには、会社との良好なコミュニケーションが何よりも重要です。
- 早めの相談と調整の重要性
- 年休を取りたい日が決まったら、できるだけ早く上司や関係者に相談しましょう。
- 特に、連続して休む場合や繁忙期に取得したい場合は、早めに伝えることで、会社も業務の調整や人員配置の計画を立てやすくなります。
- 業務の引き継ぎなど、周囲への配慮
- 自分が休むことで、誰かに業務のしわ寄せが行く可能性があります。
- 休む前に、担当業務の進捗状況を共有し、必要な引き継ぎを丁寧に行うなど、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。
- これにより、あなたが安心して休めるだけでなく、職場の理解と協力も得られやすくなります。
年次有給休暇を上手に使う!取得の便利なコツと活用法
年次有給休暇は、まとまった休みを取るためだけでなく、日々のちょっとした用事や、会社全体での取得促進にも役立つ便利な制度があります。
これらを上手に活用して、年休を賢く使いこなしましょう。
半日・時間単位で取得!年次有給休暇の賢い活用法
「半日だけ病院に行きたい。」「子どもの迎えで少し早く上がりたい。」といった時に、一日まるまる年休を使うのはもったいないと感じる人もいるでしょう。
そんな時に便利なのが、半日単位年休や時間単位年休です。
利用できるかを確認しよう
- これらの制度は、法律で義務付けられているわけではありません。
- 半日単位年休は、会社が就業規則にその旨を規定している場合に限り利用できます。
- 時間単位年休は、会社と労働者の間で労使協定を締結している場合に限り利用できます。
- 多くの場合、就業規則や労使協定の有無をすぐに確認するのは難しいでしょう。
- まずは、総務・人事担当者や、信頼できる先輩社員に、あなたの会社でこれらの制度が利用できるか、そしてその利用方法について尋ねてみましょう。
関連記事(企業担当者向け)

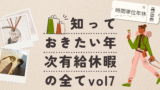
ちょっとした用事や通院に便利
- 例えば、午前中だけ、あるいは午後だけ年休を取って私用を済ませたり、病院の診察を受けたりすることができます。
- また、通勤ラッシュを避けて少し遅く出社したり、早く退社したりする際にも役立ちます。これにより、日々の生活と仕事のバランスが取りやすくなります。
計画的付与制度とは?|会社が決めた日に年休を取る仕組み
「いつ年休を取っていいか分からない。」「周りに遠慮してなかなか取得できない。」と感じる人もいるかもしれません。
そんな時に有効なのが、年次有給休暇の計画的付与制度です。
- 会社が年休取得日をあらかじめ指定
- この制度は、労使協定を結ぶことで、会社が従業員の年休取得日をあらかじめ指定できる仕組みです。
- 例えば、GWやお盆休み、年末年始などに合わせて全社一斉に年休を付与したり、部署やグループごとに交代で取得日を決めたりするケースがあります。
- 強制ではない?
- 従業員にとっては「会社に勝手に年休を決められる」と感じるかもしれませんが、この制度は労働者の合意(労使協定)が前提であり、企業が年休取得を促進するための手段です。
- 指定されるのは年休のうち5日を超える部分に限られるため、最低5日は従業員が自由に取得できる年休が残ります。
- 連休取得の促進
- 計画的付与制度は、従業員がまとまった休みを取りやすくなるメリットがあります。
- これにより、リフレッシュ効果が高まり、生産性の向上にも繋がると考えられています。
関連記事
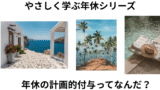
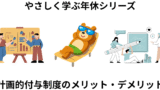
年5日の有給取得義務とは?企業の対応と従業員への影響
近年、働き方改革の一環として、年次有給休暇の取得促進がさらに進められています
。その最大のポイントが、企業による「年5日の年休取得義務化」です。
- 企業に課せられた義務
- 2019年4月1日以降、企業は、年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者に対し、毎年5日については、時季を指定して取得させなければなりません。
- もし、この義務を果たさない場合、企業には罰則が科される可能性があります。
関連記事(企業担当者向け)


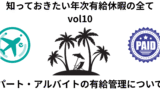
- 取得を後押しする背景
- この義務化は、労働者が「年休を取りづらい」と感じる職場の空気を変える大きな力となっています。
- 企業が積極的に取得を促す必要が生じたことで、従業員は以前よりも年休を申請しやすくなっています。
- 企業にとっても、従業員の健康維持やリフレッシュ、そしてコンプライアンス遵守のために、年休取得は「当たり前」の取り組みとなっています。
これらの制度や企業の義務化の流れを理解し活用することで、あなたはより一層、自身の年休を有効に使いこなせるようになるでしょう。
年次有給休暇のまとめ|権利と責任を理解してスムーズに取得する方法
ここまで、年次有給休暇の基本的な申請方法から、急な病欠時の対応、さらには半日・時間単位年休や5日取得義務化といった便利な制度まで、多角的に解説してきました。
年休は、あなたの心身をリフレッシュし、より豊かな生活を送るための大切な「権利」です。
しかし、その権利をただ主張するだけでは、会社との間で不必要な摩擦を生んだり、職場の同僚に負担をかけたりする可能性もあります。
権利を適切に行使するためには、会社のルールを理解し、周囲と協力する「責任」も伴います。
早めの相談、業務の丁寧な引き継ぎ、そしてお互いの状況への配慮。これらが、スムーズな年休取得の鍵となります。
会社と労働者が互いを理解し、協力し合うことで、年休を有効活用できる、より働きやすい職場環境は実現します。
このバランスを大切にしながら、あなたの年休を最大限に活用してくださいね。
次回予告|年休の計画的付与って何?会社が指定する日の仕組みを解説
次回のシリーズ第5回では、「計画的付与って何?—会社が決めた日に年休を取る仕組み」について、さらに深く掘り下げていきます。
次回の記事は👉計画的付与って何?—会社が決めた日に年休を取る仕組み【やさしく学ぶ年休シリーズ 第5回】
会社が一方的に取得日を決めるように見えるこの制度は、実は労働者にとってもメリットがあるんですよ。
その仕組みや、あなたの年休にどう影響するのかを詳しく解説しますので、どうぞお楽しみに!

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。

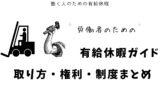
コメント