昼休みです。11時50分から12時50分までです。
嗚呼・・・昼飯のこと全く考えてなかった。
さてどうしたものか。当然学食は閉まっている、理由はわからないが学内のコンビニも閉まっている。
仕方がないので、食べさせてもらえるような店を探します。他の受験生は当然昼食は用意してます。当たり前か。
何とか昼食をとり、席に戻ります。
着席時間12時50分、ギリギリです。
落ち着いて休む暇もなく、心身ともにバタバタの状態で午後の本試験に突入することになってしまいました。
令和3年社労士試験 本当の戦い──午後の択一式試験
午後の択一式試験は13時20分から始まります。ここからが社労士試験の本丸ともいえる時間帯です。7科目・全70問、1問1点。3時間30分で解くには、集中力とスタミナ、そして何よりも正確な知識が求められます。
最初の科目、労働基準法の問題を解き始めてしばらくして、何とも言えない戸惑いが頭をよぎりました。
「ムムム、これは・・・ちょっとどうなんだ?」労働基準法の問題の途中でそう思い始めました。
「これは、ちょっと・・・あかんかも・・・」労災法、雇用保険法、一般常識と続けるほどに、その思いは強くなっていきます。
午前中の選択式で感じたちょっとした手応えは一体何だったのでしょう。
そんなものは一気に消え去り、「これは無理じゃないのか?」という現実が静かに、しかし確実に迫ってきます。
社会保険労務士試験の勉強の基本はやはり択一式対策なのです。
はっきり言ってこれを万全にやっておけば、選択式対策が不十分でも、足切りにさえ合わなければ、合格ラインに乗ってしまう事ができることもあるかと思います。
しかし、逆の言い方をすれば、択一対策が不十分だと、どこをどうあがいても合格ラインに達することは無いのではないでしょうか。
「択一式対策が基本知識を蓄積させていく」これは、間違いのないことだと思います。
その知識だけで選択式は乗り切れる時もあろうかと思います。
社労士試験で明らかになった知識不足
ただ、結論から言いますと当時の私にはその「基本知識」が全く足りていなかったのでした。
たとえば、以下のような問題に直面します。
労働基準法の問題肢
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省で定めるところにより所轄労働基準監督署に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとならない。
これを×と判断してしまう。
36協定の問題です。
この協定が届け出がなされる 「前に」行われた残業(法定時間外労働)については、たとえ労使間で協定を結んでいたとしても、遡って有効とはされません。
つまり、36協定の届け出日以前の残業は違法となります。これは基本問題でしょう。
もう一丁。
労働基準法の問題肢
- 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
これを〇と判断してしまう。出産当日は産後に含まれます。これも基本問題です。
五肢択一形式への不慣れ
「知識の絶対量が足りていない。さらにもう一つ、五肢択一という問題形式に対応できてない。」
本番で初めて、本格的な五肢択一問題と真剣に向き合ったという始末。これでは、迷ったときに「どれを切るか」という判断がつきません。
5つの肢のうち、明らかに誤りと思えるものは1つか2つ。残り3つのうち、「あれ、これ正しかったっけ……」と迷って時間が過ぎていきます。
確信を持てる肢は少ない。
知識が曖昧なために、どの選択肢も正しく見えてしまい、結果として無駄に時間をかけてしまいます。
結局、「消去法」で答えを出さなければならないのに、その消去の根拠があいまいなまま、時間ばかりが過ぎていきます。
「迷ったときにどうするか」なんてことは事前に一切考えてません。
社労士試験勉強200時間の現実と、まぐれでは受からないという事実
社労士試験は、単なるマークシート試験ではありませんでした。
特に択一式は全70問・5肢の選択肢、計350の選択肢の正誤を、限られた時間内に判断しなければならない試験です。
運に左右される場面もゼロではないでしょうが、土台となる知識と形式への対応力がなければ、運が味方する余地すら生まれないのだと痛感しました。
合否のボーダー上にいる受験生にとっては、ちょっとした判断や運が結果を左右することもあるでしょう。
しかし、明らかに実力不足のまま幸運だけで合格できるようなことは100%あり得ないですね。
私の勉強時間はおよそ200時間くらいだったと思います。
もちろん、少ないのは自覚していましたが、試験を甘く見ていたつもりもありません。
しかし、今となってはそう思わざるを得ませんし、午後の試験を通して、自分の基本知識量がいかに「不足」していたかを痛感しました。
選択式では、運や偶然が多少味方してくれることもあります。
実際、私も午前中は多少の手ごたえがありました。
しかし択一式は違います。知識の蓄積がそのまま得点に直結します。基本ができていなければ、まず合格ラインには届きません。
知識不足が露呈した択一式、迫りくる絶望
だめだ。合格できるわけがない。
択一式の試験時間は、まるで砂時計の砂が落ちるように、容赦なく過ぎていきました。
焦燥感と自信喪失の波に飲まれながら、私はただただ鉛のように重い鉛筆を動かすことしかできませんでした。
試験終了の合図の時、私の心には達成感や安堵感といったものは一切なく、ただただ深い疲労感と、打ちのめされたような感覚だけが残りました。
社労士試験が終わって感じた、絶対的な敗北と学び
終わった…ダメだった…
自己採点もクソもない。不合格を確信していました。
社労士試験は、知識の量と質、そして問題形式への慣れといった、複合的な力が試される試験です。
短期間で一発合格する人がいるかもしれませんが、それは例外と思っておいたほうがよいでしょう。
今回の受験で、私は一つだけ確かなことを学びました。
「社労士試験は、まぐれでは絶対に受からない。積み重ねた準備だけが味方してくれる試験である」
これが、私にとって最大の収穫であり、次への課題です。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。

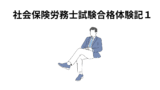

コメント