本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第2話です。第1話は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
シリーズ全体の記事はコチラからご覧ください👇
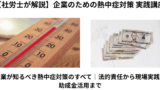
前回の記事では、2008年の労働契約法によって、企業が労働者の安全を守る「安全配慮義務」が法的に明確化された点について詳しく解説しました。
この義務には、熱中症対策も当然含まれており、企業が対策を怠れば責任を問われる基盤が作られたことをご紹介しました。
前回の記事は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
この記事で分かること
- 法改正による義務化と現場の準備状況に大きな乖離があること
- 暑さ指数の測定値を過信したり放置したりすることが招く危険性のこと
- 対策の記録がない場合に企業が負うことになる法的リスクの実態のこと
- 本社の指示と現場の実情が食い違うことで生じる機能不全の原因のこと
- 形式的な義務化を実効性のある安全管理へ変えるための改善策のこと
職場の熱中症対策法制の進化と実務課題|義務化で見える現場のギャップ
しかしながら、法的な責任の明確化だけでは、現場の熱中症リスクが完全に解消されるわけではありません。
そして、高まる熱中症の危険性を受け、2025年にはさらに具体的な熱中症対策が法的義務となるなど、法律は常に進化を続けています。
2025年6月法改正の詳しい記事は

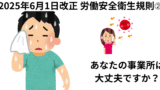
法整備が進む一方で、それを「実効性あるものにする」という大きな課題が残されているのです。
単に法律の条文を遵守するだけでなく、それが実際の職場でどのように機能し、労働者の命と健康に直結するのかが問われています。
今回は、この「実務ギャップ」に焦点を当てます。
法律が机上の空論、あるいは「絵に描いた餅」とならないために、現場で具体的にどのような混乱や盲点が生じやすいのか。
特に、熱中症リスク管理における「測定値の過信」「放置」「不記録」といった、見落とされがちな問題点を取り上げ、熱中症リスクに「実務として」どう向き合うべきかを考察していきます。
職場での熱中症対策法改正|実務上の課題と対応すべきギャップ
熱中症対策の法的義務化は、安全確保に向けた大きな一歩です。
しかし、法律が新しくなっても、それが現場で十分に機能しない「実務ギャップ」が生じることがあります。
これは、法的な要件と実際の職場の状況との間に生まれるズレです。
職場で遅れる熱中症対策|法的義務と現場準備のギャップ
まず、法律の改正が現場にもたらす変化として、企業の意識と準備の間に乖離が見られます。
1. 「罰則化されたからやる」という受動的な意識
- 熱中症対策が「法的義務」となり、違反すれば罰則が適用される可能性が出てくると、「やむを得ず対応する」という受動的な意識が生まれることがあります。
- 本来は、労働者の安全と健康を守るという積極的な目的で行われるべき対策が、罰則を回避するための義務と捉えられてしまうのです。
- これでは、真に効果的な対策にはつながりにくいでしょう。
2. 法改正内容への理解不足(具体的に何をすべきか分からない)
- 法改正によって熱中症対策が義務化されたことは知っていても、「具体的に何を、どのようにすればいいのか」が現場の担当者や責任者に十分に浸透していないケースがあります。
- 単に「対策を強化せよ」という指示だけでは、具体的な行動に移せず、形式的な対応に終わってしまうリスクをはらんでいます。
3. 予算や人員の確保が追いつかない現状
- 新たな義務に対応するためには、WBGT測定器の導入、休憩所の整備、水分・塩分補給のための物資の確保、そして対策を推進する人員の配置など、具体的なコストやマンパワーが必要になります。
- しかし、これらの予算や人員の確保が追いつかず、義務化に対応しきれない企業も少なくありません。
関連記事
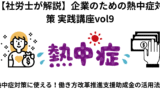
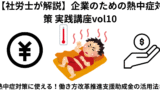
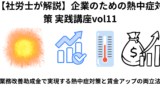

職場で想定される熱中症対策義務化の実務混乱と対応のポイント
このような意識や準備の乖離は、実際の現場で様々な混乱を引き起こす可能性があります。
1. 報告体制の未整備・周知不足
- 2025年の安全衛生規則改正で義務化される「熱中症患者の報告体制」が、現場で適切に機能しない恐れがあります。
- 誰が誰に、どのような状況で報告するのかが明確でなかったり、その体制自体が作業員に周知されていなかったりすれば、症状の早期発見や適切な対応が遅れる原因となります。
2. 症状悪化防止措置の具体的な手順が不明確
- 熱中症の症状が出た際に、「作業からの離脱」「身体の冷却」「医療機関への連絡」といった具体的な手順が、現場の管理者や作業員の間で共有されていないと、とっさの判断が遅れます。
- 誰が何を担当するのか、緊急時の連絡先はどこかなど、具体的なフローが不明確なままでは、症状が悪化するリスクが高まります。
3. 管理者・作業員への教育訓練不足
- 法改正の内容だけでなく、熱中症の危険性、初期症状、応急処置、予防策などについて、管理者も作業員も十分な教育を受けていないケースが多く見られます。
- 知識不足は、危険な状況への認識の甘さや、適切な行動の遅れに直結し、結果として労働災害の発生リスクを高めてしまうのです。
熱中症リスク管理の課題|測定値の過信や放置が招く職場の危険
熱中症対策において、WBGT(湿球黒球温度)値や気温の測定は非常に重要です。
しかし、これらの測定が現場で適切に行われ、活用されているかというと、多くの「盲点」が存在します。
制度が整っても、この盲点を見過ごしていると、いざという時に機能不全に陥りかねません。
WBGT(湿球黒球温度しっきゅうこっきゅうおんど)値は、一言でいうと「人が感じる暑さ」を数値化したものです。
ただの気温とは違い、湿度、日差し(輻射熱)、風という、熱中症に影響する3つの要素をすべて考慮して算出されます。
イメージしてください
真夏の炎天下、気温は同じ30℃でも、
- 風もなくジメジメしている日は、汗が蒸発しにくく、モワッとした暑さを強く感じます。
- カラッと晴れていて日差しが強く、風もない日は、肌にジリジリと熱を感じ、非常に暑く感じます。
このように、同じ気温でも「暑さの感じ方」は大きく違いますよね?
WBGT値は、これらの要素を複合的に計算することで、「体が実際にどれくらいの熱ストレスを受けているか」を客観的に示す指標なんです。
だから、熱中症のリスクを判断する際に、単なる気温よりもWBGT値の方がはるかに信頼性が高いとされています。
WBGT値が高ければ高いほど、熱中症になる危険性が高い、と理解しておけばOKです。
WBGT値の具体的な数値基準の目安
このWBGT値は、作業内容や個人の暑さへの慣れ(暑熱順化の有無)によって、どの値から危険かが変わります。
厚生労働省や環境省、日本スポーツ協会などが指針を出しており、大まかな目安は以下の通りです。
| WBGT値(℃) | 熱中症の危険度と推奨される行動の目安 |
|---|---|
| 31以上 | 危険 運動は原則中止。特別の場合以外は運動を中止すべき。特に子どもの場合は中止。高齢者は安静状態でも危険性が大きい。 |
| 28以上31未満 | 厳重警戒 熱中症の危険性が高い。激しい運動や持久走など、体温が上昇しやすい運動は避ける。頻繁に休憩をとり、水分・塩分を補給する。 |
| 25以上28未満 | 警戒 熱中症の危険が増す。積極的に休憩を取り、適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では30分おきくらいの休憩が目安。 |
| 21以上25未満 | 注意 熱中症による死亡事故が発生する可能性もある。熱中症の兆候に注意し、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |
| 21未満 | ほぼ安全 通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分補給は必要。市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生することがある。 |
※上記は一般的な目安であり、作業強度、個人の健康状態、暑さへの慣れなどによって、熱中症リスクは変動します。
特に、身体への負荷が大きい作業や、暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)の場合は、より低いWBGT値でも注意が必要です。
WBGT・気温測定の現状チェック|現場で見落とされがちな問題
WBGT値や気温の測定は、リスクを数値で把握する上で不可欠です。
しかし、その実施方法や結果の解釈には問題が潜んでいることが少なくありません。
WBGT値の測定値の過信(誤った理解)
- WBGT計が導入されていても、その測定値が常に現場の実情を正確に反映しているとは限りません。
- 測定機器の設置場所・方法の不適切さ
- WBGT計は、本来、作業環境を代表する地点に設置されるべきです。
- しかし、「日陰に置けば安全だろう」と安易に判断されたり、作業場所から離れた場所で測定されたりすることがあります。
- 日差しが当たる場所や、風通しの悪い場所など、実際の作業環境とは異なる条件で測られた数値は、適切なリスク評価には繋がりません。
- 一時的な測定値のみを重視し、継続的な変化を考慮しない
- 一日のうち特定の時間だけ測定し、その数値だけで判断してしまうケースもよく見られます。
- 気温や湿度は刻一刻と変化するため、継続的なモニタリングが不可欠です。
- 例えば、午後に急激に暑くなる可能性を見落とせば、対応が後手に回ってしまいます。
- WBGT値と体感温度のズレに対する認識不足
- WBGT値は温度、湿度、輻射熱、気流を総合的に評価する指標ですが、個人の体感や作業強度によって暑さの感じ方は大きく異なります。
- 数値だけを鵜呑みにし、「WBGT値が基準値内だから大丈夫」と過信すると、体調不良のサインを見逃すリスクがあります。
- 測定機器の設置場所・方法の不適切さ
WBGT値の測定結果の放置(対応の遅れ)
- せっかく測定したWBGT値や気温が、具体的な行動に結びつかない「放置」状態になることも少なくありません。
- 測定はするものの、基準値超えに対する具体的な行動計画がない
- WBGT値が基準値を超えた場合に「何を」「いつ」「誰が」行うのか、具体的な行動計画が定まっていないと、数値が高くても何も対策が講じられないことがあります。
- 「まだ大丈夫だろう」という安易な判断
- 管理者や作業員の中に「これくらいなら慣れている」「もう少し様子を見よう」といった安易な判断が働き、休憩指示や作業内容の変更が遅れることがあります。
- 特に経験則に頼りがちな現場では、この傾向が顕著です。
- 休憩指示や作業内容変更が現場の判断に委ねられ、実施されない
- 休憩や作業量の調整が現場の自主的な判断に委ねられている場合、作業の進捗を優先してしまい、適切な休憩が取られない、あるいは作業負荷が軽減されないといった事態が発生しがちです。
- 測定はするものの、基準値超えに対する具体的な行動計画がない
WBGT値の測定値・対応の不記録(エビデンス不足)
- 熱中症対策において見過ごされがちなのが、測定値やそれに基づく対応の「記録」です。これができていないと、後々大きな問題に発展する可能性があります。
- 測定結果や、それに基づいた対応が記録されていない
- WBGT値や気温の測定結果、いつ休憩を指示したか、誰に水分補給を促したかといった具体的な対応が記録に残されていないと、対策を講じていたことの証明が困難になります。
- 後日、問題発生時の原因究明や改善策立案が困難に
- 万が一、熱中症事故が発生した場合、過去の記録がなければ、当時の環境がどうだったのか、どのような対策が取られていたのかを客観的に検証できません。
- これでは、原因究明や再発防止のための改善策を効果的に立てることができません。
- 法的責任を問われた際の反証材料がない
- 労働災害が発生し、企業が安全配慮義務違反を問われた際、適切な対策を講じていたことを示す客観的な記録がなければ、企業は自らの正当性を主張することが非常に難しくなります。
- これは、企業にとって重大なリスクとなります。
- 測定結果や、それに基づいた対応が記録されていない
熱中症対策制度は整備済みでも職場で対応が追いつかない理由と課題
熱中症対策の法的義務化が進んでも、現場で機能不全に陥る原因は多岐にわたります。
先に挙げた「測定値の過信・活用不足」以外に、「制度導入後に現場が追いつかない」状況を生む、主な要因を具体的に解説します。
トップダウン指示と現場実態のギャップが引き起こす職場の熱中症リスク
本社や上層部からの熱中症対策の指示が、必ずしも現場の状況に合致しないことがあります。
- 本社からの指示が現場の作業特性や環境に合わない
- 本社や管理部門が策定した熱中症対策マニュアルが、実際の作業現場の特性や環境を十分に考慮していないケースがあります。
- 例えば、一律に「1時間ごとに休憩」と指示されても、特定の作業工程では中断が難しい、屋外作業で休憩場所の確保が困難、といった現場固有の課題を無視してしまうと、絵に描いた餅になりかねません。
- 現場担当者への裁量権不足
- 現場の状況は刻々と変化します。
- WBGT値の上昇、作業内容の急な変更、体調不良者の発生など、現場の管理者がその場で適切な判断を下す必要があります。
- しかし、本社からの指示が細かすぎたり、現場担当者に十分な裁量権が与えられていなかったりすると、柔軟な対応ができず、かえって危険度を高めてしまう可能性があります。
熱中症対策の教育訓練不足が招く職場での事故リスク
熱中症対策は、単に設備を導入するだけでなく、人々の知識と行動が重要です。
しかし、この教育訓練が不十分な現場は少なくありません。
1. 管理者層への専門知識の不足
- 熱中症対策の最前線に立つのは、現場の管理者やリーダーです。彼らがWBGT値の意味、リスク評価の方法、具体的な対応策、緊急時の判断基準といった専門知識を十分に持っていないと、適切な指示が出せません。
- 知識不足が、現場の判断の遅れや誤りにつながり、事故リスクを高めます。
2. 作業員への熱中症予防知識・応急処置知識の浸透不足
- 実際に作業を行う従業員自身が、熱中症の初期症状(めまい、吐き気、だるさなど)や、適切な水分・塩分補給の重要性、あるいは緊急時の応急処置方法を知らないと、自身の体調変化に気づかなかったり、異変に気づいても適切な行動が取れなかったりします。
- 情報が十分に伝わっていないと、個人任せの対策となり、効果は限定的です。
3. 外国人労働者への情報伝達の困難さ
- 近年、外国人労働者の増加に伴い、言語の壁が熱中症対策の課題となっています。
- 熱中症に関する注意喚起やマニュアルが日本語のみで提供されていたり、文化的な背景の違いから休憩や水分補給の習慣が異なったりすることで、重要な情報が適切に伝わらず、リスクが高まることがあります。
予算・資源不足で進まない熱中症対策の現場リスク
理想的な対策を講じるためには、相応の予算と資源が必要です。しかし、経済的な制約から、十分な投資ができない企業も少なくありません。
1. 休憩所の整備、空調設備の導入、冷水・塩飴などの提供が不十分
- 快適な休憩スペースの確保、工場や倉庫内の空調設備、作業員がいつでも利用できる冷水や塩飴などの物資は、熱中症予防の基本です。
- しかし、コストがかかるため、これらの物理的な環境整備が後回しにされたり、十分に行われなかったりする現場が見られます。
2. WBGT計などの測定器導入が進まない
- WBGT計は、客観的に熱中症リスクを評価するための重要なツールですが、その導入や適切な数の配置が進んでいない企業もあります。
- 初期費用や、複数の作業場での設置、定期的な校正などの維持管理費用がネックとなり、目に見える形でリスクを把握するための基本的な設備投資が不足しがちです。
それではどうすればいいのか?|ギャップを生じさせない熱中症対策
これまで見てきたように、法改正による義務化が進んでも、現場の実情との間に「ギャップ」が生じ、熱中症対策が形骸化するリスクは常に存在します。
では、企業は熱中症リスクに「実務として」どう向き合い、労働者の安全を確実に守っていけばよいのでしょうか。
ここでは、具体的な示唆と提案を述べます。
現場で実践する法令遵守+αの意識改革のポイント
熱中症対策は、単に法律で罰則があるから行う、という受動的な姿勢では不十分です。
重要なのは、「法令遵守+α」という意識改革です。
企業は、熱中症対策を「労働者の命と健康を守るための最優先事項」と位置づけ、積極的に取り組む必要があります。
これは、企業の社会的責任(CSR)を果たすだけでなく、生産性の向上や企業イメージの向上にもつながる、投資と捉えるべきです。
トップマネジメントが率先してこの意識を持ち、全従業員に浸透させることが肝心です。
現場担当者必見|具体的熱中症対策マニュアル作成の手順とポイント
本社で作成された画一的なマニュアルが、多様な現場の状況に合わないことはよくあります。
効果的な熱中症対策のためには、現場の実態に即した具体的なマニュアル作成が不可欠です。
- 作業の種類
- 作業場所(屋内・屋外)
- 時間帯
- 設備の状況
- 人員構成(外国人労働者の有無など)
を詳細に考慮し、
- それぞれの現場に合わせた具体的な休憩タイミング
- 水分・塩分補給の方法
- 作業内容の見直し基準
- 緊急連絡先と手順
などを明記しましょう。
現場の管理者や作業員の意見を積極的に取り入れ、実用性の高い内容にすることが重要です。
管理者・作業員必須|熱中症対策の継続教育と実践訓練のポイント
熱中症対策は「人」の行動に大きく左右されます。
そのため、管理者・作業員への継続的かつ実践的な教育訓練が欠かせません。
- 管理者向け
- WBGT値の正しい測定方法と判断基準、リスクアセスメントの実践、部下への適切な声かけと体調管理のポイント、緊急時の応急処置と医療機関との連携方法など、実践的な知識と判断力を養う訓練が必要です。
- 作業員向け
- 熱中症の初期症状の理解、自身の体調変化の気づき方、積極的に休憩や水分補給を行う意識付け、同僚の異変に気づいた際の対応など、自己防衛と相互扶助の知識を徹底的に浸透させましょう。
- 外国人労働者には、多言語での情報提供や視覚的な資料を用いる工夫も重要です。
熱中症対策データ管理|定期記録とPDCAで現場改善を実現
対策の「見える化」と改善のためには、定期的記録とデータ活用によるPDCAサイクルの確立が不可欠です。
WBGT値や気温の測定結果、休憩の取得状況、水分・塩分補給の実施状況、体調不良者の発生状況などを日々記録しましょう。
これらのデータを定期的に分析し、どのような状況でリスクが高まるのか、どの対策が有効だったのかを評価します。
その結果に基づいて、マニュアルや教育訓練の内容を改善し、より効果的な対策へとつなげていくことが、持続可能な熱中症対策の鍵となります。
職場で根付かせる熱中症対策|安全意識と企業文化の醸成
最終的には、熱中症対策が「制度だからやる」という義務感から、「当たり前のこととして、皆で協力して行う」という企業文化としての安全意識の醸成を目指すべきです。
経営層から現場の作業員まで、全員が熱中症予防の重要性を認識し、互いの安全に配慮し合う風土を育むことが何よりも大切です。
定期的なミーティングでの情報共有、ヒヤリハット事例の共有、対策に対する従業員からのフィードバックの奨励などを通じて、安全を最優先する文化を築き上げていきましょう。
まとめ|熱中症対策の現状と企業が取るべき実務対応
これまでの議論を通じて、私たちは熱中症対策をめぐる法整備の変遷と、それが現場で直面する課題について深く掘り下げてきました。
最後に、最も重要な結論として、以下の点を強調したいと思います。
熱中症対策義務化|法改正はスタートライン、現場対応がゴール
2008年の労働契約法の安全配慮義務の明文化から始まり、そして2025年の労働安全衛生規則改正による具体的な熱中症対策の義務化に至るまで、日本の労働安全衛生に関する法制度は着実に進化しています。
これは、熱中症による労働災害を防ぐ上で非常に重要な前進です。しかし、法律が改正され、罰則が強化されたからといって、それで全てが解決するわけではありません。
法改正は、あくまで企業が熱中症対策に真剣に取り組むべきであるという、明確な「スタートライン」を引いたに過ぎません。
法律の施行をもって「これで終わり」と考えるのではなく、むしろこれからが本格的な対策の実践期間だと捉えるべきです。
制度ができただけでは、現場の課題は解決しないからです。
熱中症対策|現場実務への落とし込みが労働者の命を守る鍵
最終的に労働者の命と健康を守るのは、机上の法律やマニュアルだけではありません。
重要なのは、法律で定められた内容を、それぞれの職場の特性に合わせて「現場の実務へと確実に落とし込む」ことです。
WBGT値の適切な測定と記録、そのデータに基づいた休憩や作業内容の柔軟な変更、管理者や作業員への継続的で実践的な教育、そして何よりも全員が安全を最優先するという企業文化の醸成──これら地道で具体的な取り組みの積み重ねこそが、熱中症リスクを管理し、尊い命を守る真の鍵となります。
法改正をきっかけに、企業が一丸となって熱中症対策を「絵に描いた餅」に終わらせず、生きた実務として根付かせること。
それが、夏の職場における安全と健康を確保するための、私たちの共通の目標であるべきでしょう。
次回予告|職場の熱中症対策 WBGT測定から休憩ルールまで実務チェックリスト
これまでの記事で、熱中症対策に関する法改正の変遷や、法律だけでは解決しない現場の実務ギャップについて掘り下げてきました。
法改正によって企業の責任が明確化される中、「では具体的に何をすればいいのか?」と悩む方もいるかもしれません。
次回は、そうした疑問にお答えします。
企業の安全配慮義務を果たすために、具体的に「やるべきこと」を網羅したチェックリストを作成していきます。
現場での熱中症リスク管理を強化し、従業員の安全を確実に守るための実践的なステップを、分かりやすく解説していきます。
どうぞご期待ください。
次回の記事は👉職場の熱中症対策 WBGT測定から休憩ルールまで実務チェックリスト
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
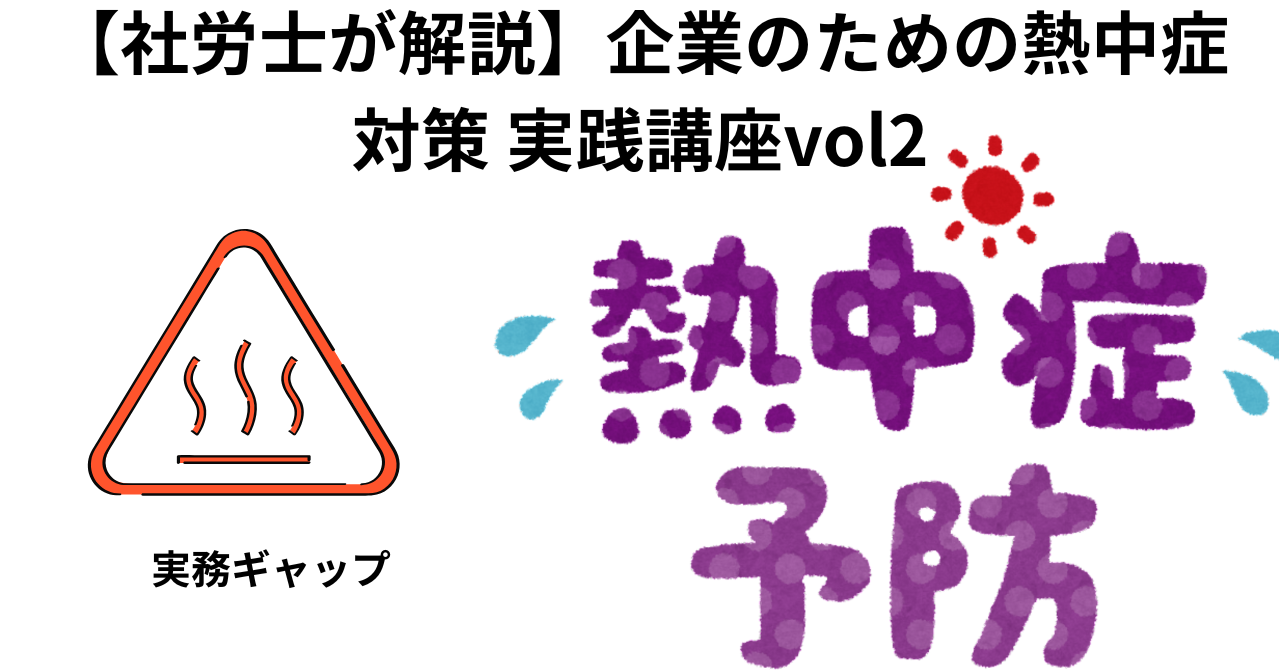

コメント