本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第3話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
前回の記事では、毎月の給与から天引きされている雇用保険料が、どのように計算され、なぜ変動するのかを解説しました。
前回の記事は👉雇用保険料の仕組みとは?計算方法と負担割合を解説
私たちが支払うこの保険料は、決して無駄な支出ではありません。
雇用保険が守ってくれるのは、失業時だけだと思っていませんか?
実は、私たちの人生における様々なリスクに備えられる、非常に心強いセーフティネットなのです。
今回の記事では、失業、育児、介護、そしてスキルアップという、働きながら直面する可能性のある4つのリスクに焦点を当てていきます。
雇用保険が具体的にどのように私たちを守ってくれるのかを一つずつ詳しく解説します。
この記事でわかること
- 雇用保険の全体像|失業保険だけではない包括的なセーフティネットの役割
- 4つのリスクと給付|失業・育児・介護・スキルアップで受け取れる給付金の概要
- 失業時の給付の種類|基本手当や再就職手当など多様な給付制度
- 育児・介護の支援|2025年創設の新しい時短給付を含む両立支援策
雇用保険は「失業保険」だけじゃない
多くの人が雇用保険のことを「失業保険」と呼ぶのを聞いたことがあるかもしれません。
確かに、会社を辞めたときに給付金がもらえるというイメージが強いですよね。
しかし、それは雇用保険のほんの一部の側面に過ぎません。
雇用保険は、私たちが働く上で直面する「もしも」の時に備えるための、より包括的なセーフティネットです。
失業したときだけでなく、育児や介護で仕事を休むとき、さらにはスキルアップのために勉強するときなど、人生のさまざまな転機を支えるための制度なのです。
この記事では、あなたがこれまで知らなかったかもしれない、失業時以外の雇用保険の給付金制度に焦点を当てて、その全貌を分かりやすく解説していきます。
雇用保険を「いざという時のお守り」として最大限に活用するために、ぜひ一緒に学んでいきましょう。
雇用保険が守ってくれる4つのリスク
この雇用保険は、あなたの働く人生における様々な「もしも」の時に備える、心強い味方です。
ここでは、具体的にどのようなリスクから私たちを守ってくれるのか、4つのケースを見ていきましょう。
【リスク1】失業|次の仕事が見つかるまでの生活と再就職を支援する
職を失ったとき、経済的な不安から焦って再就職先を決めてしまうこともあります。
雇用保険は、そのような状況からあなたを守り、安心して再就職活動ができるよう、複数の給付金を用意しています。
失業給付
- 基本手当
- 離職後の生活を支える、最も基本的な給付金です。
- 高年齢求職者給付金
- 65歳以上で離職した人が受け取れる一時金です。
- 特例一時金
- 季節労働者など、特定の雇用形態の人が受け取れる一時金です。
- 日雇労働求職者給付金
- 日雇労働者が受け取れる給付金です。
- 傷病手当
- 求職活動中に病気やケガで働けなくなった場合に、基本手当の代わりに支給される手当です。
就職促進給付
- 再就職手当
- 基本手当の受給中に早期に再就職した場合にもらえる手当です。
- 就業促進定着手当
- 再就職手当を受給し、さらに6ヶ月以上勤続した場合にもらえる手当です。
- 常用就職支度手当
- 障害などがあり就職が困難な方が、安定した職業に就いた場合にもらえる手当です。
- 広域求職活動費、移転費
- 遠方での求職活動や、再就職に伴う引越し費用を援助する手当です。
雇用保険は、単に生活費を補填するだけではありません。
一日も早くあなたが次のキャリアへと踏み出せるよう、多様な形でサポートしてくれます。
これらの給付金の詳細な受給条件や申請方法については、今後の連載記事で一つずつ掘り下げていきます。
【リスク2】育児・仕事と子育ての両立を応援する
子育ては、人生における大きな喜びである一方、キャリアの中断や収入の減少といった不安もつきものです。
雇用保険は、そんな働くママやパパを支えるために、複数の給付金制度を用意しています。
育児休業中に受け取れる主な給付金は、以下の通りです。
- 育児休業給付金
- 原則として、子どもが1歳になるまで(特定の事情がある場合は最長2歳まで)の育児休業に対して支給される給付金です。
- 出生時育児休業給付金
- 通称「産後パパ育休」と呼ばれる、子どもの出生後8週間以内に取得する休業に対して支給される給付金です。
- 出生後休業支援給付金
- 2025年4月から創設された給付金で、育児休業給付金などに上乗せして支給されます。
- 育児時短就業給付金
- 同じく2025年4月から創設された給付金で、育児のために時短勤務をしている人の収入減少分を補填する制度です。
これらの給付金があることで、キャリアをあきらめることなく、安心して子育てに専念できます。
両親が交代で取得する「パパ・ママ育休プラス」といった制度を活用すれば、より柔軟な働き方が実現できます。
これらの給付金の詳細な受給条件や申請方法については、今後の連載記事で一つずつ掘り下げていきます。
【リスク3】介護|大切な家族のケアを支える
高齢化が進む現代社会では、家族の介護が突然必要になることもあります。
雇用保険は、仕事と介護を両立するためのセーフティネットも用意しており、介護離職を防ぐ重要な役割を担っています。
このリスクに備えるための主な制度は、以下の通りです。
- 介護休業給付金
- 要介護状態の家族を介護するために仕事を休む期間、雇用保険から給付金が支給される制度です。
- 介護時短就業給付金
- 2025年4月に創設された給付金で、介護のために時短勤務をしている人の収入減少分を補填する制度です。
これらの給付金は、単に金銭的な支援に留まりません。
大切な家族をケアする期間を確保し、その後も安心して職場復帰できるよう、働く人々を包括的に支える制度です。
これらの給付金の詳細な受給条件や申請方法については、今後の連載記事で一つずつ掘り下げていきます。
【リスク4】スキルアップ|あなたの未来に投資する
雇用保険は、失業や休業といったリスクへの「備え」だけではありません。
あなたのキャリアアップや転職を前向きにサポートする役割も担っており、より良い未来を築くための「投資」としても活用できます。
この目的のために用意されているのが、以下の給付金や手当です。
教育訓練給付金
- 厚生労働大臣が指定する専門講座や資格取得にかかった費用の一部が支給される制度です。給付対象となる講座や給付率によって、以下の3種類に分かれています。
- 専門実践教育訓練給付金
- 長期的なキャリア形成を目的とした専門性の高い講座が対象です。
- 給付率は最大70%(再就職まで含む)と最も高く設定されています。
- 特定一般教育訓練給付金
- 速やかな再就職やキャリア形成に資する講座が対象です。
- 給付率は40%で、専門性の高い資格取得講座などが含まれます。
- 一般教育訓練給付金
- 上記に該当しない講座で、労働者の主体的な能力開発を支援する目的の給付金です。給付率は20%となります。
- 専門実践教育訓練給付金
求職者支援制度
- 雇用保険を受給できない求職者などが職業訓練を受講する際に、以下の給付金や手当を受け取れる制度です。
- 職業訓練受講給付金
- 職業訓練中の生活を支援するための給付金です。
- 通所手当
- 職業訓練施設への通所にかかる交通費が支給されます。
- 寄宿手当
- 職業訓練のために家族と別居して寄宿する場合に支給されます。
- 職業訓練受講給付金
「新しいスキルを身につけたい」「キャリアチェンジに挑戦したい」といったあなたの意欲も、雇用保険は力強く応援してくれます。
これらの給付金や手当の詳細な受給条件や申請方法については、今後の連載記事で一つずつ掘り下げていきます。
まとめ|雇用保険は「お守り」として活用しよう
ここまで見てきたように、雇用保険は給与から天引きされる単なる費用ではありません。
それは、私たちが働く上で直面する様々な転機や挑戦を応援してくれる、心強い「お守り」です。
失業したときだけでなく、育児や介護で仕事を休むとき、さらにはスキルアップを目指すときにも、あなたの生活とキャリアを守り、支えてくれます。
この大切な制度を、あなたはどれくらい理解できていましたか?
雇用保険の仕組みを正しく理解し、いざというときにためらわずに活用できるよう準備しておくことが、あなたの将来の安心感を大きく左右します。
次回予告|失業給付金のチェックリスト
今回の記事では、雇用保険が守ってくれる「4つのリスク」と、それぞれの給付金制度の概要を解説しました。
次回の第5話では、この連載の最大の関心事の一つである「失業給付金」に焦点を当てます。
自分が失業給付金をもらえるか不安な方必見!
給付金を受け取るための「被保険者期間」や「離職理由」の条件を、チェックリスト形式で分かりやすく解説します。
次回の記事は👉失業給付金・失業手当の基礎知識|受給条件・期間を徹底解説
ぜひ、次回の記事でご自身の状況を確認してみてください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
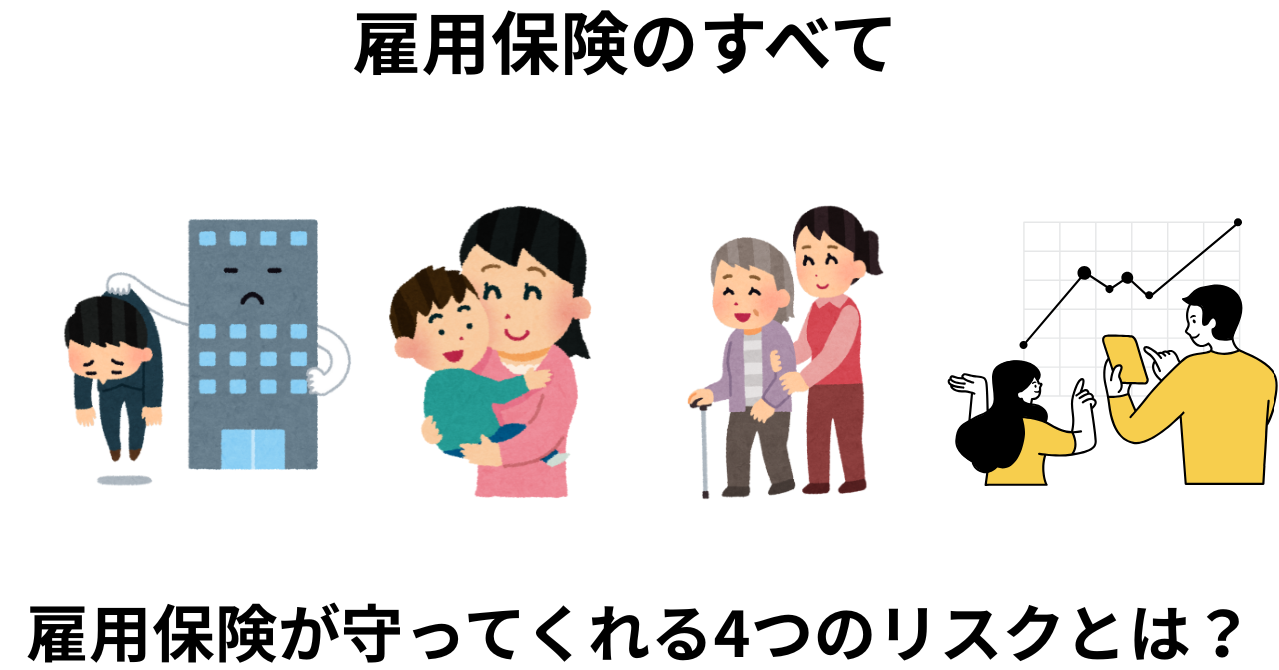
コメント