本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第24話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
出産は新たな生活の始まりです。
しかし、仕事を続ける女性にとって「産休・育休に入ると、どれくらい収入が減ってしまうのだろうか?」という経済的な不安は避けられません。
育児休業給付金は、普段から労働者として雇用保険に加入し、収入を得ている方のための給付金です。
そのため、専業主婦の方など、雇用保険に加入していない方は対象外となります。
安心してください。あなたが雇用保険に加入しているなら、育児休業給付金という国のセーフティネットが、休業中の生活を強力にサポートしてくれます。
制度を正しく理解し、ご自身の権利として最大限に活用しましょう。
本記事では、この育児休業給付金が「いつから」「いつまで」もらえるのか、そして「休業前の賃金を基に、いくら」支給されるのかを、具体的なルールに基づいてわかりやすく解説します。
制度の基本を理解し、不安なく育児休業を取得するための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
この記事でわかること
- 育児休業給付金の基本|雇用保険から支給される非課税の制度概要と支給対象者の要件
- 支給期間のルール|原則として子どもが1歳になる前日までと、最長2歳までの延長が可能なケース
- 産後休業中の注意点|母親の場合、産後56日間は出産手当金(健康保険)で対応し、給付金はその翌日から始まること
- 支給額の計算方法|休業前賃金を基にした日額の求め方と、67%と50%に分かれる支給率のルール
- 支給額の調整と上限|育休中の就業による給付金の減額・不支給の基準と、月額の上限・下限
育児休業給付金とは?制度の仕組みと支給対象をわかりやすく解説
まず、育児休業中の生活を支えてくれるこの給付金が、どのような制度なのか、基本から確認しましょう。
育児休業給付金は「雇用保険」から支給される制度です
育児休業給付金は、あなたが加入している「雇用保険」の制度の一つです。
あなたが日頃から保険料を納めているからこそ、休業という万が一の事態に備えて支給される「働いている人のための保険金」です。
会社から支払われる「賃金」ではありませんので、この給付金には所得税がかからず非課税です。
手取り額が減りにくい大きな理由の一つです。
育児休業給付金の対象者は?誰がもらえるのかをチェック
給付金を受け取れるのは、以下の3つの条件をすべて満たした方です。
- 雇用保険の被保険者であること
- 雇用形態は問いません。正社員はもちろん、契約社員、パートタイマー、アルバイトの方でも、雇用保険に加入していれば対象です。
- 休業前の一定期間に賃金支払い実績があること
- 育児休業を開始する前の2年間で、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが原則的な条件です。
- 【補足】 この「2年間」は最長で遡れる期間であり、入社から1年(12ヶ月)以上継続して雇用保険に加入していれば、この条件はクリアできます。
- 休業期間中の就業日数に制限があること
- 育児に専念するための休業であるため、就業には制限があります。
- 原則として、1支給単位期間(原則1ヶ月)ごとに就業日数が10日以下である必要があります。
- 【重要】 もし就業日数が11日以上になっても、その月の合計就業時間が80時間以下であれば給付金は支給されます。日数と時間の両方を超過すると、その月の給付金は停止されますので、注意が必要です。
これらの条件を満たせば、あなたは国からの経済的な支援を受ける権利があります。まずはご自身の雇用保険の加入状況を確認しましょう。
育児休業給付金の支給期間はいつまで?延長できるケースも解説
「いつまで休めるのか」つまり育児休業給付金を受け取れる期間のルールは、主に「原則期間」と「出産直後の例外期間」の二つに分けられます。
育児休業給付金の原則支給期間は子どもが1歳になる前日まで
育児休業給付金が支給される原則の期間は、子どもの年齢が満1歳になる誕生日を迎える日の前日までです。
これは「育児休業の期間=給付金がもらえる期間」の基本的な上限です。
育休給付金の延長特例|保育園未入所などで最長2歳まで可能
原則1歳までですが、以下のような「やむを得ない事情」がある場合は、最長2歳まで段階的に育児休業を延長し、給付金を受け取ることができます。
- 保育園に入所できない場合
- 配偶者が病気や負傷、死亡などの事情により子どもの養育が困難になった場合
この延長は1歳6ヶ月まで、さらに2歳までと段階的に申請が必要です。
【重要】延長時の申請手続きについて
延長の際も、手続きの窓口は勤め先です。延長に必要な「不承諾通知書」など、あなた自身が役所に申請して取得する証明書類を会社に提出すれば、会社がハローワークへの給付金の申請を代行します。
あなた自身がハローワークへ行く必要はありません。
「不承諾通知書」とは何か
「不承諾通知書」とは、あなたが住んでいる市区町村から発行される公的な書類です。
保育園の入園を申請したものの、定員超過などの理由で入園できなかったことを証明する書類であり、育児休業を1歳以降に延長するための「やむを得ない事情」の唯一の証明として利用されます。
- 誰が発行するか
- 市区町村の役所(自治体)。
- 誰が取得するか
- 保護者自身(あなた自身)が保育園に申し込み、その結果として役所から受け取るものです。
- 会社が用意できるか
- できません。会社は保育園の申し込みを代行できないため、この書類は従業員ご自身で取得する必要があります。
産後休業中の育児休業給付金|支給はいつから始まる?
最も注意が必要なのは、母親が出産直後に休業する場合です。
- 産後休業期間(8週間)
- 出産日の翌日から8週間(56日間)は、労働基準法に基づく「産後休業」となり、この期間は育児休業給付金の対象外です。
この期間の収入補填は、加入している健康保険によって対応が分かれます。
| 健康保険の種類 | 産後休業中の収入補填 | 補填の制度名 |
| 会社員などの健康保険(協会けんぽ・組合健保など) | あり | 出産手当金(健康保険の制度) |
| 国民健康保険(市町村国保・国保組合など) | 原則なし | (制度自体がありません) |
重要なのは、健康保険の種類に関わらず、雇用保険からの育児休業給付金は、この産後休業期間が終了した翌日から支給が開始されるという点です。
つまり、母親の場合、通常は産後57日目以降から給付金の支給対象期間がスタートします。
休業期間全体の収入を途切れさせないよう、ご自身の健康保険と雇用保険の制度をしっかり把握しておくことが大切です。
育児休業給付金の金額シミュレーション|計算方法と注意点
最も気になるのが、「結局、毎月いくらもらえるのか」という点でしょう。
育児休業給付金の額は、あなたの休業前の賃金をもとに、以下の計算式で算出されます。
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 支給率
休業開始前の賃金で決まる育休給付金|計算日額の求め方
支給額の基準となる「休業開始時賃金日額」は、原則として育児休業を開始する日の前6ヶ月間の賃金総額を180日で割って算出されます。
- 例(2026年6月10日休業開始の場合)
- 2025年12月から2026年5月までの賃金(給与)が、計算の基礎となります。
- ただし、産前産後休業期間は給与が支給されないことが一般的です。
- そのため、産前42日・産後56日分の合計約3か月分は無給となり、休業開始前6か月間の賃金計算では、この無給期間を除外して、給与が支給された月のみの賃金で日額を算出する運用が実務上一般的です。
育児休業給付金の支給率はいつ変わる?67%と50%の計算ルール
育児休業給付金の支給率は、休業期間によって大きく変動します。
- 休業開始~6ヶ月(180日)まで
- 支給率 67%
- 6ヶ月超(181日目)以降
- 支給率 50%
育児休業給付金の計算例|休業前月額25万円の場合の支給額
前提条件
- 育児休業開始日
- 2026年6月10日
- 休業開始前6か月間
- 2025年12月10日~2026年6月9日(約182日)
- 産前休業
- 2026年3月3日~2026年4月13日(42日)
- 出産
- 2026年4月14日
- 産後休業
- 2026年4月15日~2026年6月9日(56日)
- 無給期間合計
- 42日+56日=98日
- 支給対象となる賃金支払日数
- 182日 − 98日=84日
- 休業開始前の給与月額
- 25万円(給与が支給された期間のみを計算に使用)
1. 休業開始時賃金日額の算出
- 支給された給与総額
- 月額25万円 × 2.8か月(給与支給された期間) = 700,000円
- 日額計算
- 700,000円 ÷ (182日 – 98日) = 約8,333円/日
2. 支給率に基づく給付金額
- 休業開始から最初の6か月間(支給率67%)
- 1ヶ月の給付金額 = 8,333円 × 30日 × 67% = 167,493円
- 6か月目以降(支給率50%)
- 1ヶ月の給付金額 = 8,333円 × 30日 × 50% = 124,995円
※給付金は通常、2ヶ月ごとに2ヶ月分まとめて振込まれます。
育休中に働くと給付金が減額?もらえなくなるケースと計算方法
育休期間中に会社から賃金が支払われた場合、支給額が調整されます。
安易に働くと給付金が大きく減る可能性があるため注意が必要です。
この調整は、休業前の賃金月額を基に判断されます。
| 休業中の賃金が… | 賃金の目安(月収25万円の場合) | 給付金は… |
| 【調整なし】 基準となる月収の13%以下の場合 | 32,500円以下 | 全額支給 |
| 【減額調整】 基準となる月収の13%超80%未満の場合 | 32,500円超20万円未満 | 減額支給 |
| 【全額不支給】 基準となる月収の80%以上の場合 | 20万円以上 | 不支給 |
具体的な減額の計算例(休業前月収25万円、休業中15万円稼いだ場合)
月に15万円の賃金が支払われた場合、本来約16.7万円もらえるはずだった給付金は、減額調整により50,000円まで大きく減ります。
支給上限額 = (休業前月収 × 80%) - 支払われた賃金
支給上限額 = 200,000円 - 150,000円 = 50,000円
(※注:支給率が50%になる休業181日目以降は、上記の「13%」の基準が「30%」に緩和されます。)
ご提示いただいた情報を基に、育児休業給付金の計算における「上限額・下限額」について、分かりやすい説明文を作成します。
【重要】支給額には上限・下限がある
育児休業給付金の支給額は、休業前の賃金をもとに計算されます。
しかし、どれほど高い賃金の方でも、どれほど低い賃金の方でも、支給される額には公的な上限額と下限額が設けられています。
この上限・下限は、給付金の計算基準となる「休業開始時賃金日額」の段階と、実際に支給される「月額」の段階の二重で設定されています。
1. 賃金日額の上限・下限(2026年7月31日まで適用)
給付金を計算する際の基礎となる「休業開始時賃金日額」には、以下の通り上限・下限が設けられています。
| 項目 | 日額 | 調整内容 |
| 上限額 | 16,110円 | 算出された日額がこの額を超える場合、一律に16,110円として計算されます。 |
| 下限額 | 3,014円 | 算出された日額がこの額を下回る場合、一律に3,014円として計算されます。 |
2. 支給月額の上限・下限(給付率による変動)
上記の日額を基に給付率をかけた結果、実際に支給される1ヶ月(30日分)の給付金額にも、上限・下限が設定されています。
| 給付率 | 支給上限額(30日分) | 支給下限額(30日分) |
| 67%(最初の180日間) | 323,811円 | 60,581円 |
| 50%(181日目以降) | 241,650円 | 45,210円 |
仕組みのまとめ
- まず、あなたの休業前の平均賃金から「休業開始時賃金日額」を算出します。
- この日額が16,110円を超える場合は切り下げ、3,014円を下回る場合は切り上げられます。
- 調整された日額に給付率(67%または50%)をかけた結果が、上記の「支給上限額・下限額」の範囲内に収まる形で支給されます。
注意事項
この上限額と下限額の基準は、毎年8月1日に改定されます。
したがって、あなたの休業開始日や期間によっては、上記の数値が適用されない場合があるため、最新の正確な数値は厚生労働省やハローワークの情報を確認することが重要です。
育休給付金の振込スケジュール|申請から口座入金までの流れ
給付金の申請手続きの大部分は会社が窓口となり、原則として2ヶ月分がまとめて、2ヶ月に一度支給されます。
初回の振込は休業開始から時間がかかるため、事前の資金準備が不可欠です。
ここでは、2026年6月10日に育児休業を開始し、休業前賃金月額が25万円だった場合の具体的なフローを示します。
育休開始前に必要な手続き|労働者による申し出の方法
労働者が行わなければならない最も重要な行動が「申し出」です。
2026年5月10日までに、会社に育児休業の取得と給付金の申請を希望する旨を申し出てください。
このとき、産後休業中ではありますが、通常は勤め先から育児休業給付金の申請について案内があるため、それに従って本人確認書類などの必要書類を提出しましょう。
もし会社から何も案内がない場合は、こちらから積極的に確認・申し出を行うことをおすすめします。
育休給付金の初回振込|申請から入金までのタイムラグを解説
給付金は休業の実績が確定した後(最初の2ヶ月が終わった後)に申請されるため、初回の振込には時間がかかります。
- 2026年8月15日頃に、会社が最初の2ヶ月分(6月10日〜8月9日)の給付金をハローワークに申請します。
- その後の審査を経て、2026年9月25日頃に、最初の2ヶ月分である約334,986円(67%相当)が指定口座に振り込まれます。
- 注意点として、休業開始日(6月10日)からこの振込日(9月25日頃)まで、約3ヶ月半は給付金の振り込みがない「収入の空白期間」となります。
育休給付金の振込継続|支給額の変動と会社への催促の手順
初回の振込以降は、2ヶ月に一度のサイクルで支給が続きます。
- 労働者による手続き
- その都度、会社から送られてくる申請書に記入し、速やかに返送する必要があります。
- 【重要】会社からの書類が届かない場合
- 申請書が届かないと、あなたの振り込みが遅れる原因となるため、2ヶ月の支給単位期間が終わった頃を目安に、必ず会社に確認・催促してください。
- 支給率67%期間(高給付)
- 休業開始から180日目まで(2026年12月9日まで)が対象です。
- 2027年1月25日頃に振り込まれる分(2026年10月10日〜12月9日の2ヶ月分)まで、約33万円が2ヶ月に一度の頻度で振り込まれます。
- 2026年11月25日頃、2027年1月25日頃に振込。
- 休業開始から180日目まで(2026年12月9日まで)が対象です。
- 支給率50%期間(減額)
- 2026年12月10日(181日目)からは支給率が50%に切り替わり、振込額が下がります。
- この期間は約25万円弱が2ヶ月に一度の頻度で振り込まれます。
- 2027年3月25日頃、2027年5月25日頃に振込
- 2026年12月10日(181日目)からは支給率が50%に切り替わり、振込額が下がります。
- 最終の2027年6月25日頃に振込に振り込まれる分は、おそらく4日分くらいで、16,666円くらいが振り込まれます。
育児休業終了後の手続きと1歳以降の延長方法
- 最終支給日
- 原則期間は子の1歳の誕生日(2027年4月14日)の前日である2027年4月13日までが給付金の支給対象期間です。
- 職場への復帰日
- 原則として、2027年4月14日に職場へ復帰となります。
- 延長手続き
- 1歳を超えても休業が必要な場合、2027年3月31日頃まで(1歳満了日の2週間前)に会社へ申し出を行い、ご自身で取得した不承諾通知書を提出します。
まとめ|育児休業給付金の基本と支給期間・支給額の目安
本記事を通じて、育児休業給付金について以下の重要なポイントを理解していただけたかと思います。
- いつまで
- 原則、子が1歳になる誕生日の前日までが支給期間です(最長2歳までの延長あり)。
- いくらもらえるか
- 休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。
育児休業給付金|振込遅延と休業中の賃金発生に注意
給付金を受け取り、家計を安定させる上で、特に注意すべきは以下の2点です。
- 申請の遅延は、即、振込の遅延に直結します。
- 給付金は2ヶ月に一度のサイクルで支給されますが、これは会社が期限内に申請することが前提です。
- 会社から申請書類が送られてきたら速やかに記入・返送し、もし書類が届かない場合は、あなたの口座への入金が遅れないよう必ず会社に催促してください。
- 育休中の賃金発生には厳重注意が必要です。
- 勤務先から支払われる賃金が休業前賃金の80%以上になると、その月の給付金は全額不支給となります。
- わずかな就業でも減額対象になる可能性があるため、事前に会社と調整し、支給ルール(特に13%基準)を厳守してください。
次回予告|男性の育児休業|産後パパ育休と出生後休業支援給付金のポイント
次回では、男性の育児休業に焦点を当てます。
2022年10月に新設された、パパのための新たな休業制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」、そして給付率を手取りで「実質10割」に引き上げることを目指す「出生後休業支援給付金」をテーマに、制度を最大限に活用し、夫婦で育児に取り組むための具体的な方法を徹底解説します。
ご期待ください!

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
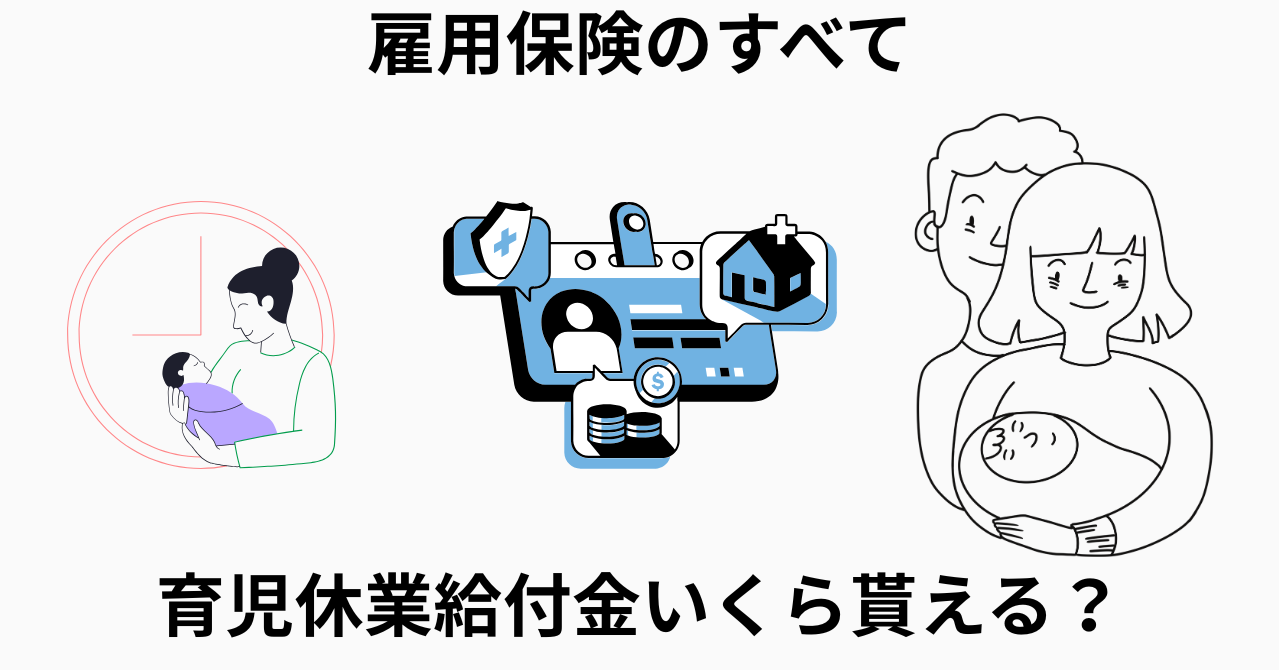
コメント