本記事は「インフルエンザ・コロナと企業の安全配慮義務」シリーズの第6話です。
シリーズの他の記事は👉インフルエンザ・コロナ対策と企業の安全配慮義務|実務ガイド
前回の記事で、私たちは感染症対策を「単なる経費」ではなく「命と事業を守るための費用対効果の高い取り組み」として捉え、予防接種の費用補助という重要な経営判断を下す必要性を解説しました。
前回の記事は👉企業はインフルエンザ・コロナ予防接種にどこまで関与すべきか?
この資金投入により、企業は最も深刻なリスクである重症化・死亡の回避に大きく舵を切ったことになります。
しかし、この取り組みを実行しただけで終わりではありません。
法律上の強制力がなくなり、マスク着用や隔離が個人の判断に委ねられた今、企業に残された次の実務課題は、「日々の感染拡大を防ぐための現場のルールと環境をどう整えるか」という点です。
義務ではないからこそ、集団感染リスクとハラスメントリスクという二つの板挟みになり、人事担当者は明確な判断基準を見失っています。
本記事は、その迷いを解消し、科学的データと安全配慮義務の観点から、トラブルなく事業継続を確実にするための環境整備と行動ルールの最適解を提示します。
この記事で分かること
- 日々の感染症対策を就業規則ではなく独立ガイドラインで柔軟に運用する方法
- いつ・どのように対策するかを具体的に示し、従業員が安心して協力できる運用方法
- CO2濃度管理や休憩・食事スペース配置など、科学的根拠に基づくオフィス環境整備のポイント
予防接種後の職場における感染症対策と実務対応のポイント
予防接種への資金投入は、企業が従業員の生命と事業継続に対する責任を果たした重要な一歩です。
しかし、これで感染症対策が完了したわけではありません。
今、多くの人事・労務担当者が直面しているのは、法律の縛りがない中で、「どこまでマスク着用を推奨すべきか」「費用をかけた換気設備が本当に機能しているのか」といった、日々の実務ルールに関する具体的な課題です。
集団感染が発生すれば業務に大きな支障をきたしますが、個人の判断を無視した過度な強制はハラスメントのリスクを招きます。
義務とリスクの狭間で、明確な行動指針が見出せないのが現状です。
感染症対策の法的義務と安全配慮のポイント
新型コロナウイルス感染症が5類へ移行したことで、国の対応は「強制・要請」から「自主的な対応」へと完全に切り替わりました。
この変化が意味するのは、感染対策が労働契約法に基づく安全配慮義務と、事業継続計画(BCP)の観点から、企業の「自主的なリスクマネジメント」になったということです。
法律上の強制力がなくなった今だからこそ、企業は従業員が安全に働ける環境を提供するための「配慮の努力」を怠っていると判断されないよう、明確な企業姿勢とルールづくりが強く問われています。
ハラスメントなどのトラブルを避けつつ、集団感染リスクの低減という最大の効果を生むための、マスク着用ルールの最適化、科学的根拠に基づくオフィス環境整備(換気基準など)、および実効性の高い行動ルールのすべてを解説します。
これにより、貴社は法的な義務に依らず、データと根拠に基づいた信頼性の高い感染対策の基準を確立できます。
企業の感染症対策における法的根拠と実行力|就業規則とガイドラインの違い
感染対策のルールの必要性は理解できても、人事担当者としてまず迷うのは、「このルールを就業規則に盛り込むべきか、それとも別の文書にすべきか」というルールの位置づけです。
この判断を誤ると、柔軟な対応ができなくなったり、かえって従業員とのトラブルを招いたりするリスクがあります。
職場のマスク着用・換気ルールを就業規則に盛り込むのが難しい理由
就業規則は、労働時間、賃金、懲戒など、労働契約の根幹に関わる重要な事項を定める文書です。
そのため、変更する際には、従業員代表からの意見聴取や労働基準監督署への届出といった厳格な手続きが義務付けられています。
私たちがこれから定める実務的な感染対策のルール(換気基準、マスク着用推奨場面など)を就業規則に盛り込むことは、実務においては以下の点で不向きです。
- 柔軟な変更の必要性
- 感染症の流行状況(例:季節性インフルエンザのピーク)に応じて、マスクの推奨レベルや出社基準は柔軟かつ迅速に変更する必要があります。
- 実務スピードの低下
- 状況が変わるたびに煩雑な変更手続きを踏んでいては、実務のスピードが落ち、感染症対策が後手に回ってしまいます。
職場の感染症対策ガイドラインを効果的に作成するポイントと手法
上記の問題を解消し、必要な強制力と柔軟性を両立させる最適解が、就業規則から独立した「感染症対策ガイドライン」の作成です。
| 項目 | ガイドラインの定義とメリット |
| 定義 | 従業員の安全配慮と事業継続のための実務的マニュアル。 就業規則を補完する「運用ルール」としての位置づけ。 |
| メリット | 必要な強制力(安全配慮義務の履行)を持たせつつ、流行状況に応じて内容を柔軟かつ迅速に修正・変更できます。 企業が安全管理を真摯に行っているという対外的な証拠にもなります。 |
感染症対策ガイドラインの労基署への提出義務は?
多くの担当者が気にされる点ですが、原則として、この「感染症対策ガイドライン」を労働基準監督署(労基署)へ提出する義務はありません。
- 原則
- 提出義務なし ガイドラインは、労働者の基本的な労働条件(賃金や懲戒など)ではなく、実務上の運用ルールや推奨事項を定めた文書です。
- そのため、労働基準法上の「就業規則」には該当せず、労基署への届出は不要です。
- 例外的な注意点
- ただし、ガイドラインの内容が、実質的に労働者に不利益を課したりするものである場合は注意が必要です。
- 例えば、「ガイドラインに違反した場合、賃金を減額する」「懲戒の対象とする」といった、労働契約の根幹に関わる不利益な内容を盛り込む場合は、就業規則に準じた扱いが必要となり、労基署への届出が必要となる可能性があります。
企業のマスク着用ルールの推奨運用と実務上の最適解
多くの企業において、低リスクの平時における一律のマスク推奨は、もはや現実的ではありません。
しかし、企業の安全配慮義務が問われるのは、季節性インフルエンザやコロナの流行拡大が確認された場合です。
企業が設けるべきルールは、平時ではなく、リスクが顕在化する時期に業務継続を確実にするための限定的なルールでなければなりません。
ここでは、「ひとたび流行拡大が確認された場合」を想定し、企業が迅速に限定的なルールを「発動」させるための設計方法を解説します。
このルールは、実効性が高く、かつハラスメントを回避できるものでなければなりません。
企業のジレンマ|感染症対策でのリスク回避とハラスメント防止の両立
感染拡大期に強制はできないものの、放置すれば集団感染リスクが高まります。
効果的なルールづくりとは、この「リスク回避(事業継続)」と「従業員の人権・感情への配慮(ハラスメント防止)」のバランスをいかに取るかにかかっています。
感染症対策でハラスメントを防ぎつつマスク着用を推奨する方法
強制ではなく、従業員が自発的に「配慮」として着用を選択する環境と枠組みを作ることが重要です。
以下の3つの柱で、発動時の推奨ルールを具体化します。
推奨の明確化|「発動条件と高リスク場面」で具体的な線引きをする
ルールは、平時と有事の境界線(発動条件)を明確にし、特定の状況下でのみ推奨が発動するように設計します。
① マスク着用推奨が発動する「特定の状況下(発動条件)」の例
企業として、「感染症対策を強化すべき有事」と判断し、全社的な推奨を発動する客観的な基準を定めます。
| 発動条件 | 具体的な判断基準の例 |
| 地域流行レベル | 自治体が、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症について、「警報レベル」や「流行拡大期」に相当する警戒情報を公式に発令した場合。 |
| 社内感染率 | 全従業員の〇%以上が、同時期に感染し、業務継続に重大な支障が出始めたと経営層が判断した場合。(例: 5%など、具体的な数値で設定) |
② 発動後に適用される「具体的な推奨場面」の例
上記の発動条件が満たされた際に、全従業員に「着用を強く推奨する」具体的な場面です。
| 推奨場面 | 理由と適用範囲 |
| 軽度な体調不良時 | 咳や喉の痛みなど軽度な呼吸器症状があるが、出勤せざるを得ない従業員。(周囲への配慮として最も重要) |
| 多人数が密集する場所 | 換気が十分でない会議室や研修室での大人数(例:10名以上)が参加する会議や打ち合わせ。 |
| 訪問・接客業務 | 医療機関、高齢者施設、あるいはお客様がマスク着用を希望されていると推察される対面での接客時。 |
「配慮」の訴求|義務ではなく、職場内の相互扶助を促す
推奨を単なる「会社の指示」ではなく、「職場内の相互扶助の精神」として訴えかけることが、自発的な協力を得るうえで最も重要です。
メッセージングの核心は、「高齢者や基礎疾患を持つ同僚への配慮」として協力を求めることです。
これにより、ルールではなく倫理観に基づいた行動を促します。
ハラスメント防止策|非着用者への攻撃を防ぐルールを明文化する
強制力を持たない推奨ルールを設ける場合、同時に非着用者への攻撃を防ぐルールも設ける必要があります。
- 差別的言動の禁止
- マスクを着用していない従業員に対し、非難や差別的な言動を禁止することをガイドラインに明文化する。
- 上司による事実上の強制の禁止
- 上司が「評価に関わる」などと威圧的な言葉を使い、実質的に着用を強制する行為をハラスメントとして明確に禁止する。
有事の職場で飛沫リスクを抑える感染症対策行動ルールの具体策
マスク着用推奨のルールを発動した有事の際、従業員が意識すべきは「飛沫リスクの高い場面をどう避けるか」です。
ここでは、業務の性質上避けられない会議や来客対応、そしてリスクの高い休憩・食事スペースにおける、現実的で効果的な行動ルールを解説します。
1. 職場の業務中に従業員の飛沫リスクを最小化する感染症対策ルール
業務を止めずに飛沫リスクを最小限に抑えるためには、環境整備と人数制限をセットにした具体的なルールが必要です。
会議・打合せのルール|換気と人数のバランスを取る
会議は、閉鎖空間で一定時間会話が続くため、最もリスクが高い場面の一つです。
- 換気量の基準と参加人数の連動
- 会議室にCO2濃度計を設置することを強く推奨し、換気状態と参加人数を連動させます。
- 例|CO2濃度が基準値(例:1,000ppm)を超えやすい会議室では、参加人数を〇名までに制限するか、人数超過の場合はオンラインでの参加を推奨する。
- 会議室にCO2濃度計を設置することを強く推奨し、換気状態と参加人数を連動させます。
- 会話時の推奨
- 長時間の会話が続く場合は、換気を徹底したうえで、短時間で集中的に議論を終えることを推奨します。
来客対応・商談のルール|相手の安心感を最優先する
お客様や取引先に対する対応は、企業の信頼に関わるため、社内ルールとは別に、相手への配慮を最優先した基準が必要です。
- 対応担当者に限定した推奨基準
- 全社的な推奨ルールの発動中、来客対応や外部との商談を行う担当者には、相手への安心感やプロフェッショナルな配慮を示すために、マスク着用を強く推奨します。
- 対面時間の短縮
- 対面による商談時間を最小限に抑え、事前の情報共有や事後のフォローアップをオンラインで済ませることを推奨します。
2. 職場の休憩・食事スペースで従業員の飛沫リスクを抑える感染症対策ルール
休憩や食事の時間は、マスクを外すため、オフィス内で最も飛沫リスクの高い場面となります。
ガイドラインでは、具体的な行動の注意点を明記する必要があります。
- 飲食時の「対面回避」
- 食事中に飛沫が飛ぶのを避けるため、向かい合って座ることを避ける「対面回避」や、斜め向きの席配置を推奨します。
- 「黙食」の推奨
- 食事中の会話は飛沫を拡散させる最大の要因です。
- 「黙食」を推奨する旨を明記し、会話をする場合は食後にマスクを着用してから行うよう促します。
- 共有備品の衛生管理
- 休憩室のテーブルや、共有の電子レンジ、給湯室の蛇口など、手が触れやすい場所の消毒を徹底するルールを定めます。
感染症対策で事業継続を支えるオフィス環境整備のポイント
行動ルールは重要ですが、従業員が安全だと感じられる物理的な環境を整えることが、企業の安全配慮義務の履行、ひいては事業継続の土台となります。
ここでは、特に重要な換気と物理的対策について、現実的な基準を解説します。
1. 職場での感染症リスクを抑えるオフィス換気基準の最適化
感染経路として軽視できないのが、エアロゾル(空気中を漂う微粒子)による感染です。
これを防ぐには、感覚的な「窓開け」ではなく、科学的なデータに基づいた換気が欠かせません。
科学的な基準と実行策
企業が目指すべきは、厚生労働省が推奨する「CO2濃度1,000ppm以下」の維持です。
CO2濃度が上がると、室内に滞留する人の息の量が増えている、つまりウイルスを吸い込むリスクが高まっていることを示します。
- CO2濃度計の活用を推奨
- 会議室や密集しやすいスペースにCO2濃度計を設置し、数値が1,000ppmに近づいたらアラートが出る仕組みを導入することで、換気の見える化を図ります。
- 実行策
- 窓の開放や換気扇の常時稼働を徹底します。
- さらに、特に換気の難しい場所では、エアロゾル感染対策として高効率フィルター(HEPA)付き空気清浄機の活用も有効です。
2. 感染症拡大時のオフィス物理的対策|机・備品・パーテーションの管理方法
飛沫対策として過去に導入された備品や習慣について、その位置づけを改めて明確にします。
消毒・清掃
感染症の流行状況にかかわらず、従業員が触れる頻度の高い場所の定期的な消毒・清掃は継続するべきです。
ドアノブ、会議室のテーブル、共有機器(コピー機など)は、感染対策の基本としてガイドラインに明記しましょう。
パーテーションの扱い
コロナ禍で一時的に普及したパーテーションですが、通常は推奨しません。
なぜなら、パーテーションは空気の流れを阻害し、かえって換気を悪化させる可能性があるためです。
ただし、これを有事の際の選択肢として位置づけることは現実的です。
季節性インフルエンザやコロナが大きく流行し、業務に重大な影響が出る際の「一時的な対策の選択肢の一つ」として活用を検討します。
この際、換気を妨げないよう、設置場所や高さに細心の注意を払うことをガイドラインに付記すべきです。
まとめ|実務担当者が知るべき感染症対策で企業の信頼と事業継続を守るポイント
企業の感染症対策は、前回の記事で解説した予防接種への資金投入と、本編で定める日々の実務ルールの整備が連動して初めて機能します。
予防接種は、従業員の重症化・死亡リスクを回避する「命の保険」であり、ガイドラインは、集団感染による事業の停滞リスクを回避する「実務上の盾」です。
この両輪が揃うことで、企業は労働契約法に基づく安全配慮義務を果たし、従業員からの信頼を確保し、ひいては企業の評判を高めることができます。
年間を通じた企業の感染症リスクマネジメント|実務担当者向け展望
感染症対策は、特定の時期や特定の感染症が流行したときだけ行う短期的な対応ではありません。
季節性インフルエンザが毎年やってくるように、感染症リスクは年間を通じて存在するリスクマネジメントとして定着すべき「ニューノーマル」です。
企業は、感情論ではなく、科学的データと費用対効果に基づき、柔軟なガイドラインと客観的な発動条件を設定することで、今後どのような感染症の波が来ても、業務を安定して継続できる、強固な体制を確立できるでしょう。
次回予告|感染症対策ルールの実効性を高めるケーススタディ
さて次回は、以下のテーマに焦点を当てて解説します。
- 過去の企業対応事例から学ぶ
- 「配慮の訴求」がうまく機能し、自発的な着用率を高めた成功事例を具体的に紹介します。
- 失敗事例の分析
- 懲罰的な表現を用いたり、ルールを十分に周知しなかったことで従業員の反発を招き、かえって集団感染リスクを高めてしまった失敗事例を分析します。
- 実務での注意点
- これらの事例から、あなたの会社がガイドラインを策定・運用する際に避けるべき実務上の落とし穴と、成功の鍵となる要素を抽出します。
次回の記事は👉企業の感染症対策|現場で役立つ成功・失敗事例から学ぶ運用ノウハウ
ご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
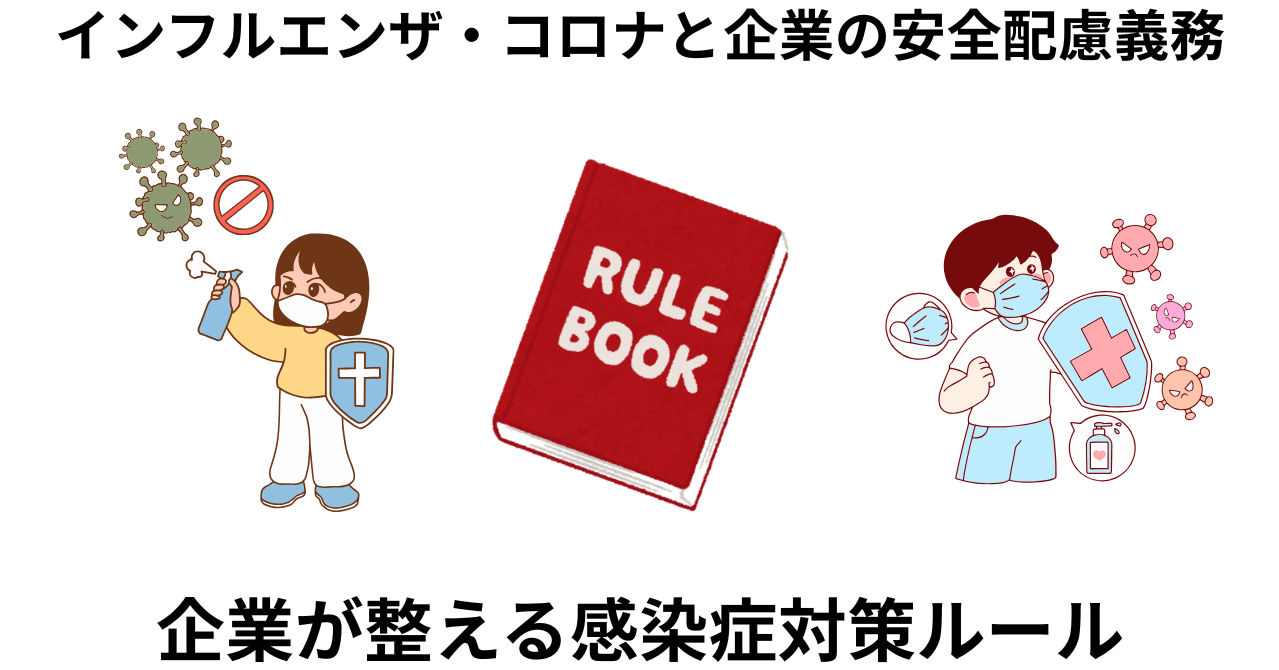

コメント