本記事は「インフルエンザ・コロナと企業の安全配慮義務」シリーズの第5話です。
シリーズの他の記事は👉インフルエンザ・コロナ対策と企業の安全配慮義務|実務ガイド
前回の記事では、季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症といった5類感染症に対し、従業員の家族が感染した場合の対応や、感染症法上の分類に応じた企業の法的義務を解説しました。
前回の記事は👉従業員の家族の感染症罹患の時の企業対応|出勤基準と休業手当
企業が自主的にルールを定め、就業制限を行うことが重要だとわかっていても、感染拡大を防ぐための対策はそれだけではありません。
最も有効で基本的な「事前の防衛策」が、予防接種です。
この記事で分かること
- 従業員の予防接種を積極的に推奨すべき理由
- 予防接種費用を補助することのメリットと費用対効果
- 企業が選べる予防接種の補助方法と実務上の選択肢
- 接種率を高め、従業員が受けやすい環境を整えるための具体的対応
予防接種に企業は関与すべきか|義務はないが責任はある?
しかし、多くの企業担当者は、予防接種の費用補助が法律上の義務ではないことを知っています。
にもかかわらず、その上で「どこまで費用を出し、どこまで推奨や関与をすべきか」という経営判断と実務上の責任に直面し、判断を迷います。
「義務ではないなら会社の出費は抑えたい。」
「しかし、見送ることで集団感染が発生した際、業務に大きな支障が出たり、コロナ禍を経験したにもかかわらず感染症に対する認識の甘さが露呈したりするリスクが生じる。」
本記事では、この「実務的な関与の是非」という企業最大の疑問を解消するため、まず企業が直面するリスクの規模を明確にします。
その上で、科学的なデータと費用対効果という明確な根拠に基づき、予防接種を巡る企業の判断基準を掘り下げていきます。
企業の予防接種投資は必須|科学的データが示す効果
「感染症対策は、もはや法律上の義務や規制の有無だけで判断できる時代ではありません。」
この認識は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを経験したことで、企業が法令遵守からリスクマネジメントへと舵を切った証です。
法律上の強制力がなくても、感染拡大がもたらす業務への支障は無視できないと理解されたのです。
その中でも、最も有効な「事前の防衛策」が予防接種です。
予防接種の有無で変わる|企業が向き合う最大リスク規模
予防接種の要否を検討するため、まずはこれらの感染症が企業と従業員にもたらすリスクの現実を、以下の年間死亡者数という具体的なデータで把握することから始めましょう。
| 感染症 | 日本の年間死亡者数(推計) | 根拠データ |
| 季節性インフルエンザ | 例年約1万人 | 直接的な死因に加え、肺炎などによる※「超過死亡」を含めた例年の推計。 (出典:厚生労働省) |
| 新型コロナウイルス | 2024年は35,865人 | 2024年の年間死亡者数は35,865人で、インフルエンザの超過死亡推計の約3倍以上に及びます。 (出典:厚生労働省の人口動態統計に基づく報告など) |
※超過死亡とは?
ある期間に実際に観測された死亡者数が、過去の統計データから予測される「通常の死亡数」を上回った分。実際の死亡数 - 予測される通常の死亡数 = 超過死亡数
これらのデータが示すのは、対策を怠れば、従業員の生命に関わるリスクに直面するということです。
そして、感染が拡大すれば業務に大きな支障が出たり、コロナ禍を経験したにもかかわらず感染症に対する認識の甘さが露呈したりするリスクが生じます。
科学的データが裏付ける予防接種の価値|企業と従業員への効果
予防接種は、この深刻なリスクを軽減するための最も確実な手段です。
特に、その効果は重症化・死亡予防において際立っています。
- インフルエンザ
- 高齢者に対して約80%~82%の死亡を阻止する効果が報告されています。
- 新型コロナウイルス
- 変異株が登場しても、ブースター接種により、未接種者と比較して死亡に対する抑制効果が強化されることが示されています。
予防接種は、従業員の生命と健康を守るという安全配慮義務の精神に合致するだけでなく、死亡や長期離脱という、事業にとって最も深刻なリスクを回避するための合理的かつ費用対効果の高い「投資」であると言えるのです。
企業の意思決定を妨げる二つの疑問
にもかかわらず、多くの企業担当者は、義務ではないがゆえに、以下の二つの実務的な疑問に直面し、判断を迷います。
- 推奨・費用の是非
- 義務ではないが、従業員の接種をどこまで強く推奨すべきか?
- また、費用を補助する是非はどうか?
- 経営判断の根拠
- 補助を見送った場合、企業姿勢やリスクマネジメントの観点から、どのようなデメリットが生じるのか?
企業の予防接種対応|義務と推奨の境界線はどこまでか?
企業の予防接種対策は、「法律上の義務ではないが、会社としてどこまで関与すべきか」という判断に迷うことがほとんどです。
しかし、先に見たように、その裏には年間数万人の命に関わる重大なリスクが潜んでいます。
ここでは、企業が取るべき姿勢を「推奨の是非」と「費用補助の是非」に分けて解説します。
1. 企業は従業員に予防接種を強く推奨すべきか?
結論として、企業は従業員に対し、予防接種を積極的かつ明確に推奨(勧奨)すべきだと思います。
法的強制力はないが、「安全配慮義務」が求める判断
企業は、予防接種の費用補助や接種の強制が法律上の義務ではないことは認識しています(※特殊業務を除く)。
しかし、ここで重要となるのが労働契約法に基づく安全配慮義務の観点です。
法律上の義務がなくとも、企業には従業員が安全で健康に働けるよう配慮する義務があります。
科学的データが示すとおり、予防接種は重症化と死亡という最も重大なリスクを回避する最善策です。
企業が積極的に接種を推奨することは、「業務に大きな支障を出さない」ための当然の配慮であり、感染症リスクから従業員を守るための努力として強く求められます。
推奨を見送った結果、集団感染が発生した場合には、コロナ禍を経験したにもかかわらず、感染症に対する認識の甘さが露呈するリスクを負うことになります。
これは、従業員からの信頼を失い、企業の評判を損なうことにつながりかねません。
2. 企業は予防接種の費用を補助すべきか?
費用補助についても、企業は支払い義務がない(任意である)と分かっています。
しかし、これは事業継続(BCP)のための重要な「投資」として捉えるべきでしょう。
費用対効果から見た費用補助のメリット
予防接種費用の補助は、数千円単位の出費です。
これに対し、集団感染が発生した場合のコストは甚大です。
予防接種の補助費用(数千円)< 従業員一人の長期離脱や死亡による企業の損害
従業員一人が重症化して長期離脱したり、万が一死亡したりした場合、その損失は業務停滞、代替要員の確保、企業の信用毀損など、数千円の補助費用とは比べ物にならないほど大きくなります。
したがって、費用補助は単なる福利厚生ではなく、接種率を向上させるための最も有効なインセンティブであり、事業継続を確実にするための合理的な「投資」であると判断できます。
予防接種費用補助は企業にとって当たり前?実態と意思決定の基準
企業が予防接種費用の補助を検討する際、最も気になるのが「他社がどうしているか」という実態、すなわちベンチマークです。
義務ではないと分かっていても、多くの企業が補助を実施しているという事実が、貴社の意思決定を後押しする確かな根拠となります。
企業の予防接種費用補助率は何%?最新ベンチマーク
インフルエンザワクチン接種の費用補助について、最新の全国的な公的統計は不足していますが、コロナ禍以前のデータと現在の社会的背景から以下の傾向が強く示唆されます。
| 補助状況 | 傾向が示唆する割合 | 示唆 |
| 何らかの補助あり | 過半数(約55%)以上(2020年データ)※ | コロナ禍以前から既に半数以上の企業が補助を実施していました。 |
| 現在の推移 | 増加傾向が確実 | コロナ禍で感染症リスク意識が極度に高まったため、この過半数という割合は現在さらに増加している可能性が極めて高いと判断されます。 |
| コロナ後の実務 | 新型コロナワクチンの費用補助についても、健康保険組合などでは同様の補助が実施される傾向にあり、「費用補助=標準的な対応」という認識が確立しています。 |
※参考|コロナ禍以前(2020年発表など)の企業調査では、インフルエンザワクチン接種費用について「全額負担が約25%、一部負担が約30%」で、合計で約55%の企業が補助を行っていました。
このデータが示す示唆は明らかです。
過半数の企業は、法的義務がなくともリスク回避と福利厚生の観点から補助を実施しており、予防接種費用をサポートすることが「企業の標準的な配慮」となりつつあります。
補助を見送ることは、同業他社や社会からの評価において、「必要なリスク対策を怠っている」と見なされるリスクにつながります。
社会保険労務士として兼業している私の目から見ても、現在の予防接種対策には大きな隔たりがあります。
本業の勤務先では費用補助による積極的な接種推奨が行われていますが、顧問先である中小零細企業の皆様は、コストや手間の面から未だそこまでの意識には至っておりません。
小規模組織こそ一人の欠員が経営に響くからこそ、この現状を打破する必要があります。
予防接種費用補助|企業が選べる具体的な選択肢
補助制度を導入する際は、自社の規模や予算、事務負担を考慮し、最も実効性の高い方法を選択すべきです。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 全額補助 vs. 一部補助 | 全額補助は接種率向上に最も効果的。 一部補助は予算を抑えつつ支援が可能。 | 全額補助は費用負担増。 一部補助は従業員の自己負担が発生する。 |
| 集団接種(現物支給) | 事務処理がシンプル。 接種率が高まりやすく、業務時間内の実施で利便性が高い。 | 実施場所の確保や医療機関との交渉が必要。 日程調整の難しさがある。 |
| 償還払い(自己負担後精算) | 従業員が好きな病院で接種でき、企業側の準備負担が少ない。 | 従業員が一時的に全額立て替える必要があり、領収書の回収・精算事務が煩雑。 |
企業は、接種率を最大限に高め、かつ従業員に「配慮されている」と感じてもらうため、できれば費用負担が最も少ない「全額補助」や、利便性の高い「集団接種」を優先的に検討すべきです。
まとめ|企業が取るべき予防接種支援の最適解|費用補助は投資
これまでの科学的データと実務上のベンチマークを踏まえると、企業の予防接種対策において取るべき道筋は明らかです。
予防接種の推奨と費用補助は、もはや「義務か任意か」の議論ではなく、「持続可能な経営を行うための必須投資」です。
予防接種を積極的に推奨し、費用を補助する
予防接種の費用補助は法律上の義務ではありません。
しかし、年間数万人が亡くなる感染症のリスクが依然として存在する中で、企業が取るべき「最適解」は以下の両側面から明確に導かれます。
- 倫理的責任(従業員の命)
- 重症化・死亡予防効果が科学的に証明されている予防接種を強く推奨することは、労働契約法に基づく安全配慮義務の精神に合致します。
- 従業員の生命と健康を守るという企業の倫理的責任を果たす最善策です。
- 経営責任(事業の安定性)
- 予防接種への数千円の補助費用は、従業員が重症化・死亡することで発生する業務停滞、代替費用、企業信用失墜といった甚大な損害を防ぐための費用対効果の高い保険です。
- 補助を通じて接種率を高めることは、事業継続計画(BCP)の実行そのものであり、経営責任を果たすことにつながります。
法的義務の有無にかかわらず、過半数の企業がすでに補助を実施しているという事実からも、予防接種の支援は「企業の標準的な配慮」として認識されており、導入しないリスクの方が大きいと判断できます。
企業の予防接種制度|次のステップと実行力の確保
推奨と費用補助という意思決定を下したら、次に企業が取り組むべきは「実行力」の確保です。
これは、ただ補助金を出すというだけでなく、従業員が「接種しやすい環境」を整えることを意味します。
- 効果的な制度設計
- 全額補助や集団接種といった、接種率が最も高まる費用補助の形式を決定する。
- スムーズな準備
- 医療機関との連携、業務時間内の接種実施、情報周知の方法など、「面倒だからやめておこう」という従業員の心理的なハードルを下げるための準備に移行すべきです。
感染症リスクがゼロになることはありません。
だからこそ、企業はデータに基づき、「命と事業」の両面から予防に投資するという確固たる姿勢を示す必要があります。
次回予告|マスク着用とオフィス環境の整備
予防接種の科学的な必要性を理解し、費用補助という経営判断を下した企業が次に直面するのは、「日々の実務的な感染対策をどうするか」という課題です。
マスク着用が個人の判断に委ねられた今、企業は従業員の健康と事業継続のために、どのようなルールを設けるべきでしょうか?
次回は、企業が講じるべき「環境整備と行動ルールの最適解」を徹底解説します。
次回の記事は👉企業が取るべき感染症対策|マスク・換気・休憩時の行動ルール
- マスク配布・着用推奨の注意点
- 義務ではない中で、ハラスメントを避けつつ、着用を効果的に促すための推奨方法とは?
- 会議や接客対応時のルール
- 飛沫リスクの高い場面(会議、来客対応)で、企業が取るべき具体的な感染対策ルールを策定します。
- 換気や飛沫防止策のポイント
- 感染リスクの高い冬場も安心できる、オフィスにおける効果的な換気基準と、今すぐできる飛沫防止策の具体例をご紹介します。
お楽しみに。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
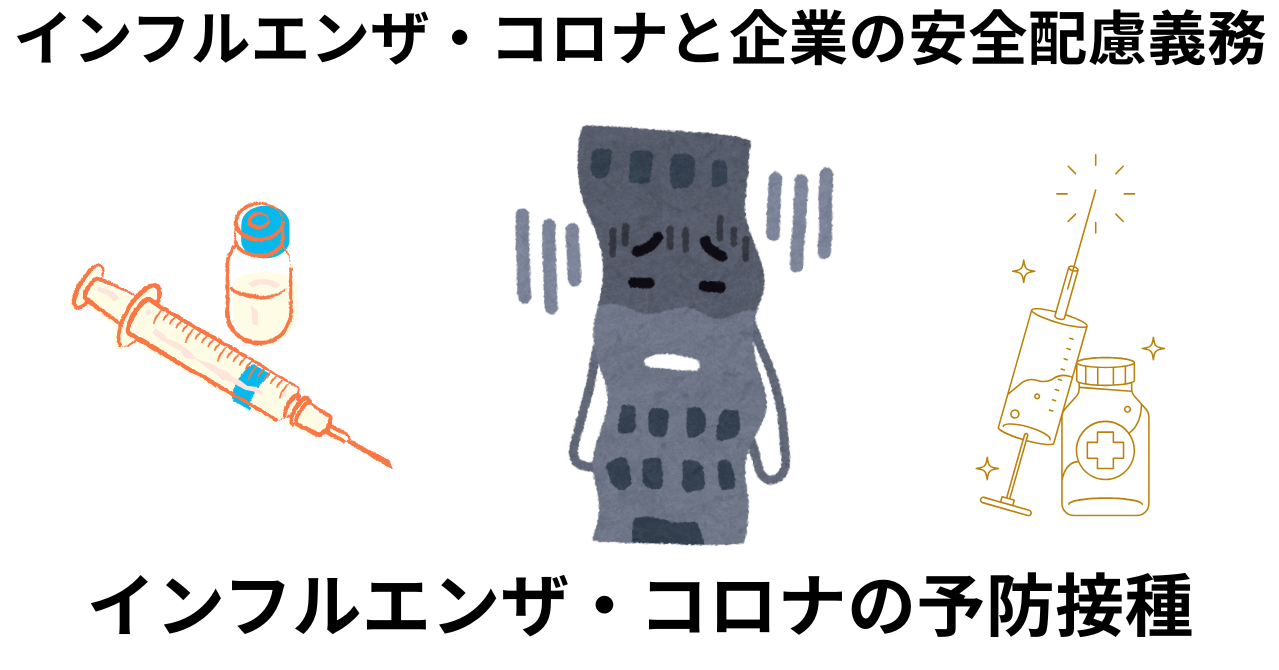

コメント