本記事は「インフルエンザ・コロナと企業の安全配慮義務」シリーズの第4話です。
シリーズの他の記事は👉インフルエンザ・コロナ対策と企業の安全配慮義務|実務ガイド
前回の記事では、季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症といった「5類感染症」に対し、企業が自主的に講じるべき対策を解説しました。
前回の記事は👉企業必見|第5類感染症(インフルエンザ・コロナ)実務的な対策
これらの感染症には法律上の就業制限義務がないため、企業が主体的にルールを定め、従業員の健康を守ることが不可欠でしたね。
しかし、感染症対策はこれで終わりではありません。
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症は、自分だけでなく家族が罹患するケースも多くあります。
もし従業員の家族が感染した場合、企業はどう対応すべきでしょうか?
「濃厚接触」という言葉が日常から薄れた今、この問題にどう向き合うべきか、企業として判断に迷う場面もあるかと思います。
この記事で分かること
- 家族が感染症にかかった場合の企業対応
- 家族が5類~4類の感染症に罹患したときの出勤・休業の判断基準
- 家族の感染リスクを踏まえた事前ルールや多層的防衛ラインの整え方
- 家族の感染対策を通じて従業員の信頼と事業継続を守るポイント
家族が感染した場合の企業対応|出勤可否と休業ルール
また、感染症法には5類以外にも、エボラ出血熱や結核など、より危険度の高い「1類」から「4類」までの分類が存在します。
本記事では、まず従業員の家族が5類に感染した場合の企業が取るべき対応について詳しく解説します。
そして、感染症法上の異なる分類ごとの企業の法的義務と具体的な対処法を、ケースごとに掘り下げていきます。
これにより、いざという時に混乱せず、状況に応じた適切な判断ができるようになります。
家族がインフルエンザに感染したときの企業対応|報告されない現実と多層的対策
「家族が季節性インフルエンザにかかったのですが、どうしたらいいですか?」
こんな風に、従業員が自ら会社に相談してくるケースは、ほとんどありません。
多くの従業員にとって、家族の誰かがインフルエンザにかかることは、さほど深刻な出来事ではありません。
自分の体調に問題がなければ、わざわざ会社に報告するほどの重大なこととは考えていないのが現実です。
しかし、この「さほど大きな出来事ではない」という従業員の感覚と、企業が捉える「事業継続へのリスク」との間には、大きなギャップが存在します。
従業員本人が健康であっても、同居の家族が感染していれば、ウイルスを職場に持ち込むリスクは格段に高まります。
たった一人の従業員がきっかけで社内クラスターが発生すれば、事業の継続が困難になるだけでなく、会社の信用を失うことにもつながりかねません。
企業は、こうした事態に備え、以下の3つの段階的なアプローチで、感染症対策を多層的に講じましょう。
1. 第一の防衛ライン|家族の感染リスクを早期に把握する
感染拡大を未然に防ぐには、症状が出る前の段階での対応が最も効果的です。
そのために、まず「家族が5類感染症に罹患した場合、速やかに会社に報告すること」というルールを、就業規則や社内規定に明確に記載しましょう。
従業員が報告をためらわないようにするためには、プライバシーに配慮した報告体制を整えることも重要です。
例えば、「直属の上司または人事担当者のみに連絡する」「詳細は口頭で簡潔に伝える」など、報告のハードルを下げる工夫も検討しましょう。
このルールは、単なる報告義務の強制ではなく、潜在的な感染リスクを早期に察知し、事業運営を守るための重要なリスクマネジメントであることを、継続的に周知することが大切です。
2. 第二の防衛ライン|従業員本人の「少しの異変」も見逃さない
家族が感染した従業員は、いつ自身に症状が出てもおかしくありません。
そのため、従業員本人の体調に少しでも異変があったら、すぐに対応できる仕組みを整えることが不可欠です。
- 体調チェックの徹底
- 出社時の検温や、毎日の体調チェックリストの記入を義務づけます。
- 明確な行動指針の提示
- 「発熱(37.5℃以上を目安)や倦怠感、咳などの症状がある場合は、出勤せず医療機関を受診すること」といった、具体的な行動基準を明確に定め、就業規則に明記しておきましょう。
3. 第三の防衛ライン|報告後の具体的な対応方法を定めておく
万が一、従業員から体調不良の報告があった場合に備え、その後の対応方法を事前に定めておくことで、現場の混乱を防ぐことができます。
- 一般的なケース
- 多くの従業員は自身の体調が悪ければ自主的に休みます。
- この場合、企業は従業員が安心して休めるよう、有給休暇の取得を推奨しましょう。
- 例外的なケース
- 「同居の家族が感染した、ひょっとしたら従業員自身も感染してるかもしれないが、少しの熱だから大丈夫」と無理に出勤しようとする場合はどうでしょう。
このケースに備え、あらかじめ以下の選択肢を明確にしておくことが重要です。
- 在宅勤務の指示
- テレワークが可能な職種であれば、自宅での業務を命じ、通勤時や職場での感染リスクをゼロにできます。
- 休業の指示
- テレワークが困難な場合は、感染拡大を防ぐために休業を命じます。
- この場合、企業が命じた休業は会社の都合による休業と見なされ、休業手当の支払い義務が発生する可能性がある点に注意が必要です。
これらの対策は、個別の部署や従業員任せにせず、会社全体で取り組むべき課題です。
従業員の健康を守り、事業の正常な運営を維持するために、今こそ現実を踏まえた新しいルールを作り、浸透させていくことが求められています。
家族が5類以外の感染症に罹患したときの行動基準
感染症法上の「家族」に対する直接の制限規定は5類感染以外の感染症でも無いため、論点は「安全配慮義務」と「休業手当の支払い義務」に絞られます。
家族が感染症にかかった場合、企業が取るべき対応は、その病気が感染症法でどのように分類されているかによって大きく異なります。
従業員本人は感染していないが、同居する家族が感染した場合の出勤基準と休業の扱いは、企業が事前に定めておくべき最も重要な行動基準となります。
家族が1類・2類感染症に罹患した場合の対応
家族がエボラ出血熱(1類)や結核(2類)などの重篤な感染症に罹患した場合、企業は極めて慎重な対応が求められます。
従業員本人の出勤基準
- 家族の罹患のみでは、従業員に法律上の就業制限義務はない。
- しかし、感染力や重篤性が高いため、企業は労働契約法上の安全配慮義務に基づき、他の従業員への感染リスクを最大限避ける必要があります。
- 推奨される対応
- 家族が罹患した場合、従業員は濃厚接触者に準ずる扱いとし、一定期間の自宅待機(出勤停止)を命じるのが合理的です。
- 待機期間や解除基準は、保健所の指導に従うべきです。
休業手当の扱い
- 休業手当の支払い義務が発生する可能性が高い。
- 従業員本人に感染症状がなく、企業の安全配慮義務の判断で休業させる場合、「会社の都合による休業」とみなされ、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務が発生します(不可抗力による休業と認められる可能性は低い)。
家族が3類・4類感染症に罹患した場合の対応
コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、狂犬病などが該当します。
これらの感染症は、感染症の種類や状況に応じて就業制限の規定が異なります。
従業員本人の出勤基準
- 家族の罹患のみでは、従業員に法律上の就業制限義務はない。
- ただし、感染経路や感染力が生活に密着していることが多いため、企業は感染症法や厚生労働省の通知を都度確認し、リスクに応じた対応が求められます。
- 推奨される対応
- 感染症の種類に応じて、自宅待機を指示するか、マスク着用、手洗いなどの厳格な感染対策を条件に出勤を認めるかを判断します。
休業手当の扱い
- 企業の判断で休業させる場合は、休業手当の支払い義務が発生します(1類・2類の場合と同様)。
- 国から直接の就業制限命令が出ていない限り、原則として支払いが必要です。
家族が新型インフルエンザ等に感染したときの対応(パンデミック時)
新型コロナウイルスのような新たな感染症が発生し、国が新型インフルエンザ等感染症に指定した場合、状況は一変します。
従業員本人の出勤基準
- 国や都道府県から休業要請・命令が出された場合、企業はこれに従う義務が発生します。
- 命令が出た場合、家族が罹患した従業員本人に対しても、自治体の定める基準に基づく厳しい行動制限が課される可能性があります。
休業手当の扱い
- 国や自治体からの休業命令や要請に基づき休業する場合、企業の責任によらないと認められ、休業手当の支払い義務が発生しない可能性が高まります。
- ただし、これは社会情勢や個別の命令の有無によって判断が分かれます。
新型コロナウイルスが示した教訓
この具体的な例が、2019年から2020年にかけて世界中で大流行した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)です。
当初、新型コロナウイルスは「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられました。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づき、国や自治体から緊急事態宣言や休業要請などが出されました。
この経験は、新型感染症が企業に与える影響の大きさを私たちに再認識させました。
特に注意すべきは、特措法に基づく休業命令が出された場合、企業が労働基準法上の休業手当の支払い義務を負わないとされる点です。
これは、企業側の都合ではなく、公的な命令によって休業せざるを得ないためです。
このように、新型インフルエンザ等感染症は、発生頻度は低いものの、企業に与える影響が甚大です。
日頃から事業継続計画(BCP)に感染症対策を組み込み、緊急時に備えておくことが、企業の重要なリスクマネジメントとなります。
まとめ|企業の感染症対策と従業員信頼の築き方
本記事で解説してきたように、企業の感染症対策は、単に法律上の義務を果たすことにとどまりません。
従業員本人の感染時と並び、従業員本人ではなく、同居する家族が感染症に罹患した場合の対応は、法的リスクの判断が特有の難しさを伴い、企業の安全配慮義務と事業継続における重要な課題となります。
季節性インフルエンザや新型コロナウイルスといった5類感染症には法律上の就業制限義務はありません。
しかし、企業には従業員の健康を守る責任があり、同居家族の罹患時の曖昧な対応は、他の従業員の不安や集団感染のリスクを高めます。
事前のルール策定と柔軟な運用が感染症対策成功の鍵
従業員が安心して働ける環境を整えるためには、以下の2点が不可欠です。
- 就業規則等への明記
- 同居家族が感染症に罹患した場合の出勤停止期間や、休業が必要な場合の有給休暇取得の推奨など、基本的な対応を就業規則やガイドラインに明確に記載しておくこと。
- 臨機応変な対応の確保
- 感染症の分類や社会情勢(例:新型インフルエンザの発生など)に応じて、ある程度の臨機応変さをもって対応できる余地を残し、現場の混乱を最小限に抑えること。
感染症法上の分類を理解し、「同居家族の罹患時も休業手当の支払い義務が発生する可能性がある」といった法的リスクを踏まえたルールを策定しておくことは、従業員を守り、会社の信用を高め、どんな危機にも立ち向かえる強い組織を育むことにつながります。
それは、目先の利益だけでなく、企業の未来を支える確固たる土台となるでしょう。
次回予告|インフルエンザ・コロナの予防接種、企業は費用を補助すべき?
感染症対策として有効な予防策の一つが、予防接種です。
しかし、従業員に予防接種を奨励する際、多くの企業担当者から「予防接種は従業員に強く推奨すべき?」「費用負担はすべき?」といった質問が寄せられます。
次回の記事で、企業が取り組むべき予防接種対策について、深掘りして考えていきましょう。
次回の記事は👉企業はインフルエンザ・コロナ予防接種にどこまで関与すべきか?
来る流行シーズンに向けて、従業員が安心して働ける環境を整える準備を始めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わるさまざまな課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を、はじめての方にもわかりやすく、やさしくお伝えします。









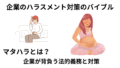
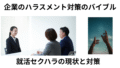
コメント