10時30分 選択式試験スタートしました。
社労士試験 労基法の選択式問題に挑む ― 本番レポート
まずは労働基準法・労働安全衛生法です。
労働基準法をはじめ、労働法はさすがに20年以上サラリーマンをやっていたので勉強の段階でも非常にとっつきやすい科目です。
専門用語に苦しめられることはしばしばありましたが、何とかなりそうだな、という思いみたいなのはありました。
最初の虫食いA、即座に正答がわかる。
いけそうだ。続くB、C。判例問題です。対策は一切していなかったので完全に勘で答えを選びます。
続くD。おそらくこれだろう。いい感じだ。
最後のE。昨年の問題と似たような問題が出ているが、内容は初見でわからない。「1メートル・1.5メートル・2メートル・3メートル」という選択肢。感覚で回答。1.5メートル。
初めての社労士試験 ― 選択式で感じた意外な手応え
順調なのか?次に労災法。
虫食いAB。
嗚呼。令和2年に法改正された部分から出題してます。昨年のテキストを使って勉強をしていた弱点が早速ここで出てしまいました。問題の問いたいことはわかるのですけれども、内容は当然初見です。当然勘で答えます。
続くCDE。わかって答えを書く。
いい感じなのか?意外な手ごたえに俄然やる気が出てきます。
雇用保険法。虫食いAB。どう見ても基本問題です。わかって答えを入れるます。
続くCDE。失業手当の支給認定についての問題。
正直に言うとよくわからなかったのですが、以前失業手当を受給したことがあるという、ただ其の一点だけをよりどころに、考えて解答。
3つの内1問か2問は当たってるのではないか?
社労士試験 労働一般常識(労一) ― 難問に揺れる感情
次は労働一般常識(労一)。
虫食いA。就職氷河期世代とは何歳以上何歳未満か?という問題です。
俺のことやん。これはわかるなぁ。正直に言って、就職氷河期世代がどこからどこまでなんてテキストにも載っていなかったし、考えたこともなっかたのですけれど、自分事として考えればわかります。
私自身が就職氷河期世代の1期生か2期生です。実際大学の1学年上の先輩までは、かなりの大手の企業にバンバン内定もらってましたので、間違いないはずです。だから選択肢の答えとしては「35歳以上50歳未満」を選択しました。
この問いだけ種明かしをするとこれは誤答でした。正解は35歳以上55歳未満だそうです。いまさらどっちでもいいのですが、この問題は未だに個人的に納得はできてません。
まぁ、それはいいとして、続くBCD。助成金の問題。全くわからない。すべて勘で答える。
さらにE。中高齢者等とは何歳以上か?知らん。
感情が揺れ動き始めます。
この労一の問題の5肢は、ひょっとしたら助成金に関しては、細かいところまで見ていけばテキストに載っていた助成金もあるとは思います。
しかし、「テキスト、問題集には載っていないことばかりだったよなぁ・・・これらの労一の問題、俺が勉強不足だから解けないのか、がっちり勉強をして臨んできた受験生でもわからないような問題なのか?」と、答えの出ない疑問が頭をよぎります。
社労士試験|選択式で感じた社一と労一の出題傾向の落差
続く社会保険一般常識(社一)。
虫食いAB。市町村の国民健康保険の問題。全くわからない。
労一を終えたあたりから、危機感がふつふつと湧いてきたのですが、この問いでさらにそれが助長されます。
ヤバい。とりあえず勘で答える。
虫食いC、船員保険の問題。2つまで答えを絞れるが・・・「えーい、こっちやろ」みたいな答え方。
虫食いD、児童手当の問題。これはテキストに載っていた、かどうかはわかりませんが、どこかで覚えていました。
問いE、確定給付企業年金。これもうろ覚えやったけど、たぶんこれ。
社会保険一般常識(社一)は、社労士試験において「鬼門」とされがちな科目ですが、今回の試験ではテキストに掲載されている基本的な内容からの出題が中心だったように感じました。
それに対して、労働一般常識(労一)は、出題内容がかなり難解で、実務経験や時事的な知識しかも細かい知識が求められるような問題も含まれていました。
この2科目の出題傾向の違いを見ると、おそらく作問を担当しているメンバーもきっと違うのでしょうね。
社労士試験|選択式 ― 好感触と勉強不足を実感した瞬間
ここで一息。この時点で11時10分くらいだったのを覚えています。どうなんだろか?
自信があるかどうかと聞かれれば、「ない」と答えるのでしょうが、全くダメということは無いのではないか。
選択式の問題に対して、本気でがっちりと向き合ったのは、この本試験が初めてでした。
もちろん、それまでに過去問には一通り目を通していました。しかし正直なところ、「過去に出た問題がそのまま出るとは思えない」という意識もどこかにあって、深く取り組むことはしていなかったのです。
そうした準備不足のまま迎えた試験本番──社一まで終えた段階で、私はある感覚を持ちました。
それは、「確かに全体で選択肢は20個あるけれど、各問いに対してすべてが候補になるわけではない」ということ。
実際には、「この4つの中のどれかだな」といった具合に、ある程度絞り込める感触がありました。
そのため、「これは何とかなるかもしれない」という淡い希望が芽生えます。
あるいは、「もしかすると、いけているのではないか?」という感覚に陥ってしまいます。──今思えば、これはある種の錯覚でした。
社労士試験|社会保険科目 ― 基本問題中心で手応えをつかむ
続く健康保険法です。なんか、これは?見覚えがありすぎる。試験開始前、眺めていた箇所がそのまま出ているではないですか。また、俄然やる気が出てきます。
厚生年金法。1問だけわからない。でも他の虫食いは、確実のこれだ、という確信は無かったのですが、いやこれしかないでしょ、みたいな感じでした。いい感じだ。
初受験の社労士試験で実感した準備不足と課題
国民年金法。
これが最後の科目なのですが、これは勉強不足を痛感した科目でした。
ABCDEの虫食いに対して、BとEは正答できる。AとCはこの時点での私ならば、間違えても仕方がない。
しかしDは正答しないとな、という問題でした。「給付として支給を受けた金銭を標準」が正答の問題。
- 給付として支給を受けた金銭を基準
- 給付として支給を受けた金銭を標準
- 給付として支給を受けた年金額を基準
- 給付として支給を受けた年金額を標準
1を選んでしまう。この問題は、出題する側からも出しやすい問題でしょう。
今思えばですが、この問題が正答できないのは勉強不足の証みたいなものです。
社労士試験択一式の午後へ向けて、気持ちを切り替える
11時50分 試験終了。
途中退席している受験生もチラホラいました。
労一の問題がすごく印象に残っていました。ああいう問題が出題された状態で、時間内に出来上がって、「いけた」と思って途中退室する受験生がいるんだな。
途中であきらめたのかな、とも考えましたが、どうなのでしょう。
とりあえず、選択式の試験は終わりました。今からあれこれ考えても仕方がない。切り替えて午後からの択一式に向かいます。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
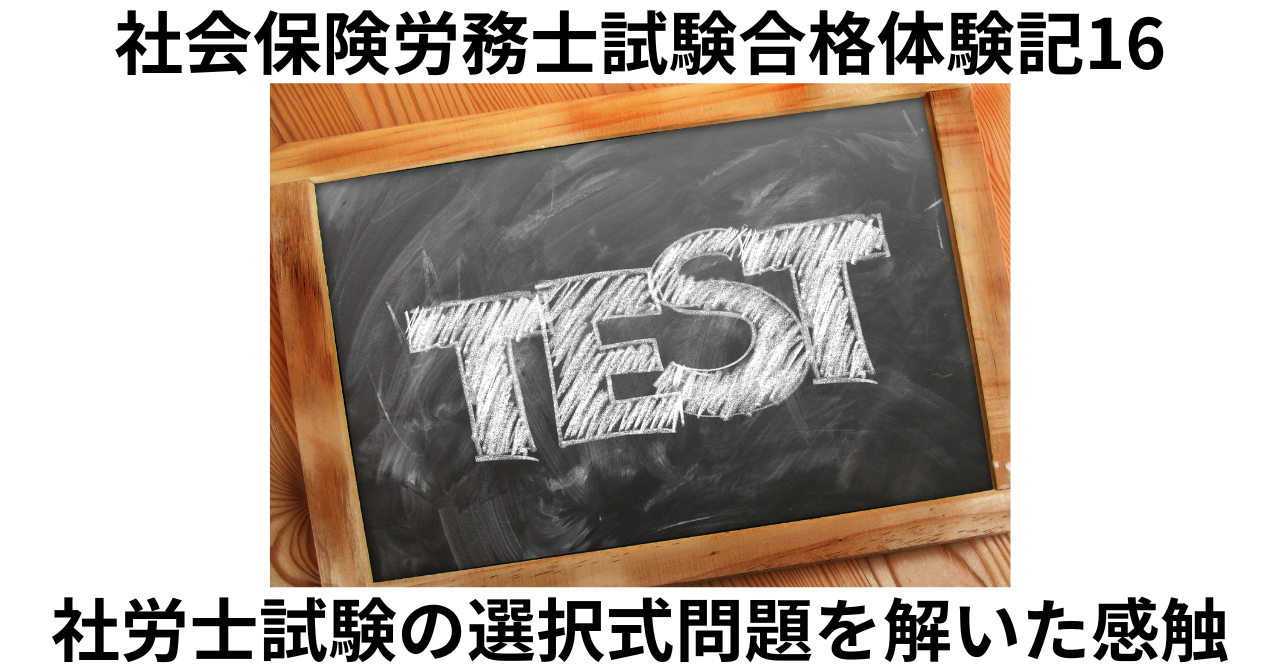
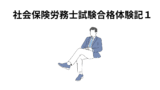

コメント