本記事は「企業のハラスメント対策バイブル」シリーズの第10話です。
前回は採用におけるハラスメントである「就活セクハラ」について解説しました。
前回の記事は👉就活セクハラ対策|2026年法改正対応で企業が取るべき具体策
今回は、企業のコンプライアンスと人材戦略において、今や回避できない重大なリスクである妊娠・出産を理由とするハラスメント、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)に焦点を当てます。
この記事でわかること|マタハラの法的責任と対策戦略
- マタハラの類型|不利益型(降格・解雇)と環境型(精神的嫌がらせ)という法的な二類型
- 法的義務の確立|男女雇用機会均等法、育児介護休業法に加え、最高裁判例により「回避不可能な企業の義務」が確定
- 企業が負う責任|安全配慮義務違反と使用者責任という二重の法的リスク
- 構造的な原因|制度利用による業務のしわ寄せ、意識のギャップ、評価システムの課題
- 実効性のある対策|トップダウンの方針、規則への明確な明記、管理職の実践的研修による組織文化の構築
- 発生時の対応|初動の迅速性、公正な事実認定、厳正な懲戒処分という迅速な対応フロー
マタハラとは何か? 法的視点から見た二つの類型
かつては「寿退社」という言葉に象徴されるように、結婚や妊娠を機に女性が退職することが社会の当然の慣習であり、職場環境の整備は進んでいませんでした。
そのため、妊娠・出産に伴う業務軽減の要求や、雇用継続そのものに対して異議が唱えられ、「問題だ」と認識されることはほとんどありませんでした。
しかし、女性の社会進出が進み、働き続けることが一般的となるにつれてこの問題が顕在化し、法的に厳しく規制される「回避不可能な企業の義務」へと変わっていきました。
マタハラの歴史的経緯と法的整備の変遷をたどり、企業が負う責任の重さを理解することから、実効性のある対策は始まります。
企業が負うリスクを理解するためには、マタハラが単なる嫌がらせではなく、法的に何を指すのかを明確に把握する必要があります。
マタハラは、職場で女性従業員が妊娠・出産・育児に関する制度を利用することや、妊娠していること自体を理由として、精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、不利益な取り扱いをされたりすることです。
マタハラは、行為の性質により、「不利益型」と「環境型」の二つに大きく分類されます。
不利益型マタハラ(制度の利用を妨げる行為)
これは、妊娠・出産や制度の利用(産休・育休の申請や取得など)を直接的な理由として、労働者にマイナスの扱いをすることです。
法律で最も厳しく禁止されています。
| 行為の例 | 法的リスクの核心 |
| 降格・減給・解雇 | 妊娠・出産や制度利用を理由とした人事上の不利益は、最高裁判例でも原則として違法と判断されています。 |
| 不当な配置転換 | 育休明けに、正当な理由なく業務内容やポジションを著しく変える行為。実質的な不利益取扱いとみなされます。 |
環境型マタハラ(就業環境を害する言動)
これは、妊娠中の体調変化や業務軽減の要求に対し、上司や同僚が嫌がらせや心無い言動を行うことで、社員の働く意欲や環境を悪化させる行為です。
| 行為の例 | 法的リスクの核心 |
| 精神的な嫌がらせ | 「妊娠は病気じゃない」「周りに迷惑をかけるな」といった精神的苦痛を与える言動。 |
| 無視・隔離 | 業務軽減を申し出た社員に対し、仕事を与えなかったり、会話を拒否したりして就業環境を悪化させる行為。 |
マタハラに対する法整備の変遷と企業に課せられた「回避不可能な義務」の重み
マタハラ対策が単なる企業の任意から絶対的な義務へと変わった背景には、国の法改正と裁判所の判断があります。
これらの法規制や判決は、加害者個人を罰することを主目的とはせず、企業に環境整備と是正措置を義務づけるものであることを理解することが重要です。
「対処義務」の確立|二大法による規制
マタハラ防止は、男女雇用機会均等法と育児介護休業法という二つの法律によって、企業に包括的に義務づけられています。
| 法律名 | 規制対象と企業の義務 | 該当条文と明記されている内容 |
| 男女雇用機会均等法 | 妊娠・出産などに関する不利益取扱いを禁止し、職場でのハラスメントを防止するための措置義務を課します。 | 第11条の2 事業主は、職場における妊娠、出産等に関する言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
| 育児介護休業法 | 育児休業や子の看護休暇などの制度利用に関する不利益取扱いを禁止し、その制度利用に関するハラスメントを防止するための措置義務を課します。 | 第25条 事業主は、職場における育児休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
【重要な点】
これらの法律が企業に課しているのは「安全な職場環境を維持する義務」であり、マタハラという事態を放置せず、発生を予防・是正することを求めています。
最高裁判例が定めた「不利益取扱いの境界線」
マタハラ対策を語る上で、企業の責任の厳格さと、最適な対応の基準を明確に確立したのは、先ほど触れた法律が定めた義務と、以下の最高裁の具体的な判断が組み合わさった結果です。
最高裁判所第一小法廷判決(平成26年10月23日|広島中央保健生協事件)
最高裁は、妊娠中の女性社員への軽易業務への転換に伴う降格処分の有効性が争われたこの裁判で、以下の判断を下しました。
- 「業務上の必要性」があったとしても、それによって生じる「労働者が被る不利益の程度」を比較衡量し、実質的に不利益となる措置は原則として違法である。
- 企業は、妊娠中の社員の不利益を回避するために、あらゆる努力を尽くしたかを厳しく問われる。
判例の教訓と最適解への指針
この最高裁の判断こそが、男女雇用機会均等法・育児介護休業法という二大法が企業に課した義務を裏付け、「社員に不利益を与えないための実務的な配慮を尽くすこと」が企業の取るべき法的対応の最適解であると確定させたのです。
これらの法律と判例が定める厳格な基準は、企業がマタハラを放置したり、対応を誤ったりした場合に、単なる信用失墜に留まらない「具体的な法的責任」を負うことを意味します。
その法的リスクの正体と、優秀な人材の定着に繋がる具体的な実効性のある対策戦略について解説します。
マタハラ防止|企業の法的責任と実効性のある対策戦略
法規制と最高裁判例によって、マタハラ対策が「努力目標」から「回避不可能な義務」へと変わった今、企業が取るべき行動は明確です。
それは、法的責任を回避しつつ、優秀な女性社員の能力を最大限に引き出すための戦略的な「職場環境の設計」です。
まず、この対策がなぜ必要なのか、マタハラが昨今問題視され、頻繁に発生している構造的な原因から見ていきましょう。
マタハラが問題視され、発生している構造的な原因
マタハラは、単なる個人の意地の悪さではなく、組織の仕組みや社会的な価値観が絡み合って発生する構造的な問題です。
企業の対策は、これらの根本原因を解消することを目指すべきです。
1. 意識・価値観のギャップ(ジェネレーション・ギャップ)
- 専業主婦がデフォルトだった管理職世代の存在
- 多くの管理職や経営層は、女性が結婚や出産を機に退職することが当然だった時代にキャリアを築いています。
- このため、女性社員が「働き続けること」や「制度を利用すること」に対して、特別な配慮や例外的な対応だと無意識に捉えがちです。
- 子育て世代と独身者の認識の違い
- 子育てを経験していない社員は、妊娠中の体調変化の予測不可能性や、育児による時間の制約を具体的にイメージできず、「自己管理ができていない」といった誤った認識を持ちやすいです。
2. 組織構造と制度運用上の問題(負担のしわ寄せ)
- 産休・育休などで他社員の負担が増える
- これがマタハラの最も直接的な原因です。
- 社員が休業や時短勤務に入った際、代替要員の補充がない、あるいは業務の明確な見直しが行われない場合、残った社員に業務がしわ寄せされます。
- この不公平感が、制度利用者への敵意(環境型ハラスメント)として現れます。
- 属人性の高い業務体制
- 特定の社員にしかできない属人性の高い業務が多い職場では、現場の混乱と負担が大きくなり、制度利用者を「組織の混乱の原因」と見なす要因となります。
3. キャリア評価システムの問題(不利益型の温床)
- 時間や物理的貢献度を重視する評価システム
- 成果ではなく、長時間労働や在席時間を重視するシステムが根強い場合、時短勤務者や休業者を自動的に「評価が低い」と見なす傾向があります。
- これが不利益型マタハラ(降格、昇進遅延など)の温床となります。
- 曖昧な配置転換の基準
- 育休からの復帰時に、「軽易な業務」や「配慮」の名目で、キャリアと無関係な部署や閑職に異動させられる「マミートラック」が発生しやすいです。
マタハラに関して企業が負うダブルの法的責任
マタハラが発生し、社員が苦痛を負った場合、企業は加害者個人よりも重い、二重の法的責任を負うことになります。
- 安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
- 企業が社員に対して、ハラスメントを予防・是正し、安全で健康的に働ける職場環境を整備する義務(安全配慮義務)を果たさなかった責任を問われます。
- 使用者責任(民法第715条)
- 上司や同僚(加害者)が業務の執行に関して不法行為を行った場合、企業(使用者)も連帯して損害賠償責任(使用者責任)を負います。
リスクの極大化 |企業の損害の二側面
企業の対応の遅れや放置は、上記の責任に加え、さらに賠償リスクを飛躍的に高めます。
このとき企業が負う損害は、二つの側面に及びます。
- 間接的な信用のコスト
- 企業が世間や求職者から信頼を失うことによるブランドイメージの決定的な失墜。
- これは優秀な人材の獲得難や売上減少など、長期的な経営リスクに繋がります。
- 直接的な金銭的コスト
- 裁判で命じられる損害賠償額(慰謝料や、離職によって失われた賃金など)。
マタハラ予防措置|ハラスメントを許さない組織文化の構築
マタハラ対策の最適解は、構造的な原因を解消し、法的リスクをゼロに近づける「仕組み」を作ることです。企業が取るべき具体的なステップは以下の通りです。
1. トップダウンの方針決定と行動原則の策定
- トップコミットメントの表明
- 経営トップが「マタハラは許容しない」「制度利用はキャリアのマイナスにならない」という強いメッセージを全社に発信します。
- 経営戦略としての位置づけ
- マタハラ防止を優秀な人材の定着に不可欠な経営戦略として位置づけます。
2. 就業規則等への明記と周知活動
- 禁止行為の定義
- 規則に、「不利益型マタハラ」「環境型マタハラ」の具体例を含め、どのような行為がマタハラに該当するのかを明確に記載します。
- 厳正な処分の明記
- マタハラを行った者に対しては、就業規則に基づき厳正に処分する旨を明記し、抑止力を高めます。
3. 継続的な研修と評価システムの是正
- 全従業員向け研修
- マタハラの定義、法的なリスク、そして当事者意識を持つことの重要性をテーマとした研修を義務付けます。
- 管理職向けの実践的研修
- 妊娠中の社員への適切な業務調整と軽易業務への転換、チーム全体の業務標準化・効率化による負担軽減の手法を教育します。
- 評価システムの是正
- 時間や物理的貢献度だけでなく、成果やアウトプットを正当に評価するシステムへと是正し、時短勤務者や育休明けの社員を自動的に「評価が低い」と見なす不利益型マタハラの温床を断ちます。
4. 相談窓口の設置と機能強化
ハラスメントの兆候を早期に発見し、事態の深刻化を防ぐために、機能する相談窓口の設置は企業の義務です。
- 統合窓口の運用
- パワハラやセクハラなどの相談窓口と統合し、一本化して運用することが効率的かつ望ましいです。
- 専門性の確保(人選)
- 窓口担当者は、男女雇用機会均等法や育児介護休業法の規定、特に「不利益取扱い禁止」の判断基準に精通している必要があります。
- 報復行為の禁止の明示
- 相談者や協力者に対して、いかなる不利益な取り扱いも行わないことを明確に保証し、安心して相談できる環境を整備します。
マタハラが発生したら|企業が取るべき迅速な対応フロー
マタニティ・ハラスメント(マタハラ)が発生した場合、企業の対応の迅速性と公正性が、法的な責任の重さと社員の信頼を大きく左右します。
対応を誤るか、迅速さを欠いた場合、それは単なる問題ではなく、企業の信用と財務を脅かす「致命傷」となります。
企業は、「発見・申告」から「再発防止」まで、以下のフローに沿って一刻を争う危機対応を徹底する必要があります。
ステップ1|事態の把握と初期対応(最優先事項)
マタハラの疑いが生じた場合、対応の遅れが安全配慮義務違反の責任を決定づけます。
- 事実関係の速やかな確認(初動が全て)
- 即座に被害者(相談者)から詳細な聴取を行います。
- この初期対応が遅れると、企業がハラスメントを容認したと見なされ、後の使用者責任(民法第715条)回避が極めて困難になります。
- 相談者の心身のケアを最優先とし、必要であれば緊急避難措置(配置転換など)を直ちに講じます。
- 秘密保持の徹底
- 相談内容や相談者の情報は、外部に漏らさないことを明確に保証し、相談者への報復行為は厳禁であることを関係者に周知します。
- 記録の作成
- 初期の聴取内容や対応、関係者への指示を全て詳細に記録に残します。
ステップ2|公正な事実確認(迅速かつ客観的な調査)
調査の遅延や、企業に都合の良い結論への誘導は、危機をさらに悪化させます。
- 調査委員会の設置と迅速な聴取
- 人事部門やコンプライアンス担当者など、中立的な立場の者で構成される調査チームを即座に立ち上げます。
- 行為者(加害者)と第三者の証人への聴取を、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐため、迅速かつ個別に行うことが必須です。
- 事実の認定
- 集めた証拠、被害者の主張、証言などを総合的に判断し、マタハラ行為の有無と内容、深刻度を客観的に認定します。
ステップ3|是正措置と被害回復(公正な処分の実行)
事実が認定されたにもかかわらず、曖昧な処分で済ませることは、再度の安全配慮義務違反を招きます。
- 行為者への厳正な処分
- 認定された事実に基づき、就業規則に定めてある懲戒規定に従って、厳正な処分を直ちに実行します。
- この公正な処分こそが、企業の責任を果たす上で最も重要な要素です。
- 被害者への措置
- 被害者が安心して就業できる環境を回復させるため、配置転換、休職措置、産業医による継続的なケアなどを講じます。
- 行為者と被害者の隔離
- 職場復帰後も、不必要な接触を避けるため、業務上の接触を最小限にするための配置を検討します。
ステップ4|再発防止の徹底(組織文化の改善)
問題が終結したと見なすのではなく、構造的な問題の解消に努めます。
- 原因の特定と対策
- 当該マタハラの原因が、特定の管理職の知識不足なのか、業務のしわ寄せが常態化している組織構造にあるのかを分析し、根本的な解決策を実行します。
- 研修・周知の強化
- マタハラ防止に関する教育や周知活動を全社的に実施します。
- 報復行為の監視
- 処分を受けた行為者や、その関係者が被害者に対して二次的な嫌がらせや報復行為を行わないよう、一定期間、人事部門が状況を注意深く監視します。
承知いたしました。「まとめ」の後に続く「次回予告」の見出しを、内容を明確に伝える形で書き直します。
まとめ|法令と判例が示す厳格な義務|「実務的配慮」の徹底
マタニティ・ハラスメント(マタハラ)対策は、もはや「女性社員への配慮」というレベルの話ではありません。
それは、男女雇用機会均等法(第11条の2)や育児介護休業法(第25条)、そして最高裁判例によって、企業に回避不可能な「法的義務」として課せられた、極めて厳格なリスクマネジメントです。
企業がマタハラを放置したり、対応を誤ったりした場合、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務違反や、民法第715条に基づく使用者責任によって、多額の損害賠償を負うことになります。
さらに、その事実は企業のブランドイメージを決定的に失墜させ、優秀な人材の獲得競争から後退するという、長期的な経営リスクへと直結します。
このリスクを回避し、持続的な成長を実現するための最適解は、「社員に不利益を与えないための実務的な配慮を尽くすこと」に尽きます。
マタハラの根本的な原因である「業務のしわ寄せ」や「価値観のギャップ」を解消するため、企業は、トップダウンの強い方針のもと、就業規則の整備、管理職の実践的な教育、そして成果を正当に評価するシステムへの是正を進める必要があります。
そして、万が一問題が発生した際には、初動の迅速性と公正な懲戒処分が企業の信頼を守る最後の砦となります。
マタハラ防止は、短期的なコストではなく、優秀な女性社員の能力を最大限に引き出し、長期的に定着させるための不可欠な戦略なのです。
次回予告|裁判例から学ぶ、マタハラ問題の「法的グレーゾーン」の判断基準
次回は、今回解説した法的基準が、実際の裁判でどのように適用されたのかを深く掘り下げます。
企業が敗訴したケース、勝訴したケースの具体的な事例を通じて、法的なグレーゾーンにおける企業の具体的な判断基準を徹底的に解説します。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わるさまざまな課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を、はじめての方にもわかりやすく、やさしくお伝えします。








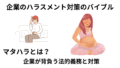
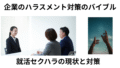
コメント