本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第17話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
前回の記事では、既存の教育訓練給付金(受講費用の一部を支援)について、あなたが給付金を受け取るための手続きを詳しく解説しました。
前回の記事は👉教育訓練給付金の申請手続きガイド|給付金を確実に受け取る方法
そして、2025年10月に施行された、あなたのキャリア形成をより力強く後押しする新たな給付金制度が、この「教育訓練休暇給付金」です。
「長期でスキルアップしたいけれど、無給の休暇を取るのは生活が不安…」
この給付金は、まさにその不安を解消するための制度です。あなたが会社の規定に基づき30日以上連続の無給休暇を取得して学習に専念する場合、その期間の生活費の一部が国から支給されます。
この記事でわかること
- 教育訓練休暇給付金制度の概要|在職中の無給休暇(30日以上連続)で学習する場合に、生活費の一部が国から支給される仕組み
- 受給の基本要件|休暇開始日前の雇用保険期間(通算5年以上など)と65歳未満という必須条件
- 給付額と最大日数|賃金日額の50〜80%が支給される目安と、通算被保険者期間に基づく最大受給日数
- 手続きの鍵|受給の前提となる会社の教育訓練休暇制度の有無の確認と、会社との連携手順
- 期限の厳守|会社がハローワークへ提出する期限と、あなた自身の最終申請期限の徹底管理
教育訓練休暇給付金制度の概要|まとまった学習期間を経済的にサポート
2025年10月からスタートした「教育訓練休暇給付金」は、あなたがデジタル化や産業構造の変化に対応するためのスキルを習得できるよう、国が支援する制度です。
これは、あなたが勤め先の会社の規定に基づき30日以上連続で無給の教育訓練休暇を取得し、指定された訓練を受講する場合に、休暇中の生活費の一部を国が支給する仕組みです。
国がこの教育訓練休暇給付金制度に込める狙い
この制度の最大の目的は、あなたが生活の不安なく学びに集中できる環境を提供し、主体的なキャリア形成を支援することにあります。
具体的には、以下のような目的があります。
- 生活支援とリスキリングの促進
- 雇用保険の被保険者が、無給の休暇中も生活の心配をせずにスキルアップやリスキリングに取り組めるよう支援します。
- 能力開発と雇用の安定化
- 労働者の主体的な能力開発を国として支援し、中高年層や非正規労働者など従来支援が届きにくかった層にも教育訓練の機会を拡大することで、長期的な雇用の安定や再就職支援を強化します。
- 経済活性化への寄与
- 働く人々のスキルアップを通じて、経済全体の活性化と、多様な働き方の実現に貢献します。
この記事では、あなたがこの制度を最大限に活用し、給付金をスムーズに受け取るために必要な「要件」「手続き」「注意点」を整理し、解説していきます。
受給の基本要件|あなたが「教育訓練休暇給付金」を受け取るためのポイント
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者であることを大前提として、以下の要件を満たすことで受給できます。
あなた(労働者)に関する教育訓練休暇給付金受給要件
| 項目 | 詳細な要件 |
| 前提条件 | 休暇開始日時点で雇用保険の被保険者であること。 【注意】 会社を退職すると、雇用保険の被保険者ではなくなります。この給付金は在職中に利用する制度です。 |
| 年齢 | 休暇開始日時点で65歳未満であること。 |
| 雇用保険期間 | 以下の両方の期間を満たしていること。 ➀休暇開始日前の2年間に、被保険者期間が12か月以上あること。 ➁過去の通算で被保険者期間が5年以上あること。 |
| 休暇要件 | 会社の規定(就業規則など)に基づき、教育訓練を目的とした無給の休暇を30日以上連続で取得すること。 |
| 受講対象 | 大学、高等専門学校、専門学校など、または厚生労働大臣等が指定した講座を受講すること。 |
教育訓練休暇給付金給付額と受給できる最大日数
給付金は、あなたが無給休暇を取得した際の生活費の補助を目的としており、失業手当(基本手当)に準じた計算方法が採用されています。
給付額の目安
- 直近6か月の賃金日額の50〜80%が支給されます。
- 給付率は年齢などによって変動し、失業手当と同様に上限額と下限額が設定されています。
受給できる最大日数
給付金を受け取れる最大日数は、あなたの雇用保険被保険者期間(通算)によって異なります。
| 雇用保険被保険者期間(通算) | 最大受給日数 |
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
受給期間は、休暇開始日から原則1年間です。
ただし、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情がある場合は、申請により最大4年まで延長が可能です。
教育訓練休暇給付金給付金の受給のための「手続きステップ」と会社との連携
教育訓練休暇給付金を受け取るには、あなた自身の資格要件を満たすだけでなく、会社が制度を導入し、ハローワークへの手続きを行うことが必須です。
以下のステップと、会社への依頼事項を明確にしましょう。
【最重要】会社の教育訓練休暇制度の有無を確認する
給付金は、会社が「30日以上の無給教育訓練休暇制度」を就業規則に定めていることが大前提です。
まず、人事部や総務部に連絡を取り、会社の体制が整っているかを確認してください。
| 会社の運用体制 | あなたのアクション |
| 導入済み | 利用ルール(申請期限、対象講座など)と、給付金手続きの担当者を確認し、申請準備に入る。 |
| 導入予定・検討中 | 利用開始時期を具体的に確認し、あなたの取得意向を伝えて導入を後押しする。 |
| 導入の予定なし | 残念ながら給付金は利用できません。 制度を導入しても、会社が給付金を直接負担することはないため、導入のメリット(人材定着・スキル向上)を説明し、要望を伝える働きかけが必要です。 |
教育訓練休暇給付金|休暇申請から最終申請までの手続きステップ
会社の制度が利用可能であることを確認したら、以下の4つのステップで手続きを進めます。
ステップ1|休暇の申請と業務調整(会社への依頼)
| あなたのアクション | 会社(担当者)への依頼・確認事項 |
| 会社に教育訓練休暇を申請し、期間や受講内容について合意を得る。 | 円滑な休暇取得のため、業務調整・引き継ぎを協力して行う。 |
ステップ2|重要書類の受取と交付(会社との連携)
| あなたのアクション | 会社(担当者)への依頼・確認事項 |
| 給付金申請の前提となる※「教育訓練休暇取得確認票」の作成と交付を会社に依頼する。 | 会社がこの書類に必要事項を記入し、あなたが申請手続きを進められるよう速やかに交付してもらう。 |
※教育訓練休暇取得確認票は、労働者が用意して会社に提出するものです。
労働者は休暇取得の申請としてこの確認票を会社に提出し、会社側は内容を確認して必要事項を記入し承認します。
会社はその後、休暇開始日から10日以内に賃金月額証明書などの必要書類をハローワークに提出し、ハローワークから交付された給付金申請に必要な書類を労働者に渡します。
労働者はその書類を使ってハローワークに給付金申請を行います。
このように、労働者がまず確認票を会社に提出し、会社が承認・証明する形で手続きが進みます。
「教育訓練休暇取得確認票」は以下からダウンロードできます。
ステップ3|会社によるハローワークへの提出(期限厳守の確認)
会社がハローワークに書類を提出する「期限」は、あなたが給付金を受け取るうえで最も重要です。必ず進捗を確認してください。
| あなたのアクション | 会社(担当者)への依頼・確認事項 |
| 会社が休暇開始日から10日以内にハローワークへ提出する「教育訓練休暇開始時賃金月額証明書」などの書類の進捗を管理し、確認する。 | 休暇開始日から10日以内という期限を会社に再確認し、必要書類をハローワークに提出してもらう。 |
ステップ4|あなた自身による最終申請(給付金受け取り)
最終的な支給申請はあなた自身が行います。
| あなたのアクション | 会社(担当者)への依頼・確認事項 |
| 会社経由でハローワークから交付される「教育訓練休暇給付金支給申請書」を速やかに受け取る。 | ハローワークから交付された申請書を、遅滞なくあなたに渡してもらう。 |
| 支給申請書に必要事項を記入し、受講証明書などを添えて、あなた自身がハローワークに提出する。 | ※申請期限は教育訓練休暇の終了日の翌日から起算して、2ヶ月後の末日までとなります。 |
※もし教育訓練休暇が11月15日に終了した場合、その翌日(11月16日)から起算して2ヶ月後の末日、つまり翌年1月31日が申請期限となります。
この期限を過ぎると、たとえあなたが受給要件を満たし、訓練を修了していたとしても、給付金を受給できなくなります。
【重要】 会社への依頼事項が多くなりますが、すべての書類提出が揃って初めて給付金が支給されます。会社と密に連絡を取り合い、期限を管理することが、給付金を受け取るための鍵となります。
教育訓練休暇給付金|休暇中の留意点とトラブル防止策|安心して学ぶために
教育訓練休暇制度を利用するにあたり、給付金を確実に受け取り、職場との関係を良好に保つためには、あなたが知っておくべき重要なルールと行動があります。
あなたの権利を守る「不利益取扱いの禁止」
教育訓練休暇の取得は、あなたの正当な権利です。
これを理由として会社があなたに対して不利な扱いをすることは、法律で厳しく禁止されています。
- 禁止されている行為の例
- 休暇取得を理由とする解雇、減給、昇進・評価の差別、配置転換(嫌がらせ的なもの)など。
- あなたの行動
- 制度を利用することで不当な扱いを受ける心配はありません。
- もし疑義が生じた場合は、一人で抱え込まず、会社の相談窓口や労働局に相談してください。
会社との信頼関係を保つための協力
あなたの長期休暇は、職場に少なからず影響を与えます。
円滑な制度運用と復帰後の良好な関係のためにも、会社への協力は不可欠です。
- 業務調整への協力
- 休暇が会社の業務に支障をきたさないよう、業務の引き継ぎを丁寧に行い、代行する社員や部署としっかり情報共有しましょう。
- あなたの行動休
- 暇の合意が取れた後も、業務調整や引き継ぎには最後まで責任を持って対応し、職場への誠意を示しましょう。
教育訓練休暇給付金を受け取るための「期限の徹底管理」
給付金が支給されるかどうかは、会社とあなた、双方の書類提出が期限通りに行われるかにかかっています。
特に期限の管理は慎重に行ってください。
- 給付金停止のリスク
- 会社が提出する書類や、あなた自身の最終申請(支給申請書)の期限が遅れると、給付金が受け取れない、または支給が遅れるリスクがあります。
- あなたの行動
- 会社が提出する書類の「休暇開始日から10日以内」という期限や、あなた自身の申請期限を把握し、遅れがないか進捗を注意深く管理しましょう。
疑問や不安は事前に解消する
制度の要件や手続きは複雑な場合があります。
自己判断によるミスを防ぐために、疑問や不明点は必ず解消してから行動に移しましょう。
- 疑問の解消
- 申請書類の書き方、受講講座の対象可否、手続きの期限など、申請・運用中に疑問が生じた場合は、会社の担当者またはハローワークに事前に相談しましょう。
- あなたの行動
- 早めに疑問点を洗い出し、専門機関に確認する姿勢を持つことで、手続きのミスを未然に防げます。
まとめ|教育訓練休暇給付金獲得の鍵は「最初の行動」にあり
教育訓練休暇給付金は、あなたが「仕事」と「学び」の間にあった経済的な壁を取り払い、スキルアップに集中できるように国が用意した制度です。
この制度は、あなたの長期的なキャリア安定と市場価値の向上に直結する大きなチャンスとなります。
教育訓練休暇給付金の受給成功に不可欠な3つのアクション
給付金を確実に受け取り、このチャンスを掴むための鍵は、複雑な手続きを完了させることだけでなく、その準備段階にあります。
- 【大前提の確認】会社の制度導入状況を確認する
- 給付金制度を利用できるかどうかは、会社が「30日以上の無給教育訓練休暇制度」を就業規則に定めているかにかかっています。
- まずは人事部や総務部に連絡を取り、制度の有無や適用開始時期を確認してください。
- 【要件の把握】自身の受給資格を正確に確認する
- 年齢や雇用保険の加入期間(通算5年以上など)といった要件を正確に把握し、自分が制度の対象者であることを確認します。
- 【期限の徹底管理】会社と連携し、期限を厳守する
- 会社がハローワークへ提出する「休暇開始日から10日以内」の書類期限、そしてあなた自身が責任を持つ「休暇終了後の支給申請期限」を必ず管理し、会社と密に連携を取りましょう。
給付金獲得に向けた最初のステップは、「人事部や総務部に連絡を取り、教育訓練休暇制度が就業規則に明記され、運用開始されるかを確認すること」です。
まずはこの「最初の行動」を起こし、あなたの新しいキャリアへの一歩を踏み出してください。
次回予告|学びへの意欲を強力にサポート!「ハロートレーニング」徹底活用ガイド
今回、私たちは「教育訓練休暇給付金」の制度概要や手続きについて詳しく見てきました。
この給付金制度を活用して、あなたがスキルアップに専念できる環境は整いつつあります。
しかし、次に直面するのは「では、何を学べばいいのか?」という疑問です。
そこで次回は、国が費用を負担し、あなたのスキルアップを強力に支援する公的な職業訓練制度、「ハロートレーニング(公的職業訓練)」に焦点を当てます。
- 費用はかかるの?
- 訓練費が原則無料となる仕組みを解説します。
- どんなコースがあるの?
- デジタルスキルから専門技術まで、再就職やキャリアアップに役立つ具体的なコースを紹介します。
- 訓練中の生活は?
- 条件を満たせば、訓練期間中に手当を受け取れる制度(求職者支援制度など)もご紹介します。
給付金制度とハロートレーニングを組み合わせることで、経済的な不安なく、新しいキャリアを築くための第一歩を踏み出すことができます。
次回の記事は👉ハロートレーニングとは?無料で学ぶ公的職業訓練の全体像と種類
どうぞご期待ください!

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
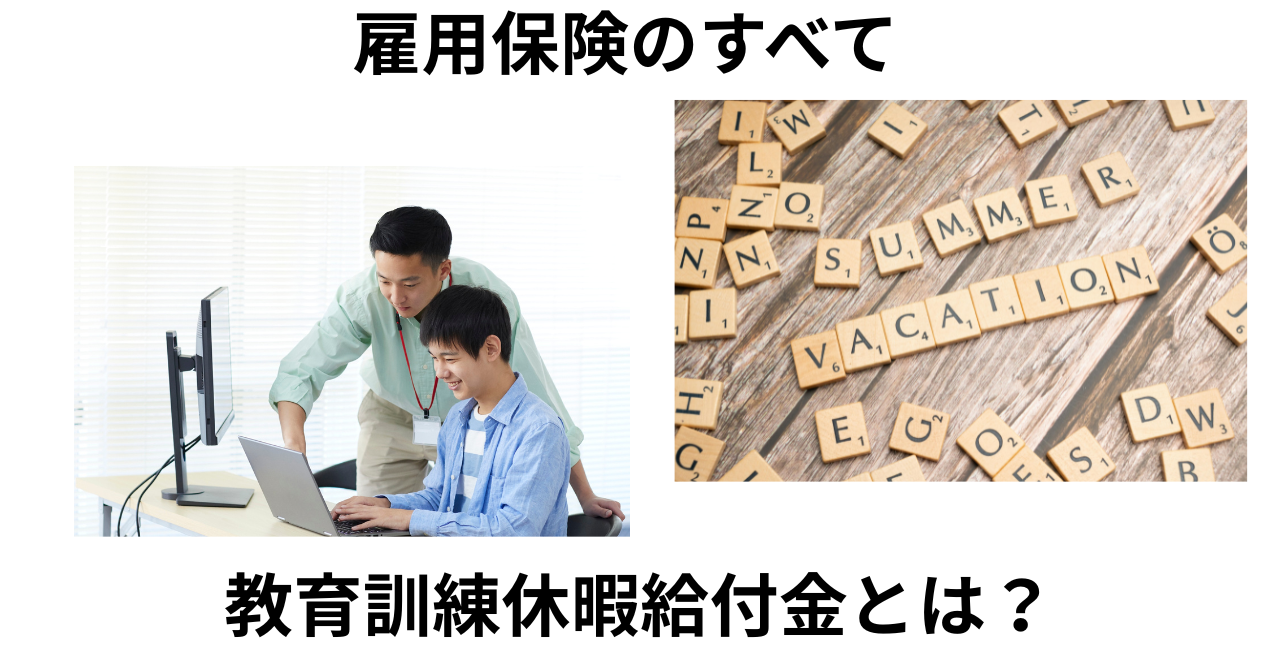

コメント