本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第15話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
皆さま、こんにちは。
失業中の生活を支える雇用保険の制度について、前回は病気や怪我で働けない期間に頼りになる「傷病手当」を解説しました。
前回の記事は👉雇用保険の傷病手当|支給条件・手続き・注意点
雇用保険は、失業手当や傷病手当の他にも、育児や介護など、働き続ける人を多岐にわたってサポートする制度です。
その中でも、あなたのキャリアアップを力強く後押ししてくれる心強い仕組みがあることをご存知でしょうか?
この記事でわかること
- 教育訓練給付金制度の目的|教育訓練給付金が働く人々の主体的な能力開発を支援し、費用の一部を支給する仕組み
- 3つの給付金|一般・特定一般・専門実践の3種類それぞれの支給率と対象講座の違い
- 大前提の条件|雇用保険の被保険者期間(初回利用時1年以上または2年以上)という必須要件
- 特別な条件|特定一般・専門実践給付金では受講前のキャリアコンサルティングが必須であること
- 事前確認の重要性|受給資格は自己判断せず、必ず事前にハローワークで照会すること
教育訓練給付金とは?
「再就職に向けて、新しいスキルを身につけたい」
「キャリアアップのために、専門的な資格を取りたいけど、お金がかかる…」
そう感じているあなたにぜひ知ってほしいのが、今回のテーマである「教育訓練給付金」です。
この制度を賢く利用すれば、経済的な負担を減らしながら、あなたの市場価値を高めることができます。
今回の記事では、この教育訓練給付金がどんな制度なのか、そしてあなたが給付金を受け取るための「支給条件」について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
教育訓練給付金とは、働く人々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するために、厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合に、その費用の一部が国から支給される制度です。
近年、私たちの働き方は大きく変わってきています。
テクノロジーの進化や世の中のニーズの変化に伴い、「ずっと同じ会社、同じ仕事で働き続ける」というキャリアだけではなくなってきました。
転職やキャリアチェンジに関心を持つ人が増え、「学び直し(リスキリング)」の重要性が高まっています。
このような変化に対応し、私たちが自らの意志で新しいスキルを身につけ、キャリアを築いていけるようサポートするため、国はこの教育訓練給付金を設けました。
これは単に生活を保障するだけでなく、変化の時代を生き抜くための自己投資を後押しする重要な仕組みなのです。
3つの教育訓練給付金
教育訓練給付金には、受講する講座の内容や雇用保険の加入期間などに応じて、以下の3つの種類があります。
ご自身の目的や、どのくらい本格的にスキルを身につけたいかに合わせて、どの給付金が適用されるかを確認しましょう。
どのような講座が対象になっているかは、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で調べることができます。
ご自身の興味のある分野や、現在お住まいの地域で絞り込んで検索してみてください。
- 教育訓練講座検索システムURL|教育訓練給付の講座指定について|厚生労働省
1. 一般教育訓練給付金
この給付金は、比較的短期間で取得できる資格や、業務に役立つスキルを身につけるための講座が対象です。
簿記検定、TOEIC、ITパスポートなど、幅広い分野の講座が指定されています。
- 目的
- 現職でのスキルアップや、転職活動に備えるための基礎的な知識・技術の習得。
- 具体的な講座例
- 簿記検定講座、語学学校のTOEIC対策講座、プログラミング入門講座、医療事務講座、介護職員初任者研修など。
- 支給額
- 受講費用の20%が支給されます(上限は10万円)。
2. 特定一般教育訓練給付金
一般教育訓練よりも専門性が高く、より早期の再就職に結びつきやすい講座が対象となります。
特定の国家資格(例:宅地建物取引士、社会保険労務士)や、IT関連の専門的な講座などが含まれます。
- 目的
- 専門的な知識やスキルを習得し、早期のキャリアチェンジや再就職を目指す。
- 具体的な講座例
- 宅地建物取引士講座、社会保険労務士講座、中小企業診断士講座、専門性の高いWebデザインやプログラミング講座など。
- 支給額
- 受講費用の40%が支給されます(上限は20万円)。
3. 専門実践教育訓練給付金
3つの中で最も専門性が高く、中長期的なキャリア形成を支援するための給付金です。
看護師、保育士、理学療法士といった業務独占資格や、高度なITスキルを習得するような、専門学校や大学院の講座が該当します。
- 目的
- 専門性の高い分野でのキャリアアップや、資格取得による大幅なキャリアチェンジ。
- 具体的な講座例
- 看護師養成課程、保育士養成課程、理学療法士養成課程、大学院の専門職学位課程、高度IT人材育成講座など。
- 支給額
- 受講費用の50%が支給されます(年間上限40万円)。
- 「年間上限」とは?
- 看護師や保育士のように、資格取得までに2年や3年といった複数年かかる講座も対象となっています。
- そのため、この給付金は「1年間」で計算される上限額が設定されています。
- 例えば、2年間の講座を受講する場合、最大80万円(40万円×2年)の支給を受けることができます。
- さらに、受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職・転職に成功した場合は、追加で受講費用の20%が支給されます。
- この追加支給は、最初に受け取った50%と合わせて、合計で最大70%(最大支給額は56万円/年)まで給付を受けることができます。
このように、目的や講座の専門性に応じて給付金の支給率や上限額が大きく異なります。
ご自身が学びたい内容がどの給付金に該当するのか、まずは「教育訓練講座検索システム」で確認することが大切です。
支給条件をチェック!あなたは対象者?
教育訓練給付金は、誰もが受け取れるわけではありません。
まずは、あなたが以下の支給条件を満たしているか確認しましょう。
ご自身の状況を把握し、スムーズな手続きに繋げましょう。
大前提となる条件
これからご紹介する条件は、3つの給付金に共通する、最も重要な要件です。
- 雇用保険の被保険者期間(在職者・離職者共通)
- 受講を開始した日時点で、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が一定以上ある必要があります。
- これは、あなたが給与を受け取り、雇用保険料を支払っていた期間を指します。
- 公務員の方は雇用保険の適用対象外となるため、原則としてこの制度を利用することはできません。
- 初めて制度を利用する方
- 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金
- 原則として1年以上
- 例えば、新卒で入社し、勤続6ヶ月で離職したAさんの場合 、Aさんは雇用保険の被保険者期間が1年に満たないため、この時点では給付金を利用することはできません。
- 専門実践教育訓練給付金
- 原則として2年以上
- 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金
- 2回目以降の方
- 前回の給付金を受け取った日から、一定期間(原則3年以上)経過していること。
- 例えば、入社3年目で特定一般教育訓練給付金を利用したBさんが給付金を受け取った後、すぐに別の講座を利用しようと思っても、次の給付金を受け取るためには、そこからさらに3年以上、雇用保険に加入している必要があります。
- 離職中の場合
- 受講開始日時点で離職している方は、離職日の翌日から1年以内に受講を開始する必要があります。
例外的なケースと注意点
上記の条件には、例外的に期間が延長されるケースがあります。
- 離職中の受講開始期限の延長
- 離職日の翌日から1年以内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で30日以上続けて訓練の受講を開始できない場合、その期間を最大20年まで延長できる可能性があります。
このような例外的なケースに該当するかどうか、また最新の正確な情報を把握するためには、ご自身で判断せず、必ず以下の厚生労働省の公式情報や、最寄りのハローワークの窓口で確認してください。
- 厚生労働省・教育訓練給付制度 |教育訓練給付金|厚生労働省
給付金ごとの特別な条件|キャリアコンサルティング
一部の給付金には、上記の他に満たすべき特別な要件があります。
- 特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金
- これらの給付金は、受講前にハローワークでキャリアコンサルティングを受けることが必須です。
これは、あなたが受講しようとしている講座が、将来のキャリア目標に合っているかどうかを専門家と一緒に確認するための大切なプロセスです。
このキャリアコンサルティングを受けずに講座を修了しても、給付金を受け取ることはできません。
キャリアコンサルティングはどこで受けられる?
キャリアコンサルティングは、全国各地のハローワークで受けることができます。
事前の予約が必要となることが一般的ですので、まずは最寄りのハローワークに電話で問い合わせてみましょう。
給付金の申請期限に間に合うよう、余裕を持って早めに予約を取ることが大切です。
【重要】受給資格は必ず事前にハローワークで確認!
ご自身の雇用保険の加入期間や受給資格の有無は、自己判断せずに必ず事前にハローワークで確認しましょう。
ハローワークの窓口で「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出すれば、正確な情報を教えてもらえます。
この事前確認が、給付金を受け取るための第一歩であり、手続きをスムーズに進めるための最も重要なポイントとなります。
まとめ|教育訓練給付金は、あなたのキャリアを後押しする制度
今回は、雇用保険が提供する「教育訓練給付金」について、その制度の概要と、給付金を受け取るための支給条件を詳しく解説しました。
教育訓練給付金は、単なる生活保障ではなく、私たちが変わりゆく時代の中でスキルを磨き、キャリアを切り拓くための心強い制度です。
ご自身の雇用保険の加入期間や、学びたい内容がどの給付金に当てはまるか、ぜひ確認してみてください。
次回予告|給付金を受け取るための申請手続きの流れ
次回は、いよいよ具体的な「申請手続きの流れ」について解説します。
給付金を受け取るための具体的なステップや、必要な書類について一つひとつ丁寧にご説明しますので、どうぞお楽しみに。
次回の記事は👉教育訓練給付金の申請手続きガイド|給付金を確実に受け取る方法

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
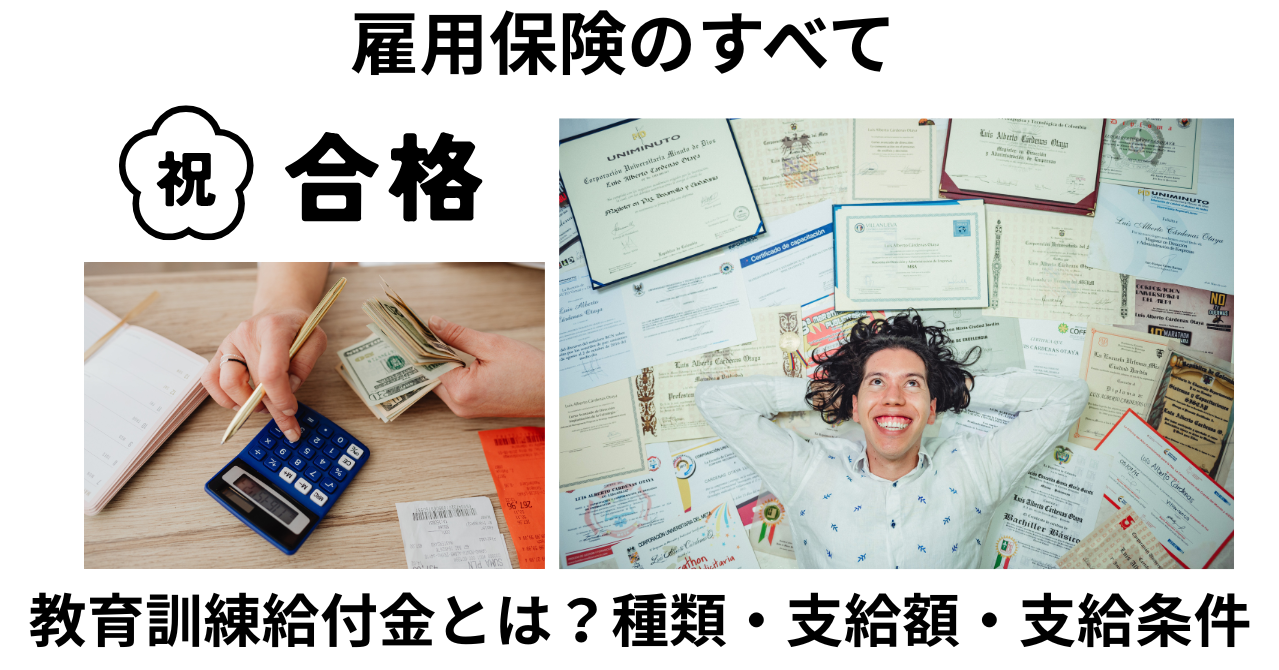
コメント