本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第13話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
前回の記事では、再就職手当を賢く活用することで、早期に新しいキャリアをスタートさせる方法をご紹介しました。
前回の記事は👉再就職手当受給を確実に!8つの支給条件、申請手続き、必要書類
再就職への意欲が高い方にとって、大変心強い制度です。
しかし、再就職活動は常に順風満帆に進むとは限りません。
万全の準備をしていても、思わぬ病気や怪我で思うように求職活動ができなくなることもあります。
本来、失業保険(基本手当)は「働く意思と能力があること」が受給の前提であるため、病気や怪我で働けない期間は支給されません。
「働きたくても働けない」という状況は、経済的な不安をさらに増幅させかねません。
そんな求職者を守るための心強いセーフティネットこそ、今回ご紹介する「傷病手当」です。
この記事では、いざという時に困らないよう、雇用保険の傷病手当の全体像をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 制度の役割|傷病手当が失業手当の「代替」として、求職活動中に働けない期間の生活を保障する仕組み
- 受給期間の延長|病気で働けない期間、失業手当の受給期間がカウントされず、期限が延長される仕組み
- 制度の違い|健康保険の「傷病手当金」とは全く別物であることと、同時受給ができない理由
- 対象となる条件|求職の申し込みをした後で病気が発覚した場合のみ対象となる大原則と具体例
失業中の病気や怪我に備える|傷病手当と失業手当の違いを徹底比較
雇用保険の傷病手当は、失業手当(基本手当)の受給資格を持つ人が、病気や怪我で15日以上継続して働けない場合に、基本手当の代わりに支給される手当です。
これは、あなたが病気や怪我で求職活動を一時的に中断せざるを得ないときに、生活を支えるための重要な制度です。
「傷病手当」という名前がついていますが、これはあくまで失業手当の「代替」として機能します。
この制度を理解する上で最も重要なのが、失業手当との根本的な違いです。
| 項目 | 基本手当(失業手当) | 傷病手当 |
| 制度の目的 | 再就職を支援し、失業中の生活を保障すること | 求職活動中に病気や怪我で働けない期間の生活を保障すること |
| 対象者 | ハローワークで求職の申し込みをした、働く意思と能力のある人 | 基本手当の受給資格者で、求職の申し込み後に病気や怪我で15日以上働けない人 |
| 受給の前提 | 「働く意思と能力」があり、積極的に求職活動を行っていること | 「働く意思はあるが、病気や怪我で働く能力がない」状況であること |
| 給付開始時期 | 待期期間(7日間)満了後 | 待期期間(7日間)満了後、病気や怪我で働けない期間 |
| 必要となる行動 | 積極的に求職活動を行うこと(就職活動実績の報告など) | 療養に専念すること(求職活動は停止) |
傷病手当の受給期間と失業手当の期間比較|何日もらえるかチェック
基本手当と傷病手当は、受給できる期間にも明確な違いがあります。
| 項目 | 基本手当(失業手当) | 傷病手当 |
| 受給期間 | 離職した日の翌日から1年間が原則(ただし、所定給付日数が330日の場合は1年+30日など、延長される場合あり) この期間内に受給を終える必要があります 90日〜360日のあいだで所定給付日数が決まる | 基本手当の所定給付日数から、すでに基本手当が支給された日数を差し引いた日数が上限となります |
つまり、失業手当が「働ける人」を支援する制度であるのに対し、傷病手当は「働きたいのに働けない人」を支援する制度です。
これらの違いを理解することが、制度を正しく利用する第一歩となります。
そもそも「受給期間」とは?
雇用保険の「受給期間」とは、基本手当(失業手当)を受け取ることができる期間の期限を指します。
原則として、あなたが会社を離職した日の翌日から1年間と定められています。
たとえば、離職日が2025年6月30日であれば、受給期間は2026年6月30日までとなります。
この1年間の間に、定められた所定給付日数(例:90日、120日など)をすべて受け取る必要があるのです。
もし、この1年間の期限を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていても、手当は一切もらえなくなってしまいます。
傷病手当による受給期間の延長|具体例
傷病手当を受給すると、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給期間がその分だけ延長されます。
これは、病気や怪我で失業状態と見なされない期間を、受給期間のカウントから除外するためです。
具体例で見る受給期間の延長
ここでは、以下の条件で考えてみましょう。
- 所定給付日数
- 90日
- 基本手当の受給期間
- 原則1年間(離職日の翌日から1年間)
- 病気で働けなかった期間
- 20日間
本来の受給期間
離職日の翌日から1年間の間に、基本手当の90日分を受け取り終える必要があります。
この1年を超えてしまうと、たとえ給付日数が残っていても、手当は支給されなくなります。
傷病手当を利用した場合
あなたが基本手当の受給中に病気になり、20日間働けない状態が続いたとします。
この20日間は、ハローワークに傷病手当を申請して療養に専念します。
この場合、以下のような処理がなされます。
- 基本手当のカウントが一時停止
- 20日間は、基本手当のカウントがストップします。
- 受給期間が延長
- その20日間分、受給期間の期限が延長されます。
結果として、あなたの基本手当の受給期間は「1年+20日間」となり、病気が治ってから改めて残りの日数分の基本手当を受け取ることができます。
このように、傷病手当は、単に療養中の生活を保障するだけでなく、病気や怪我で失業手当がもらえない期間を無駄にせず、その後の再就職活動をしっかりサポートするための重要な仕組みなのです。
知っておくべき大原則|健康保険の「傷病手当金」とは別物!
「傷病手当」という言葉を聞いて、「会社を休んだ時にもらう手当と同じ?」と思った方もいるかもしれません。
しかし、これらは全く別の制度です。多くの方が混同しやすい、この2つの制度を比較してみましょう。
健康保険の「傷病手当金」とは?
まず、健康保険の傷病手当金は、主に会社員が加入する健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)の給付制度です。
- 目的
- 在職中に、業務外の病気や怪我で働けず、給料がもらえない期間の生活を保障するものです。
- 対象者
- 健康保険の被保険者(会社員など)。
- 支給額
- 休業1日につき、おおよそ「標準報酬日額の3分の2」が支給されます。
- 受給期間
- 支給を開始した日から最長で1年6ヶ月間です。
この制度は、退職後も一定の条件(退職日までに1年以上継続して被保険者期間があるなど)を満たせば引き続き受給できる場合がありますが、これはあくまで「在職中の延長」であり、「失業手当」とは別の仕組みです。
雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当金」との違い
一方、雇用保険の傷病手当は、失業手当の受給者を対象とした全く別の制度です。
| 項目 | 健康保険の傷病手当金 | 雇用保険の傷病手当 |
| 対象者 | 会社の健康保険に加入している会社員など | 雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格者 |
| 制度の目的 | 在職中に、業務外の病気や怪我で働けず、給料がもらえない期間の生活を保障する | 失業手当の受給中に、病気や怪我で求職活動ができない期間の生活を保障する |
| 受給期間 | 最大で1年6ヶ月間 | 基本手当の所定給付日数が上限 |
このように、両者は目的も管轄も全く異なる制度であり、同時に受け取ることはできません。
健康保険の傷病手当金は、「働くことができない」状態を保障するものですが、失業保険は「働く意思と能力がある」ことが受給の前提です。
失業手当の受給資格を得た時点で、その「働くことができない」状態が解消されたとみなされることが一般的であり、健康保険の傷病手当金の支給は原則として終了します。
ご自身の状況がどちらに当てはまるのかを正しく把握し、制度を混同しないことが非常に重要です。
病気や怪我で退職した場合も雇用保険の傷病手当はもらえるのか?
「病気や怪我で会社を辞めた場合、雇用保険の傷病手当はもらえるの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。
この場合の答えは、「失業手当の受給資格を得た後でなければ、対象にはならない」です。
雇用保険の傷病手当は、あくまで「失業手当の受給資格者」が対象となる制度です。
したがって、まずはハローワークで求職の申し込みを行い、失業手当の受給資格を得る必要があります。
具体的なケースで考えてみましょう。
ケース1|退職後、失業手当の手続きを終えた後に病気が発覚した場合
- この場合は、すでに失業手当の受給資格を得ており、「働く意思と能力」がある状態でハローワークに登録しています。
- そのため、その後の病気や怪我で働けなくなった期間は、傷病手当の対象となりえます。
ケース2|退職前から病気や怪我の療養に入っており、現在も働けない状態が続いている場合
- この場合は、そもそも「働く意思と能力がある」という失業手当の受給条件を満たしていません。
- 「働く意思はある」けれども「働く能力」が現状ではない、という状態です。
- ハローワークは、こうした状態を「失業」とは認めません。
- そのため、失業手当の受給資格自体が認められず、結果として傷病手当も支給されません。
ケース3|退職したときは健康だったが、ハローワークに行く直前に病気や怪我になった場合
- この場合も、ハローワークに求職の申し込みができていないため、「働く意思と能力」がある状態とみなされません。
- そのため、傷病手当の対象外となります。
- まずは病気や怪我を治し、働くことができる状態になってから、改めてハローワークに求職の申し込みを行う必要があります。
ケース4|待期期間中(求職の申し込みから7日間)に病気等になった場合
- 待期期間とは、求職の申し込みをした日を含めて7日間を指します。
- この期間に病気や怪我になった場合、その後の状況によって手続きや手当の有無が変わります。
- 待期期間満了後も引き続き動けない状態だった場合
- 待期期間満了日の翌日以降も働けない状態が続く場合は、その日から「傷病手当」の対象期間となります。
- 待期期間中に病気が治り、動けるようになった場合
- この場合は、傷病手当は支給されません。
- 待期期間中に病気が治ったということは、7日間のうちに「働く意思と能力」が回復したとみなされるからです。
- この場合は、通常の失業手当が支給されます。
ケース5|給付制限期間中に病気や怪我になった場合
- 自己都合退職などにより、通常1ヶ月間の給付制限期間がある場合があります。
- この期間は、失業手当の給付が行われません。
- この給付制限期間中に病気や怪我で働けなくなった場合、その期間は「働く意思と能力がない」状態とみなされます。
- 給付制限期間が終わった後に改めて求職活動ができる状態に戻ってから、失業手当の給付が始まります。
- つまり、給付制限期間中に病気や怪我をしても、その期間は傷病手当の対象にはなりません。
- 傷病手当は、あくまで「基本手当の支給が開始された後」に、病気等で求職活動ができなくなった場合に適用される制度であるためです。
結論として、雇用保険の傷病手当を受給するためには、まず病気や怪我を治し、「働ける状態」になってからハローワークで求職の申し込みを行うことが大原則となります。
その時点で初めて、失業保険の給付制度の対象者となるのです。
雇用保険の傷病手当は、失業手当受給中の万が一に備えるための制度であると覚えておきましょう。
まとめ|不安な時期を乗り越えるための「傷病手当」
ここまで、失業手当を受給している期間に病気や怪我をした場合に頼りになる「傷病手当」について、その概要と失業手当・健康保険の制度との違いを詳しく解説してきました。
再就職活動中の予期せぬ出来事によって、あなたの生活が不安定になるのを防ぐための大切な制度です。
- 「失業手当」は、働く意思と能力がある人が対象です。
- 「傷病手当」は、働く意思はあるけれど、一時的に働けない人が対象です。
この2つの制度は、それぞれ異なる目的と役割を持っているため、混同しないことが非常に重要です。
万が一、再就職活動中に病気や怪我をしてしまった場合は、まずは療養に専念し、回復後にハローワークに相談してください。
自己判断で手続きを進めると、本来受け取れるはずの手当がもらえなくなる可能性もあります。
傷病手当は、あなたが安心して治療に専念し、再び前向きに再就職活動に戻るための大きな支えになります。
この制度を正しく理解し、新しいキャリアのスタートに力強く臨みましょう。
次回予告|雇用保険傷病手当の支給額・申請手続き・受給期間の注意点
ここまでで「傷病手当」の制度の概要と、どんな状況なら対象になるのかをご理解いただけたかと思います。
しかし、実際に手当を受け取るためには、具体的な手続きが必要です。
- 「もらえる金額はいくらになるの?」
- 「ハローワークへの申請手続きはどうすればいいの?」
- 「必要書類は何を準備すればいいの?」
次回の記事では、こうした具体的な疑問にお答えします。
第2弾として、「傷病手当」の支給額の計算方法、申請手続きの流れ、そして受給期間中の注意点を徹底的に解説します。
次回の記事は👉雇用保険の傷病手当|支給条件・手続き・注意点
いざという時に困らないよう、知っておくべきポイントを詳しくお伝えします。
どうぞお楽しみに。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
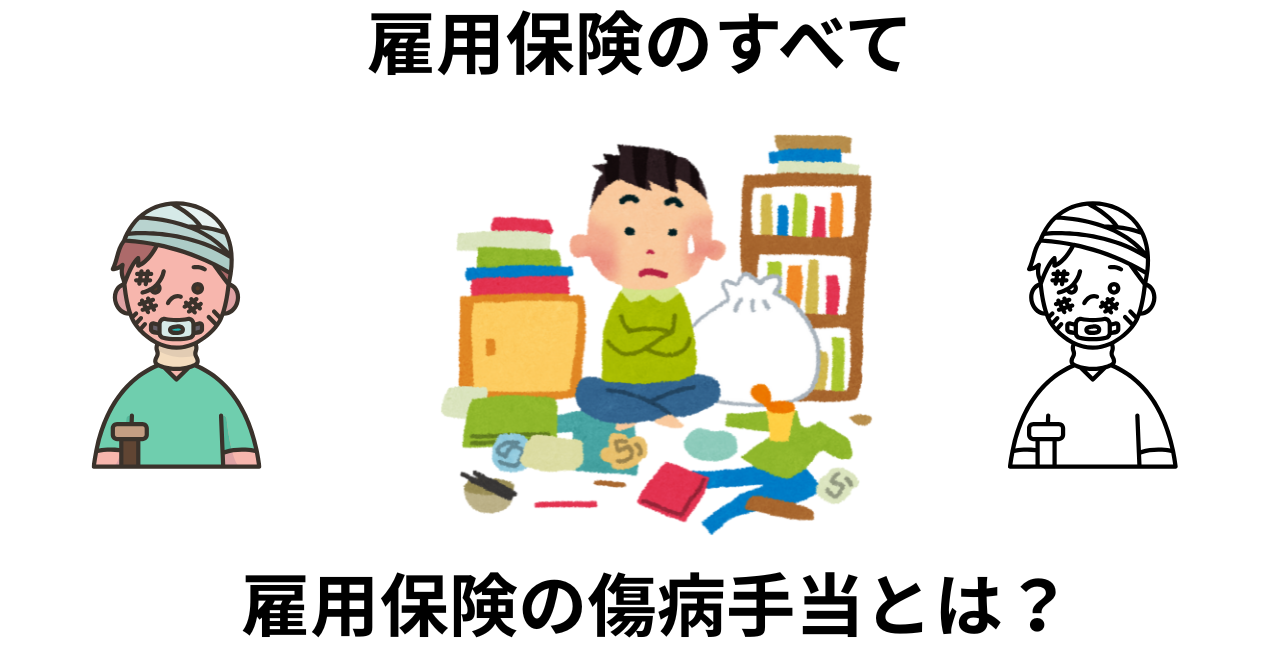
コメント