本記事は「企業のハラスメント対策バイブル」シリーズの第4話です。
前回の記事では、パワーハラスメントが単なる「嫌がらせ」ではなく、企業に深刻な法的・経営的リスクをもたらすことを、具体的な裁判例を通して解説しました。
前回の記事は👉パワハラの裁判例から学ぶ|企業が負うリスクを徹底解説
2020年6月のパワハラ防止法(正式には「労働施策総合推進法」)施行から数年が経ち、企業はパワハラ防止の措置を講じることが義務となりました。
多くの職場では研修や相談窓口の設置が進み、ハラスメントに対する意識は以前より高まっています。
しかし、その効果はまだ道半ばです。
この記事でわかること
- パワハラの根本原因|個人の無自覚と組織のストレス・閉鎖的風土による問題の構造
- 相談件数の意味|法整備により潜在的な問題が表面化したことと、予防策の一定の効果
- 企業が実践すべき対策|パワハラを予防・解決するための具体的な5つのステップ
- 5ステップの内容|就業規則、研修、相談体制、事実確認、組織風土改善の具体的な行動
- 対策の目的|ハラスメント対策は、心理的安全性と企業成長のための未来への投資であること
ハラスメントはなぜ消えないのか?その根本原因を理解する
厚生労働省の「総合労働相談コーナー」に寄せられた相談件数を見ると、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は依然として高い水準で推移しています。
これは、ハラスメントが職場の大きな問題であり続けていることを示しています。
| 年度 | いじめ・嫌がらせ(パワハラ)関連相談件数 |
| 令和元年度(2019年) | 87,580件 |
| 令和2年度(2020年) | 82,797件 |
| 令和3年度(2021年) | 86,034件 |
| 令和4年度(2022年) | 82,965件 |
| 令和5年度(2023年) | 80,024件 |
※出典|厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」より
「法律ができたのに、なぜ減らないのか?」と疑問に思うかもしれません。
しかし、このデータには重要な背景が隠されています。
パワハラ問題の顕在化|相談件数の推移から読み解くポイント
これまでの社会では、「厳しい指導」や「職場の慣習」として、多くのハラスメントが水面下に隠されていました。
被害者が声を上げても解決しない、あるいは声を上げる勇気すらない、そうした諦めが根底にあったのです。
しかし、パワハラ防止法の施行は、この状況を大きく変えました。
法律によって「これはハラスメントだ」と明確に認識する人が増え、相談窓口が整備されたことで、これまで隠れていた問題が初めて表面化する大きなきっかけとなりました。
この状況下で、相談件数が大幅に増加しなかっただけでなく、わずかではありますが微減傾向が見られることは、決してネガティブな兆候ではありません。
潜在的な問題が表面化したにもかかわらず、件数が爆発的に増えなかったことは、企業が講じた予防策が一定の効果を上げている証拠と解釈できます。
しかし、これはまだスタートラインに立ったに過ぎません。
ハラスメントを根絶するためには、その根本的な原因を深く理解し、アプローチすることが不可欠です。
ハラスメントは、以下の二つの要因が複雑に絡み合って生まれます。
1. 個人の要因|無知と無自覚が招くパワハラ行為
ハラスメント行為の多くは、加害者に悪意がないケースが少なくありません。
彼らは、自身の言動が他者を傷つけ、法的リスクに晒すハラスメントであるという認識がないまま行動してしまいます。
これは、以下の2つの点に起因します。
- ハラスメントの定義を正しく知らない
- 「厳しい指導」と「パワハラ」の線引きを理解しておらず、旧来の価値観に基づいた指導方法を続けてしまう。
- 自身の言動がハラスメントになっていると気づかない
- 相手の表情や態度から不快感に気づくことができず、一方的な価値観を押し付けてしまう。
2. 組織風土による要因|パワハラを助長する職場環境と組織文化
個人の意識改革だけでは、ハラスメントを根絶することはできません。
組織そのものに問題があれば、ハラスメントは繰り返し発生します。
ハラスメントを助長する組織風土には、以下のような特徴があります。
- 過度なストレス
- 恒常的な長時間労働や、達成不可能なノルマ設定など、過剰なストレスは従業員の心理的余裕を奪い、他者への攻撃性を高めます。
- 閉鎖的な環境
- 意見が言いにくい、風通しが悪い、上司への異論が許されないといった閉鎖的な組織風土は、不適切な言動を抑止する力が働きにくくなります。
- 問題への曖昧な態度
- 会社がハラスメントを「個人の問題」として放置したり、相談窓口が形骸化していたりする場合、被害者は声を上げにくくなり、加害者も「大した問題ではない」と誤解します。
パワハラ防止法は、こうした潜在的なハラスメントを表面化させる大きなきっかけとなりました。
しかし、その先にある根本的な原因、つまり「個人の意識」と「組織の構造」に踏み込まなければ、本当の意味でのハラスメントのない職場は実現できません。
これらの要因を解消するために、具体的にどのような予防策と解決策を講じるべきかを掘り下げていきます。
企業が実践すべきハラスメント防止の5つのステップ
ハラスメントは、あなたの会社に計り知れないリスクをもたらすだけでなく、従業員のパフォーマンスや企業の成長をも阻害する深刻な問題です。
ここでは、ハラスメントをなくすための具体的な取り組みを、確実に成果につながる5つのステップとして体系化しました。
このフローは、パワーハラスメントはもちろん、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントなど、あらゆるハラスメントの予防と解決に共通して活用できるものです。
この5ステップを理解し、実践することで、あなたの会社はハラスメントのない、健全で活力のある職場へと変わっていくでしょう。
Step1|就業規則にハラスメント防止ルールを明記する
まず、ハラスメントが「許されない行為」であることを社内外に明確に示すためのルールを確立します。これがすべての土台となります。
- 就業規則への明確な記載
- パワハラ6類型をはじめ、どのような行為がハラスメントに当たるのかを具体的に明記します。
- また、懲戒処分の内容や相談窓口についても定めます。
- 「ハラスメントは許さない」という組織の意思表示
- 規則を定めるだけでなく、経営層が主体となってこのルールを社内外に強く発信します。
Step2|研修で学ぶパワハラ防止と職場の心理的安全性
次に、定めたルールを従業員全員に浸透させ、一人ひとりの意識を変えるための教育を行います。
- 全従業員向け研修
- ハラスメントの定義や法律上のリスクを学び、「被害者にも加害者にも傍観者にもならない」という意識を共有します。
- 管理職向け研修
- 「厳しい指導」と「ハラスメント」の明確な線引き、適切なコミュニケーション手法などを重点的に習得します。
Step3|評価制度と相談窓口でハラスメント防止体制を整備
個人の意識に頼るだけでなく、ハラスメント防止の取り組みを制度として定着させます。
- 人事評価制度の見直し
- パワハラ防止への貢献度を評価項目に加えるなど、ハラスメントをしないことが昇進・昇格の前提条件であることを明確にします。
- また、360度評価を導入し、管理職の行動を客観的に把握します。
- 相談窓口の設置
- 社内だけでなく、外部の専門家と連携した窓口を設置することで、相談の選択肢を広げ、安心感を高めます。
- プライバシー保護の徹底
- 相談内容が漏れることや、相談した従業員が不利益な扱いを受けないことを厳格にルール化し、周知します。
Step4|ハラスメントの事実確認と証拠収集のポイント
相談があった場合、迅速かつ公正に事実関係を調査します。
このステップを怠ると、組織への信頼が大きく損なわれます。
- 事実確認の徹底
- 被害者、加害者、目撃者などから丁寧にヒアリングを行います。
- 客観的な証拠収集
- メールや音声記録など、客観的な証拠を収集し、事実関係を総合的に判断します。
Step5|ハラスメントの再発防止と組織風土改善の方法
最後に、ハラスメントの事実が確認された場合、適切な処分を行うとともに、再発防止のための根本的な対策を講じます。
- 適切な処分の実施
- 就業規則に基づき、加害者に対する処分を決定・実行します。
- 組織風土の改善
- ハラスメントの背景にあった、過度なストレスや閉鎖的な環境といった構造的な問題に目を向け、業務負担の軽減やチームビルディングを通して、風通しの良い職場づくりを推進します。
まとめ|ハラスメント対策は企業成長の投資|職場改善の重要性
これまでの解説で、ハラスメントがなぜ、そしてどのようにして職場で発生するのか、その根本原因を理解していただけたのではないでしょうか。
単なる個人の無自覚や悪意だけでなく、組織の構造的な問題がハラスメントの温床となっているのです。
しかし、ハラスメントは決して根絶できない問題ではありません。
今回ご紹介した「5つのステップ」を体系的に実践することで、予防から解決、そして再発防止までを確実に進めることができます。
ハラスメント対策は、単に法律を遵守するための義務ではありません。
それは、従業員が安心して能力を発揮できる「心理的安全性」の高い職場を築くための、企業にとって不可欠な「未来への投資」です。
健全な職場環境は、従業員のエンゲージメントと生産性を高め、結果として企業の持続的な成長を可能にする最も重要な基盤となります。
次回予告|ハラスメント防止5ステップを段階的に深掘り
次回は、今回ご紹介した「ハラスメント対策の5ステップ」を1つずつ丁寧に深掘りしていきます。
「Step 1: ルールを定める」から始め、今日からでも実践できる具体的な方法を詳しく解説します。どうぞお楽しみに。
次回の記事は👉パワハラ防止の実践|対策5ステップ|ルール作りと意識改革
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
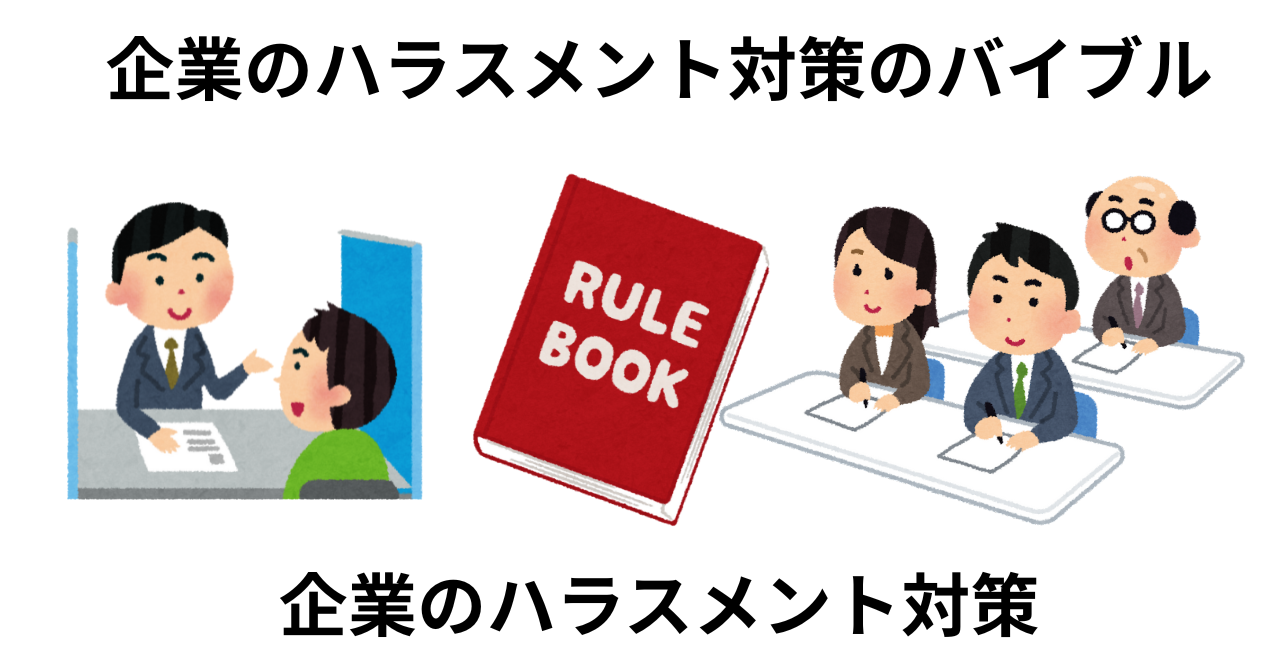

コメント