本記事は「企業のハラスメント対策バイブル」シリーズの第1話です。
ハラスメント対策は、もはや企業の努力目標ではありません。
2020年に施行された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、大企業ではすでに、中小企業でも2022年4月から、ハラスメント対策を講じることが法的に義務化されました。
この法律は、パワハラだけでなく、関連する男女雇用機会均等法や育児・介護休業法と連携し、セクハラやマタハラ、パタハラなども含めた包括的なハラスメント対策を企業に求めています。
さらに、近年問題となっているカスハラ(カスタマー・ハラスメント)についても、労働契約法に基づく企業の安全配慮義務から、対策を講じるべき重要な課題とされています。
ハラスメントを放置することは、もはや個人のモラルに委ねられる問題ではなく、企業が健全に存続するための必須条件なのです。
この法改正は、ハラスメントが企業の存続に関わる重大な経営リスクであるという、社会全体の認識の高まりを反映しています。
この記事でわかること
- ハラスメント対策の法的な位置づけ|パワハラ防止法などによる、全企業での対策義務化とその背景
- ハラスメント放置の経営リスク|人材流出や生産性低下など、企業存続に関わる具体的な悪影響
- 企業が講じるべき法的義務|各種ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ)に対応するための具体的な措置
ハラスメント放置が企業にもたらす存続リスク
ハラスメントを放置すると、単に個人の問題で済まされません。
被害者の離職や生産性の低下、そして企業の評判悪化といった深刻な事態を招きます。
SNSでハラスメントの実態が瞬時に拡散される現代では、一度失墜した企業イメージを取り戻すことは非常に困難です。
このように、ハラスメント対策は単なる法令遵守の「コスト」ではなく、健全な組織文化を育み、企業の持続的成長を支えるための重要な「投資」なのです。
ハラスメントが企業経営に及ぼす3つの具体的リスク
ハラスメントが企業に与える悪影響は、単に個人の問題に留まりません。
それは、組織全体の健全な機能、そして企業の持続可能性そのものを脅かす深刻な経営リスクです。
以下に、ハラスメントが企業にもたらす具体的な3つのリスクを解説します。
リスク1|人材流出リスク|ハラスメントが引き起こす離職と採用コスト増
ハラスメントは、従業員にとって深刻な精神的・肉体的負担となり、その結果として離職率の増加を招きます。
上司からのパワハラ、同僚からのセクハラやマタハラに耐えかねた社員が退職を決意するケースは後を絶ちません。
一度離職者が増え始めると、企業は新たな人材を確保するために、膨大な採用コスト(求人広告費、面接や新人教育にかかる人件費など)を投じることになります。
また、退職した社員がSNSや口コミサイトでハラスメントの実態を公表した場合、企業の評判は急速に悪化し、優秀な人材が集まらないという悪循環に陥ります。
リスク2|生産性低下リスク|ハラスメントが組織力を弱める影響
ハラスメントは、被害者だけでなく、周囲の従業員にも悪影響を及ぼします。
恐怖心やストレスから、被害者は業務への集中力を失い、生産性が著しく低下します。
さらに、ハラスメントを目の当たりにした周囲の従業員は、「次は自分が被害に遭うかもしれない」という不安や、「見て見ぬふりをするしかない」という無力感に苛まれます。
その結果、チーム内でのコミュニケーションが停滞し、自由な意見交換や協力体制が失われます。
これは、単なる個人の問題ではなく、組織全体のチームワークやイノベーションを阻害し、組織力そのものを弱体化させる深刻な事態です。
リスク3|企業イメージの失墜リスク|ハラスメントによる法的問題
ハラスメントを放置した企業は、被害者からの訴訟リスクに直面します。
裁判でハラスメントの事実が認められれば、企業は多額の損害賠償を命じられることになります。
加えて、こうした問題はマスメディアやSNSで広く報道・拡散され、企業名が公に晒されることになります。
一度失われた社会的信用を取り戻すことは非常に困難であり、顧客からの信頼を失い、顧客離れや株価の下落につながる可能性も否定できません。
これは単なる金銭的な損失に留まらず、企業の存続そのものを脅かすリスクなのです。
企業が知っておくべき|ハラスメント防止の法的義務
ハラスメント対策は、企業の倫理観だけでなく、法律によって厳格に定められた義務です。
企業がハラスメント対策を講じる根拠には、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」があります。
これは、企業が労働者の生命、身体、または健康を危険から保護するように配慮する義務を定めており、ハラスメントによる労働者の心身の健康被害を防ぐことも含まれます。
ハラスメント対策は、企業の倫理観だけでなく、法律によって厳格に定められた義務です。
特に以下の法律は、すべての企業が理解しておくべき重要なポイントです。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の義務と企業対応
この法律は、パワーハラスメントの防止措置を企業に義務付けています。
しかし、この法律がハラスメント対策全体の中心的な役割を担っており、厚生労働省の指針では、セクハラやマタハラを含む他のハラスメントについても、この法律の枠組みの中で一体的に対応することが望ましいとされています。
施行日: 大企業は2020年6月1日、中小企業は2022年4月1日より義務化されました。
法律が求める主な措置
- 方針の明確化と周知
- ハラスメントは許されないという方針を就業規則などに明記し、従業員に周知・啓発します。
- 相談体制の整備
- 相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる体制を整えます。
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 相談があった場合は、速やかに事実関係を確認し、加害者への懲戒処分や、被害者への配慮措置を講じます。
- プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止
- 相談したことなどを理由に従業員に不利益な扱いをしないことを徹底します。
男女雇用機会均等法|セクハラ・マタハラ防止の企業義務
この法律は、セクシャルハラスメント(セクハラ)や、妊娠・出産・育児休業等に関するマタニティハラスメント(マタハラ)を防止するための措置を企業に義務付けています。
施行日: セクハラ防止の規定は1999年の法改正で事業主の義務となり、マタハラ防止の規定は2017年1月1日に義務化されました。
育児・介護休業法|パタハラ・ケアハラ防止の企業義務
この法律は、育児休業や介護休業を理由とするパタニティハラスメント(パタハラ)やケアハラスメント(ケアハラ)を防止するための措置を企業に義務付けています。
施行日: 育児休業制度の改正に伴い、2017年1月1日に事業主の義務となりました。
カスタマーハラスメント(カスハラ)|企業が講じる防止措置
顧客等からのカスタマーハラスメントは、直接の法規制はありませんでしたが、労働施策総合推進法の改正により、企業に防止措置を講じることが義務化されることになりました。
これは、企業が従業員に対して負う安全配慮義務を果たすための重要な対策です。
- 施行予定: 2026年中の施行を目指しています。
まとめ|ハラスメント対策は、企業と従業員、双方の未来を守る
このように、ハラスメント対策は、もはや義務であり、経営戦略そのものです。
法律が求める最低限の対応を超え、積極的な対策を講じることは、従業員が安心して働ける環境を作り、企業の持続的な成長を確実なものにします。
健全な組織文化は一朝一夕には築けません。
企業全体が共通の理解を持ち、一人ひとりが意識的に行動することで、ハラスメントのない、より良い未来を築いていくことができます。
次回予告|パワハラとは|3要素と6類型について解説
次回は「パワハラとは|3要素と6類型について解説」をお届けします。
職場でよく耳にする「パワハラ」ですが、実は法律上、明確な定義や分類があります。
この記事では、パワハラの3つの要素と6つの類型をわかりやすく整理します。
「これは自分の職場でも当てはまるかも…」と感じる方も多いはず。
次回の記事は👉パワハラとは|3要素と6類型を徹底解説|職場での防止策も紹介
職場環境の改善やリスク回避のヒントとして、ぜひご参考ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
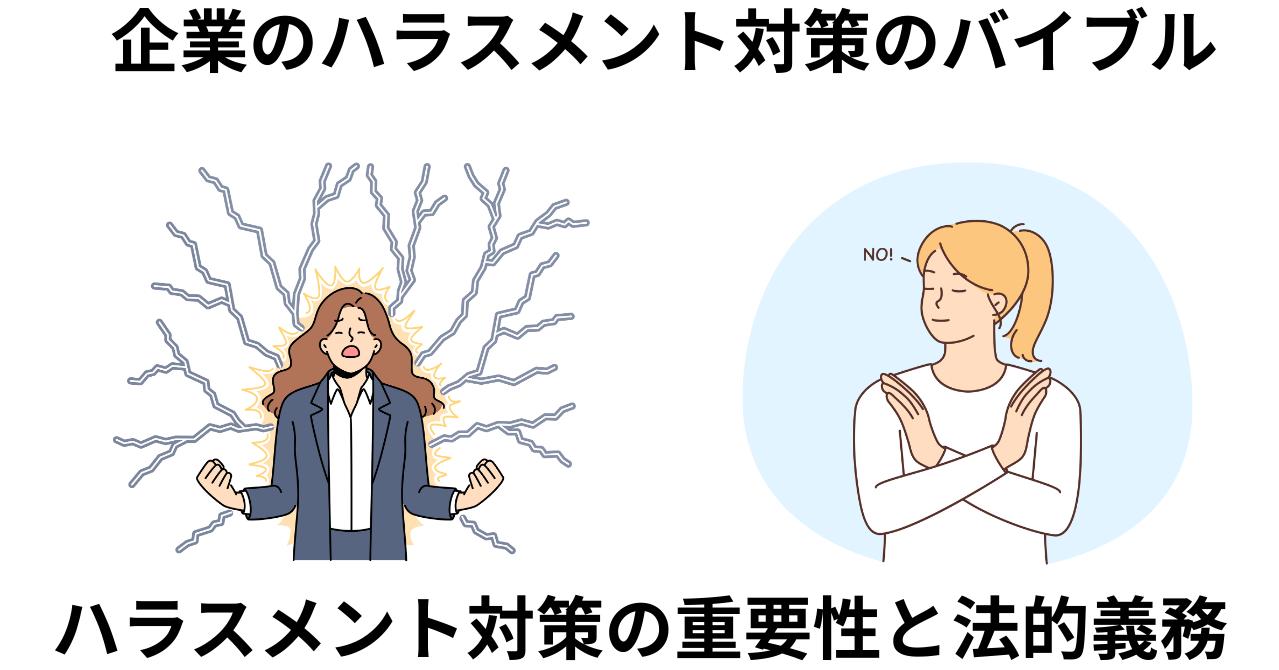

コメント