本記事は「【社労士が解説】企業のための熱中症対策 実践講座」シリーズの第12話です。第1話は👉熱中症は「他人事」ではない!企業に求められる安全配慮義務の基礎
シリーズ全体の記事はコチラからご覧ください👇
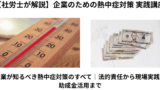
前回は、中小企業が熱中症対策を行う際に活用できる「業務改善助成金」の概要と、なぜこの助成金が熱中症対策にも適用されるのか、その論理的な理由について詳しく解説しました。
前回の記事は👉業務改善助成金で実現する熱中症対策と賃金アップの両立法
制度の仕組みやメリットはご理解いただけたかと思います。
しかし、いざ「申請してみよう」と思っても、何から始めればよいか分からず、手続きの煩雑さから申請をためらってしまう企業も少なくありません。
そこで今回は、熱中症対策を機に助成金の活用を考えている中小企業の皆さまのために、申請から助成金の支給を受けるまでの全プロセスを、ステップごとに分かりやすく解説していきます。
この記事を実務ガイドとして、不備なくスムーズに手続きを進めるためのポイントを押さえていきましょう。
熱中症対策を行う際に活用できる業務改善助成金の申請の全体像(ゴールイメージ)を掴む
業務改善助成金の申請は、以下の4つのステップで構成される一本の道筋です。
- 交付申請(事前申請) → 2. 設備導入・賃金引上げの実施 → 3. 支給申請(事後申請) → 助成金入金
このプロセスには、特に重要な2つの大きなフェーズが存在します。
1. 業務改善助成金の交付申請(事前申請)
👉中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付申請書
- これは、計画を実行する前に、その内容を提出して承認を得るフェーズです。
- この段階では、主に以下の3点を記載した書類を提出します。
- 事業場内最低賃金の引き上げ計画
- 従業員の賃金をいつ、いくら引き上げるか。
- 業務改善計画
- 賃金引き上げと同時に、どのような設備投資(例:業務用エアコン導入)を行って生産性を向上させるか。
- 助成対象経費の見積もり
- 設備投資にかかる費用の見積もり。
- 事業場内最低賃金の引き上げ計画
書類を提出し、労働局による審査を経て、交付決定通知書が届いたら、計画を進めて良いという許可が出たことになります。
この決定通知が届く前に計画を開始してしまうと、助成金を受け取れなくなるため、注意が必要です。
- 交付決定とは?
- 「交付決定」とは、あなたが提出した助成金の計画書を労働局が審査し、内容が適切であると認めた際に下される、「あなたの計画に沿って事業を進めても良いですよ」という許可のことです。
- これはあくまで「計画の承認」であり、この時点ではまだ助成金は入金されません。
- 交付決定通知が届いた後で初めて、設備投資や賃金引上げを実施できます。
2. 設備導入・賃金引上げの実施
交付決定通知を受け取ったら、計画通りに事業を実施します。
- 設備導入
- 計画した設備(例:業務用エアコン)を発注・購入し、設置します。
- 賃金引上げ
- 計画通りに賃金を引き上げ、従業員に適用します。
この段階では、領収書や賃金台帳など、後で提出が必要な書類をしっかり保管しておくことが重要です。
3. 業務改善助成金の支給申請(事後申請)
👉中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)支給申請書
これは、事業が完了した後に、助成金の支給を求めるフェーズです。
事業が完了したら、以下の書類を提出します。
- 支給申請書
- 助成金の支給を正式に求める書類。
- 事業実績報告書👉事業実績報告書中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)事業実績報告書
- 業務改善計画(設備投資)と賃金引上げが計画通りに実施されたことを証明する書類。
- 経費の支払いを証明する書類
- 領収書や請求書、契約書など。
- 賃金引上げを証明する書類
- 賃金台帳など。
これらの書類を提出して労働局の審査が通ると、晴れて助成金が振り込まれます。
これが、一連の手続きのゴールとなります。
熱中症対策を行う際に活用できる業務改善助成金の交付申請(事前申請)の具体的なステップ
まずは、助成金を受け取るための最初の関門である「交付申請」について、詳しく見ていきましょう。
計画書作成のポイント|「なぜ熱中症対策が生産性向上につながるのか?」を明確に
交付申請の中心となるのが、「事業実施計画書」です。
この計画書には、賃金引上げ計画、設備投資の内容、そしてそれらがどのように生産性向上に繋がるのかを具体的に記載します。
熱中症対策を盛り込む場合、単に「エアコンを買います」と書くだけでは不十分です。
「なぜその設備が必要で、それが会社の生産性をどのように向上させるのか」という論理的な因果関係を明確に説明することが重要です。
設備投資の内容の書き方 例
- 「工場内の作業スペースに業務用エアコン(〇台)とスポットクーラー(〇台)を導入する」
- 「屋外作業員向けに、暑さ指数(WBGT)を測定する機器を導入し、休憩のタイミングを科学的に管理する」など、具体的な設備名と導入目的を詳細に記載します。
生産性向上の根拠の書き方|例
- 「空調設備導入により作業場の温度が下がり、従業員の集中力が向上するため、作業効率が〇〇%アップし、不良品の発生率が〇〇%減少する見込み」といったように、具体的な数値目標や効果を盛り込むと、労働局の審査で高く評価されます。
業務改善助成金の交付申請時に必要な書類リスト
計画書を裏付けるため、以下の書類を準備します。
- 賃金規程または就業規則の写し
- 賃金台帳または給与明細(現状確認用)
- 見積書(設備導入予定のもの)
- 会社概要書
追加で求められることが多い書類例
- 労働者名簿(従業員の氏名・生年月日・雇用形態など)
- 雇用保険被保険者資格取得届の写し(雇用保険加入状況の確認用)
- 現場写真(導入前の状態を証明するため)
- 熱中症対策関連の資料(WBGT測定結果や現場温湿度の記録など)
- 生産性向上に関する資料(過去の生産実績や作業効率データなど)
重要な注意点
地域ごとにフォーマットや提出方法、必要書類は異なるのが通常です。
また、助成金のコースや年度によっても要件や様式が変わります。
そのため、申請前に必ず各都道府県労働局のウェブサイトや窓口で最新情報を確認しましょう。
審査期間の目安
交付申請を提出してから交付決定までの期間は、一般的におおむね1〜2か月が目安です。
ただし、この期間は法令で保証されたものではなく、繁忙期(年度末や制度改正直後など)や書類不備があった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、助成金を前提に設備導入や賃金引上げのスケジュールを組む場合は、余裕をもった計画が必要です。
事業実施期間中(熱中症対策と賃金引上げ)の注意点
交付決定通知が届き、実際に事業を実施する期間には、いくつか重要な注意点があります。
これらを理解しておくことで、不支給となるリスクを回避できます。
- 交付決定通知を受ける前に設備を購入しない
- 助成金の対象となる経費は、交付決定日以降に発注・契約・支払いが行われたものに限られます。
- 通知が届く前に設備を購入してしまうと、その費用は助成金の対象外となります。
- 設備導入と賃金引上げの順番はどちらが先でも可
- 支給申請を行う時点で、両方が完了していれば問題ありません。
- ただし、賃金引上げは地域の最低賃金改定日までに適用する必要があります。
- 計画のスケジュールに合わせて進めましょう。
- 領収書や設置写真など、証拠資料を確実に残す
- 支給申請では、計画通りに事業が実施されたことを証明する必要があります。
- 設備導入に関する請求書、領収書、契約書、そして設置後の写真などは、必ず保管しておいてください。
- また、賃金引上げについては、改定後の賃金台帳や就業規則などの提出を求められます。
これらのポイントを押さえて、計画を確実に実行することが助成金を受け取るための鍵となります。
熱中症対策を行う際に活用できる業務改善助成金|支給申請のステップ
支給申請は、交付決定後に計画通りに事業が完了したことを証明し、助成金の支払いを求める手続きです。
計画の実施結果報告と必要書類
計画の実行を証明するため、以下の書類を提出します。
1. 業務改善助成金の支給申請書
👉中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)支給申請書
- 助成金の支給を正式に求める書類です。
2. 賃金台帳
- 賃金引上げが実施されたことを証明するため、賃金改定後の数ヶ月分が必要です。
- 具体的には、支給申請時に賃金引上げ後の全期間分を提出します。
- これは、計画通りに賃金が支払われ、それが継続されていることを証明するために必要です。
- また、交付申請時には、現在の賃金水準を確認するために、直近3ヶ月分の提出が必要になります。
3. 設備の領収書・納品書・設置写真
- 設備投資が完了したことを証明する重要な書類です。
4. 生産性向上を示す資料(任意)
- 業務改善によって、作業効率が向上したことや不良率が改善したことなどを示す資料です。
- 必須ではありませんが、より高い助成率を狙う場合に提出します。
- 熱中症対策の場合の具体例
- 数値で示す
- 導入前後の特定の作業時間の短縮、休憩時間の削減、欠勤・早退件数の減少などを比較したデータ。
- 写真で示す
- 導入前の暑い環境と、導入後の快適な環境での作業の様子を比較した写真。
- アンケートで示す
- 導入前後の作業環境について、従業員に行ったアンケート結果。
- 数値で示す
- 熱中症対策の場合の具体例
提出期限
これらの書類は、原則として事業実施期間終了後1ヶ月以内に提出する必要があります。
事業実施期間とは、交付決定通知を受け取った日から、賃金の引上げと設備投資・支払いがすべて完了する日までの期間を指します。
具体的には、以下の3つのうち最も遅い日が事業完了日となります。
- 設備等の納品日
- 設備等の支払い完了日
- 賃金の引上げ日
期限を過ぎてしまうと、助成金を受け取れなくなる(不支給)リスクがあるため、注意が必要です。
熱中症対策を行う際に活用できる業務改善助成金|よくある不支給事例
業務改善助成金は、企業の生産性向上と賃金引上げを支援する制度ですが、申請手続きや要件に不備があると、せっかくの取り組みが助成金の対象外となってしまうことがあります。
ここでは、特に注意すべき「よくある不支給事例」を紹介します。
1. 業務改善助成金の交付決定前に設備を購入してしまった
業務改善助成金は、交付決定通知を受け取ってから事業を開始することが大前提です。
もし、交付決定より前に設備を購入したり、発注したりした場合、その経費は助成金の対象外となります。
ポイント
交付申請から交付決定までには通常1〜2ヶ月かかります。
事業計画を立てる際は、この期間を考慮してスケジュールを組みましょう。
2. 賃金引上げ額が要件に満たない
助成金の対象となるには、事業場内最低賃金を指定された金額以上引き上げることが必須です。
例えば、コースによっては「30円以上」「45円以上」といった引上げ額が定められています。
この要件を満たしていない場合、助成金は支給されません。
ポイント
賃金引上げ額は、必ずしもすべての従業員の賃金を上げる必要はなく、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げることで要件を満たします。
(例)
- 賃上げ前
- Aさん(時給1,250円)、Bさん(時給1,200円)、Cさん(時給1,350円)
- 事業場内最低賃金
- 1,200円(Bさんの時給)
- 助成金要件
- 事業場内最低賃金を30円引上げ
- 賃上げ後1
- Bさんの時給を1,230円に引き上げれば要件達成。
- AさんやCさんの賃金は据え置きでも構いません。
- この場合、1人の時給を上げたことになります。
- 賃上げ後2
- Aさん、Bさん、Cさんの全員の時給を30円ずつ引き上げると、Aさん(1,280円)、Bさん(1,230円)、Cさん(1,380円)となり、全員の賃金が最低要件を満たします。
- この場合、3人全員の時給を上げたことになります。
3. 業務改善助成金の対象外の設備を導入してしまった
業務改善助成金の対象となる経費は、「生産性向上に資する設備」に限定されています。
例えば、以下のようなものは対象外となることが多いため、注意が必要です。
- 汎用性の高いもの
- パソコン、タブレット、スマートフォンなど
- 熱中症対策の例
- 扇風機(一般的な家電製品として販売されているもの)など、他の目的にも広く使えるもの。
- 単なる維持・管理のためのもの
- ソフトウェアの更新費用、設備の保守費用など
- 熱中症対策の例
- 既存の空調設備のフィルター清掃や、故障した部品の交換費用など。
- 購入価格が安価なもの
- 事務用品、文具など
- 熱中症対策の例
- 保冷剤、塩飴、水分補給用のペットボトル飲料など。
導入を検討している設備が助成対象となるかどうか、事前に各都道府県労働局に確認しておくことが重要です。
4. 生産性向上の説明が不十分
生産性向上の説明は必須ではありませんが、より高い助成率を目指す場合には、事業計画書に生産性向上効果を具体的に記載する必要があります。
この説明が抽象的であったり、設備導入との関連性が不明瞭であったりすると、十分な評価を得られない可能性があります。
ポイント
設備導入によって、「どの作業が、どのくらい効率化され、どのくらい時間が短縮されるか」など、具体的な数値目標を盛り込むと説得力が高まります。
これらの不支給事例を参考に、交付申請前の準備から計画の実行、そして支給申請までの各段階で、不備がないように慎重に進めていきましょう。
熱中症対策を行う際に活用できる業務改善助成金|入金までのスケジュール
業務改善助成金は、申請から入金までに一定の時間がかかります。
具体的な日付を例にして、全体のスケジュール感を確認しましょう。
1. 業務改善助成金の交付申請(スタート)
- 例
- 2025年8月30日
- 流れ
- 事業を開始する前に、まず交付申請を行います。
- 事業計画書や賃金台帳(直近3ヶ月分)などの必要書類を提出します。
2. 業務改善助成金の交付決定
- 例
- 2025年10月30日
- 所要期間
- 交付申請から約2ヶ月で交付決定通知が届きます。
- 流れ
- この通知を受け取ってから、初めて設備投資や賃金引上げといった事業を開始できます。
3. 事業実施期間
- 例
- 2025年10月30日〜2026年4月30日
- 期間
- 交付決定日からおおむね6ヶ月以内に、事業を完了させる必要があります。
- この期間は、厚生労働省が定める「業務改善助成金交付要綱」によって定められています。
- 原則として、この期間を超えると助成金の対象外となるため、計画的な進行が不可欠です。
- 流れ
- この期間中に、計画していた設備投資を行います。
- 賃金引上げもこの期間内に実施します。
- すべての事業が完了した日が「事業完了日」となります。
- 補足
- やむを得ない事情がある場合は、事前に労働局に相談し、承認を得ることで期間を延長できる場合があります。
4. 業務改善助成金の支給申請
- 例
- 2026年5月30日
- 所要期間
- 事業完了日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
- この期限も、「業務改善助成金交付要綱」で定められています。
- 流れ
- 支給申請書、賃金台帳(賃金引上げ後の全期間分)、領収書、納品書などの書類を提出します。
5. 業務改善助成金の入金
- 例
- 2026年7月30日〜2026年8月30日
- 所要期間
- 支給申請から約2〜3ヶ月で指定の口座に助成金が入金されます。
- 流れ
- 労働局による書類審査が完了し、問題がなければ助成金が支払われます。
このように、交付申請から入金までは、合計で10ヶ月前後の期間を要する可能性があります。
計画を立てる際には、このスケジュールを念頭に置いて進めるようにしましょう。
まとめ|熱中症対策を行う際に活用できる申請成功の4つのカギ
業務改善助成金の申請を成功させるためには、以下の4つのポイントを押さえることが不可欠です。
- 事前申請(交付申請)と事後申請(支給申請)の両方が必要
- 助成金は、計画の提出(事前申請)と実施報告(事後申請)の両方が承認されて初めて支給されます。どちらか一方では受け取れません。
- 書類の整備と証拠資料の保存が成功のカギ
- 申請時に提出する書類はもちろん、領収書や納品書、賃金台帳など、計画の実施を証明する証拠書類を漏れなく保存することが極めて重要です。
- 設備購入のタイミングには特に注意
- 交付決定通知を受け取る前に設備を購入してしまうと、助成金の対象外となります。
- 必ず交付決定を待ってから発注するようにしましょう。
- 労働局とのやりとりは早めに行い、不明点は確認する
- 申請期間の延長や、計画の変更など、不明な点や不安な点があれば、自己判断せず、早めに労働局に相談しましょう。
【シリーズ最終回】熱中症対策から業務改善助成金まで
これまで、複数回にわたって「熱中症対策」をテーマに、様々な視点から企業の取り組みを解説してきました。
本シリーズを通じて、熱中症対策は単なる福利厚生ではなく、企業の安全配慮義務に関わる重要な法的責任であり、生産性向上にも直結する経営課題であることをお伝えしてきました。
また、その具体的な対策として、WBGT値の測定や休憩時間の運用、就業規則の整備といった実務的なポイントから、業務改善助成金を活用した設備投資の方法まで、幅広くご紹介しました。
これらの情報が、皆さまの事業所における安全で働きやすい環境づくりと、そのための戦略的な助成金活用の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
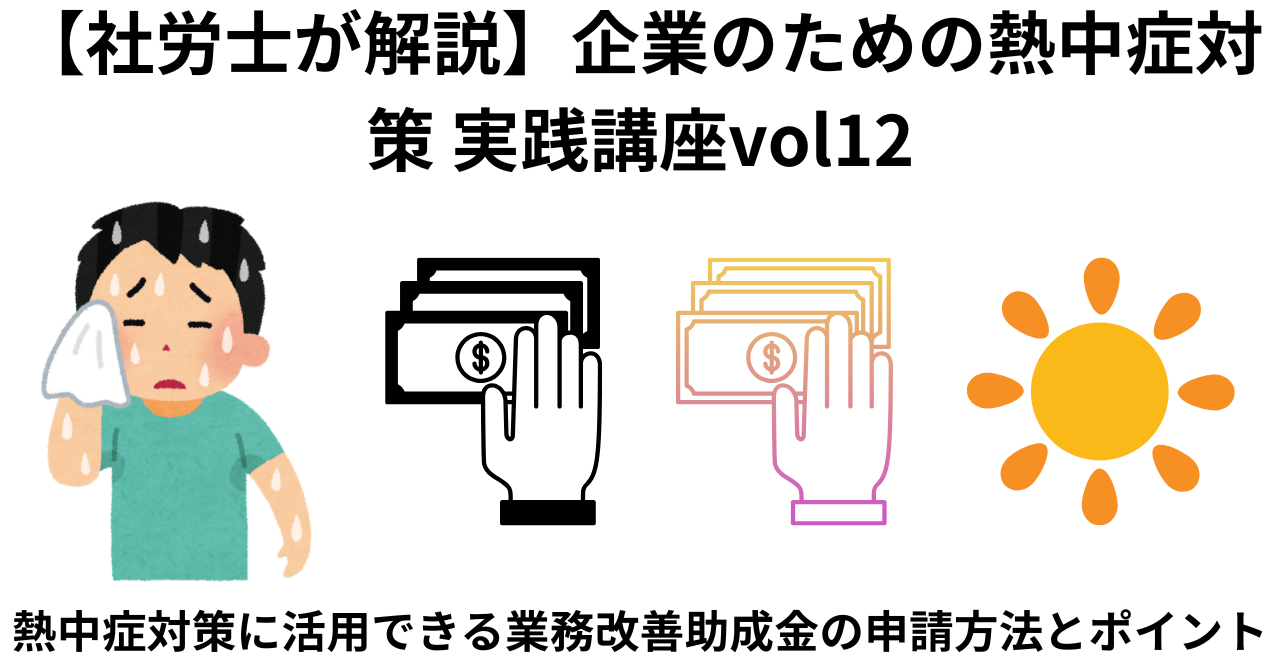

コメント