本記事は「あなたの働く人生を守るセーフティネット!雇用保険のすべて」シリーズの第2話です。第1話は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
前回の記事では、雇用保険が私たちの働き方を守る大切なセーフティネットであることを解説しました。
前回の記事は👉雇用保険とは?何のためにある?|加入メリットや目的を解説
「失業」「育児」「介護」「スキルアップ」の4つのリスクに備える雇用保険ですが、その財源となるのが、毎月のお給料から天引きされている雇用保険料です。
しかし、「なぜこの金額が引かれているの?」「会社と自分、それぞれどれくらい負担しているんだろう?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、雇用保険料の計算方法と、会社と労働者の負担割合について、2025年度の最新情報をもとに分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 負担割合と料率|会社と労働者の雇用保険料の負担割合と2025年度の料率
- 正確な計算式|給与や手当を含めた賃金総額での計算方法と具体例
- 変動する理由|コロナ禍などによる保険料率が変動する背景とその仕組み
- 保険料の使い道|支払った保険料が何に活用されているかの全貌
2025年度最新版|雇用保険料は会社と労働者どちらがどれだけ負担する?
雇用保険料は、企業が全額を負担するわけではなく、会社(事業主)と私たち労働者が共同で分担して支払うのが原則です。
会社は、給与から天引きした私たちの保険料と、会社が負担する分の保険料を合わせて、国に納めています。
雇用保険料は、「賃金総額」に「雇用保険料率」をかけて計算されます。
この保険料率は、事業の種類によって異なり、また、毎年の雇用情勢や財政状況によって見直されます。
2025年度(令和7年度)の雇用保険料率は以下の通りです。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 全体 |
| 一般の事業 | 0.55% | 0.9% | 1.45% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.65% | 1.0% | 1.65% |
| 建設の事業 | 0.65% | 1.1% | 1.75% |
※ この料率は、賃金総額に対する割合です。
このように、雇用保険料は会社と労働者がお互いに支え合いながら、私たちの働く環境を維持するために使われています。
雇用保険料の計算方法をわかりやすく解説|給与・年収別の具体例つき
では、実際にあなたの給与から天引きされている雇用保険料が、どのように計算されているのかを見ていきましょう。
計算自体は非常にシンプルです。
雇用保険料の計算式
雇用保険料は、以下の簡単な計算式で算出されます。
賃金総額 × 雇用保険料率(労働者負担分)
この「賃金総額」とは、基本給だけではありません。
税金や社会保険料が引かれる前の、会社から支払われるすべての賃金が対象となります。
具体的には、以下のようなものが含まれます。
- 基本給
- 残業手当、深夜手当、休日手当
- 役職手当、家族手当、通勤手当など
- ボーナス(賞与)
一方、結婚祝金や災害見舞金など、臨時に支払われるものは計算の対象外です。
具体的な雇用保険料の計算例を見てみよう
ここで、具体的な数字を使って計算してみましょう。
- 勤務先
- 一般の事業
- 2025年度の雇用保険料率(労働者負担分)
- 0.55%
【ケース1 月収での計算】
ある月の給与明細が以下の通りだったとします。
- 基本給
- 190,000円
- 役職手当
- 10,000円
- 通勤手当
- 15,000円
- 残業手当
- 35,000円
- 結婚祝金
- 10,000円
この月の支給総額は260,000円(給与、手当、祝金などの合計)となります。
しかし、雇用保険料を計算する際の賃金総額は250,000円です。
なぜなら、結婚祝金は労働の対価として支払われたものではないため、計算の対象外だからです。
- 計算対象となる賃金総額
- 190,000 + 10,000 + 15,000 + 35,000 = 250,000円
- 計算
- 250,000円 × 0.55% = 1,375円
この1,375円が、あなたの給与明細から天引きされる雇用保険料です。
【ケース2 年収での計算】
- 年収(賃金総額)が400万円の場合
- 計算
- 4,000,000円 × 0.55% = 22,000円
- 計算
年収ベースで計算すると、年間で支払う雇用保険料の総額を把握することができます。
「年収が400万円くらいだと、年間で22,000円くらい負担しているのだな」という目安として参考にしてください。
このように、毎月の給与だけでなく、ボーナスも含めた総支給額が雇用保険料の計算対象となります。
あなたの給与明細や源泉徴収票に記載されている金額と照らし合わせながら確認してみてください。
雇用保険料が変動する理由|コロナ禍と財政状況の影響を解説
「最近、雇用保険料が上がった気がする…」と感じた方は、間違いありません。
実は、雇用保険料率は、2022年度と2023年度に立て続けに引き上げられました。
そして2025年度には、再び引き下げられました。なぜこのように変動するのでしょうか?
その背景には、日本の雇用情勢が大きく関係しています。
コロナ前とコロナ後で雇用保険料率はどう変わった?
コロナ禍での雇用情勢の悪化により、雇用保険の財政がひっ迫したため、雇用保険料率は大きく変動しました。
2025年度の最新の料率と、コロナ前の水準を比較してみましょう。
| 事業の種類 | コロナ前(〜2020年度) | コロナ後(2023年度) | 2025年度(最新) |
| 労働者負担 | 0.3% | 0.6% | 0.55% |
| 事業主負担 | 0.6% | 0.95% | 0.9% |
| 全体 | 0.9% | 1.55% | 1.45% |
※いずれも一般の事業における料率です。
雇用保険料率が上がった理由
2022年度と2023年度に雇用保険料が引き上げられた主な原因は、新型コロナウイルス感染症による雇用保険の財政悪化です。
コロナ禍で多くの企業が打撃を受け、従業員の雇用を守るために、国が企業に支払う「雇用調整助成金」の支給額が急増しました。
この助成金は、雇用保険の財源から支払われるため、多額の支出が発生しました。
さらに、失業者が増えたことで、「失業給付金」の支給も大幅に増加しました。
これらの助成金や給付金の支出が大幅に増えたことで雇用保険の積立金が減少し、財政を立て直すために保険料率の引き上げが必要と判断されたのです。
そして2025年度に雇用保険料率引き下げへ
2024年度は据え置かれていましたが、雇用情勢が改善し、雇用保険の財政状況が安定してきたことから、2025年度には保険料率が引き下げられました。
この引き下げには、物価高騰が続く中で、私たち労働者や企業の負担を少しでも軽減しようという国の狙いもあります。
このように、雇用保険料は、その時々の社会経済状況によって変動します。
私たちが支払う保険料が、いざというときのセーフティネットを支えていることを改めて理解しておきましょう。
まとめ|雇用保険料の使い道と失業・育児・介護・スキルアップへの活用
今回の記事では、雇用保険料がどのように計算され、なぜ変動するのかを解説しました。
給与明細から天引きされる保険料は、単なる負担ではありません。
そのお金は、私たちが日々安心して働くための大切な「備え」です。
私たちが支払った雇用保険料は、もしものときにあなた自身を守るだけでなく、同じように働く仲間や日本の雇用全体を支える、社会全体のセーフティネットなのです。
このお金は、あなたが安心して働き、そして生きるための「お守り」です。
だからこそ、あなたが退職して収入が途絶えたとき、育児や介護で仕事を休むとき、スキルアップのために学ぶときなど、いざというときはためらわずに給付金を活用してください。
雇用保険は、あなたと会社が共に積み立てたものです。
きっちり支払う義務があるように、必要なときに給付金を受け取る権利が、あなたにはあります。
この連載で雇用保険をしっかり把握し、もらえるはずだった給付金をもらい損ねてしまうことがないようにしましょう。
次回予告|雇用保険が守る4つのリスクと給付金制度の全貌
雇用保険は、あなたが失業、育児、介護、スキルアップといった人生の転機に直面したとき、生活を支える心強いセーフティネットです。
次回の記事では、これらのリスクを具体的にどうカバーしてくれるのか、その全貌を解き明かします。
次回の記事は👉雇用保険は失業だけじゃない!育児・介護・スキルアップも支える4つの給付制度
雇用保険が守ってくれる「4つのリスク」と、それぞれの給付金制度について詳しく解説していきます。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点に立った情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
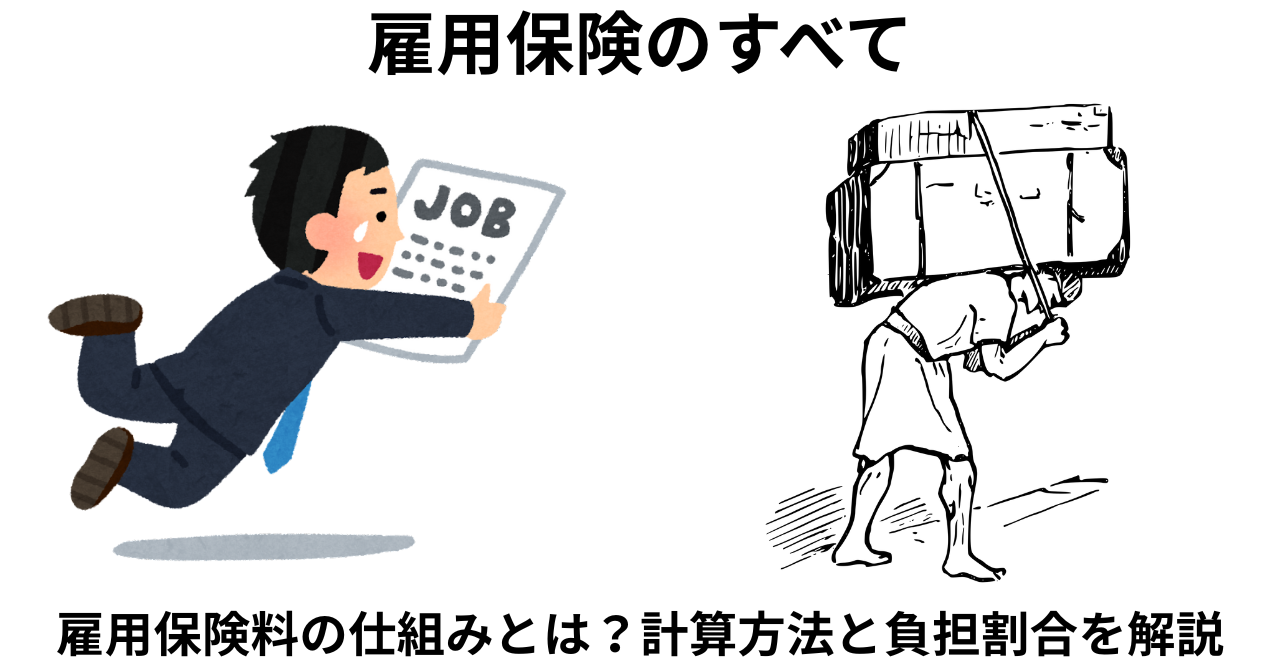




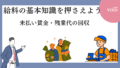
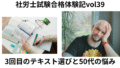
コメント