本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol9です。
前回の記事では、2019年4月1日に施行された年5日間の年次有給休暇(年休)取得義務化について、その背景や目的、企業が取るべき対応の概要を詳しく解説しました。
前回の記事は👉義務化された年5日有給|対象者、罰則、企業への影響
この法改正は、日本の低い年休取得率を改善し、労働者の健康とワークライフバランスの向上、ひいては企業全体の生産性向上を目指すものでした。
企業には、単に年休を付与するだけでなく、その取得を「管理」し「確実に取得させる」という新たな役割と責任が加わりました。
しかし、法改正の趣旨を理解しただけでは、実際の運用は難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
「具体的に、どこから手をつければいいの?」そう思われた方もいるのではないでしょうか。
就業規則・年休管理簿の整備で年5日間有給取得をスムーズに運用する
そこで今回の記事では、この年5日間の年休取得義務化を企業が円滑かつ確実に進めるために不可欠な「就業規則」の整備と「年次有給休暇管理簿」の作成・運用に焦点を当てます。
この記事を読み終える頃には、あなたは以下の具体的な知識とメリットを得られるでしょう。
- 年休義務化に対応した就業規則の具体的な記載例を理解し、自社の就業規則を見直す際の明確な指針が得られます。
- 企業に作成・保存が義務付けられている年次有給休暇管理簿の具体的な作り方と運用方法を習得し、適切な年休管理ができるようになります。
- これらの知識を活用することで、法令遵守はもちろんのこと、労働者との無用なトラブルを回避し、より健全で生産性の高い職場環境を構築するための実務的なスキルが身につきます。
さあ、共に年休取得義務化の実務における具体的なステップを見ていきましょう。
就業規則における年次有給5日間取得義務の具体例と対応方法
年5日間の年休取得義務化を円滑に進めるためには、企業のルールブックである就業規則の整備が欠かせません。
この就業規則は、単に法律で定められているから作成するだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整え、労使間の無用なトラブルを防ぐための重要なツールとなります。
就業規則の役割と年次有給休暇5日取得義務対応における実務上の重要性
就業規則は、労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成・届出が義務付けられているルールブックです。
労働時間、賃金、休暇など、労働条件に関する具体的な事項を明記することで、従業員は自身の権利や義務を理解し、企業は一貫した労務管理を行うことができます。
年休取得義務化においては、この就業規則が特に重要な役割を担います。
- 労働者への周知徹底
- 義務化された年休取得ルールを就業規則に明記し、従業員に周知することで、「いつまでに何日休む必要があるのか」「企業からの時季指定はどのような場合に行われるのか」といった疑問を解消し、安心して年休を取得できる環境を醸成します。
- トラブル防止
- 年休の時季指定や時季変更、計画的付与などに関するルールを明確にすることで、労使間の認識の齟齬によるトラブルを未然に防ぎます。
- 万が一、問題が発生した場合でも、就業規則に明確な根拠があれば、円滑な解決につながります。
年次有給休暇5日取得義務に対応する就業規則の必須記載事項と実務ポイント
年5日間の年休取得義務化に対応するために、就業規則には以下の事項を明確に記載する必要があります。
年次有給休暇の付与基準
- 付与日数、付与タイミング
- 労働基準法で定められた年休の付与日数と、勤続年数に応じた付与タイミングを明確に記載します。
- パート・アルバイトへの比例付与
- 週の所定労働日数や年間所定労働時間に応じて年10日以上の年休が付与されるパートタイマーやアルバイトも義務化の対象となるため、これらの従業員への比例付与についても明記が必要です。
年5日間の時季指定義務に関する規定
企業が年5日の年休取得を義務として実行するための、最も重要な条項です。
- 企業が時季指定を行う場合の条件
- 「労働者が年5日の年休を取得していない場合に、企業が時季を指定して取得させる」旨を明記します。
- 労働者の意見聴取の義務
- 企業が時季指定をする前に、必ず労働者の意見を聴き、その意見を尊重する旨を記載します。
- 企業からの時季指定の方法
- 時季を指定する際の通知方法(例:書面による通知、電子メールなど)を定めます。
- 労働者からの時季変更申し出に関する規定
- 企業が指定した日であっても、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、労働者が時季変更を申し出られる旨と、その際の対応についても記載します。ただし、この「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断は客観的かつ慎重に行う必要があります。
計画的付与制度に関する規定(導入する場合)
労使協定を締結して年休の計画的付与制度を導入する場合は、就業規則にもその旨を記載します。
- 労使協定の締結が必要であること
- 計画的付与制度の導入には、労働者の過半数を代表する者(または労働組合)との間で労使協定を締結する必要があることを明記します。
- 計画的付与の対象となる年休日数
- 義務化された5日を含め、何日を計画的付与の対象とするかを定めます。
- 具体的な付与方法
- ゴールデンウィークや夏季休暇、年末年始の一斉休暇、部署ごとの交代制など、具体的な付与方法を記載します。
年休の計画的付与制度に関する詳しい記事はコチラ👇
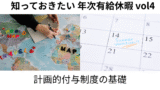
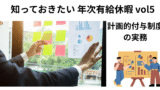
年休の単位
- 原則1日単位
- 年休は原則として1日単位で与えることを明記します。
- 時間単位年休、半日単位年休の規定
- 労働者の利便性を高めるために時間単位年休や半日単位年休を導入する場合は、その旨と取得条件を記載します。
- これらの導入は義務ではありませんが、柔軟な働き方を促進するために有効です。
就業規則に使える具体的な年次有給休暇の文言例
就業規則への具体的な記載例をいくつかご紹介します。自社の状況に合わせて調整してください。
例1 シンプルな時季指定規定
年次有給休暇の時季指定
第〇条 会社は、労働基準法第39条第7項に基づき、前条で定める年次有給休暇のうち、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、そのうち年5日については、時季を指定して取得させるものとします。ただし、労働者が既に当該年に5日以上の年次有給休暇を自主的に取得している場合はこの限りではありません。
- 会社が前項の時季指定を行うにあたっては、事前に労働者の意見を聴取し、その意見を十分に尊重するものとします。
- 会社は、第1項の時季指定を行う場合、事前に指定する時季を当該労働者に書面または電磁的方法により通知します。
年次有給休暇の時季変更
第〇条 会社が指定した年次有給休暇の時季、または労働者が請求した年次有給休暇の時季について、その取得が事業の正常な運営を妨げる場合は、会社または労働者は、相手方に対し、他の時季への変更を申し出ることができます。
- 前項の申し出があった場合、会社および労働者は、その理由を十分に考慮し、代替の時季について誠実に協議し、決定するものとします。
規定のポイント
この「シンプルな時季指定規定」は、年5日間の年休取得義務化に対応するための基本的な条文群です。
- 会社による時季指定の明確化
- 会社が年5日の年休を労働者に取得させる義務があること、そしてその際に労働者の意見を尊重し、事前に通知することが明記されています。
- 時季変更の柔軟性
- 会社が指定した日であっても、後から予期せぬ事情が発生し「事業の正常な運営を妨げる」と判断される場合、会社側からも労働者側からも変更を申し出ることが可能です。
- これにより、双方の緊急事態に対応できる柔軟性を持たせています。
- 協議による解決
- 変更の申し出があった際には、労使双方が誠実に協議し、合意の上で代替日を決定するプロセスを重視しています。
この規定は、従業員にとって分かりやすく、会社としても法令を遵守しながら円滑に年休管理を行うための基盤となります。
例2 計画的付与制度を組み込んだ規定
この規定は、労使協定を締結して年次有給休暇の計画的付与制度を導入する企業が就業規則に盛り込むべき内容です。
(年次有給休暇の計画的付与)
第〇条 会社は、労働者の過半数を代表する者(または労働組合)との書面による労使協定に基づき、年次有給休暇のうち、年間〇日を限度として、労働者の時季指定権にかかわらず、計画的に取得日を定めることができるものとします。
- 前項の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、労働者の年次有給休暇の日数のうち、5日を超える部分について適用します。
- 計画的付与の方法については、労使協定において定めるものとします。
規定のポイント
- 労使協定の必要性
- 計画的付与制度の導入には、労働者側の代表者との間で労使協定を締結することが法的に必須である点が明確に示されています。
- 対象日数
- 義務化された年5日の年休は、原則として労働者の意向を尊重して取得させるべきものであり、計画的付与の対象となるのは、その5日を超える部分の年休であることが明記されています。これにより、法律の趣旨と制度の目的が両立します。
- 具体的な方法の明示
- どのような形で計画的付与を行うのか(例:全社一斉休業、部署ごとの交替など)は、労使協定で具体的に定める旨を示しています。
この規定を就業規則に盛り込むことで、企業は計画的に年休取得を進めることができ、労働者も安心して長期の休暇を取りやすくなるでしょう。
就業規則を改定する際の注意事項と押さえるべきポイント
就業規則を改定する際には、以下の点に注意が必要です。
- 労働基準監督署への届け出義務
- 就業規則の変更は、労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
- 変更後の就業規則と、変更内容を記載した意見書(労働者の過半数を代表する者または労働組合の意見を聴いた旨を記載したもの)を提出しましょう。
- 労働者への周知方法と合意形成の重要性
- 改定した就業規則は、必ず全従業員に周知しなければなりません。
- 社内掲示、イントラネットへの掲載、説明会の開催など、確実に伝わる方法で周知を徹底しましょう。
- また、労働者の意見を聴取し、可能であれば合意形成を図ることで、スムーズな運用につながります。
この就業規則は、企業と労働者双方にとっての道しるべです。今回の年休義務化を機に、ぜひ自社の就業規則を見直し、より実態に即した、分かりやすい内容に更新してみてください。
年次有給休暇管理簿の作り方と運用方法|記入例・フォーマット付き
年5日間の年次有給休暇(年休)取得義務化において、就業規則の整備と並んで重要なのが、年次有給休暇管理簿の作成と適切な運用です。
この管理簿は、単なる記録ではなく、企業が法律を遵守し、従業員の健康と生産性を守るための大切なツールになります。
年次有給休暇管理簿の法的義務と活用ポイント|記録・管理の実務ポイント
年休管理簿は、労働基準法によって企業に作成と保存が義務付けられています。(労働基準法施行規則第24条の7に明記されています。)
- 作成・保存義務(3年間保存)
- 企業は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、年休を与えた期間およびその期間の満了後3年間保存しなければなりません。
- これにより、いつ、誰に、何日年休が付与され、いつ、何日取得されたかを明確に記録できます。
- 年休取得状況の正確な把握と法令遵守の証明
- 管理簿があることで、企業は各従業員の年休取得状況を正確に把握できます。
- これにより、年5日間の取得義務が果たされているかをいつでも確認でき、労働基準監督署などからの調査があった際にも、適切に管理していることを証明できます。
年次有給休暇管理簿の記載項目一覧|必須項目と記入例付き
年休管理簿には、以下の項目を必ず記載しましょう。
必須項目
- 労働者氏名
- 誰の年休情報か、従業員名を記載します。
- 基準日(年休付与日:年次有給休暇が労働者に初めて付与された日、または、その後の年次有給休暇が定期的に付与される日)
- 年次有給休暇が付与された日付を記載します。
- 通常は入社日やその後の特定の基準日です。
- 付与日数
- その基準日に付与された年休の総日数を記載します。
- 取得日数
- 労働者が実際に取得した年休の合計日数を記載します。
- 取得時季(日付)
- 各年休が取得された具体的な日付を記載します。これが、年5日取得義務の確認に特に重要です。
- 残日数
- 付与日数から取得日数を差し引いた残りの年休の日数を記載します。
その他、管理に役立つ項目
必須ではありませんが、これらを記載するとより詳細な管理ができます。
- 時間単位年休の取得時間数
- 時間単位年休を導入している場合、取得した時間数を記録します。
- これは年5日義務には直接カウントされませんが、総年休残数を把握するのに役立ちます。
- 計画的付与による取得日数
- 計画的付与制度を導入している場合、その制度によって取得させた年休の日数を区分して記録します。
- 備考欄(特記事項など)
- 個別の事情や、時季変更があった場合などの特記事項を記載するスペースがあると便利です。
年次有給休暇管理簿の作成手順とテンプレート活用法|実務で使えるステップ解説
年休管理簿の作成方法はいくつかありますが、自社の規模や管理体制に合わせて選択しましょう。
- Excel等での自作方法(シンプルなテンプレート例)
- 中小企業など、導入コストを抑えたい場合は、Excelでシンプルな管理簿を作成するのが一般的です。
- 以下のような項目を列に設定し、従業員ごとにシートを分けるか、一つのシートにまとめて管理できます。
| 氏名 | 基準日 | 付与日数 | 取得時季(日付) | 取得日数 | 残日数 | 会社指定分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 2024/4/1 | 10日 | 2024/7/102024/8/5… | 5日 | 5日 | 会社指定分 |
| 鈴木花子 | 2024/5/1 | 12日 | 2024/9/202024/10/10 | 2日 | 10日 |
- (※「取得時季(日付)」欄は、複数日付を列挙できるようにセルを結合するか、別途詳細欄を設けるなどの工夫が必要です。)
- クラウド勤怠管理システム等の活用メリット(自動化、効率化)
- 多くの従業員を抱える企業や、管理業務の効率化を図りたい場合は、クラウド型の勤怠管理システムや人事労務管理システムの導入を強くおすすめします。
- 自動化
- 従業員がシステム上で年休を申請・取得すると、付与日数や残日数が自動で計算・更新され、年休管理簿も自動で作成されます。
- 法令遵守のサポート
- 5日取得義務の進捗状況をシステムがアラートで知らせてくれる機能を持つものも多く、未取得者への声かけ漏れを防げます。
- 効率化
- 管理業務の負担が大幅に軽減され、ミスも減らせます。
- 自動化
- 多くの従業員を抱える企業や、管理業務の効率化を図りたい場合は、クラウド型の勤怠管理システムや人事労務管理システムの導入を強くおすすめします。
お勧めのクラウド勤怠管理システムソフト👉パソコンで勤怠管理3 スマートパッケージ版
年次有給休暇管理簿の正しい運用ポイント|トラブルを防ぐ実務チェックリスト
年休管理簿は、作成して終わりではありません。
適切に運用してこそ、その真価を発揮します。
- 担当者の明確化
- 誰が年休管理簿の作成、更新、チェックを行うのかを明確にしましょう。
- 担当者を決めることで責任の所在がはっきりし、管理が滞るのを防げます。
- 定期的な更新と確認
- 従業員が年休を取得するたびに、速やかに管理簿を更新しましょう。
- また、定期的に(例えば、月に一度や四半期に一度など)全従業員の取得状況を確認し、年5日取得義務が未達成の従業員がいないかをチェックします。
- 労働者への情報提供
- 従業員が自身の年休残日数や取得状況をいつでも確認できる仕組みを整えましょう。
- これにより、従業員自身が計画的に年休を取得しやすくなり、会社への信頼感も高まります。
- トラブル防止のための活用
- 年休管理簿は、未取得者への声かけや、会社が時季指定を行う際の根拠となります。
- 計画的な年休取得を促し、未取得者を把握することで、義務違反のリスクを回避し、従業員の心身の健康維持にも繋がります。
年次有給休暇管理簿を適切に作成・運用することで、企業は法令遵守を果たし、従業員は安心して休暇を取得できる、健全な職場環境を築くことができます。
まとめ|年5日有給取得義務化を円滑に進めるための就業規則と管理簿の両輪
年次有給休暇の年5日取得義務化は、単に「5日休ませればよい」というものではありません。
企業がこの義務を確実に果たし、かつ円滑な事業運営を維持するためには、「就業規則」と「年次有給休暇管理簿」という二つのツールを適切に整備し、運用することが不可欠です。
- 就業規則
- 年休取得のルール(会社の時季指定、時季変更、計画的付与など)を明確に定め、従業員に周知することで、労使間の認識の齟齬を防ぎ、トラブルを未然に防ぐ「羅針盤」の役割を果たします。
- 従業員は、自身の権利と義務を理解し、安心して年休を取得できる基盤となります。
- 年次有給休暇管理簿
- 各従業員の年休付与日、付与日数、取得日数、取得時季などを正確に記録し、3年間保存する義務があります。
- 誰が何日取得しているかを一目で把握でき、年5日取得義務の達成状況をリアルタイムで確認できる「進捗管理ツール」であり、法令遵守の証明にもなります。
この二つが適切に機能することで、企業は法令違反のリスクを回避し、従業員は自身の健康と生活を大切にしながら、安心して働くことができる環境が整います。
年5日有給取得義務化の適切な運用|法令遵守と労働者の健康・生産性向上
年5日取得義務化は、労働者の健康確保とワークライフバランスの推進を目的としています。
就業規則と年休管理簿を適切に運用することは、単に法律を守るだけでなく、以下のようなメリットをもたらします。
- 法令遵守の徹底
- 義務を確実に果たすことで、労働基準監督署からの指導や罰則のリスクを回避できます。
- 労働者の健康維持・生産性向上
- 計画的な年休取得は、従業員の心身のリフレッシュを促し、ストレス軽減やモチベーション向上につながります。結果として、業務への集中力が高まり、生産性の向上にも寄与します。
- 企業イメージの向上
- 従業員の働きやすさを重視する企業姿勢は、採用活動においても有利に働き、優秀な人材の確保にも繋がります。
次回予告|非正規雇用・多様な働き方における有給休暇のポイント
次回の記事では、現代の多様な働き方に焦点を当て、非正規雇用の従業員における年次有給休暇の具体的な付与や管理方法について深掘りしていきます。
- パートタイム労働者への有給休暇は、どのように付与されるのでしょうか?
- 契約社員や派遣社員の場合、有給休暇の扱いはどうなるのでしょうか?
- 週の労働日数が少ない従業員にも、年5日の取得義務は適用されるのでしょうか?
これらの疑問に答えながら、企業が多様な働き方を推進しつつ、全ての従業員が安心して年次有給休暇を取得できるような、法令遵守と実務対応のポイントを詳しく解説します。
複雑に感じられる非正規雇用者の有給休暇管理も、正しい知識と具体的な対応策を知れば、きっと円滑に進められます。次回の記事もどうぞご期待ください!
次回の記事は👉知っておきたい!年次有給休暇のすべてvol10 パート・アルバイトの有給休暇管理、中小企業が知るべき実務と法的リスク
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント