本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol8です。
働き方改革が推進される現代において、労働者の健康と生産性の向上は、企業にとって喫緊の課題となっています。
前回の記事では、柔軟な働き方を支援する「時間単位年休」について解説しました。
前回の記事は👉【企業向け徹底解説】時間単位年休とは?➁時間単位年休の導入・運用を徹底解説!成功事例とポイント
今回はさらに一歩踏み込んだ国の施策、「年5日間の年次有給休暇(以下、年休)取得義務化」について、その具体的な内容と、企業・労働者が知っておくべきポイントを詳しく見ていきましょう。
年5日間の年次有給休暇取得義務化とは?企業が押さえるべきポイント
2019年4月1日より施行された労働基準法改正により、企業は特定の条件を満たす労働者に対し、年次有給休暇を年5日間取得させることが義務付けられました。
これは、日本における年休取得率の低さを改善し、労働者が確実に休暇を取得できる環境を整備することを目的とした、画期的な制度です。
年次有給休暇5日取得義務化のポイント|誰が対象で企業は何をする?
この義務化の最も重要な点は、年10日以上の年休が付与されるすべての労働者に対し、企業(使用者)が、そのうち年5日について、労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して年休を取得させなければならない、ということにあります。
制度の主要ポイント
具体的には、以下の点がポイントです。
対象となる労働者
- 正社員はもちろん、週の所定労働日数や年間所定労働時間に応じて年10日以上の年休が付与されるパートタイマーやアルバイトも対象です。
- 例えば、週4日勤務で継続勤務3年6ヶ月の場合や、週3日勤務で継続勤務5年6ヶ月の場合などが該当します。
義務の主体は企業
- 年休取得を義務付けられるのは、あくまで企業側です。
- 労働者が自ら年5日取得しなかったからといって、労働者に罰則が科されることはありません。
時季指定の原則
- 企業は、労働者の意見を十分に尊重した上で、年休を取得させる時季を指定する必要があります。
- 一方的に企業が時季を決めるのではなく、まずは労働者の希望を聴くことが求められます。
- もし労働者からの希望がない場合や、希望する時季に取得が難しい場合に、企業が時季を指定することになります。
違反時の罰則
- この義務に違反した場合、労働基準法に基づき、労働基準法に基づき、対象労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- これは、企業が年休取得を促進する責務を負うという国の強い意思の表れと言えるでしょう。
施行による企業の新たな役割
この制度は、2019年4月1日の施行以降、企業が年休をただ付与するだけのものではありません。その取得を「管理」し、「確実に取得させる」という新たな役割と責任を負うことになりました。
年5日有給取得義務化の目的と背景|企業に課された理由をわかりやすく解説
なぜ国は、企業に対して年5日間の年休取得を義務化するまでに踏み込んだのでしょうか。
その背景には、日本の労働環境が抱える深刻な課題と、それを解決しようとする明確な目的があります。
年5日有給取得義務化の背景|日本の低い年休取得率と課題
最大の背景として挙げられるのが、日本の年次有給休暇取得率の低さです。
法改正以前、日本の年休取得率は長年にわたり国際的に見ても極めて低い水準にありました。
低い年休取得率の実態と国際比較
厚生労働省が公表している「平成29年就労条件総合調査」(2017年実績)によると、日本の年次有給休暇取得率は49.4%でした。
これは、付与された有給休暇の半分も取得されていないという実態を示しています。
同時期の国際比較調査でもこの傾向は顕著です
例えば2018年に発表されたエクスペディアの「世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査」によると、日本の取得率が50%で調査対象19ヶ国中3年連続最下位だったのに対し、欧米主要国では以下のような高い取得率が報告されていました。
- フランス、スペイン、ブラジル:100%
- ドイツ:93%
- イギリス:84%
- アメリカ:80%
- オーストラリア:70%(日本の次に取得率が低い国でも、日本より20ポイント高い)
このように、日本の取得率は欧米主要国と比較して倍近く、あるいはそれ以上に低い状況が常態化していました。
低い取得率が引き起こす問題と改革の必要性
これは、労働者に年休が付与されていても、実際に取得されていないという実態を示しております。そして
以下のような問題を引き起こしていました。
- 長時間労働の常態化
- 年休が取得しにくい環境は、結果として労働者の長時間労働を助長し、心身の疲労蓄積につながっていました。
- ワークライフバランスの欠如
- 仕事と私生活の調和が取れず、プライベートの充実や自己啓発、育児・介護といった家庭責任との両立が難しい状況がありました。
- 労働者の心身の健康への影響
- 休息が十分に取れないことで、過労による健康問題やメンタルヘルスの不調が増加するリスクがありました。
- 生産性の伸び悩み
- 疲弊した状態では、業務の質や効率が低下し、企業全体の生産性向上を妨げる要因にもなっていました。
こうした状況を改善し、「働き方改革」を実効性のあるものとするために、年休取得の促進が不可欠とされました。
年5日有給取得義務化の目的|労働者の休暇取得促進と企業の責務
年5日間の年休取得義務化には、明確な目的があります。
- 労働者の年休取得の促進と取得率の向上
- まずは何よりも、労働者がためらいなく年休を取得できるような環境を整備し、実際の取得率を底上げすることを目指しています。
- 企業における年休取得の計画的かつ確実な実施
- これまでは労働者自身が希望する時季に取得を申し出た場合を除き、企業側から積極的に取得を促すことが少なかった年休取得について、企業が「計画的に」「確実に」実行する仕組みへと転換させることが目的です。
- これにより、企業は業務計画に年休を織り込みやすくなり、労働者は「休みづらい」といった心理的なハードルが下がる効果が期待されます。
この義務化は、単なる罰則規定の追加ではありません。
労働者の健康維持と生活の質の向上、ひいては企業全体の活力と生産性の向上へとつなげるための、重要な一歩として位置づけられています。
年次有給休暇5日取得義務化|企業が取るべき対応と実務の手順
年5日間の年休取得義務化は、企業にとって単に「休みを取らせればいい」という話ではありません。
法改正の趣旨を理解し、適切に運用するためには、具体的な対応と留意点があります。
年次有給休暇5日取得義務化|企業がすぐ実施できる具体的対応ポイント
この義務化に対応するため、企業は主に以下の点を実施する必要があります。
年休管理簿の作成と保管
- 企業は、労働者一人ひとりの年次有給休暇の取得状況を把握するため、「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務があります(法的には5年間と定められていますが、当分の間、経過措置として3年間保存する義務があります)。
- ここには、労働者ごとに「基準日(年休付与日)」「付与日数」「取得日数」「取得時季」などを記載します。
- これにより、誰が何日年休を取得し、あと何日残っているかを正確に管理できます。
時季指定の仕組み構築
- 義務化の核心である年5日の年休取得を確実にするため、企業は時季指定の仕組みを整える必要があります。
- 具体的には、労働者の意見を十分に聴き、その意見を尊重した上で、企業が取得時季を指定することになります。
- この際、就業規則に年休の時季指定に関する規定を明記し、労働者へ周知徹底することが重要です。
- 労働者がすでに5日以上年休を取得している場合は、企業が時季指定を行う必要はありません。
計画的付与制度の活用
- 企業が年休を計画的に取得させる方法として有効なのが「計画的付与制度」です。
- これは、労使協定を締結することで、あらかじめ企業が年休取得日を計画的に割り振る制度です。
- 例えば、ゴールデンウィークの谷間や夏季休暇、年末年始などに一斉休暇日を設ける方法や、部署・グループごとに交代で取得させる方法などがあります。
- この制度を活用すれば、確実に5日以上の年休を取得させることができ、企業にとっても業務計画が立てやすくなるメリットがあります。
計画的付与制度の記事はコチラ
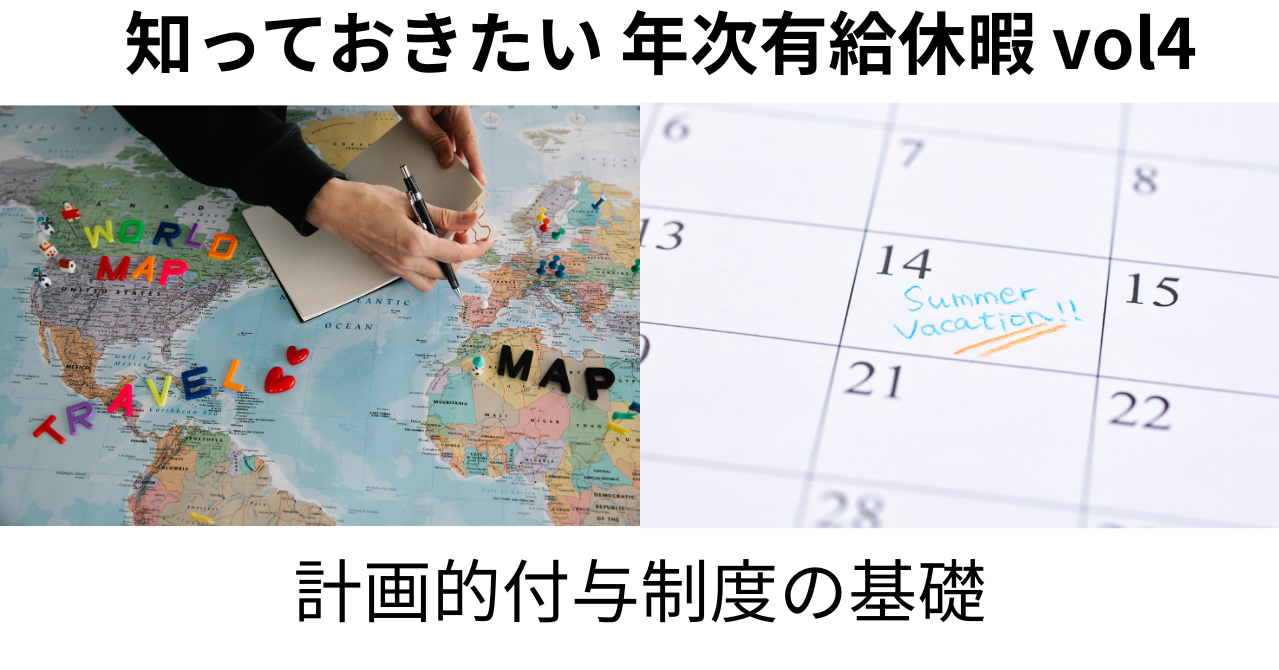
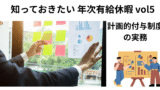
労働者への周知徹底
- 新制度の導入にあたり、企業は年5日間の年休取得が義務化されたこと、そのルール、そして年休管理簿の存在などを、全労働者に漏れなく周知する必要があります。
- 説明会の実施、社内掲示、イントラネットでの情報提供など、多角的なアプローチで理解を促すことが大切です。
年次有給休暇5日取得義務化で企業が注意すべき点|運用時の留意事項まとめ
スムーズな運用のためには、以下の点に留意してください。
- 労働者の意見を最大限尊重すること
- 企業が年休の時季を指定する場合でも、まずは労働者の希望を聴くことが必須です。
- 労働者の希望を無視して一方的に時季を指定することは、制度の趣旨に反するだけでなく、労働者のモチベーション低下やトラブルの原因にもなりかねません。
- できる限り労働者のライフスタイルや業務状況を考慮し、調整を図る姿勢が求められます。
- 企業側の時季指定権の行使条件
- 企業が時季指定権を行使できるのは、労働者が自ら年5日間の年休を取得しなかった場合に限られます。
- また、企業が指定した日であっても、事業の正常な運営を妨げる場合は、労働者は企業に時季変更を申し出る権利があります。
- この「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断は慎重に行う必要があり、客観的な根拠が求められます。
- 既存の年休取得制度との兼ね合い
- すでに独自の年休取得促進策や、年休の計画的付与制度を導入している企業も多いでしょう。
- 今回の義務化は、これまでの制度に上乗せされる形で適用されます。
- 既存の制度と新しい義務化のルールが矛盾しないか、労働者にとってより有利な運用を阻害しないかなどを確認し、必要に応じて就業規則の見直しを含めた調整が必要です。
これらの対応を適切に行うことで、企業は法定義務を果たすだけでなく、労働者のワークライフバランス向上と、ひいては企業全体の生産性向上にもつなげられるでしょう。
年5日の有給休暇義務化後の取得率推移と企業対応の効果
年5日間の年休取得義務化は、その効果を着実に示しています。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、2023年(令和5年調査)における日本の年次有給休暇取得率は、過去最高の65.3%を記録しました。
義務化が施行される直前の2017年の取得率が49.4%(平成29年調査)であったことを考えると、約16ポイントも上昇したことになります。
この明確な上昇は、年5日の取得義務化が、日本の低い年休取得率改善に大きく貢献していることを示しています。
「努力義務」ではなく「義務」として企業に責任を課し、罰則規定を設けたことが、企業側の年休取得促進への取り組みを促し、結果として労働者の年休取得が進んだと言えるでしょう。
年5日間の有給休暇義務化による企業への影響と今後の課題
年5日間の年休取得義務化は、取得率の向上という成果を上げつつも、企業や社会全体に様々な影響を与え、今後も継続的な取り組みが求められる課題も存在します。
年5日有給義務化が企業に与える影響|業務負担や人員配置の変化を解説
- 年休管理の負担増
- 義務化により、企業は年休管理簿の作成や時季指定の調整など、年休管理に関する業務負担が増加しました。
- 特に中小企業にとっては、新たな体制構築が課題となるケースもあります。
- 業務体制の見直し、人員配置の最適化
- 労働者の年休取得が確実になることで、企業は業務計画を立てる際に、より計画的に人員配置や業務分担を考慮する必要が生じました。
- これにより、属人化の解消や業務の標準化が進むきっかけとなる場合もあります。
- 生産性向上への期待
- 労働者が適切に休息を取ることで、心身のリフレッシュが図られ、結果として業務効率や集中力の向上、ひいては企業全体の生産性向上につながることが期待されます。
- また、年休取得を前提とした業務設計は、無駄の排除や効率化を促す側面も持ちます。
年5日有給義務化が社会に与える影響|働き方改革と労働環境改善の効果
- 働き方改革のさらなる推進
- 年休取得義務化は、長時間労働の是正や多様な働き方の推進といった「働き方改革」の旗印の下で導入されました。
- この義務化が浸透することで、社会全体の労働時間に対する意識が変化し、より健康で持続可能な働き方が実現に近づくと考えられます。
- 労働環境改善への意識向上
- 企業が年休取得を積極的に促すようになることで、労働者側も自身の権利意識が高まり、休息の重要性に対する認識が深まります。
- これにより、企業と労働者双方の意識変革が進み、より良い労働環境を共に作り上げていく土壌が育まれることが期待されます。
年5日有給取得義務化の課題|企業と労働者が直面する運用上の問題
政府は「少子化社会対策大綱」などで、年次有給休暇の取得率を「2025年までに70%以上」とする目標を掲げています。
取得率は着実に向上しているものの、この目標にはまだ達しておらず、引き続き以下の課題が挙げられます。
- 中小企業における対応の難しさ
- 大企業に比べ、人員やリソースが限られる中小企業では、年休管理や代替要員の確保に引き続き課題を抱えるケースが少なくありません。
- 政府や関係機関による、よりきめ細やかな支援が求められます。
- 実効性の担保と運用上の課題
- 義務化されたとはいえ、全ての企業で円滑に運用されているとは限りません。
- 「休みづらい雰囲気」の払拭や、業務繁忙期の年休取得調整など、実効性を高めるための運用上の工夫が各企業に求められます。
- 単に5日取得させるだけでなく、労働者が本当に「休みたい」ときに休める環境整備が重要です。
- さらなる年休取得促進のための施策
- 義務化は最低限の5日間ですが、日本の年休取得率は国際的に見てまだ改善の余地があります。
- 今後は、さらなる取得促進に向けた追加的な施策や、企業文化そのものの変革が重要になってくるでしょう。
- 例えば、年休取得の推奨期間の設定や、管理職が率先して年休を取得するといった、企業文化を醸成する取り組みが求められます。
まとめ|年5日間年次有給休暇取得義務化のポイントと企業対応
2019年4月1日に施行された年5日間の年次有給休暇取得義務化は、日本の低い年休取得率を改善し、労働者の健康とワークライフバランスの向上、ひいては企業全体の生産性向上を目指す重要な法改正です。
この義務化は、企業に年休管理簿の作成や時季指定の仕組み構築といった新たな責任を課す一方で、計画的付与制度の活用などにより、計画的な年休取得を可能にしました。
企業は、労働者の意見を尊重しつつ、これらの対応を適切に行うことで、法的義務を果たすだけでなく、より良い職場環境を構築することができます。
働き方改革を推進する上で、年休取得義務化は大きな一歩となりました。
厚生労働省のデータが示す通り、取得率は着実に向上しており、この法改正の効果は明確です。
企業と労働者双方が制度の趣旨を理解し、協力しながら運用していくことが、持続可能な社会と企業の成長、そして労働者一人ひとりの豊かな生活を実現するために不可欠と言えるでしょう。
次回予告|年休取得義務化に対応する就業規則と管理簿の作成・運用
今回の記事で、年5日間の年次有給休暇(年休)取得義務化の背景、目的、そして企業が取るべき対応の概要をご理解いただけたかと思います。
しかし、実際に制度を運用する上で、具体的な疑問や課題を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで次回は、この義務化における就業規則への具体的な記載例と、企業に作成・保存が義務付けられている年次有給休暇管理簿の具体的な作り方を詳しく解説します。
法改正への対応をより確実にするため、実務に役立つ情報をお届けしますので、ぜひご期待ください。
次回の記事は👉年5日有給取得義務を運用!就業規則の書き方と管理簿の具体例
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
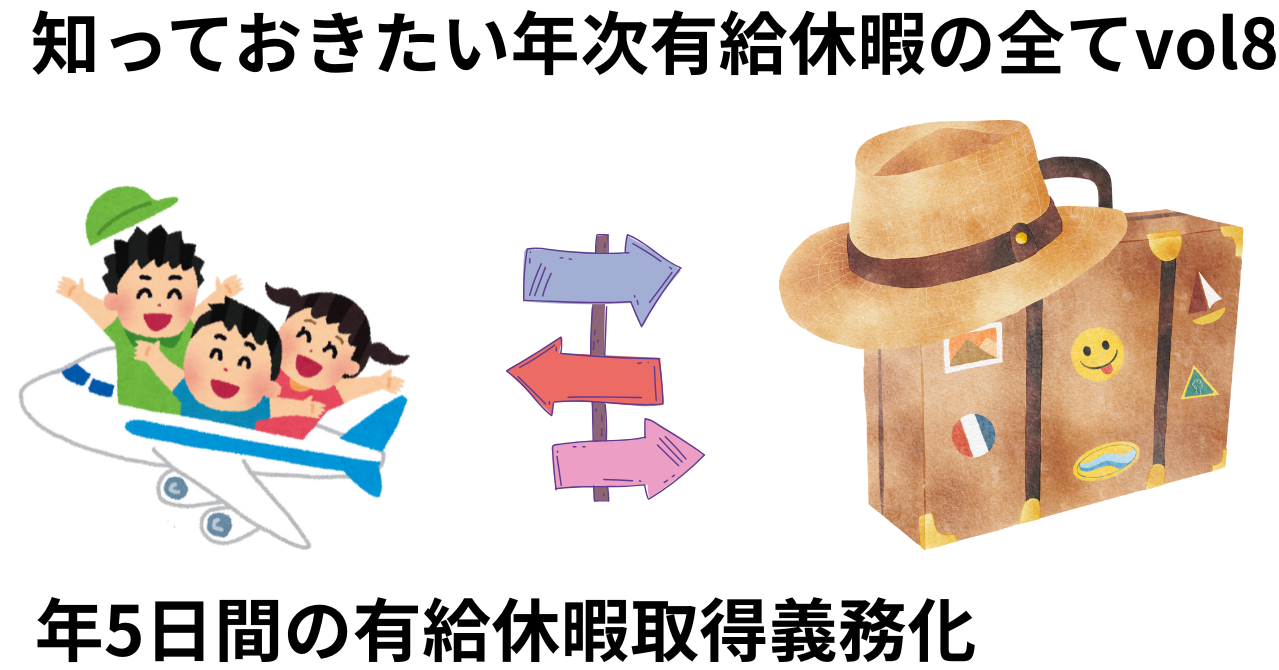

コメント