本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol7です。
前回の記事では、時間単位年休が従業員のワークライフバランス向上といかに深く結びついているか、そしてその法的背景や企業・従業員双方にもたらすメリット・デメリット(留意点)について詳しく解説しました。
前回の記事は👉【企業向け徹底解説】時間単位年休とは?➀導入のメリットと制度概要を徹底解説
この柔軟な制度を導入し、最大限にその効果を発揮させるためには、ただ制度を設けるだけでなく、適切な準備と継続的な運用が不可欠です。
今回焦点を当てるのは、まさにその「導入・運用」に関する実践的なポイントです。
労使間の合意形成から就業規則への明確な記載、そして日々の勤怠管理や従業員への周知徹底に至るまで、時間単位年休を形骸化させず、企業と従業員の双方にとって真に有益な制度として機能させるためのステップを具体的に見ていきましょう。
企業向け|時間単位年休の導入・運用ポイントと活用法
時間単位年休は、適切に導入・運用することでその効果を最大限に発揮します。制度を形骸化させず、企業と従業員双方にとって有益なものとするためには、以下のポイントを押さえることが不可欠です。
労使協定で時間単位年休を導入する際の手順とポイント
時間単位年休を導入する上で最も重要なのが、労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定)の締結です。
これは労働基準法第39条第4項で義務付けられており、労使協定で以下の項目を明確に定める必要があります。
- 時間単位年休の対象となる労働者の範囲
- 全従業員を対象とするのが一般的ですが、特定の部署や職種に限定する場合はその旨を明記します。
- 時間単位年休として取得できる年次有給休暇の日数
- 法律で年間5日が上限と定められているため、その範囲内で具体的な日数を設定します。
- 1日の年次有給休暇に相当する時間数
- 従業員の所定労働時間に合わせて、1日分の年休が何時間に相当するかを定めます。
- 例えば、1日の所定労働時間が8時間の企業であれば「8時間」となります。
- この時間数は、所定労働時間が異なる従業員がいる場合でも、原則として全従業員で統一する必要があります。根拠規則・通達(労働基準法施行規則 第24条の5 第3項)(厚生労働省通達(基発0426第3号、平成22年4月26日)
- 時間単位年休の取得方法
- 申請手続き、承認フロー、申請期限などを具体的に定めます。
労使協定を締結することで、時間単位年休の適用範囲やルールが明確になり、従業員は安心して制度を利用でき、企業側も公平かつ適切に運用できます。
時間単位年次有給休暇に関する労使協定書
株式会社[会社名](以下、「甲」という。)と、甲の従業員の過半数で組織する労働組合[労働組合名](労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者[氏名])(以下、「乙」という。)は、時間単位年次有給休暇制度の導入に関し、以下のとおり協定を締結する。
第1条(目的)
本協定は、従業員のワークライフバランスの向上と、より柔軟な働き方を実現するため、労働基準法第39条第4項に基づき、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度(以下、「時間単位年休」という。)を設けることを目的とする。
第2条(時間単位年休の対象者)
時間単位年休の対象となる労働者は、甲に雇用される全ての労働者とする。ただし、[特別の事情がある場合に限定する記述。例:日雇労働者、週の所定労働時間が極めて短い労働者など、時間単位年休になじまない者は除くことができる]を除く。
第3条(時間単位年休として取得できる日数)
時間単位年休として取得できる年次有給休暇の日数は、1年につき5日を上限とする。
第4条(1日の年次有給休暇に相当する時間数)
1日の年次有給休暇に相当する時間数は、8時間とする。 ただし、所定労働時間が8時間以外の従業員(例:短時間勤務者)がいる場合においても、原則としてこの時間を適用する。
第5条(取得単位)
時間単位年休は、1時間単位で取得するものとし、半日単位年休と併用することはできない。
第6条(時間単位年休の取得方法)
- 時間単位年休を取得しようとする従業員は、原則として、取得希望日の前日までに、所定の申請書または[会社が指定するシステム名称]を通じて所属長に申請するものとする。
- 申請書には、取得希望日時、取得時間数、取得理由(理由を問わない場合はその旨を記載)を明記するものとする。
- 所属長は、申請された時間単位年休が業務の正常な運営を妨げる場合に限り、時季変更を求めることができる。
- 時間単位年休は、従業員が請求する時季に与えるものとし、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、拒否することはできない。
第7条(年次有給休暇残日数への換算)
時間単位年休として取得した時間数は、1日の年次有給休暇に相当する時間数(第4条)をもって日単位の年次有給休暇から控除するものとする。 例:所定労働時間8時間の従業員が3時間取得した場合、日単位の年休残日数から3/8日(0.375日)を控除する。
第8条(不利益取扱いの禁止)
従業員が時間単位年休を取得したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第9条(協定の改廃)
本協定を改廃する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定は、[締結年月日]より発効する。
[締結年月日]
甲:株式会社[会社名] 代表者役職・氏名:[代表取締役氏名] 印
乙:[労働組合名](または労働者の過半数を代表する者) 代表者氏名:[代表者氏名] 印
【注記】
- [会社名]、[労働組合名]、[代表取締役氏名]、[代表者氏名]、[締結年月日]は貴社の情報に置き換えてください。
- 第2条の対象者範囲や、第4条の1日あたりの時間数は、貴社の実態に合わせて調整してください(特に短時間勤務者が多い場合など)。
- 第6条の取得方法(申請期限、承認フロー)も、貴社の運用に合わせて具体的に記述してください。
- このサンプルは一般的なものであり、個別の事情や特殊な業種によっては追加・修正が必要となる場合があります。専門家(社会保険労務士等)にご相談の上、最終的な作成を行ってください。
労使協定の取扱い
- 提出義務:なし
- 保管義務:あり
- 従業員説明:推奨
- 労使署名済の原本を会社で保管しておくことで、将来のトラブル対応にも備えられます。
時間単位年休を就業規則に記載する際のポイント
労使協定で定めた内容に基づき、就業規則にも時間単位年休に関する規定を明記する必要があります。
就業規則は職場のルールブックであり、従業員はこれを通じて制度の詳細を把握します。
具体的には、以下の項目を盛り込みましょう。
- 時間単位年休の取得に関する条文(労使協定締結の旨を含む)
- 対象となる労働者
- 取得可能時間数(年間上限)
- 1日の年休に相当する時間数
- 申請手続き、取得単位(例:1時間単位)
- その他、必要な事項
就業規則に明確に記載することで、従業員への周知が徹底され、制度に対する理解が深まります。
以下に、就業規則に記載する時間単位年次有給休暇に関する条文のサンプルを示します。貴社の既存の就業規則に合わせ、必要に応じて章や条の番号を調整してください。
第〇条(時間単位年次有給休暇)
- 社員が、労働基準法第39条に定める年次有給休暇を、時間単位で取得することを希望する場合は、労使協定に定めるところにより、時間単位で取得することができる。
- 前項の時間単位年次有給休暇の取得に関する事項は、別に定める「時間単位年次有給休暇に関する労使協定書」によるものとする。
- 時間単位年次有給休暇の対象となる社員の範囲、取得できる日数(年間上限5日)、1日の年次有給休暇に相当する時間数、取得方法、その他の取り扱いについては、前項の労使協定に定める。
【就業規則への記載ポイント】
- 労使協定との連携
- 就業規則では、労使協定で定めた詳細な内容をすべて書き出すのではなく、「労使協定に定める」とすることで、規則自体を簡潔に保ちつつ、法的要件を満たします。
- 必須事項の明記
- 労働基準法で定められている上限日数(年間5日)や、1日の年次有給休暇に相当する時間数など、特に重要な項目については、労使協定の存在を明示しつつ、就業規則にも記載することで、社員への周知を徹底します。
- 柔軟性
- 労使協定は従業員の過半数代表者との合意で比較的柔軟に変更できますが、就業規則の変更は届出などが必要になるため、両者の関係性を考慮した記載が重要です。
このサンプルは一般的な例ですので、貴社の労使協定の内容と完全に一致するよう、必要に応じて文言を調整してください。
勤怠管理・申請承認フローを整備して時間単位年休を活用
時間単位年休の円滑な運用には、適切な管理体制の整備が不可欠です。
1時間単位という細かい取得に対応するため、以下の点を見直しましょう。
- 勤怠管理システムの活用
- 手作業での管理はミスや手間が増えるため、時間単位年休の取得状況を正確に記録・集計できる勤怠管理システムの導入や既存システムへの機能追加を検討しましょう。
- システムを活用することで、管理業務の効率化と正確性の向上が図れます。
- 申請・承認フローの明確化
- 従業員が迷うことなく申請でき、上長が迅速に承認できるようなシンプルで分かりやすいフローを確立します。
- 口頭でのやり取りだけでなく、書面やシステム上での申請・承認履歴が残るようにすることも重要です。
- 業務への影響を考慮した上での承認判断基準も明確にしておくと良いでしょう。
時間単位年休の制度周知と従業員理解の促進
制度を導入しても、従業員にその存在や利用方法が十分に伝わっていなければ、形骸化してしまいます。以下の方法で、従業員への周知を徹底しましょう。
- 説明会の実施
- 制度導入時や定期的に説明会を開催し、制度の目的、取得方法、利用上の注意点などを直接説明する機会を設けます。
- 質疑応答の時間を設けることで、従業員の疑問や不安を解消できます。
- 社内イントラネットや掲示板での情報公開
- いつでも制度内容を確認できるよう、社内ポータルサイトや掲示板に労使協定や就業規則の関連部分、FAQ(よくある質問)などを掲載します。
- 研修やマニュアルの提供
- 管理職向けには、部下の申請を適切に承認するための判断基準や、業務調整のポイントなどを学ぶ研修を実施したり、マニュアルを提供したりすることも有効です。
これらのポイントを実践することで、時間単位年休は従業員の多様な働き方を支援し、企業の生産性向上にも貢献する、実効性のある制度として機能するでしょう。
企業事例で学ぶ時間単位年休の活用法|導入成功のポイント解説
これまで、時間単位年休の法的側面から導入・運用のポイントまでを見てきました。
しかし、制度の真価は、実際に企業でどのように活用され、従業員にどんな影響を与えているかにあります。
ここでは、時間単位年休を効果的に活用している企業の事例を通じて、その成功の秘訣を探ります。
時間単位年休を効果的に運用する企業事例|具体的な活用法
時間単位年休の導入は、業種や企業規模を問わず広がりを見せています。
ここでは架空の事例ですが、制度の効果を実感している企業の共通点をご紹介します。
事例1|IT企業A社の時間単位年休導入事例 – 従業員の自律性を尊重した運用
成長著しいIT企業A社では、開発部門を中心に時間単位年休の利用が活発です。
特徴は、申請理由を原則として問わない「従業員の自律性」を尊重した運用と、チーム内での情報共有の徹底です。
- 具体的な活用例
- 週に一度、数時間だけ業務を抜け出して子どもの習い事の送迎を行う社員。
- 集中力を高めるため、午後の数時間を自己啓発やリフレッシュに充てる社員。
- 朝の混雑時間を避けて通勤し、その分を午後の業務に充てる社員。(※この活用方法はフレックスタイム制度とは異なり、あくまで年次有給休暇の枠内で柔軟な出退勤を実現するものです。)
- 成功の秘訣
- 経営層からの強いメッセージ
- 「社員の生産性は時間で測るものではない。成果を出しつつ、自分の時間を有効活用してほしい」という明確なメッセージが社員に安心感を与えています。
- 透明性の高い共有ツール
- チーム内で時間単位年休の取得状況がリアルタイムで確認できるツールを導入。
- これにより、他のメンバーが業務調整をスムーズに行うことができ、お互いの状況を理解し協力し合う文化が醸成されています。
- 経営層からの強いメッセージ
事例2|製造業B社の時間単位年休活用事例 – 長期的な人材育成と定着への貢献
伝統的な製造業であるB社では、以前は有給休暇の取得率が低いことが課題でした。
しかし、時間単位年休を導入し、特に若手社員や育児・介護中の社員向けに積極的に推奨した結果、定着率向上に繋がっています。
- 具体的な活用例
- 共働きで子育て中の社員が、子どもの急な発熱や保育園の行事に合わせて柔軟に数時間単位で休暇を取得。
- ベテラン社員が、親の通院付き添いや自身の健康診断のために利用。
- 業務の繁閑に合わせて、集中的に作業した後に短時間でリフレッシュする社員。
- 成功の秘訣
- 部門長の理解と推進
- 各部門長が時間単位年休の重要性を理解し、率先して取得を促すことで、部下が申請しやすい雰囲気を作っています。
- 業務の標準化と多能工化
- 誰かが短時間抜けても業務が滞らないよう、業務プロセスの標準化を進め、複数の社員が多様な業務に対応できる「多能工化」を推進。
- これにより、属人化を解消し、休暇取得を容易にしています。
- 部門長の理解と推進
時間単位年休導入の工夫と成功要因の分析 – 効果的運用のポイント
上記のような企業事例から見えてくる、時間単位年休を成功させるための共通の要素は以下の通りです。
- 経営層・管理職の強いコミットメントと理解
- 制度を単なる義務ではなく、「従業員への投資」と捉え、経営層が積極的に導入の意義を発信することが重要です。
- 管理職が制度を理解し、部下の取得を後押しする姿勢がなければ、従業員は利用をためらってしまいます。
- 明確なルールとシンプルな運用フロー
- 労使協定や就業規則で、取得条件、申請方法、承認プロセスを曖昧なく明確に定めることがトラブルを防ぎます。
- 勤怠管理システムなどを活用し、申請から承認、記録までを簡素化することで、従業員も管理側も負担なく運用できます。
- 職場の協力体制とコミュニケーション
- 誰かが時間単位年休を取得しても、業務が円滑に進むような協力体制が必要です。
- 日頃からの業務共有、マルチタスク化、そしてチーム内でのオープンなコミュニケーションが、お互いの状況を理解し、支え合う文化を育みます。
- 制度の目的とメリットの継続的な周知
- 導入時だけでなく、定期的に全従業員に対し、時間単位年休の目的(ワークライフバランス向上、生産性アップなど)や具体的な利用例を周知することが大切です。
- これにより、制度が形骸化することなく、従業員の働き方の選択肢として定着します。
時間単位年休は、単なる休暇制度ではなく、現代の多様な働き方を支え、企業の成長と従業員の幸福を両立させるための戦略的なツールとなり得ます。
自社の状況に合わせて工夫を凝らし、効果的な運用を目指しましょう。
柔軟な働き方と時間単位年休の未来 – 労働生産性向上とワークライフバランスの実現
これまでの記事で、時間単位年休の基本的な概要から、法改正による導入の経緯、企業と従業員双方にとってのメリット・デメリット(留意点)、そして導入・運用上の具体的なポイントや成功事例まで、多角的に解説してきました。
時間単位年休が企業と従業員にもたらすメリット – 生産性向上とワークライフバランスの実現
時間単位年休は、単なる福利厚生制度の追加にとどまらず、現代社会が求める柔軟な働き方を実現するための強力なツールです。
- 従業員にとって
- 短時間の通院や子どもの学校行事、役所での手続きといった「ちょっとした用事」のために、大切な1日分の有給休暇を消費する必要がなくなります。
- これにより、プライベートな都合と仕事との両立が格段にしやすくなり、結果として従業員満足度の向上やストレスの軽減につながります。
- より計画的に有給休暇を消化できることで、心身のリフレッシュが促され、仕事への集中力やモチベーション維持にも良い影響を与えます。
- 企業にとって
- 従業員の満足度向上は、そのまま定着率アップや優秀な人材の確保に直結します。
- 従業員が安心して働ける環境は、結果的に生産性の向上にも寄与し、企業の競争力を高めます。
- また、柔軟な働き方を推進する企業としての姿勢は、企業イメージの向上にもつながり、採用活動やブランド価値向上にも好影響をもたらします。
このように、時間単位年休は、従業員のニーズに応えることで、巡り巡って企業の成長を後押しするという、まさにWin-Winの関係を築くための制度だと言えるでしょう。
まとめ|時間単位年休の導入・活用で企業と従業員の両立支援を実現
現代は、少子高齢化による労働人口の減少、多様な価値観を持つ人材の増加、そしてAIやDXの進展による働き方の変化など、企業を取り巻く環境は大きく変動しています。
このような中で、「働き方改革」は企業が持続的に成長していく上で避けて通れないテーマとなっています。
時間単位年休は、この働き方改革の中核をなす制度の一つとして、今後もその重要性を増していくでしょう。
- 多様な人材の活躍推進
- 育児や介護と仕事を両立する人、副業・兼業を行う人、自己研鑽に時間を充てたい人など、多様な背景を持つ従業員が自身のライフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境は、企業のダイバーシティ推進に不可欠です。
- エンゲージメントの向上
- 従業員が「会社が自分の働き方を尊重してくれている」と感じることは、企業への信頼とエンゲージメントを高めます。
- これは、単なる労働時間短縮ではない、より質の高い働き方を追求する上で重要です。
- 企業文化の変革
- 制度の導入をきっかけに、従業員同士が業務を助け合い、情報を共有し合うといった協力的な企業文化が育まれることも期待できます。
時間単位年休は、単に法律で定められた制度として導入するだけでありません。
企業の成長戦略の一環として捉え、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整備するための重要な施策として、今後も積極的に活用されていくことでしょう。
次回予告|年5日間の年次有給休暇取得義務化の企業対応ポイント
さて次回は、企業にとって重要な課題である「年5日間の年次有給休暇取得義務化」に焦点を当てます。
次回の記事は👉年5日間の有給休暇取得義務化とは?企業の対応と実務ポイントを徹底解説
この義務化は、働き方改革の中でも特に企業が実務で対応を迫られるポイントです。
企業がどのようにこの義務を果たし、かつ効率的な運用を行うべきか、具体的な対応策や注意点を分かりやすく解説します。
法律遵守はもちろんのこと、従業員の健康とモチベーション維持に繋がる実務の秘訣をお伝えしますので、ぜひご期待ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
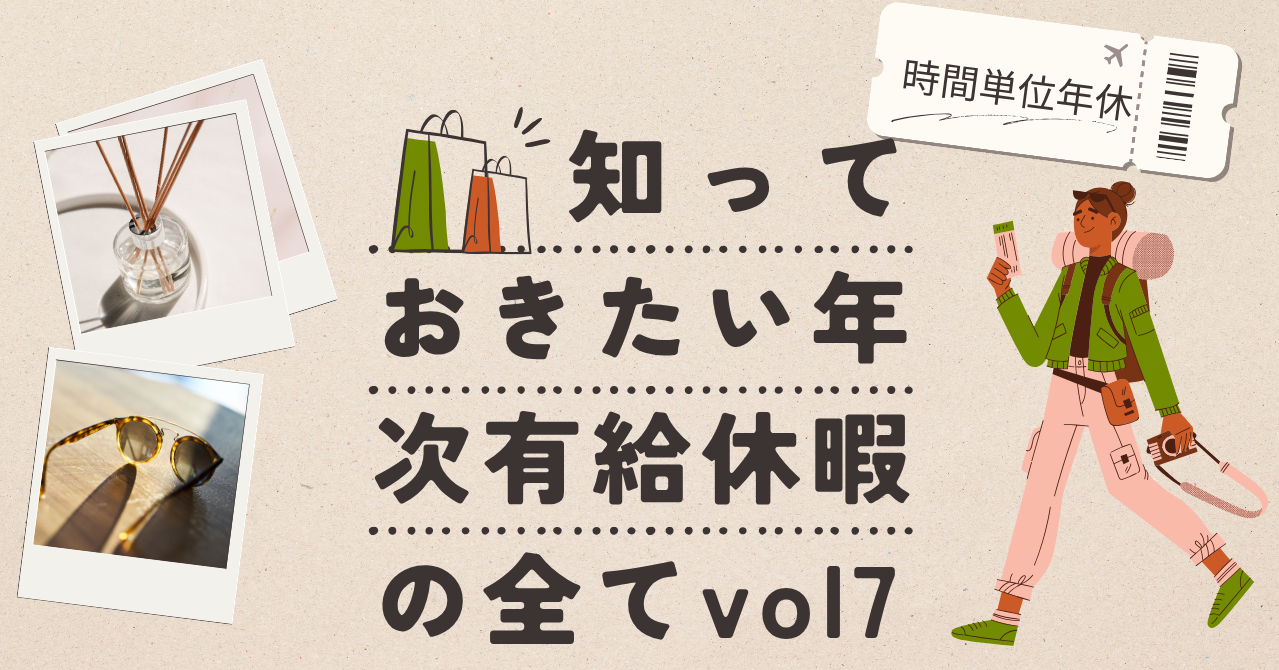

コメント