本記事は「知っておきたい!年次有給休暇のすべて」シリーズのvol6です。
前々回、前回と2話にわたり「年次有給休暇の計画的付与制度」について深掘りして解説しました。
この年次有給休暇の計画的付与制度は、会社と従業員の双方にとって多くのメリットがある、とても有効な制度です。
従業員はためらいなく有給休暇を取りやすくなり、会社は計画的に業務を進められるようになります。
前回・前々回の記事は👇
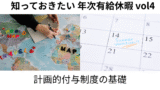
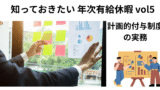
現代社会において、働き方は多様化し、個々のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が求められるようになっています。
このような背景の中で、従業員がより効率的に、かつ私生活と両立しながら働けるよう、日本の労働法制においても様々な制度が導入されてきました。
その中でも、従業員の高いニーズに応え、柔軟な働き方を促進する上で重要な制度として注目されているのが「時間単位年次有給休暇」、通称「時間単位年休」です。
時間単位年次有給休暇(時間単位年休)の概要と導入背景
年次有給休暇は、労働者の心身の疲労回復とゆとりのある生活を保障するために、労働基準法で定められた重要な権利です。
この年次有給休暇の取得は、労働基準法の原則として1日単位が基本とされてきました。
まず、時間単位年休の概要と導入の背景を見ていきましょう。
年次有給休暇制度の歴史と変遷|半日・時間単位取得への新たなニーズ
1995年(平成7年)7月27日付の通達(行政解釈)により、労働者が希望し、使用者が同意する場合に限り、1日単位での取得を阻害しない範囲で、半日単位での有給休暇(半日年休)の付与が認められてきました。
その後、2008年(平成20年)4月1日施行の労働基準法改正により、労使協定の締結を要件として、法律の条文として半日単位年次有給休暇の取得が明確に認められる形になりました。
多くの企業でこの半日年休が活用され、短時間のリフレッシュや、午前または午後の用事に対応する手段として定着しています。
しかし、短時間の通院や子どもの学校行事への参加、役所での短時間の手続き、あるいは急な体調不良など、1日や半日休むほどではないけれど、業務時間中に一時的に抜け出す必要のある用事は少なくありません。
従来の1日単位や半日単位の有給休暇では、こうした数時間程度の用事のために、過剰に休暇を消費してしまうことになります。
結果として従業員が有給休暇の取得をためらってしまうという課題がありました。
法改正による時間単位年休の導入と制度上の位置づけ
こうした課題を解決し、従業員がより気軽に、そして有効に年次有給休暇を利用できるようにする必要がありました。
そのような中で、時間単位年休は2010年(平成22年)4月1日に施行された改正労働基準法によって、正式に労働基準法に明記され、導入が認められるようになりました。
当初は企業の努力義務という位置づけでした。
しかし、2019年(平成31年)4月1日に施行された「働き方改革関連法」により、企業が労使協定を締結すれば、年5日を上限として時間単位で有給休暇を付与することが可能となり、その導入がより一層推進されることになりました。
この法改正により、時間単位年休は、単なる柔軟な制度としてだけでなく、年次有給休暇の確実な取得を促す重要な手段としても位置づけられています。
時間単位年休とは?制度の仕組み・特徴・導入メリットを解説
時間単位年休は、文字通り、年次有給休暇を1時間単位で取得することを可能にする制度です。
この制度は、従来の1日単位や半日単位の有給休暇では対応しきれなかった、より短時間の私的な用事に対応するために導入されました。
時間単位年休の定義とは?1時間単位で取得できる年次有給休暇の仕組み
時間単位年休は、労働基準法第39条第4項に基づいて運用される、労働者が1時間単位で取得できる年次有給休暇です。
これは、原則として1日単位で付与される年次有給休暇の一部を、労使協定で定めた範囲内で、より細かく分割して取得することを認めるものです。
例えば、所定労働時間が8時間労働の企業であれば、1日分の年休を8時間の時間単位年休として利用でき、必要な時間だけ取得し、残りの時間は通常通り業務を行うことが可能になります。
ただし、時間単位年休として取得できるのは、年間5日分が上限と定められています。
時間単位年休の目的|従業員のワークライフバランス向上と柔軟な働き方の推進
時間単位年休の導入目的は、主に以下の2点に集約されます。
- 従業員のワークライフバランスの向上
- 短時間の通院、子どもの学校行事、役所での手続き、介護、あるいは単に気分転換のための短時間の休憩など、従業員が私生活における多様なニーズに柔軟に対応できるようになります。
- これにより、仕事とプライベートの調和が図られ、従業員の心身の負担が軽減され、生活の質(QOL)の向上が期待されます。
- 柔軟な働き方の推進
- 企業にとっても、従業員の様々な状況に合わせた柔軟な働き方を提供できることで、生産性の向上、優秀な人材の確保・定着、従業員満足度の向上、そして企業イメージの向上に繋がります。
- 特に、育児や介護と仕事を両立する従業員にとっては、この制度がキャリア継続の大きな支えとなります。
時間単位年休の法的根拠|労働基準法改正による導入と制度化の背景
時間単位年休は、2010年(平成22年)4月1日に施行された改正労働基準法によって、正式に労働基準法第39条第4項に明記され、導入が認められるようになりました。
この時点では、時間単位年休の取得上限は特に設けられていませんでした。
その後、2019年(平成31年)4月1日に施行された「働き方改革関連法」による労働基準法第39条第4項の改正により、企業が労使協定を締結することで、年間5日を上限として時間単位で有給休暇を付与することが可能となり、その導入がより一層推進されることになりました。
この「働き方改革関連法」の施行においては、労働基準法第39条に第7項が追加され、「年5日の年次有給休暇の時季指定義務」が企業に課されました。
時間単位年休で取得した日数は、この義務化された5日間の取得にはカウントされません。
しかしながら、厚生労働省は、年次有給休暇の取得促進という全体的な流れの中で、従業員の多様な事情に対応できるよう、時間単位年休の積極的な活用をウェブサイトやパンフレットなどで推奨しました。
具体的には、「治療のための通院、子どもの学校行事参加、家族の介護など、労働者の多様な事情に応じて柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位年休制度を導入しましょう」といったメッセージを発信しています。
時間単位年休の企業側メリット・デメリット|導入による影響と注意点
時間単位年休の導入は、企業側にとっても多くの利点をもたらしますが、同時にいくつかの課題も発生させます。
制度導入を検討する際は、これらのメリットとデメリットを総合的に理解し、自社にとって最適な運用方法を検討することが重要です。
時間単位年休の企業側メリット|従業員満足度・生産性向上・人材確保
時間単位年休を導入することで、企業は以下のような多角的なメリットを享受できます。
従業員満足度の向上と定着率アップ
従業員が自身のライフスタイルや急な用事に合わせて柔軟に有給休暇を取得できることは、従業員満足度の向上に直結します。
プライベートな用事を諦めたり、無理に1日休む必要がなくなったりすることで、仕事と私生活のバランスが取りやすくなり、従業員のストレス軽減にも繋がります。
結果として、企業に対するエンゲージメントが高まり、離職率の低下や定着率の向上に貢献します。
優秀な人材の確保
今日の労働市場では、給与だけでなく、働き方の柔軟性も企業選びの重要な要素となっています。
時間単位年休のような柔軟な休暇制度は、特に育児や介護と仕事を両立したいと考える層や、自身の時間を大切にしたいと考える優秀な人材にとって魅力的な条件となります。
これにより、採用競争力が高まり、多様なバックグラウンドを持つ優秀な人材を確保しやすくなります。
柔軟な働き方による生産性向上
従業員が心身ともに健康で、安心して働ける環境は、生産性向上に不可欠です。
短時間で必要な用事を済ませられることで、集中力が途切れずに業務に戻ることができ、結果として業務効率の向上に繋がります。
また、無理な出勤による体調悪化を防ぎ、パフォーマンスの低下を回避できることも、長期的な視点での生産性向上に貢献します。
企業イメージの向上
従業員の働きやすさを重視し、ワークライフバランスを推進する企業姿勢は、社外からの企業イメージ向上にも繋がります。
特に、CSR(企業の社会的責任)やESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)が注目される現代において、従業員を大切にする企業としての評価は、ブランド価値の向上や顧客からの信頼獲得にも寄与します。
時間単位年休の企業側デメリット|勤怠管理・業務調整・運用コストの課題
一方で、時間単位年休の導入には、運用面での課題も伴います。
勤怠管理の複雑化
1日単位や半日単位の休暇と異なり、1時間単位での細かな取得を管理するためには、より詳細な勤怠管理が必要になります。
手作業での管理ではミスが発生しやすくなるため、勤怠管理システムの導入や改修が求められる場合が多く、そのためのコストや手間が発生します。
また、従業員自身も正確な申請・記録が求められるため、運用の周知徹底も重要です。
業務調整の負担増
短時間の休暇が頻繁に発生することで、部署内での業務調整や引き継ぎの頻度が増加する可能性があります。
特に、特定の業務を一人で担当している場合や、チームでの連携が密な業務においては、他の従業員への負担が増えたり、業務の停滞を招いたりするリスクも考えられます。
スムーズな運用のためには、事前の情報共有や業務の属人化解消に向けた工夫が求められます。
制度設計・運用コストの発生
時間単位年休を導入するには、労使協定の締結や就業規則の改定が必要です。
これには法務的な知識や手続きが必要となり、専門家への相談費用などが発生することもあります。
また、前述の勤怠管理システムの導入・改修費用、従業員への説明会の実施費用など、制度を設計し、円滑に運用するための初期コストや継続的なコストが発生する可能性があります。
時間単位年休の従業員のメリット・デメリット|働く人にとっての利点と注意点
時間単位年休は、その柔軟性によって、従業員一人ひとりの多様なライフスタイルやニーズに寄り添う、非常に利便性の高い制度です。
しかし、利用する上で考慮すべき点も存在します。
時間単位年休の従業員のメリット|短時間取得でワークライフバランス向上
時間単位年休の導入は、従業員にとって以下のような具体的なメリットをもたらします。
短時間の用事に対応しやすい柔軟性
最も大きなメリットは、まさに「かゆいところに手が届く」その柔軟性です。
これまでの1日単位や半日単位の有給休暇では対応しきれなかった、数時間で済むような短時間の用事に対して、ピンポイントで休暇を取得できます。
例えば、以下のようなシーンで大いに役立ちます。
- 通院や検診
- 業務時間中に病院を受診する際、半日休む必要がなくなり、必要な時間だけを充てられます。
- 子の学校行事や習い事の送迎
- 授業参観や個人面談、発表会など、短時間で参加できる学校行事への参加が容易になります。
- 役所での手続きや金融機関での用事
- 平日の日中にしか対応できない手続きも、業務に大きな支障を出さずに済ませられます。
- 介護や育児に関する突発的な対応
- 家族の急な体調不良や保育園からの呼び出しなど、緊急性の高い事態にも対応しやすくなります。
これにより、従業員はプライベートを犠牲にすることなく、仕事と両立しながら生活の質を高められます。
お勧めのクラウド勤怠管理システムソフト👉パソコンで勤怠管理3 スマートパッケージ版
年次有給休暇の取得促進と有効活用
短時間の用事に活用できることで、従業員は有給休暇の取得にためらいを感じにくくなります。
「たったこれだけの用事のために1日(または半日)休むのはもったいない」という心理的なハードルが下がるため、結果として年間の有給休暇取得日数が増加し、消化率の向上に繋がります。
これにより、従業員は心身のリフレッシュをより計画的に、かつ有効に行えるようになります。
仕事と私生活の両立が図りやすい
時間単位年休は、ワークライフバランスの実現に大きく貢献します。
業務中に発生する個人的なタスクを柔軟に処理できることで、仕事とプライベートの境界線がより明確になり、ストレスの軽減にも繋がります。
特に、育児中の親や、家族の介護を担う従業員にとっては、仕事の継続を可能にする重要な支援制度となります。
時間単位年休の従業員のデメリット|利用時の注意点と課題を解説
従業員側から見れば、時間単位年休は基本的に大きなメリットをもたらす制度であり、直接的な不利益と呼べるほどのデメリットはほとんどありません。
しかし、その利用や運用において、以下の点に留意が必要です。
企業による利用上限や運用の違い
時間単位年休は年間5日分という法的な上限がありますが、企業によってはそれ以下に制限していたり、特定の部門や職種での利用に制限を設けていたりする場合があります。
また、労使協定で定められた運用ルール(例えば、申請期限や最低取得時間など)が企業ごとに異なるため、自社の制度を事前にしっかりと確認する必要があります。
周囲との調整が必要となる場合がある
時間単位で頻繁に席を外すことが増えるため、業務の引き継ぎやチーム内での連携がより重要になります。
特に、少人数の部署や特定の業務を専門とする場合、他の従業員への一時的な負担増に繋がり、周囲への配慮や事前の綿密な調整が求められることがあります。
これにより、気軽に取得しにくいと感じる従業員もいるかもしれません。
まとめ|時間単位年休の導入メリット・デメリットと活用ポイント
今回の記事では、時間単位年休の導入背景からその法的根拠、そして企業側と従業員側の双方にもたらす具体的なメリット・デメリットについて詳しく解説しました。
柔軟な働き方が求められる現代において、時間単位年休は、従業員のワークライフバランスの向上と企業の生産性向上を両立させる可能性を秘めた、非常に重要な制度であることがお分かりいただけたかと思います。
次回予告|時間単位年休の導入・運用を成功させる実践ポイント
次回は、企業が実際に時間単位年休を導入・運用する際の具体的なポイントに焦点を当てます。
労使協定の締結方法から就業規則への記載、適切な管理体制の整備、そして従業員への効果的な周知方法まで、円滑な制度運用のための実践的なアドバイスを提供します。お楽しみに!
次回の記事は👉【企業向け徹底解説】時間単位年休とは?➁時間単位年休の導入・運用を徹底解説!成功事例とポイント
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。


コメント