本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第3話です。
こんにちは!「やさしく学ぶ年休シリーズ」、いよいよ第3話です。
第1話では、年次有給休暇(年休)がそもそもどんな制度なのか、その基本を解説しましたね。
そして第2話では、「年休はいつからもらえるの?」「何日もらえるの?」といった皆さんの疑問に答え、「6か月・8割ルール」という年休が付与されるための具体的な条件や、もらえる日数の計算方法について詳しく見てきました。
第2話は👉年休はいつもらえる?何日もらえる?—付与要件と日数の計算方法【やさしく学ぶ年休シリーズ 第2回】
もしかしたら、ここまで読んで「それって、正社員の話でしょう?」と思った方もいるかもしれませんね。
残念ながら、そう思っている方は少なくないようです。
実際に、「パートやアルバイトだから有給休暇はない」と諦めてしまっている方もいるかもしれません。
しかし、それは大きな間違いです!
パート・アルバイトでも年次有給休暇はある!「ない」という誤解を解消
今回の第3話では、この誤解をきっぱりと解消します。
年次有給休暇は、正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規雇用の皆さんも、条件を満たせば当然のように持っている大切な権利なのです。
「え、そうなの!?」と驚いた方もいるかもしれませんね。
この記事を読めば、その理由と、あなたにも年休があること、そしてその目的がきっと理解できるはずです。それでは、早速見ていきましょう。
「パート・アルバイトだから年休はない」は間違い!取得条件と日数も紹介
繰り返しになりますが、「パートやアルバイトだから年次有給休暇はない」という考えは、全くの誤りです。
労働基準法では、労働者の権利として年次有給休暇の付与が義務付けられています。
この「労働者」には、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態の名称に関わらず、会社と雇用契約を結び、指揮命令を受けて働くすべての人が含まれるのです。
つまり、あなたが雇用されて働き、法律で定められた条件を満たしていれば、どのような働き方であっても年次有給休暇を得る権利があります。
年次有給休暇の目的とは?心身の健康と生活の安定を守る2つの理由
では、なぜ年次有給休暇がこれほどまでに重要なのでしょうか? その目的は大きく分けて二つあります。
- 心身のリフレッシュと健康維持
- 日々の労働によって蓄積される疲労を回復し、心身の健康を保つために、まとまった休息は不可欠です。
- 年休は、労働者がリフレッシュし、仕事への活力を取り戻すための大切な時間です。
- 生活の安定と労働者の保護
- 年休は、休んだ日も賃金が支払われる「有給」の休暇です。
- これにより、病気や家庭の事情などで休む必要が生じた際にも、収入の心配をすることなく安心して休むことができ、労働者の生活を経済的に保障する役割も果たしています。
なぜ「パート・アルバイトは年休なし」と思われるのか?誤解の原因を解説
それなのに、なぜ「パート・アルバイトには年休がない」という誤解が広く流布してしまっているのでしょうか?
その背景には、いくつかの要因が考えられます。
一つは、昔の慣習や企業の誤った認識です。
かつては、非正規雇用の労働者への年休付与が十分に浸透していなかった時代もあり、その古い認識が根強く残ってしまっているケースがあります。
また、企業側が制度を正しく理解していなかったり、従業員への情報提供が不足していたりすることも大きな原因です。
労働者側も、自分の権利について十分な知識がないために、年休の存在を知らないまま働いている、という状況も少なくありません。
しかし、現在は法改正も進み、すべての労働者が自身の権利を正しく理解し、行使できるよう、国も企業に情報提供を促しています。
この機会に、あなたの「年休」について正しい知識を身につけましょう。
パート・アルバイトの年休付与条件|6か月勤務・出勤率8割ルールを確認
「パートやアルバイトだから、正社員とは違う特別な条件があるのでは?」と心配される方もいるかもしれませんね。
しかし、年次有給休暇が付与されるための基本的な条件は、正社員もパート・アルバイトも全く同じです。
年休が付与されるには、以下の2つの条件をクリアする必要があります。
年休条件①|パート・アルバイトも6か月以上の継続勤務で付与
これは、あなたが現在の会社で働き始めてから、最初の6か月間が経過していることを意味します。
例えば、2025年4月1日に働き始めた場合、2025年10月1日にはこの条件を満たすことになります。途中で雇用契約が更新されたとしても、実質的に継続して勤務していれば、この期間は通算されます。
年休条件②|パート・アルバイトも全労働日の8割以上出勤で有給付与
これは、最初の6か月間の間に、会社が定めた労働日のうち8割以上を実際に出勤している必要がある、ということです。
例えば、週5日勤務の人が6か月で約130日(26週 × 5日)の労働日があるとします。その8割は104日。つまり、この期間に104日以上出勤していれば、この条件をクリアしたことになります。
年次有給休暇の「出勤」とみなされる期間の具体例
- 業務上の怪我や病気で休業した期間(労災による休業)
- 育児休業や介護休業を取得した期間
- 有給休暇を取得した日
これらの日は、実際には働いていなくても、出勤率を計算する上では「出勤したもの」として扱われますのでご安心ください。
この2つの条件は、雇用形態に関わらず、すべての労働者に共通する年休付与のスタートラインとなります。
あなたがパートやアルバイトであっても、この条件を満たしていれば、年次有給休暇が付与される権利があるのです。
パート・アルバイトの年休は何日?「比例付与」の仕組みをわかりやすく解説
さて、先ほどの「6か月・8割ルール」を満たした皆さん。次に気になるのは「一体、何日有給休暇がもらえるの?」ということですよね。
正社員の場合は勤続年数に応じて日数が決まるのはご存じかもしれません。
しかし、パートやアルバイトのように、週の所定労働日数や年間の所定労働日数が少ない方の場合、もらえる年休の日数は「比例付与」という特別な仕組みで決まります。
パート・アルバイトの年休は労働日数で変わる!「比例付与」とは
「比例付与」とは、その名の通り、皆さんの働き方(労働日数)に応じて、もらえる年休の日数が「比例して少なくなる」仕組みです。
フルタイムで働く正社員と同じ日数を付与すると、労働日数に対して年休の割合が不均衡になってしまうため、このような調整が行われます。
具体的には、通常の労働者(週5日勤務など)がもらえる年休日数を基準に、皆さんの週の所定労働日数や年間の所定労働日数に応じて、もらえる年休の日数が決められます。
パート・アルバイトの年休日数を確認!比例付与の具体例と早見表
それでは、実際にあなたの年休が何日になるのか、具体的な例と表で確認してみましょう。
【週の所定労働日数と勤続年数に応じた年休付与日数(比例付与)】
| 継続勤務年数 | 週4日勤務 (年169~216日) | 週3日勤務(年121~168日) | 週2日勤務(年73~120日) | 週1日勤務(年48~72日) |
|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
(※)週所定労働日数が5日以上、または年間所定労働日数が217日以上の場合は、フルタイム労働者と同じ日数(6か月で10日、1年6か月で11日…最大20日)が付与されます。
【具体的な計算例】
- 例1
- 週3日勤務で勤続1年半の場合 上記の表を見ると、「週所定労働日数:3日」の列と「勤続期間:1年6か月」の行が交わる部分に「6日」とあります。
- つまり、このケースでは年間6日の年休が付与されることになります。
- 例2
- 週4日勤務で勤続3年半の場合 「週所定労働日数:4日」の列と「勤続期間:3年6か月」の行を見ると「10日」です。
このように、あなたの働き方と勤続年数に合わせて、もらえる年休の日数が変わるのが「比例付与」の大きな特徴です。
パート・アルバイトの年休|労働日数のカウント方法をわかりやすく解説
ここでいう「労働日数」とは、雇用契約書に書かれている日数だけを指すわけではありません。
大切なのは、実際にどれだけ働いているか、その実態です。
例えば、「契約では週5日」となっていても、実際には「週3日しかシフトに入っていない」という期間が長く続いている場合、実態に合わせて週3日勤務の年休付与日数になる可能性があります。
逆に、契約は週3日でも、恒常的に週4日以上働いている場合は、その実態に合わせて多く年休がもらえる可能性もあります。
正確な日数を把握するためには、まずはご自身の雇用契約書や直近の勤務実績を確認し、会社の人事担当者や管理者に問い合わせてみることが一番確実です。
パート・アルバイトでも簡単!自分の年休を確認する方法
さて、これまでの説明で「私にも年休があるんだ!」と理解できたことと思います。
では、実際に自分が何日の年休を持っているのか、どうすれば確認できるのでしょうか?
いざ年休を使おうと思った時に、「自分の年休残日数が分からない」という方も少なくありません。
ここでは、皆さんが自分の年休を確認するための具体的な方法をいくつかご紹介します。
年休の残日数は会社に直接確認しよう|パート・アルバイト向け
最も確実で直接的な方法は、やはり会社に確認することです。
- 就業規則を確認する
- 多くの会社では、年次有給休暇に関するルールを「就業規則」に定めています。
- 就業規則は、職場の休憩室や共有ファイルサーバーなど、従業員がいつでも閲覧できる場所に置かれているのが一般的です。
- そこに、年休の付与条件や日数、取得方法などが記載されているはずです。
- 人事担当者や管理者に問い合わせる
- あなたの年休残日数や、いつ次の年休が付与されるのかといった具体的な情報は、人事部や労務担当部署、あるいはあなたの直属の管理者(店長、リーダーなど)が把握しています。
- 遠慮せずに直接尋ねてみましょう。問い合わせる際は、「私の年休の残日数を教えていただけますか?」のように具体的に伝えるのがスムーズです。
書面で年休を確認する方法|給与明細や会社通知を活用
会社によっては、給与明細や定期的な通知で年休に関する情報が提供されていることもあります。
- 給与明細を確認する
- 会社によっては、毎月の給与明細に「有給休暇残日数」や「取得日数」が記載されている場合があります。
- 紙の明細だけでなく、ウェブで閲覧する電子明細でも確認できることがありますので、一度見てみましょう。
- 会社からの通知を確認する
- 年次有給休暇は、付与される際に会社から書面などで通知されることが義務付けられています(労働基準法施行規則第24条の7)。
- 例えば、年休が付与されたタイミングで「あなたの今年の年休付与日数は〇日です。残日数は現在〇日です」といった通知を受け取っているかもしれません。過去の通知書を探してみるのも良いでしょう。
もし、これらの方法で確認しても不明な場合は、躊躇せず、会社の担当部署に問い合わせてください。自分の持つ権利を知ることは、健全な働き方のためにとても大切なことです。
まとめ|年休はパート・アルバイトでも取得できる大切な権利
ここまで、「やさしく学ぶ年休シリーズ」の第3話として、パートやアルバイトの皆さんにも年次有給休暇が付与されること、そしてその具体的な条件や日数の計算方法について解説してきました。
改めて強調したいのは、年次有給休暇は、雇用形態や働き方に関わらず、労働基準法によってすべて働く人に保障された大切な権利であるということです。
正社員だから、パートだからといった違いで、この権利がなくなることはありません。
自分の年休の権利を知ることは、健全な働き方を実現し、心身の健康を保つ上で非常に重要です。
疲れた時にしっかりと休み、リフレッシュすることで、仕事のパフォーマンスも向上し、より充実した日々を送ることができるでしょう。
もし、この記事を読んで自分の年休について不明な点があったり、会社に問い合わせても納得のいく回答が得られなかったりした場合は、一人で悩まず、会社の担当部署に再度確認したり、あるいは労働基準監督署のような公的な機関に相談することをためらわないでください。
あなたの権利を守るためのサポートは、必ず存在します。
次回予告|年休の取得方法と申請ルールを詳しく解説
あなたの年休、きちんと取得できていますか?
年休の権利があることが分かったら、次は「どうやって取得するの?」という疑問が湧いてくるはずです。
次回の第4話では、いざ年休を取ろうと思った時の「申請ルール」や「会社は拒否できるの?」といった疑問、そして年休取得時の「注意点」について、詳しく解説していきます。
お楽しみに!
次回の記事は👉年休の取り方・使い方—申請ルールと注意点【やさしく学ぶ年休シリーズ 第4回】

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
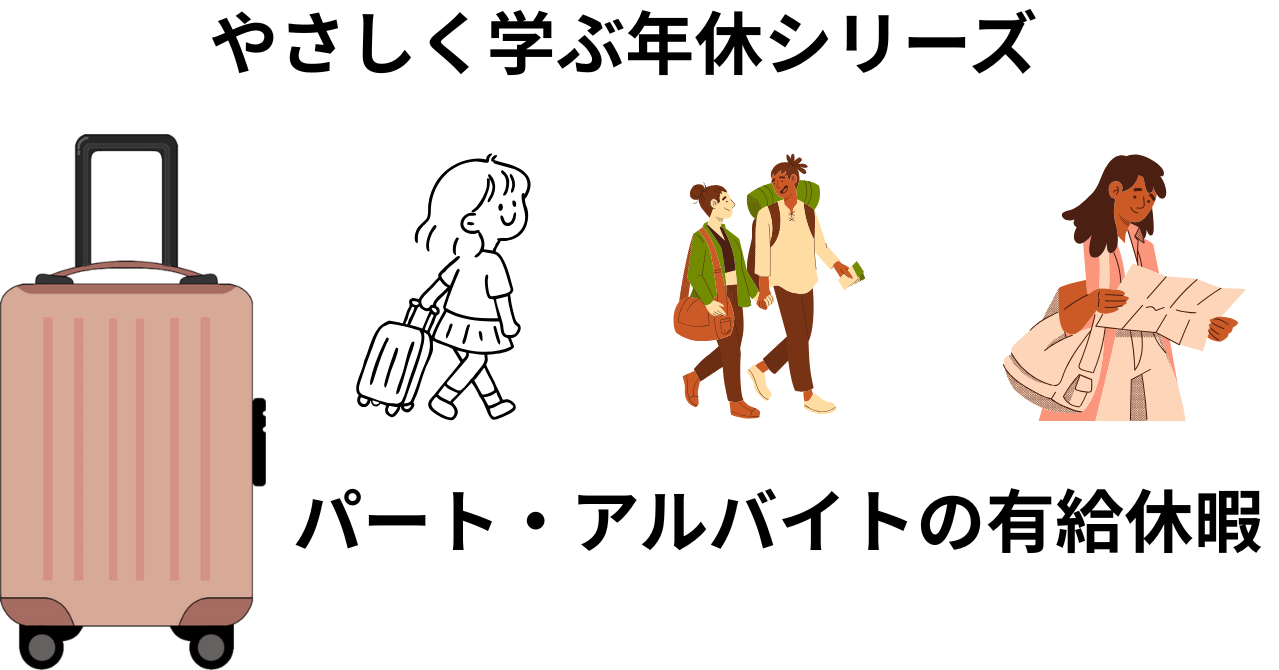
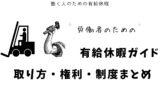
コメント