本記事は「やさしく学ぶ年休シリーズ」シリーズの第2話です。
皆さん、こんにちは!「やさしく学ぶ年休シリーズ」第2話へようこそ。
前回は、年次有給休暇(年休)が働く私たちにとってどれほど大切な制度であるか、その基本的な考え方についてお話ししました。年休は、心身のリフレッシュや自己啓発のために不可欠な権利であることをご理解いただけたでしょうか。
前回の記事は👉会社員が押さえておくべき年次有給休暇の基本知識
さて、そんな大切な年休ですが、「一体いつから使えるようになるの?」「会社に入ってすぐもらえるものなの?」といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
今回の第2話では、その最初のステップとなる「年次有給休暇が付与されるための条件」について、やさしく、そして具体的に解説していきます。
年休をもらうためにクリアすべき、「6か月・8割ルール」と呼ばれる2つの要件をしっかり理解しましょう!
年次有給休暇、もらうためのたった2つの条件
年次有給休暇が付与されるためには、労働基準法で明確に定められたたった2つの条件を満たす必要があります。
この2つの条件を満たすことで、初めてあなたの年休取得の権利が発生するのです。
その2つの条件とは、以下の通りです。
- 雇い入れの日から「6ヶ月継続勤務」していること
- その6ヶ月間の全労働日の「8割以上出勤」していること
これらの条件は、労働者の安定した勤続と、一定の貢献を前提としていると考えると分かりやすいでしょう。それでは、それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
条件1 雇い入れの日から「6ヶ月継続勤務」していること
最初の条件は、あなたが会社に雇われた日(=雇い入れの日、つまり入社日ですね)から数えて、途切れることなく6ヶ月間、その会社で働き続けているというものです。
例えば、2025年4月1日に入社した方であれば、2025年9月30日まで継続して勤務していれば、この条件をクリアしたことになります。
ここで言う「継続勤務」とは、原則として雇用契約が途切れることなく続いている状態を指します。たとえ途中で休職期間があったとしても、雇用関係が継続していれば問題ありません。
ただし、一度退職して再入社した場合など、雇用契約が完全に終了し、新たに結び直された場合は、原則として再入社の日から再び継続勤務期間がスタートすることになります。
条件2 その6ヶ月間の全労働日の「8割以上出勤」していること
6ヶ月間の継続勤務に加え、もう一つ大切な条件があります。それは、その6ヶ月間の期間中に、会社が定めた全労働日の8割以上をきちんと出勤している必要があるというものです。
「全労働日」とは、会社があなたに労働を義務付けている日のことを指します。
例えば、土日祝日が休日の会社で週5日勤務の場合、1ヶ月におよそ20日前後が全労働日となります。そのうちの8割以上、つまり「ほとんどの日数をきちんと出勤している」ことが求められます。
「8割以上出勤」の計算でポイントとなること
出勤率を計算する上で、欠勤扱いにならない「出勤とみなされる日」があることを知っておきましょう。
- 年次有給休暇を取得して休んだ日
- 年休は出勤したものとみなされます。
- 業務上の怪我や病気で休業した期間(労災)
- 労働者の責任ではないため、出勤として扱われます。
- 育児休業や介護休業の期間
- これらは法律で認められた権利であり、労働者の不利益にならないよう出勤したものとみなされます。
- 遅刻や早退
- 一部でも勤務していれば、その日は出勤としてカウントされます。
一方で、自己都合による欠勤や、正当な理由のない無断欠勤などは、出勤率の計算において「欠勤」として扱われますので注意が必要です。
2つの条件を満たせば、年次有給休暇が付与される!
この「6ヶ月継続勤務」と「8割以上出勤」という2つの条件を、どちらも満たした時に、あなたは初めて年次有給休暇を取得する権利を得ることができます。
つまり、あなたの入社日から数えて6ヶ月が経過し、その期間の出勤率が8割を超えていれば、晴れて年次有給休暇が付与されるのです。
これが、あなたが年休をもらえるようになる「最初の日」であり、この日に法律で定められた日数の年休が与えられます。
「自分はいつから年休がもらえるんだろう?」と疑問に思っていた方は、まずご自身の入社日と、これまでの出勤状況を振り返ってみてください。
この「6か月・8割ルール」をクリアしていれば、あなたも年休取得の資格があるということになります。
勤続年数で増える年休の付与日数
労働基準法では、年次有給休暇(年休)の付与日数が、あなたの勤続年数に応じて以下のように定められています。
これは、フルタイムで働く一般的な労働者(週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上)に適用される基準です。
| 勤続期間(雇い入れの日から) | 付与される年休の日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
この表を見ていただくと分かるように、最初に年休が付与されるのは「雇い入れの日から6ヶ月」が経過した時点で、10日です。
その後は、1年6ヶ月、2年6ヶ月…と半年ごとに勤続期間が延びるにつれて、付与される年休の日数が増えていく仕組みです。最大で年間20日まで付与されることになります。
年次有給休暇は入社日からカウントされる
ここで非常に重要なのが、年休の付与日数を数える際の「起算日」です。年休の付与日数は、常にあなたの「雇い入れの日(入社日)」から数えて決まります。
例えば、2025年4月1日に入社したAさんの場合で考えてみましょう。
- 2025年10月1日(入社から6ヶ月後)
- 10日の年休が付与されます。
- 2026年10月1日(入社から1年6ヶ月後)
- 11日の年休が付与されます。
このように、年休が付与されるタイミングは、入社日を基準として「半年後」「1年半後」「2年半後」…というように、入社日と同じ日付(または会社によって定められた日)で発生します。
年次有給休暇の日数を正しく計算するポイント
年次有給休暇(年休)の付与要件や日数が分かったところで、実際にいつから、どのように日数が計算されるのか、そのポイントをさらに深掘りしていきましょう。
特に重要なのが「年休の発生日」と「出勤率の計算方法」です。
年次有給休暇はいつ付与される?発生日をわかりやすく解説
年次有給休暇は、法律で定められた条件を満たした特定の「日」に発生し、従業員に付与されます。
- 最初の付与日
- 年休が初めて付与されるのは、前述の「6か月・8割ルール」を満たした日です。
- 具体的には、雇い入れの日(入社日)から6ヶ月が経過し、かつその期間の全労働日の8割以上出勤した時点で、最初の10日付与されます。
- 例えば、2025年4月1日入社の場合、2025年10月1日が最初の付与日となります。
- その後の付与日の考え方
- 2回目以降の年休は、最初の付与日を基準として、1年ごとに付与されます。
- つまり、最初の付与日から1年経過した日に次の年休が付与されるというサイクルになります。
- 例を挙げると、2025年4月1日入社で、最初の年休が2025年10月1日に付与された場合、次の年休は2026年10月1日、その次は2027年10月1日というように、毎年10月1日が年休の「基準日」となります。
- この基準日に、勤続年数に応じた日数が付与されていくわけです。
まとめ|年次有給休暇|付与条件と日数をわかりやすく整理
年次有給休暇は、働く私たちにとって、心身のリフレッシュや自己成長のために国が保障している大切な権利です。
この権利を適切に行使し、有効活用することは、健康で充実した職業生活を送る上で非常に重要です。
今回の記事で解説した「6か月・8割ルール」という付与要件、そして勤続年数に応じた付与日数を理解することで、ご自身が「いつから」「何日」年休をもらえるのかが明確になったことと思います。
自分の権利を正しく知り、計画的に年休を取得していくことが、ワークライフバランスを保つ第一歩となるでしょう。
次回予告|労働日数が少ない人の年休の計算方法を解説
「やさしく学ぶ年休シリーズ」第3話では、今回触れなかった「労働日数が少ない人への比例付与」について、詳しく解説していきます。
次回の記事は👉働く人のための有給休暇ガイド|パート・アルバイトの付与条件と日数【やさしく学ぶ年休シリーズ 第3回】
「週3日勤務のパートさんにも年休ってあるの?」
「アルバイトの私は何日もらえるの?」
…そんな疑問にお答えする第3話、どうぞお楽しみに!

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|29240010号)
- 会社員歴30年以上、転職5回を経験した氷河期世代の社会保険労務士です。自らが激動の時代を生き抜いたからこそ、机上の空論ではない、働く人の視点にたった情報提供をモットーとしています。あなたの働き方と権利を守るために必要な、労働法や社会保険の知識、そしてキャリア形成に役立つヒントを、あなたの日常に寄り添いながら、分かりやすく解説します。
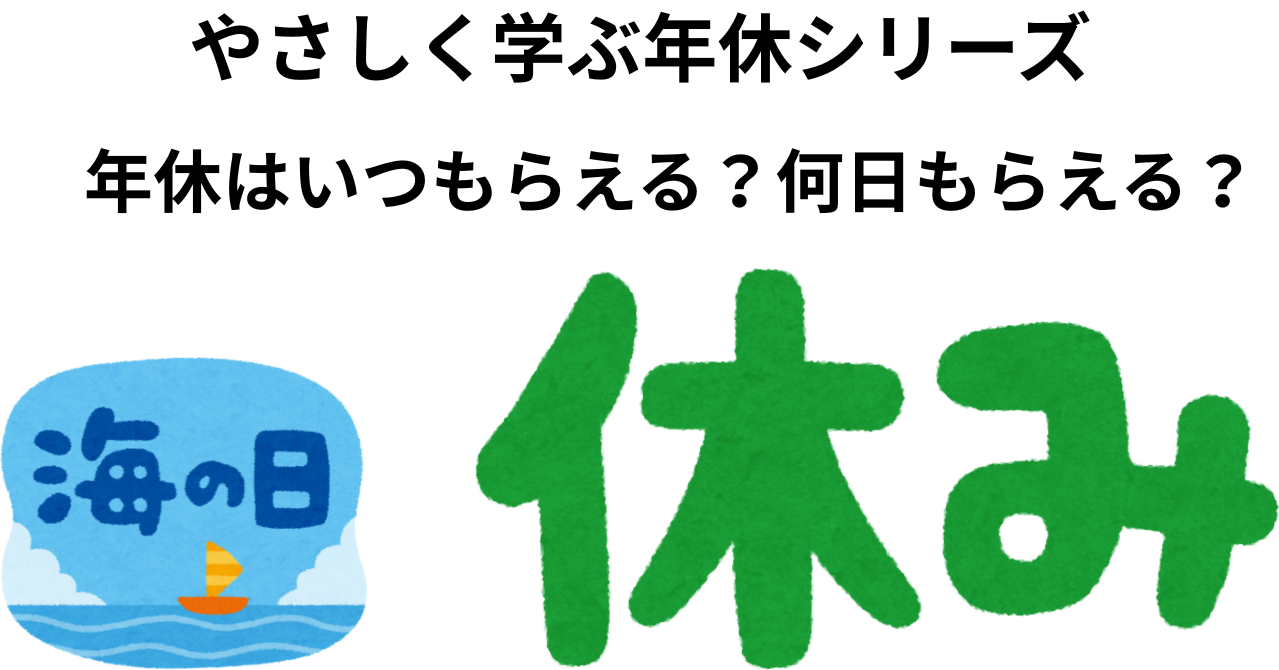
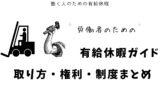
コメント