資格試験や受験勉強。目の前に広がる膨大な知識を、いかに効率よく脳に叩き込み、本番で使える状態にするか。
これは、すべての学習者にとって共通の、そして最大の課題ですし、ひょっとしたら「全て」ではないでしょうか?
私が勉強をするとき、何かを覚えようとするときに心掛けている方法として、まず前回のブログでご紹介した「アクティブ・リコール」です。
このアクティブ・リコールについての詳細はこちらからご確認ください。
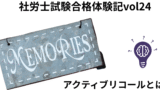
これだけでも「記憶力は飛躍的に向上した」と実感できると思いますが、さらに記憶の定着率を高めるために私が意識していたのが、「感覚の多重化」、名付けて「三感記憶術」です。
記憶を定着させる三感記憶術とは?
膨大な情報を前に、ただ漫然とテキストを読むだけでは、なかなか記憶に残りません。
情報を取り込む際に、一つだけでなく複数の感覚を同時に、あるいは連続的に活用することで、記憶の質と定着率を飛躍的に高める戦略です。
人間には五感(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)がありますが、勉強に直接活用できるのはそのうちの三つ、つまり「視覚」「聴覚」「触覚」ではないでしょうか。
嗅覚や味覚を使って学習する方もいるかもしれませんが、私は少なくとも試したことがありません。
視覚、聴覚、触覚の三感を意識的に、そして人工的に「多重化」して活用することで、知識は格段に「もの」になりやすくなります。
これは決して特別なことではなく、そのメカニズムを理解し、意図的に実践することで、その効果を最大限に引き出すことができます。
※1年目の道のりをまだ読んでいない方は、まずはこちらからどうぞ。
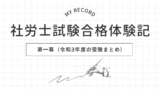
視覚を活用した多角的インプットで記憶を深める方法|社労士試験の勉強法
まず、最も一般的に使われる感覚が視覚です。
多くの学習者はテキストや問題集を目で追うことから始めます。しかし、ただ同じテキストを10回繰り返して見るよりも、同じ情報を異なる媒体で見る方が、記憶の定着にはるかに効果的です。
異なる教材で「重ね視」する効果
例えば、「Aという事柄」を覚える場合を考えてみます。
- まず、基本となるテキストでその情報を読み込み、全体像を把握します。
- 次に、その「A」に関連する問題集を開き、それがどのように問われるのか、どのような形で出題されるのかを目で確認します。
- さらに、月刊社労士受験などの月刊誌、あるいはブログ記事などで、別の視点からの解説や事例を見ることで、情報はさらに深く刻み込まれます。
このプロセスは、まるで異なる角度から同じ物体を観察するようです。
一つの情報が、テキスト、問題集、月刊誌といった複数の「入口」から脳に入ってくることで、単調な繰り返しでは得られない刺激が与えられます。
「人工的な偶発性」で記憶を強固に
さらに、この「Aという事柄」が、偶然にもニュースで取り上げられたり、ラジオで専門家が解説しているのを耳にしたりすると、驚くほど記憶に定着することがあります。
これは、日常の中に学習内容が入り込むことで、より生きた情報として認識されるためです。
例えば英単語の学習でもそうなのですが、市販の単語帳を買って英単語を覚えようとします。なかなか覚えられない単語でも、とある長文を読んでいたらその単語が出てきた、ただそれだけで、一気に記憶に定着するものです。
私が意識していたのは、こうした「偶発的な出会い」を待つのではなく、人工的にそうした場面を作り出し、強引に記憶に定着させることでした。
聴覚で記憶を強化|音の力を活かした社労士試験の学習法
次に、聴覚も記憶の定着に非常に貢献します。
視覚情報だけでなく、耳から入る音の情報は、脳の異なる経路を刺激し、記憶を強化します。
まずは動画視聴
聴覚活用法の代表例としては、まず動画視聴が挙げられますよね。
これは視覚と聴覚を同時に使う多感覚学習の典型です。
私の場合は月刊社労士受験の山川靖樹先生の動画解説をよく拝聴してました。YouTubeを活用した記憶はあまり無いですが、各法律の目的条文の聞き流しの動画はよく聞き流していました。
文字を読むだけでは理解しづらい複雑な概念も、講師の声と映像を通して学ぶことで、頭に入ってきやすくなります。
特に、専門家による解説は、その声の抑揚やリズムが、情報を記憶する上でのフックとなることもあります。
音読の効用
そして、私が特に重宝していたのが「音読」です。
自宅で勉強する際は声に出して音読し、電車の中など声が出せない環境では、いわゆる「ブツブツ法」として超小声で、あるいは頭の中でブツブツと繰り返していました。
なぜ音読が記憶に良いのでしょうか?
それは、声に出すことが、脳にとって「アウトプット」の一種だからだそうです。
情報を声に出して発することで、脳はそれを能動的に処理し、自分の理解度を確認します。
また、テキストを目で見て、さらに自分の声を聞くことで、視覚情報と聴覚情報が同時に脳にインプットされます。
複数の感覚経路を通じて情報が入力されることで、脳は情報をより深く処理し、記憶として定着しやすくなるのでしょう。
この「聴覚フィードバック」は、自分の声が骨伝導によって直接脳に響くため、より強く情報を脳に刻み込む効果があります。
学生時代に、英語や社会科の暗記にこの音読とブツブツ法を多用し、その効果は30年以上前に実感していました。
触覚を活用|書くことで記憶を定着させる社労士試験の学習法
最後は触覚。これも意外と侮れません。触覚を活用した学習、つまり「書く」という行為です。
「社労士試験は全問マーク式だから、書く行為は時間の無駄」という意見を耳にすることもありました。
確かに、マークシートに答えを書き込むという最終的なアウトプットにおいては、「書く」必要はないかもしれません。
しかし、それはどうかな、とずっと思ってましたし、社労士試験勉強の時は結構書いていました。
例えば、雇用保険法の失業等給付の全体構造の図、健康保険法の高額療養費等の所得区分と高額療養費算定基準額の表、は書いて覚えようとしましたし、実際それで効果はあったと思います。
書くという行為は、目で見ながら手を動かす、つまり視覚と触覚を同時に使う学習です。
さらに言えば、ペンを持って、ノートに書いて、手を動かしているという行為自体が脳を活性化させ、記憶の補助になるように感じています。
三感記憶術で効率アップ|視覚・聴覚・触覚を組み合わせて知識を定着
今回ご紹介した三感記憶術(視覚・聴覚・触覚)を振り返ると、それぞれを単独で使うのではなく、意図的に人工的に組み合わせて活用することが大切だとわかります。
- 同じ情報を問題集・動画・雑誌などで複数回触れる(視覚多重化)
- 動画を視聴する・テキストを見ながら声に出して読む(視覚+聴覚)
- 音読した後に図にして書いてまとめる(聴覚+触覚+視覚)
…という具合に、感覚を「掛け算」で使うことで、脳に複数の経路から情報が届き、結果的に「忘れにくい」状態がつくれるのです。
前回ご紹介した「アクティブ・リコール」と今回の「三感記憶術」は、私が社労士試験で実践していた「基本心構え」であり「土台」でした。
資格試験に挑んでおられる受験生の方は、すでに自分なりの効果的な勉強方法、心構えをお持ちの方も多いかと思います。
しかし、「なかなか覚えられない」「すぐに忘れてしまう」と悩んでいる方は、ぜひ一度「アクティブ・リコール」「感覚の多重化(三感記憶術)」を試してみていただけたらと思います。
きっと、記憶の定着に新たな突破口を見つけられるはずです。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。

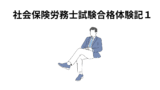

コメント