関連記事|熱中症と企業の安全配慮義務の記事もシリーズ化してます。是非ご覧ください。
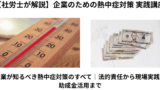
毎年夏が来るたびに、職場の熱中症対策に頭を悩ませていませんか?
「今年も酷暑になるだろうか」「従業員の健康は守れるだろうか」と、不安を感じている経営者や安全衛生担当者の方も少なくないと思います。
地球温暖化の影響で、夏の暑さは年々厳しさを増しています。それに伴い、職場での熱中症による労働災害も増加の一途をたどっています。
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正が施行され、職場における熱中症対策が強化、義務化されました。
本記事では、今回の改正の背景から主要なポイント、そしてなぜ今この改正が重要なのかを徹底的に解説します。
この記事を読むことで、改正内容を正確に理解し、義務違反のリスクを回避し、何よりも従業員の安全と健康を守るための第一歩を踏み出すことができるでしょう。
「義務化」の夏に備え、今からしっかりと準備を進めていきましょう。
この記事で分かること
- 2025年6月1日から、職場での熱中症対策が「努力」から「法的義務」へ強化
- 過去10年、熱中症による労働災害は増加傾向にあり、2023年は死傷者1,000人超、死亡31人の深刻な事態
- 新たな義務①:本人や周囲が異変に気づいた際の「報告ルート」の整備と周知
- 新たな義務②:症状が出た際の「冷却・水分補給・医師の診察」等の具体的な手順の準備
- 地球温暖化によるリスクを、一時的なものではなく「構造的な経営リスク」として捉える必要性
2025年の熱中症対策義務化|背景と改正労働安全衛生規則のポイント
「なぜ、わざわざ法律で義務付けられるほど熱中症対策が重要視されているのか?」そう疑問に思う方もいるかもしれません。
その背景には、看過できないほど深刻化している熱中症による労働災害の現状と、気候変動という避けられない現実があります。
熱中症による労働災害の現状|死亡者数と統計
厚生労働省の統計によると、熱中症による労働災害は近年、増加傾向にあります。
特に、過去10年間(2014年~2023年)の推移を見ると、熱中症による死傷者数(死亡者数と休業4日以上の者を含む)は、年によって変動はあるものの、全体として増加傾向にあります。
たとえば、2018年には一時的に1,178人と大幅に増加し、その後やや減少したものの、2023年には1,106人(速報値では1,045人、確定値では1,106人)と再び高い水準に達しています。
死亡者数も同様に推移しており、2023年の死亡者数は31人に上っています。これらの数字は、熱中症が単なる体調不良ではなく、命に関わる重大な労働災害であることを示しています。
詳しい資料は(厚生労働省資料)👉職場における熱中症による死傷災害の発生状況 (令和7年1月7日時点速報値)
屋外作業・高温環境での業種別の熱中症リスク
特に、建設業、製造業、運送業といった屋外作業や高温環境下での作業が多い業種での発生が顕著です。
これらの現場では、作業中に熱中症の初期症状に気づきにくかったり、休憩や水分補給が十分に取れないといった状況も少なくありません。
熱中症は、一度発生すると作業効率は低下します。それどころか、重症化すれば後遺症が残ったり、最悪の場合は命を落とす可能性もあります。
このような労働災害は、被災者やその家族に深い悲しみをもたらすだけでなく、企業にとっても生産性の低下、損害賠償、企業イメージの悪化など、計り知れない損失を招きます。
地球温暖化・異常気象による職場の熱中症リスク
私たちが直面しているもう一つの大きな課題は、地球温暖化の進行です。気象庁のデータを見ても、日本の年平均気温は着実に上昇しており、「猛暑日」や「酷暑日」といった極端な暑さの日数が増加しています。
もはや、夏の暑さは「一時的なもの」ではなく、労働環境における構造的なリスクとして捉える必要があります。
これまで経験したことのないような猛暑が日常化する中で、従来の熱中症対策だけでは不十分であることが明らかになってきています。
このような気候変動の影響は、屋外作業だけでなく、屋内の工場や倉庫、厨房など、空調設備の不十分な場所でも熱中症のリスクを高めています。
労働者が安全に働くためには、気候変動という新たなリスクに対応した、より強固で実効性のある対策が不可欠なのです。
熱中症対策の歴史と課題|2025年法改正が必要となった理由
熱中症対策は、労働者の安全を守る上で企業にとって非常に重要な課題です。
法整備の動きは、年々その重要性を増しており、特に2008年以降、以下のように段階的に企業の責任が明確化されてきました。
2008年|労働契約法による企業の熱中症対策安全配慮義務の明文化
- 法律
- 労働契約法 第5条(2008年3月1日施行)
- 内容
- この法律で、企業(使用者)は「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という安全配慮義務が明確に法的義務として明記されました。
- 熱中症との関係
- この安全配慮義務は、労働者の健康と安全全般にわたる包括的な義務です。
- そのため、当然ながら、高温多湿な環境での作業における熱中症への対策も、この安全配慮義務の対象に含まれることになりました。
- つまり、この時点から、企業が熱中症対策を怠り、従業員が熱中症になった場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性が生じました。
- ただし、熱中症に特化した具体的な対策が詳細に規定されていたわけではありません。
2014年|労働安全衛生法による熱中症リスクアセスメント義務化
- 法律
- 労働安全衛生法(2014年6月25日公布、2016年6月1日施行)
- 内容
- この改正で、化学物質を取り扱う事業場におけるリスクアセスメントの実施が義務化されました。
- リスクアセスメントとは、職場の危険性や有害性を特定し、そのリスクを評価した上で、リスクを低減するための措置を講じる一連のプロセスのことです。
- 熱中症との関係
- 2014年の改正自体が直接「熱中症対策を努力義務化」したわけではありません。
- しかし、リスクアセスメントの考え方は、職場におけるあらゆる危険・有害性を評価するものであり、熱中症のリスクも当然その対象となります。
- そのため、企業はリスクアセスメントを通じて熱中症のリスクを認識し、そのリスクを低減するための措置を講じる「努力」が実質的に求められるようになりました。
- 熱中症に特化した具体的な措置が「義務」として規定されたわけではないため、あくまでリスクアセスメントの一環として対応が期待されるという段階でした。
これらの2008年の労働契約法による安全配慮義務の明文化や、2014年の労働安全衛生法改正によるリスクアセスメントの義務化だけでは、近年の急増する熱中症による労働災害、特に死亡事故を十分に抑制することが不十分でした。
そのため、熱中症対策をさらに強化し、事業者により具体的で実践的な措置を義務付ける必要があるため、2025年の法改正に踏み切ったのです。
2025年6月施行|労働安全衛生規則による熱中症対策の義務化ポイント
いよいよ本題に入ります。
厚生労働省では、令和7年4月15日に、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために、労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し、熱中症を発症した者の早期発見のための体制整備等を義務づけました。
今回の改正では、労働安全衛生規則第21条に新たな条文が追加され、熱中症対策に関する具体的な義務が事業者に対して課せられます。その核心は、以下の2つのポイントです。
- ポイント1:熱中症患者の報告体制の整備と周知
- ポイント2:熱中症の悪化防止措置の準備と周知
これらの義務は、熱中症が発症した際の「早期発見」と「適切な初期対応」に焦点を当てたものです。
新たな義務化措置①|熱中症患者の「報告体制」の整備と周知
最も重要なのは、これまで「努力義務」とされてきた熱中症対策の一部が、「法的義務」に変わるという点です。
これは、事業者が対策を講じなかった場合に、法的措置の対象となり得ることを意味します。
熱中症の自覚症状がある労働者からの報告体制
- 「なんだか頭が痛い」「めまいがする」「体がだるい」といった初期症状を感じた際に、すぐに「誰に」、「どのように」報告すれば良いのかを明確にすることです。
- 例としては、「体調不良を感じたら、すぐに直属の上司に報告すること」「休憩所担当者に声をかけること」といった具体的な報告ルートを定めることです。
- 口頭での報告だけでなく、内線電話、無線、作業用チャットツールなど、状況に応じた報告方法があれば、なお良いでしょう。
熱中症のおそれがある労働者を発見した者からの報告体制
- 「あの人、いつもと様子が違うな」「顔色が悪いな」「ふらついているな」など、同僚や巡視員、管理者などが異変に気づいた際に、「誰に」、「どのように」報告すれば良いのかを明確にすることです。
- 例としては、「異変に気づいたら、すぐに〇〇(安全衛生担当者、管理職など)に連絡する」といったルールを定めておくことです。
- 特に、一人作業や少人数作業が多い現場では、定期的な声かけや、お互いの体調を確認し合うバディシステム(2人1組、または小グループで互いに監視・協力しあいながら行動する安全管理の方法)の導入も有効です。
- 近年では、心拍数や体温をリアルタイムで測定できるウェアラブルデバイスを活用し、異常を自動で検知して管理者に通知するシステムも注目されています。
- これらも報告体制の一部として検討する価値があります。
なぜこの義務が重要なのか?
熱中症は、初期症状の段階で適切な対応を取れば、重症化を防ぐことが可能です。
しかし、「これくらいなら大丈夫だろう」「周りに迷惑をかけたくない」といった心理から、自身の体調不良を報告しない労働者も少なくありません。
また、周りの人も「ただ疲れているだけだろう」と見過ごしてしまうこともあります。
この報告体制の義務化は、そうした「見過ごし」や「報告の遅れ」を防ぎ、早期発見・早期対応を徹底することで、熱中症による重篤な事態を未然に防ぐことを目的としています。
労働者が安心して体調不良を報告でき、異変に気づいた人がためらわずに報告できる環境を整えることが、命を守る第一歩となるのです。
「周知」の重要性
せっかく報告体制を定めても、それが労働者に知られていなければ意味がありません。
定めた報告体制は、関係する全ての労働者に対して、以下の方法で徹底的に周知する必要があります。
- 安全衛生教育
- 入社時教育や定期的な安全衛生教育のカリキュラムに組み込み、具体的な報告方法を指導します。
- 掲示物
- 作業現場や休憩室など、目立つ場所にポスターやイラストを活用した分かりやすい掲示を行います。
- マニュアル・リーフレット
- 携帯できるカード型のマニュアルを配布し、いつでも確認できるようにします。
- 朝礼・ミーティング
- 日常的な朝礼やミーティングで、定期的に報告体制について再確認を促します。
- サイン(署名)の取得
- 労働者が報告体制を理解したことの確認として、理解度テストやサインの取得を任意で行うことも推奨されます。
新たな義務化措置➁|熱中症の「悪化防止措置」の準備と周知
二つ目の重要な義務は、「熱中症の悪化防止措置の準備と周知」です。
これは、万が一熱中症の症状が出た場合に、その症状が重症化するのを防ぎ、迅速かつ適切な初期対応を行うための準備を指します。
悪化防止措置の内容と実施手順とは具体的に何を指すのか?
この義務は、熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置の内容と、その実施に関する手順を事業場ごとにあらかじめ定めることを求めています。具体的な措置としては、以下のような内容が挙げられます。
1. 作業からの離脱
- 熱中症の症状が見られた労働者を、直ちに作業を中断させ、涼しい場所(冷房完備の休憩室、日陰など)に移動させること。
2. 身体の冷却
- 体温を下げるための具体的な方法を定めること。
- 衣類を緩める、露出した部位(首筋、脇の下、足の付け根など、太い血管が通る場所)を冷却材(氷のう、冷却パック、冷たいタオルなど)で冷やす、体を霧吹きで濡らし、風を当てるなど。
- これらの冷却資材をどこに、どれだけ常備しておくか、使用方法なども明確にします。
3. 水分・塩分補給
- 意識がある場合、経口補水液やスポーツドリンクを少量ずつこまめに摂取させること。
- 自力で飲めない場合は無理に飲ませず、専門家の指示を仰ぐこと。
- 塩飴や塩分補給タブレットなどの準備も有効です。
4. 必要に応じた医師の診察または処置
- 熱中症の症状が重度の場合(意識障害、けいれん、自力で水分補給ができない、呼びかけに反応しないなど)、速やかに医師の診察を受けさせる、あるいは救急車を呼ぶ判断基準を明確にします。
- 事業場における緊急連絡網(担当者、責任者、衛生管理者、産業医など)、緊急搬送先の連絡先(近隣の病院名、電話番号、地図)、所在地、搬送経路などをあらかじめ確認し、リスト化しておきます。
- 救急車の要請をためらわないことの重要性を強調します。
なぜこの義務が重要なのか?
熱中症は進行が早く、短時間で重篤な状態に陥ることがあります。
適切な初期対応が遅れると、脳や臓器に回復不能なダメージを与えたり、最悪の場合は死に至ることもあります。
この悪化防止措置の義務化は、緊急時に「誰が」、「何を」、「どのように」行うべきかを明確にすることで、現場の混乱を防ぎ、迅速かつ的確な初期対応を可能にすることを目的としています。
あらかじめ準備された手順に従うことで、判断に迷うことなく、最も適切な処置を行うことができるようになります。
「手順」と「周知」の重要性
定めた悪化防止措置の内容と実施手順は、以下の方法で徹底的に周知し、誰もが実行できるようにしておく必要があります。
- 緊急時対応フローチャートの作成
- 状況に応じてどのように対応すべきか、具体的な流れをフローチャート形式で作成し、分かりやすく掲示します。
- 緊急時対応訓練(シミュレーション)の実施
- 実際に熱中症で倒れた労働者がいると想定し、通報、応急処置、搬送までの流れを実践形式で訓練します。
- 訓練を通じて課題を発見し、手順を改善する機会とします。
- 従業員への定期的な情報提供
- 熱中症の症状、応急処置の方法、緊急時の連絡方法などを継続的に周知し、いざという時に対応できるよう意識付けを行います。
まとめ|2025年改正で義務化された熱中症対策のポイント
今回は、2025年6月1日に施行される労働安全衛生規則の改正について、その背景と、特に重要な「熱中症患者の報告体制の整備・周知」および「熱中症の症状悪化防止措置の準備・周知」という新たな義務について解説しました。
近年深刻化する熱中症による労働災害を食い止めるため、今回の改正は、単なる法令順守を超え、従業員の命と健康を守る事業者の責務を明確にするものです。
義務違反のリスクを避け、何よりも大切な労働者を守るためにも、改正内容の正確な理解と、迅速な対応が求められます。
「具体的に自社で何をすればいいのか?」「どの範囲まで対策が必要なのか?」といった疑問は尽きないでしょう。
次回予告|2025年改正熱中症対策の義務化対象と具体的な実務対応
そこで、次回の記事では、今回の改正によって義務化の対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」の具体的な基準を詳しく解説するとともに、事業者としてまず何から着手すべきかという、実務対応をご紹介します。
次回の記事は👉【2025年6月施行】改正労働安全衛生規則(後編)熱中症対策の義務化、対象となる職場と具体的な対策
ぜひ次回の記事もご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 日々、企業の「ヒト」と「組織」に関わる様々な課題に真摯に向き合っています。労働法の基本的な知識から、実務に役立つ労務管理の考え方や人事制度の整え方まで、専門家として確かな情報を初めての方にもわかりやすくお伝えします。
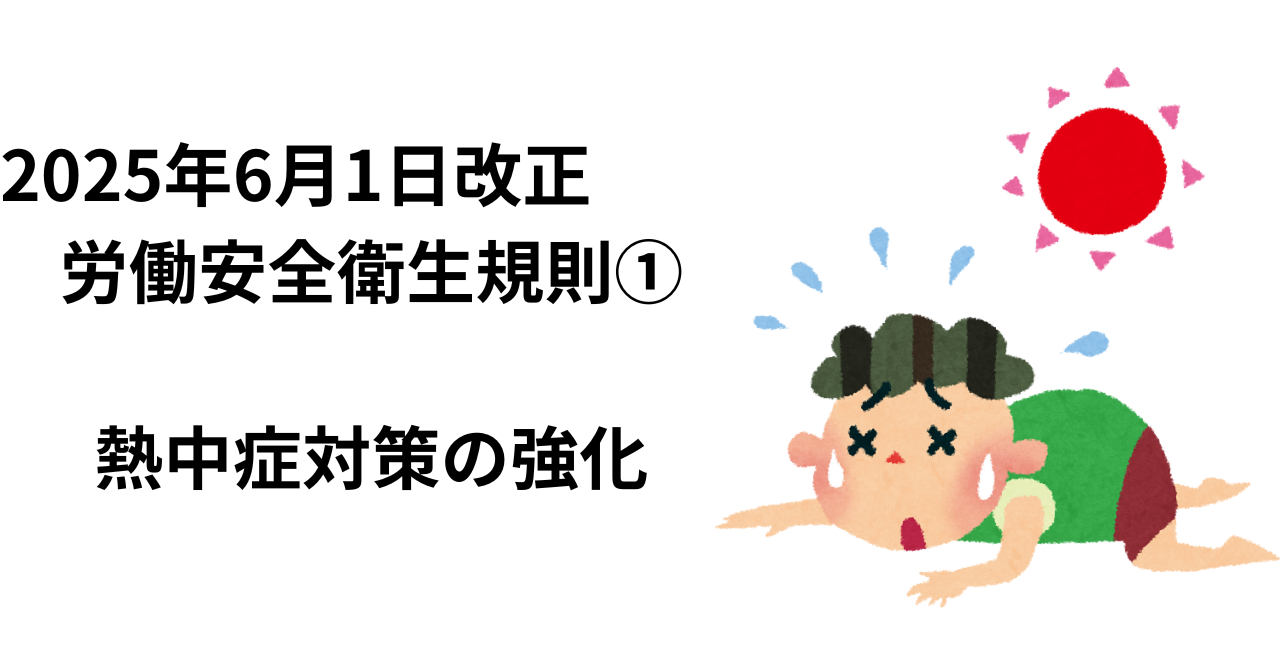

コメント