6月24日のTAC模試(全国中間模試)の得点にすっかり気をよくしている五十路の男です。
社労士試験を思い立ってから、1年と8ヶ月くらいです。
途中で病気をしたり、職場でも色々あり、濃度・質にばらつきはありますが、やってきた勉強は間違いでは無かった、と感じました。
※1年目の道のりをまだ読んでいない方は、まずはこちらからどうぞ。
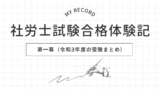
社会保険労務士試験に「合格できるのでは」──自信が生まれた手応え
あと2ヶ月、このままのペースを守って進めていけば、今年は合格できるのではないか。
そう思えるくらいには、手応えがあります。
勉強の累計時間も問題は無い。試験当日までに1000時間には到達します。前年の分を入れれば1200時間になります。
「合格者の平均学習時間」と言われる時間をベースにしても、時間的な土台は整ったといえるのではないでしょうか。
ただし不安もある──社労士試験選択式での基準点割れのリスクと対策
模試の得点そのものは、悪くありません。択一式はボーダーを超えています。
これまでの学習の軸が「択一対策」だったため、ここにはある程度の自信が芽生えました。
しかし、気になるのは、選択式の基準点割れです。思っていた通り、「労働基準法・安衛法」「労一」がネックになってます。
社労士試験は「合計点で取れていれば良し」ではありません。1科目でも基準点(選択式は原則3点)を下回ると不合格になる、という厳しいルールです。
ですから、「トータルではまずまずの得点だったから良し」では済まないのです。
ですから、ここの部分をあと2ヶ月集中的に勉強していき、克服していくだけです。
社労士試験合格に向けて勉強方針の転換──選択式対策に5割のリソースを割く
模試を受けたことによって自分のある程度の立ち位置がはっきりしました。
いまの自分の立ち位置は合格ボーダーライン上より少し上にあるのではないか。
これまでの勉強方法は、基本的に択一式対策、択一の得点を伸ばすための勉強が基本を作り上げていく、というものでした。その方法により択一のボーダーは超えています。
あとは選択式、特に労働基準法・安衛法、労一の対策をあと2ヶ月でやり切れば合格するはずです。
これまでは、8割くらいが択一対策の勉強でした。もちろん使用テキストは、
- 【10年分収録】2026年版 出る順社労士 必修過去問題集 1 労働編【必修基本書に準拠】 (出る順社労士シリーズ)
- 【10年分収録】2026年版 出る順社労士 必修過去問題集 2 社会保険編【必修基本書に準拠】 (出る順社労士シリーズ)
です。しかし、今回の模試の結果を受けて、残り2ヶ月は学習配分を見直します。
択一:選択式=5:5
選択式対策にも、しっかり時間を割きます。
社労士試験の苦手科目対策|教材選びと学習方針
やはり選択式の労働基準法、安衛法の対策としては、判例対策です。当然使用テキストは
- 社労士V 第2版 イラストでわかる労働判例100
- これは、判例の論点を視覚的に理解できるので、記憶に残りやすいです。繰り返し読み込み、設問形式の変化にも対応できる応用力を養います。
- 月刊社労士受験
- 月間社労士受験には毎月、判例専用ページがあり、それを徹底的に復習します。
労一の統計・白書対策
- 月刊社労士受験
- 直前対策 一般常識・統計/白書/労務管理 【赤シート対応/社会保険労務士 TAC公式教材】(TAC出版)
- 社労士Ⅴ 2025年度版 選択式・労一を切り抜ける! 厚労省パンフレット・リーフレット攻略問題集
でいきます。これらの教材は「読む」ことに徹することにします。無理に暗記しようとせず、背景や文脈を理解しながら頭に入れることで、設問に対する対応力をつけていきます。
次の社労士模試へ──全国公開模試
次のTAC模試(全国公開模試)は7月15日です。前回の模試から3週間後です。ネットの情報によれば、難易度が多少上がる、とのことなので、気を引き締めていきたいと思います。
7月15日金曜日、再度適当な理由をつけて、有給休暇を取りました。
この時点で累計勉強時間930時間を超えてます。決して油断せずに、本試験まで突っ走ります。勉強方法は、先ほど触れたとおり、選択式に重心を寄せてます。
全国公開模試|選択式の詳細結果
まずは、全国公開模試の選択式の結果から。
| 科目 | 点数 |
|---|---|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 3点 |
| 労働者災害補償保険法 | 4点 |
| 雇用保険法 | 3点 |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 2点 |
| 社会保険に関する一般常識 | 3点 |
| 健康保険法 | 4点 |
| 厚生年金保険法 | 5点 |
| 国民年金法 | 4点 |
| 総得点 | 28点 |
結果的には、合計点は全国中間模試と変わらずでした。昨年度令和3年度の本試験の合格基準点24点はクリアしてます。しかし今回も労一が基準点割れをしてます。
労働基準法・安衛法はギリギリいけてますが、迷った挙句たまたま良いほうの結果が出た、というような感じでした。
本試験を1ヶ月前にして、未だ克服は出来ておりません。なかなか手強い。他の科目は恐らくいける。ただ、この労働基準法・安衛法、労一を克服せねば。
選択式は多少実力不足でもそこそこ点数が取れてしまうので、合計点に目が行ってはいけません。普通にそこそこ勉強して臨めば、合計点割れは起こらないでしょう。この基準点割れをなくすことが全てです。
午後からは択一式です。油断せずに行きます。続く。

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
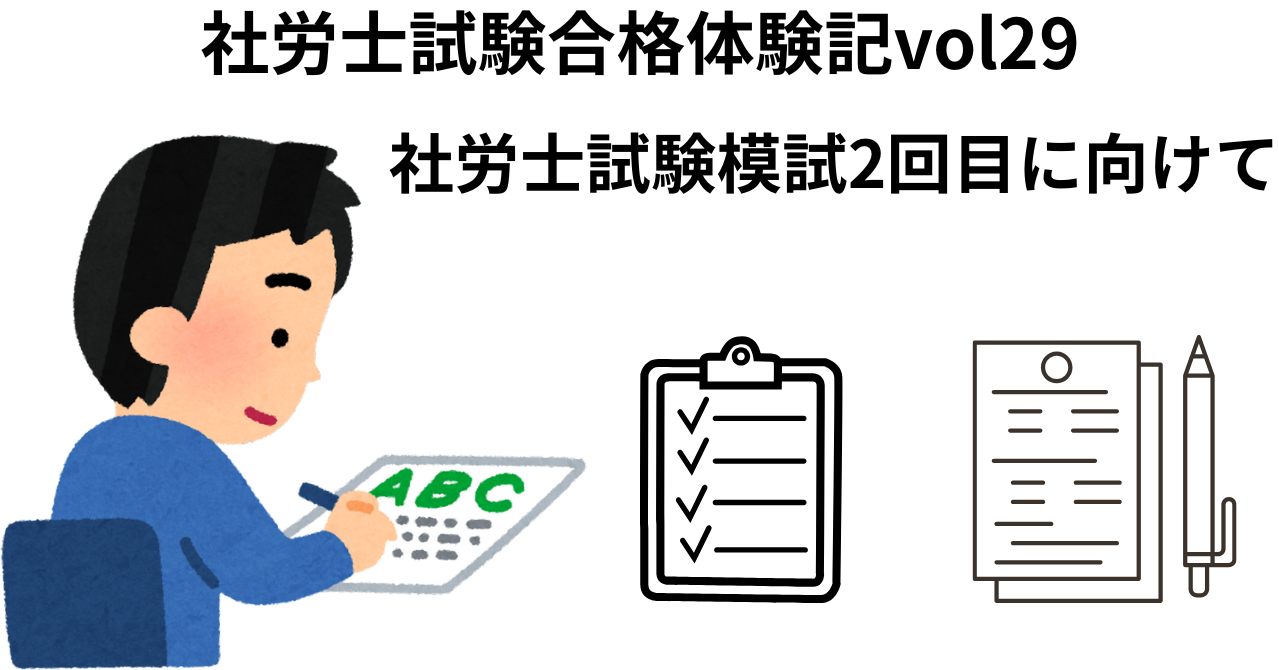
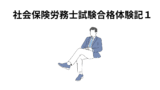


コメント