2021年(令和3年)4月16日(だったと思います)。
この日、官報にて令和3年度の社会保険労務士試験の実施が公示されました。
受験資格については事前にしっかり調べていたので、大学の卒業証明書を準備し、申込書に同封。
勤務先でもある中央市場内の郵便局から受験料を払い込み、そのまま申し込み書類を発送しました。
そういえば、受験料について少し驚いたのを覚えています。
たしか前年までは9,000円だったものが、この年から15,000円に値上がりしていました。
申込者数は例年およそ5万人、そのうち実際に受験するのは4万人程度だったと、どこかで見た記憶があります。
単純計算ですが、5万人が15,000円ずつ支払うと、それだけで7億5,000万円の収入が試験センター(全国社会保険労務士会連合会)に入るのだなぁ…。
郵便局の窓口で手続きをしながら、ふとそんなことを考えていました。
ついに、賽は投げられました。
あとは、勉強して合格を勝ち取るだけ――。
日々の仕事と社労士試験の勉強の両立、現実は甘くない
とは言ったものの、正直に申し上げますと、ここまでの勉強の進捗は決して順調とは言えません。
一番の壁は、やはり「時間の確保」です。
私の一日は、早朝3時半の起床から始まります。
5時には市場に出社し、仕事を終えて帰宅するのは16時、遅ければ17時を過ぎることもあります。
そこからは、洗濯物を取り込んで畳み、食器を洗ってご飯を炊く。お風呂の準備をしながら、バイヤーや店舗への野菜の売り込み、翌日の仕入れ確認、現場への指示書の作成……と、目まぐるしくタスクをこなしていきます。
ここまでくると、さすがに脳も体もクタクタです。
「さぁ勉強しよう!」という気持ちには、なかなかなれません。
それでも、少しでも前に進もうと、毎日30分、1時間でもテキストを開くようにしています。
ただ、そこに待ち構えているのは、次から次へと押し寄せてくる法律用語の波。
読めば読むほど、もがけばもがくほど、まぶたが重くなります。
ついにはテキストを枕にしてしまいそうになるのです。
「これはもう、水曜と日曜の休みに賭けるしかない」
そう腹をくくって、休日にはできるだけまとまった時間を確保し、集中して勉強するように心がけます。
この試験に対する本気度だけは、忘れないように。
暗記より理解・難解な社労士試験における気づいた“学び方の変化”
とはいえ、不思議なもので、そんな日々の中でも、続けていると少しずつ「掴めてきた」感覚もあるのです。
本来であれば、
・4月くらいまではインプット中心(テキストを読む・理解する)
・5月〜6月はアウトプット期(問題演習で問題を解きまくる)
・7月〜8月は全科目を横断しながら総仕上げ(総復習・苦手克服)
――といった当初予定の学習スケジュールでいきたいところです。
しかしそんな計画を遂行している余裕など、正直まったくありません、どころか、無理でした。
計画の頓挫と現実的な学習法へ
現実は、「とにかく今できることをやる」だけ、というところに落ち着いてしまいました。
- テキストを読み込んでは、一問一答の問題集を解く。
- 間違えたらすぐにテキストに戻って確認し、また読み直す。
- そしてまたテキストを読み込んで再び問題集に挑戦する。
- 機械的にこの地道な作業を繰り返していきます。
地道な反復と、確かな手応え
それでも、続けていると、少しずつですが「なんかわかってきたかも」と思える瞬間があるんですよね。
社労士試験は「暗記の試験だ」なんて言われることがあります。
確かに、条文や制度の数字、要件など、覚えなければいけないことは山ほどあります。
でもこの時思ったんですが、極端な話、テキストの文言を一字一句覚えようとするよりも、「まず理解しよう」と心がけた方が、結果的に学力って伸びていくのではないか、と。
報われた気がした、小さな「できた」の積み重ね
問題を解いていても、ただ「〇」or「×」と、当たった・外れた、と一喜一憂していたのが、
「この問題、俺に何を問いたいのか?」
「この選択肢の論点はどこにあるのか?」
と、考えるようになってきました。
そうすると、ふとした瞬間に知識と知識がつながって、「あ、こういうことか」と理解の糸がピンと張るような感覚になることがあるんです。
それが、意外と嬉しいんですよね。
小さな「できた」が育む確かな自信
ちょっとした理解の積み重ねだったり、前に間違えた問題がすっと解けたりするだけで、「あれ?なんか今回はいけたな、ちゃんと分かった気がする」みたいな感覚が生まれる。
たったそれだけのことで、「まだまだやれるかもしれない」と思えてくるもんです。
結局、人間ってそういう小さな手応えとか、ほんのわずかな前進にすごく救われるんだなと、この時しみじみ感じました。
学習って、努力の割にすぐ結果が見えにくいことが多いです。
しかし、そうした「微差」みたいなものを拾い集めていくことが、意外と大きな自信につながるんじゃないかと思っています。それがすごくうれしいのですよね。
人間ちょっとした小さな幸福で、「まだまだやれるかもな」って、ちょっとだけ前向きになれるものだなぁ、とこのときつくづく思いました。
人間様も偉そうなこと言ってますが、単純なものです。
もちろん、そんな「おー、わかった気がする、行けんじゃね?」と思える瞬間ばかりではないです。むしろわからないことの方が多いです。
でも、「理解しよう」とする姿勢を持ち続けることが、きっとこの長い戦いを乗り越えるカギになるんじゃないかなと、その時はそんなふうに感じました。
「秒」のスキマ時間も、社労士になるための勉強に変える
また、仕事の合間のほんのわずかな時間でも、無駄にしたくないと思い、「秒トレ」というスマホのアプリを活用していました。
仕事の合間、ちょっとした移動時間、夜の食事中、寝落ちする前の数分間。
そんな「秒」のスキマ時間を、できる限り勉強に当てるようにしていました。
社労士試験の「底知れなさ」に気づき始めた頃
……と、ここまで書いていると、なんだか順調に物事が進んでいるようにも見えるかもしれませんが、実のところ、そうでもありません。
何が問題かというと――やはり、社労士試験は範囲が広すぎるということです。
本当に、広い。しかも、初学者にとっては「どこまで深く理解すればいいのか」「どこが重要なのか」といった「勉強の深さ」の感覚もつかみにくい。
最初は「とりあえずテキストを読んで進めていって、問題を数多くこなして・・・」くらいの軽い気持ちで始めたのですが、ある程度進んできた今、むしろこの試験の「底知れなさ」を感じ始めていきます。
法律ごとの専門用語や制度の複雑さ、全10科目あるのですが、意外と「似たような」論点があり、しかも科目ごとに答えが微妙に違う、「横断学習が必要」という意味が分かり始める。
さらに、暗記だけでは太刀打ちできないような事例問題も最近多い……。
「恐るべし、社会保険労務士試験」
そう痛感する日々。
手応えを感じる瞬間もある一方で、「これは本当に間に合うのか?」という不安も常に背中合わせ。
でも、そうした試験の難しさを知ったこと自体が、ある意味で前進なのかもしれません。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)
- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。
- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。
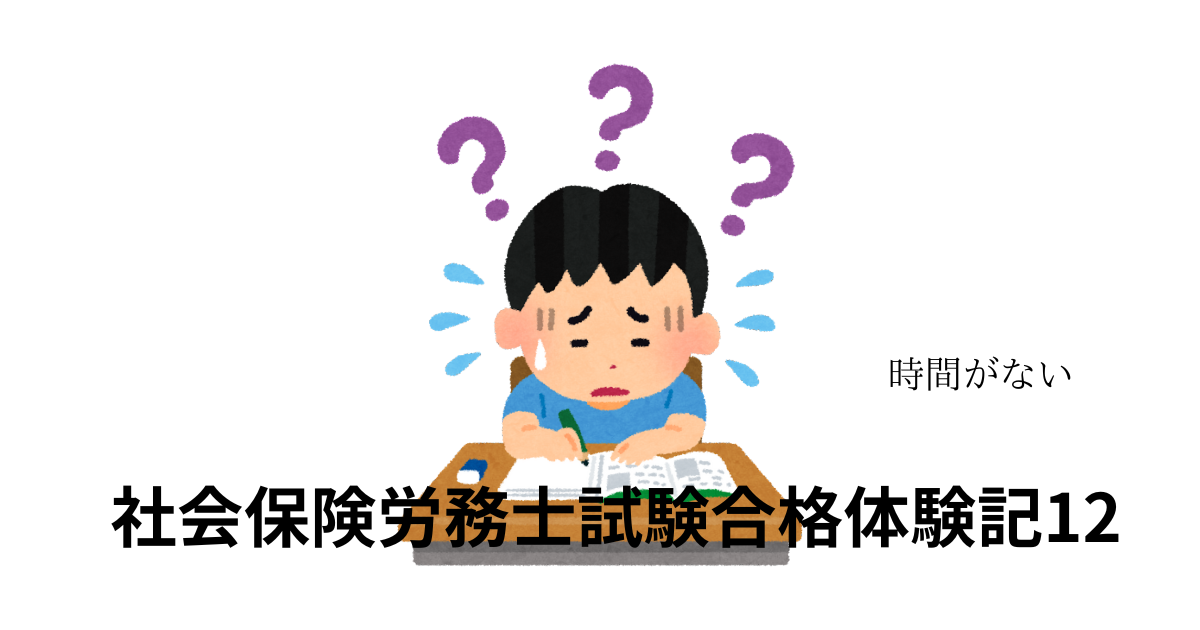
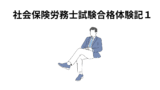

コメント