2025年の育児介護休業法の改正により、企業は育児休業制度の周知と意向確認の徹底が義務付けられています。
この改正は、特に中小企業にとっては大きな影響を与えるものです。今回は、中小企業の現場で実際に求められる対応や、就業規則の整備方法、育児休業規程の作成ポイントについて解説します。
2025年改正育児介護休業法の改正ポイント
改正内容の詳細については、以前のブログ記事☟で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。
今回記事では、改正後の実務対応に焦点を当てて解説を進めていきます。
実務対応の具体策
育児休業の周知・意向確認の強化に対応するためには、まず就業規則の見直しが欠かせません。就業規則の中では基本的なルールのみ記載し、具体的な運用手順やフローは育児休業規程に落とし込むことで、柔軟な対応が可能になります。今回は特に「就業規則の整備方法」と「育児休業規程の作成ポイント」にフォーカスして解説します。
就業規則
- 現行規則の確認
- 現在の就業規則に育児休業の周知や意向確認に関する規定があるか確認します。
- 法改正への適合
- 2025年改正内容に基づき、不足している箇所や曖昧な記述を洗い出します。
- 具体的な運用方法の明記
- 意向確認の実施時期や手順について、明確な記載が求められます。
基本的に現行の就業規則がある場合は、その内容確認を行うことが当然第一歩になります。
記載するべき内容
育児休業の周知・意向確認の強化に対応するためには、就業規則の整備が重要です。ただし、どこまでを就業規則に記載するかは、育児休業規程の有無によって異なります。
就業規則のみで対応する場合
就業規則の中に、育児休業の基本的なルールから申請手続き、意向確認の流れ、記録管理までを一貫して盛り込みます。この場合、具体的な手続きの詳細も記載する必要があります。特に中小企業の場合、個別の規程を作らないケースも多いため、就業規則の中で確実に網羅することが求められます。
育児休業の取得要件
誰が対象となるか、パートや契約社員も含まれるかを明確に記載します。 例:「育児休業は、当社に1年以上勤務している従業員(正社員、週20時間以上の契約社員)を対象とする」など
申請手続きの流れ
申請書の提出期限や承認プロセスを具体的に示します。 例:「育児休業の申請は出産予定日の2か月前までに申請書を提出すること。提出後、管理部門は内容を確認し、1週間以内に承認または否認の通知を行う」など
意向確認の実施方法
どのタイミングで意向確認を行い、どのような方法で記録するかを具体的に明記します。 例:「意向確認は、出産予定日の3か月前および1か月前に個別面談を実施し、結果は書面に残す。書面は本人と管理者が署名し、3年間保管する」など
記録の管理方法
書面の保存期間や電子データの管理ルールも詳細に定める必要があります。 例:「意向確認や育児休業申請に関連する書面は、社内システムに5年間保存し、退職後も一定期間管理する」など
ポイント
就業規則のみで対応する場合、法的要件を満たすだけでなく、具体的な運用手順まで細かく記載することが求められます。不備があると法令違反やトラブルの原因となるため、特に注意が必要です。
就業規則と育児休業規程を分ける場合
就業規則には基本的な枠組みのみを記載し、詳細な運用手続きやフローは育児休業規程として別途作成します。この方法により、法改正時の対応が柔軟になり、手続き変更時も規程の更新だけで済むため効率的です。
就業規則の記載例(育児休業規程を設ける場合)
第○条(育児休業の取得)
- 当社は従業員が育児を行うために、育児・介護休業法に基づき育児休業を取得できるものとする。
- 育児休業の取得要件、申請手続き、意向確認の実施方法、復職手続きについては、別途定める「育児休業規程」による。
第○条(育児休業の周知および意向確認)
- 会社は、育児休業に関する制度の周知および従業員の意向確認を行うものとする。
- 意向確認の具体的な手続きについては「育児休業規程」に記載する。
このように就業規則の中で「育児休業規程に基づく」と記載することで、詳細な運用手順については個別の規程で管理できます。これには以下のメリットがあります。
メリット
- 規程の分離で改訂が容易
- 法改正や運用の見直しが発生した場合、就業規則そのものを変更せずに、育児休業規程のみを改訂できます。
- 労基署への届出が必要な就業規則の変更回数が減少します。
- 運用ルールの明確化
- 育児休業規程に詳細な手順を明示することで、従業員も迷わず手続きを進められます。
- 文書管理がシンプル
- 就業規則は基本ルールに絞り込み、育児休業規程で具体的な手続きをまとめることで、内容が分かりやすくなります。
育児休業規程
育児休業規程に記載すべき主な項目は以下の通りです。
- 目的
- 対象者
- 育児休業の取得要件
- 申請手続き
- 意向確認の実施
- 周知義務
- 通知方法
- 休業中の待遇
- 記録の管理
- 復職手続き
- 禁止事項
- 規程の改定
- 附則
これらの項目を明文化することで、法令に準拠した対応が可能になります。
育児休業規程記載例
それでは、一部具体例として、育児休業規程では次のような形で記載しましょう。
(目的)第1条
本規程は、従業員の育児休業の取得に関する手続き、意向確認、復職支援の詳細を定める。
(対象者)第2条
育児休業の対象は、当社で勤務する正社員、パートタイム労働者、契約社員とする。
(申請手続き)第3条
- 育児休業を希望する者は、出産予定日の2か月前までに「育児休業申請書」を提出する。
- 申請書には、取得希望期間、復職予定日、配偶者の育児休業取得予定の有無を記載する。
(意向確認の実施)第4条
- 意向確認は、育児休業開始予定日の3か月前および1か月前に実施する。
- 面談または書面通知により、休業期間、復職時期、勤務形態について確認を行う。
(記録の管理)第5条
- 育児休業に関する書類は電子データで管理し、少なくとも5年間保管する。
- 記録へのアクセスは人事部が管理し、情報漏洩に注意する。
第6条(復職手続き)
- 職予定日の1か月前までに、復職意思の確認を行う。
- 要に応じて、時短勤務やテレワークなどの希望を確認する。
以上、2025年改正育児介護休業法に対応した就業規則の整備方法と育児休業規程の作成ポイントについて解説しました。法改正に伴う対応は煩雑に感じられるかもしれませんが、ポイントを押さえて規程を整備することで、トラブルの未然防止や円滑な運用が可能になります。
特に就業規則と育児休業規程を分けることで、柔軟な改定対応が可能になる点は見逃せません。
次回の記事は「取得促進のための具体的措置」「取得意向確認後のアクション義務」「取得率向上のための文化的な推進」を中心に、育児休業の実効性を高めるための取り組みに焦点を当てていきます。企業がどのように育児休業の取得を促進し、実際に制度が活用される文化を築いていけるのか、その具体策を明確に解説していきます。育児休業の周知・意向確認は、単なる手続きではなく、育児休業の取得率を向上させ、働きやすい環境を実現するための重要な一歩です。次回もぜひお楽しみにしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。
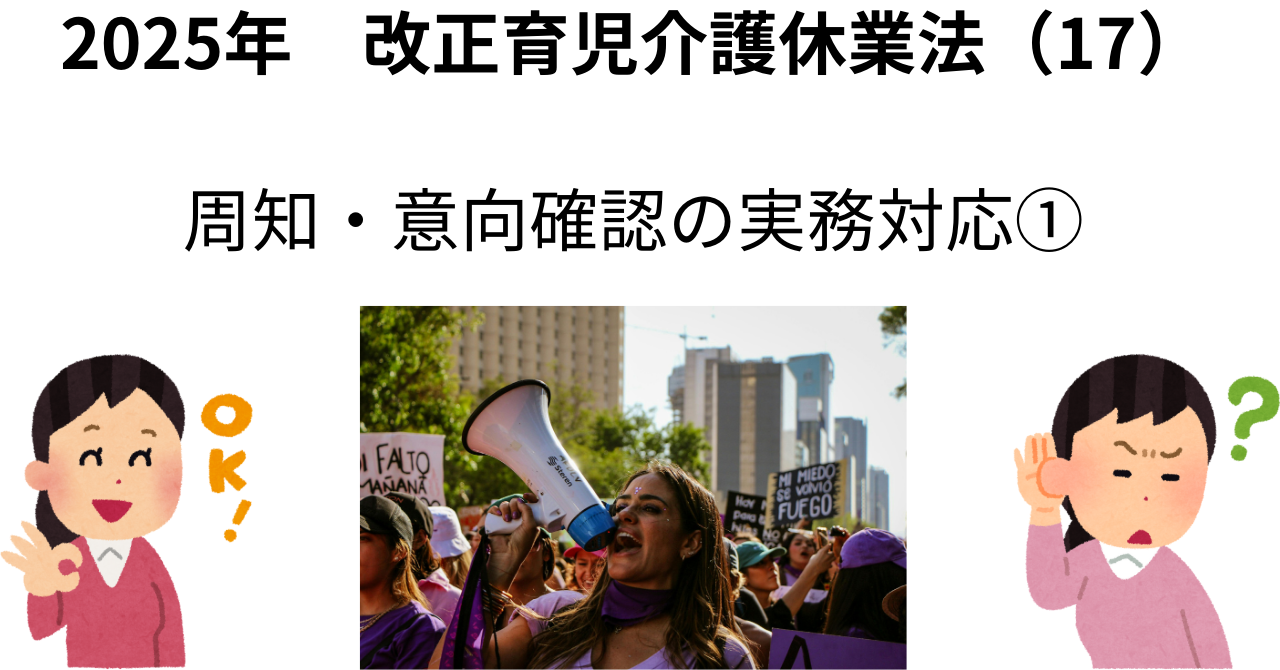

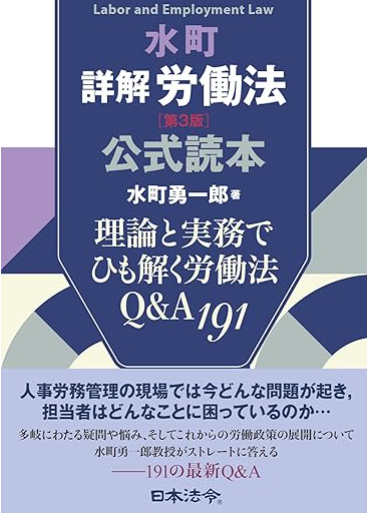
コメント