
執筆者:社会保険労務士 戸塚淳二
法改正対応のスペシャリスト。戸塚淳二社会保険労務士事務所 代表として、多岐にわたる労働関連法規の解説から、実践的な労務管理、人事制度設計、助成金活用まで、企業の「ヒト」と「組織」に関する課題解決をサポートしています。本記事では、事業主の皆さまが安心して法改正に対応できるよう、専門家の視点から最新情報をお届けします。
社会保険労務士登録番号:第29240010号
前回の記事では、2025年改正育児介護休業法への対応における重要なステップとして、育児休業制度の周知・意向確認、そしてそれに伴う就業規則や育児休業規程の整備について詳しく解説しました。これで第一歩は踏み出せたと感じる企業もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はここからが本番です。
社内にどれだけ立派な育児休業規程があっても、それだけでは誰も育児休業を取得しない…。こんな事態は決して珍しくありません。なぜなら、従業員が実際に育児休業を取るかどうかは、単に制度があるかないかだけでなく、会社の「雰囲気」や「取得しやすい環境」に大きく左右されるからです。
「制度があるだけ」で終わらせない!法改正の真の狙い
2025年の法改正が真に目指すのは、「育児休業が単なる絵に描いた餅」で終わらせないこと。周知・意向確認義務の徹底に加え、企業には「取得促進のための具体的な措置」「取得意向確認後のアクション義務」そして「取得率向上のための企業文化の醸成」が求められています。
この「規則は作ったけれど、その先どうすればいい?」という疑問に、今回の記事と次回の記事の2回に分けて、中小企業の現場で本当に役立つ実務対応に焦点を当ててお答えしていきます。法改正を単なる義務として捉えるのではなく、働きやすい職場づくりのチャンスとして活かすための具体的な一歩を、一緒に考えていきましょう。
周知・意向確認から「取得」への橋渡し
今回の法改正が本当に狙っているのは、単に書類上のルールを整えることではありません。その先にある、育児休業を「実際に取得してもらう」ことです。実際に従業員に利用され、その結果として多様な働き方が実現されることです。なぜ「周知・意向確認」に加えて「取得促進」がこれほどまでに企業にとって、労働者にとって、そして今の社会において重要視されているのでしょうか。
「取得促進」が重要な3つの理由
- 法改正の真の趣旨
- 改正育児介護休業法の目的は、育児休業が単なる「権利」として存在するだけでなく、実際に利用されることで、男女ともに育児に参加しやすい社会、そして企業が従業員のライフイベントに対応できる柔軟な働き方を実現することにあります。形骸化した制度では、その目的は達成できません。
- 企業のメリット
- 育児休業の取得促進は、単なる法令遵守に留まりません。従業員が安心して育児と仕事を両立できる環境は、従業員エンゲージメントの向上、優秀な人材の確保・定着、企業イメージの向上に直結します。結果として、企業の競争力強化にも繋がるのです。
- 労働者のニーズ
- 現代の労働者は、キャリアを中断せずに育児に関わりたいという強いニーズを持っています。しかし、「休んだらキャリアに響くのでは」「職場の同僚に迷惑をかけるのでは」といった不安から、制度利用を躊躇するケースも少なくありません。企業が積極的に取得を促進することで、これらの不安を取り除き、従業員が安心して制度を利用できる環境を構築できます。
中小企業における取得促進の課題と解決策
大企業と異なり、多くの中小企業では「人員不足で代替要員の確保が難しい」「育児休業取得のノウハウがない」「制度運用に割けるリソースが限られている」といった現実的な課題に直面しています。
このような中小企業の現場の声を深く理解した上で、限られたリソースの中でも実行可能で、かつ効果的な育児休業取得促進の具体策に焦点を当てて解説していきます。単なる制度整備に終わらず、従業員が「安心して休める」「戻ってきて活躍できる」と実感できる職場環境をどのように築いていくか。その実践的なヒントとステップを、社会保険労務士の視点からお伝えします。
取得促進のための具体的措置(義務化された対応)
2025年改正育児介護休業法では、単に制度を周知し意向を確認するだけでなく、企業が育児休業の取得を実質的に後押しするための具体的なアクションが義務化されています。これは、従業員が「制度は知っているけれど、どうすればいいか分からない」「取得して本当に大丈夫なのか」といった不安を解消し、実際に制度を利用へと繋げるための重要なステップです。
個別周知・意向確認後のアクション義務の再確認
育児休業に関する個別周知と意向確認は、最初の義務化されたステップでした。しかし、その確認結果に応じて、企業はさらなる対応が求められます。
育児休業を希望しない従業員への情報提供義務
意向確認の結果、従業員が育児休業を「希望しない」と回答した場合でも、企業はそこで終わりではありません。対象となる従業員に対し、育児休業に関する制度の再度の情報提供を行う必要があります。これは、従業員が制度について十分に理解していなかったり、一時的に取得を躊躇している可能性を考慮するためです。具体的には、育児休業中の待遇(社会保険料免除や育児休業給付金など)、育児休業に関する相談窓口の案内、会社の支援策などを改めて丁寧に説明し、改めて検討を促すことが重要です。
取得を希望する従業員への個別支援の具体例
一方、育児休業の取得を「希望する」と回答した従業員に対しては、より具体的な支援が求められます。これは、単に申請書を渡すだけでなく、休業期間や復職後の働き方に関する相談に乗ったり、利用可能な支援制度(例えば、社内独自の時短勤務制度やフレックス制度など)を積極的に案内したりするといった、きめ細やかな対応が含まれます。従業員の不安を解消し、スムーズな取得と復職をサポートする姿勢が重要です。
育児休業取得に関する情報提供の義務化
企業は、育児休業を予定している従業員に対して、制度に関する詳細な情報を提供する義務があります。これは、従業員が安心して休業し、復職後のキャリアを計画できるよう、必要不可欠な情報提供です。
提供すべき情報の範囲
単に休業が「できる」というだけでなく、休業期間中の生活や復職後に影響する詳細な情報を提供しましょう。具体的には、育児休業の対象期間、取得要件、育児休業中の賃金や待遇(社会保険料免除の仕組み)、育児休業給付金の申請方法や支給額の目安、休業中の社会保険等の取り扱い、復職後の勤務条件や配置に関する事項、会社独自の支援制度など、多岐にわたります。
情報提供の方法
情報は、従業員が理解しやすい方法で提供することが求められます。書面での資料配布はもちろん、個別面談を通じて直接説明したり、社内ポータルサイトやオンラインツールでいつでも確認できる環境を整えたりすることも有効です。一方的に情報を与えるだけでなく、従業員からの質問を受け付け、疑問点を解消できるような双方向のコミュニケーションを心がけましょう。
情報提供のタイミングと記録の重要性
情報提供のタイミングも重要です。妊娠・出産の申し出があった際や、育児休業の意向確認を行う際など、適切なタイミングで、漏れなく情報を提供することが求められます。また、いつ、誰に、どのような情報を提供したかを記録に残しておくことも忘れてはなりません。これは、法令遵守の証拠となるだけでなく、後々のトラブル防止にも繋がります。
育児休業取得に関する相談窓口の設置
従業員が育児休業について気軽に相談できる窓口の設置は、制度利用へのハードルを下げる上で極めて重要です。
相談窓口の役割と重要性
相談窓口は、従業員が育児休業に関する疑問や不安、懸念を率直に打ち明けられる「安全な場所」であるべきです。単なる情報提供だけでなく、個別の状況に応じたアドバイスや、場合によっては社内の他部署との連携を調整する役割も担います。従業員が制度を「自分事」として捉え、安心して利用を検討できる環境を提供するために不可欠ですし、これは企業がハラスメント防止義務を果たす上でも重要な拠点となります。
相談対応者のスキルと情報共有の徹底
相談窓口の担当者は、育児介護休業法に関する知識はもちろん、会社の育児休業規程や関連制度について正確な情報を持っている必要があります。また、従業員の心情に寄り添い、丁寧に対応できるコミュニケーションスキルも求められます。担当者間での情報共有を徹底し、対応に一貫性を持たせることも重要です。定期的な研修を実施し、最新情報へのアップデートを欠かさないようにしましょう。
外部専門家(社会保険労務士など)の活用
社内に専門的な知識やリソースが不足している中小企業の場合、社会保険労務士などの外部専門家の活用を検討するのも有効な手段です。法改正への対応、規程の見直し、従業員への説明、個別の相談対応など、専門家の視点から客観的かつ正確なアドバイスを得ることで、安心して制度を運用できます。
次回の記事は?
今回は、2025年改正育児介護休業法で義務化された「取得促進のための具体的措置」に焦点を当てて解説しました。これらは、単に「制度がある」だけでなく、従業員が「安心して使える」環境を築くための第一歩です。
次回の記事では、これらの義務化された対応を超えて、「育児休業の実効性を高めるための取り組み」、具体的には「取得意向確認後のアクション義務の具体的な進め方」、そして「取得率向上のための企業文化の推進」について、さらに深掘りしていきます。企業がどのように育児休業の取得を促進し、実際に制度が活用される文化を築いていけるのか、その具体策を明確に解説しますので、ぜひ次回も楽しみにしていてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。ご相談の際は、以下よりお気軽にお問い合わせください。☟
📌社会保険・労務対応・就業規則作成等について👉奈良県・大阪府・京都府・三重県など、近隣地域の企業・個人の方は・・・⇨戸塚淳二社会保険労務士事務所 公式ホームページからお問い合わせください。
📌遠方の方や、オンラインでのご相談をご希望の方は⇨ココナラ出品ページをご利用ください。
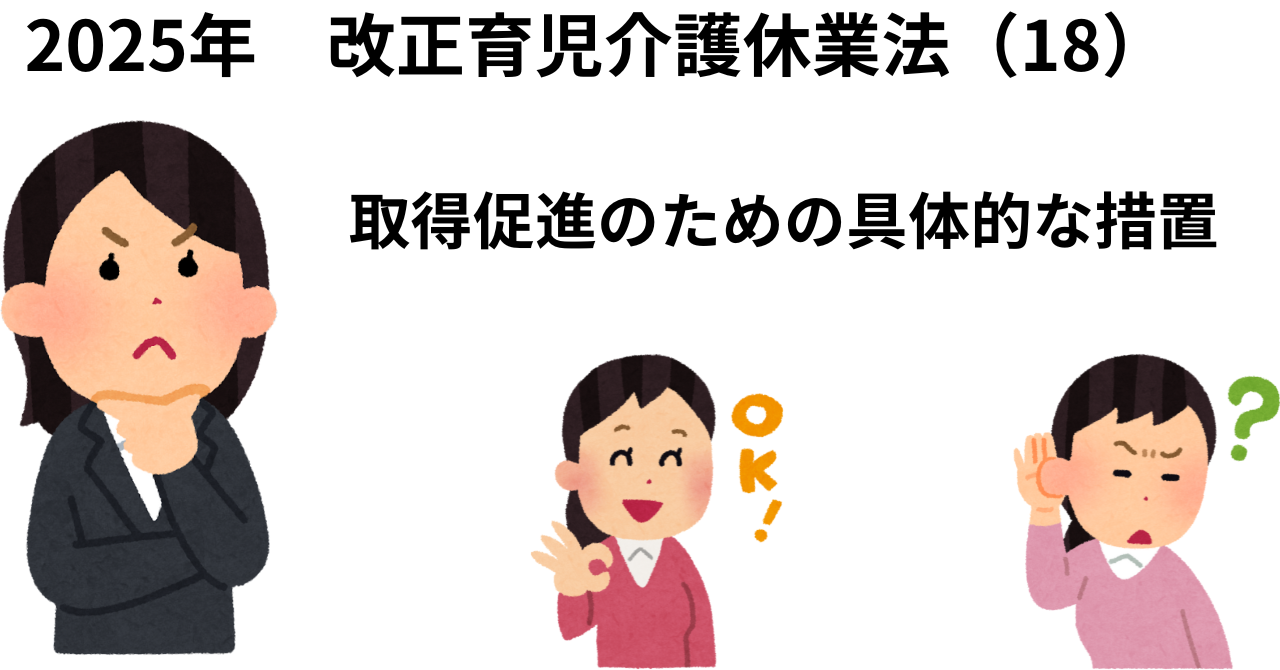
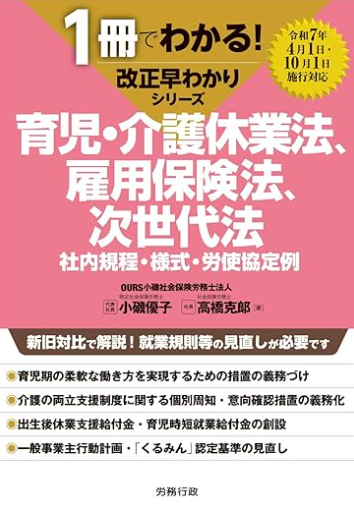
コメント