社労士事務所を副業で開業して、はや半年が経過しました。まぁ予想通りといえば予想通りなのですが、パッとしないなぁ、という状態です。
顧問先1社、以上。一応収入はあります。この顧問先は近いうちに法人化して云々・・・。と会社を大きくしようとしている真っ最中です。社労士としてお役に立てればと思っております。
とりあえず動きます
副業開業という形態をとっているため、独立開業した先生方と違い、危機感が足りないというのもあるとは思います。
ただ一つ分かったことは、何もしなければ何も起こらないということです。何でもいいので、何か行動を起こすのは必須ですよね。黙って待っていっれば仕事が舞い込んでくるということは絶対にないですね。
何でもいいのです。例えば都道府県の社労士会や支部が開催する研修会などに積極的に参加して、同業者の中で顔と名前を覚えてもらう、でもいいです。今、私が真っ最中のブログ記事を発信する、ホームページを作る、などでもいいと思います。
私はX(旧ツイッター)をよくやっているのですが、同じ士業で行政書士事務所を開業してる方の投稿を見てますと、「ポスティング」「DM送付」という文言がよく出てきます。しかし、社労士の方でこれをやっているというのは今のところ聞いたことがないです。この件に関してはアンテナを張って追っていこうとは思います。有効な手段なのであれば真似しようかな?
その他、今は一応色々試しにやってみてはいますが、まだ結果が出ていないので、追々発信できればと思います。
支部の総会に参加
そんな中で、先月支部の総会の案内がありました。総会ってなんだ?と思いながら、参加してきました。
総会というくらいなので、議題がいくつかあり、賛成の方・異議のない方は挙手を、と一つ一つの議題ごとに挙手を求められる、という感じで進行していきます。
はっきり言って、手を挙げて良いのか悪いのか、よくわからないという状態なのです。しかし、何を思ったのか、最初に席に着くときに何故かほぼ最前列に座ってしまいます。そのため、他の先生方が挙手をするのを確認してから手を挙げるという戦法が使えませんでした。
いちいち後ろを振り向くのもカッコ悪すぎるので、後ろの先生方の手が挙がるのか挙がらないのかの気配を全集中で感じ取ろうと試みます。意外とわかるもので、気配がした0.2秒後くらいに挙手をして凌ぎました。
一見どうでもいいような話ですが、初めて参加する会、研修会などではなるべく後ろのほうに陣取って、全体を俯瞰できる状態にしておいたほうが無難である、という教訓が得られました。
懇親会にて
つづいて、懇親会がありました。全く初対面の方々ばかりのところに飛び込むのは、多少どころかかなり躊躇してしまうところもあったのですが、とりあえず参加してみます。
私の社労士としての区分は「開業」社労士です。ほかに、「勤務」社労士、「その他登録」があります。
私は社労士事務所を開業しましたが、正直に言って「副業」で開業したということに対して、若干負い目みたいなのはありました。どういうことかというと、完全に前職を辞めて、社労士のみでやっていくという「独立」で開業している先生方からすると「なんだ、甘い事やってんなぁ」と思われているんじゃないか、という思いがありました。しかし、私からすると、何故わざわざいわゆる「背水の陣」のような陣をしかないといけないのか?という考えもあります。
懇親会に参加した、先輩社労士の先生方と話をしましたが、本当に色々な年代の方々、色々な経歴の方々がいて、とても驚きました。とある先生は、支部の役員をやっておられるのですが、開業したのは58歳の時で、まぁ年金の足しにでもなればなぁ、と思って開業した、とおっしゃってました。
社労士になるきっかけ、どういう形で社労士として活動しているのか、は人それぞれなのだな。多様性という言葉が昨今流行ってますが、少なくとも社労士業界は多様性に満ちていて、それを認めるという土壌がある、と感じました。
という感じで、最近の社労士としての行動、考え、感じたことなどをザクっと書いてみました。
ではまた。ご拝読ありがとうございました。

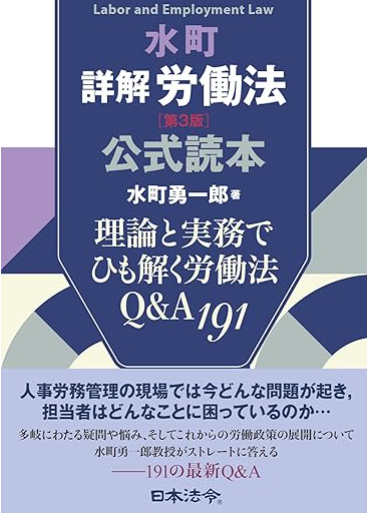
コメント