2025年の育児・介護休業法改正をテーマにした本ブログ連載も、今回で第7回目を迎えました。これまで、
- ➀男性の育児休業取得の促進
- ➁介護離職を防ぎ、経験豊富な労働力の確保
といったテーマを取り上げてきました。いずれも、出産や介護といったライフステージ上の大きな出来事を支える制度であり、離職の防止や、家庭内における負担の公平化を進めるための重要な施策でした。
一方で、今回のテーマ③「仕事と家庭を両立しやすい柔軟な働き方の実現」は、そうした一時的なイベントに備えるだけでなく、子どもの発熱や学校行事、保育園からの急な呼び出しといった「日常的な場面」で、働き方に柔軟性を持たせられるようにすることを目的としています。
言い換えれば、これまでの制度が「育児や介護に直面したときの離職を防ぐ」ことに重点を置いていたのに対し、今回の改正では「そもそも辞めなくて済むような、無理のない働き方を日々の中に実現する」ための基盤整備が進められた、といえるでしょう。
今回はこれまで触れられなかった注目の改正項目、「子の看護休暇制度の見直し」「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大」についてご紹介します。
働き方を「柔軟に」するということ
「柔軟な働き方」という言葉はすっかり定着しましたが、育児や介護を担う方々にとっての柔軟さとは、「自分に必要なときに、必要なだけ時間を調整できる」ことにほかなりません。
たとえば、保育園の呼び出し、学校行事、急な通院。これらの出来事は予告なく短時間だけ発生するものが多く、従来のように「フルタイムで働くか、辞めるか」といった二者択一では、家庭と仕事の両立は到底難しいのです。
こうした背景を踏まえ、2025年の法改正では、働き方そのものの柔軟性を支える制度として、いくつかの重要な見直しが行われています。
「子の看護休暇制度」の見直し
これまでのブログでは、男性の育休取得や介護支援といった節目・ライフイベントにおける制度を取り上げてきましたが、育児と仕事の両立を日常的にサポートするという意味では、「子の看護休暇制度」「所定外労働の制限(残業免除)」の見直しこそ、実際の働き方に最も影響を与える改正といえるでしょう。まずは、「子の看護休暇制度」について見ていきましょう。
現行制度の課題
改正前の制度では、小学校就学前の子が対象で、保護者は年に最大5日(子が2人以上いる場合は最大10日)の「子の看護休暇」を取得することができます。しかし、子どもが小学校に上がった瞬間にこの制度が使えなくなってしまうという、「制度の壁」が存在していました。
小学生になったからといって、急な発熱、インフルエンザ、けが、慢性疾患への通院等がなくなるわけではありません。むしろ、1人での通院がまだ難しい学齢期の初期(1〜3年生)は、保護者の付き添いや対応が欠かせない場面も多いのが実情です。
小学校3年生修了前まで拡大
このような現実に対応すべく、2025年4月からは、子の看護休暇の対象となる子の範囲が、「小学校就学前」から「小学校3年生修了前」へと拡大されます。
つまり、これまでは使えなかった小1〜小3の子どもが対象に加わることで、現場にとって非常に使い勝手の良い制度へと進化することになります。
取得事由の拡大
従来の取得事由(2025年3月まで)
- 子の 病気やけが に伴う看護
- 予防接種 の付き添い
- 健康診断 の付き添い
改正後の取得事由
- 子の 病気やけが に伴う看護
- 予防接種 の付き添い
- 健康診断 の付き添い
- 感染症に伴う学級閉鎖等
- 入園式・入学式、卒園式への出席
これにより、取得事由が「病気・けが」だけに限られず、育児を日常的に支える幅広いシーンへと拡大されることが期待されています。
休暇取得要件の緩和
今回の法改正により、「子の看護休暇」を取得できない労働者、いわゆる取得除外の対象者の条件についても見直しが行われました。
これまでは、介護休暇と同様に以下のような労働者が取得除外とされていました。
- 週の所定労働時間が2日以下の労働者
- 継続雇用期間が6か月未満の労働者
しかし、2025年4月の改正により、このうち「継続雇用期間が6か月未満」の要件が削除され、以下のように変更されます。
- 週の所定労働時間が2日以下の労働者
この改正により、「雇い入れから6か月経過していなくても」、所定労働日数が週3日以上であれば、子の看護休暇を取得できるようになります。
これもまた、非正規労働者や短時間勤務者への配慮の一環といえるでしょう。これまで制度の恩恵を受けられなかった方々にも、子育て支援の仕組みが届きやすくなります。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
次に「所定外労働の制限(残業免除)」について見ていきます。
これまで、育児と仕事の両立を支援する制度の一つとして、「所定外労働の制限(いわゆる残業免除)」が設けられていました。
「所定外労働の制限(いわゆる残業免除)」の制度は、2009年6月の育児・介護休業法の改正(2010年6月30日施行)によって創設されました。
この制度は、育児休業中ではなく、すでに職場復帰して働いている親を支援する仕組みです。育児休業からの復帰後も、子どもの成長に合わせた働き方の柔軟性が求められる中で、特に「時間的拘束」がネックとなるケースに対応する重要な制度でした。
制度創設の背景としては、「育児休業の取得支援」から一歩進み、「育児と仕事を無理なく両立させる職場環境の整備」が求められていました。特に、職場復帰後の長時間労働が育児との両立を困難にしていたため、「残業をしない」という選択肢を法的に認め、制度として整えたのがこの改正です。
対象者:3歳未満の子を養育する労働者(性別不問)
内容:労働者から申し出があれば、事業主は所定外労働(残業)をさせてはならない※免除の義務あり(単なる配慮義務ではない)
改正前と改正後の違い
改正前は「3歳未満の子を養育する労働者」が対象でしたが、改正後(2025年4月以降)は「小学校就学前の子を養育する労働者」までに拡大されます。いずれも労働者から申し出があった場合、事業主は所定外労働(残業)を免除する義務があります。
この改正によって、対象となる期間がおよそ3年間延びることになります。これにより、たとえば保育園年長クラスの年齢や、幼稚園に通うお子さんを持つ親も、残業免除の請求ができるようになります。
制度を「使える形」にする
ここまで制度の中身を見てきましたが、制度は作っただけでは意味がありません。「使える」制度にするためには、企業内での準備と整備が必要不可欠です。
ここでは、制度を真に活かすために企業が取り組むべき2つの視点を整理してみましょう。
就業規則や社内制度の見直し
まず必要なのは、法改正内容を正確に反映した就業規則や育児関連制度の見直しです。
例えば、子の看護休暇の対象が「小学校3年生修了前」まで拡大されたり、残業免除の対象が「小学校就学前」まで広がったことは、従業員の働き方に直接関わる重要な変更です。
これらが就業規則に明記されていなければ、制度の存在そのものが知られず、利用されにくくなってしまいます。
また、取得条件や申請手続きも、過度に複雑になっていないかを見直すことが肝心です。パートタイマーや有期契約社員など、これまで制度対象外だった層にも制度が広がっている点を踏まえ、就業形態を問わずわかりやすい制度設計が求められます。
従業員への周知と制度活用の促進
制度は整えて終わりではなく、それを誰もが安心して使える状態にすることが重要です。
そのためには、改正内容を含めた制度の概要を、従業員へわかりやすく周知することが不可欠です。ガイドブックや社内ポータルサイトを活用して、対象者・取得手順・申請様式などを明示し、制度の「見える化」を図ると効果的です。
さらに、直属の上司や管理職が制度内容を正しく理解し、取得希望者に対して前向きに対応できるよう、管理職向けの研修やQ&A対応も視野に入れておきたいところです。
実際の制度活用には、周囲の理解や協力も大きく影響します。「使っても大丈夫」「制度があるから安心して働ける」という雰囲気づくりも、企業に求められる役割の一つです。
私たち社会保険労務士としても、こうした社内制度の見直しや、従業員説明会の実施支援など、企業の内側から制度の定着を後押しする支援が重要になってきます。
テレワークやフレックスなど他制度との併用もカギ
柔軟な働き方の実現には、「子の看護休暇の見直し」「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大」だけでは足りません。むしろ、
- テレワーク
- フレックスタイム制
- 短時間勤務制度
- 時間単位の有給休暇制度
といった制度を併用する形で“家庭と仕事の両立”が成り立つということを、企業側も意識していく必要があります。
例えば、朝に通院付き添い → 午後はテレワーク、といった柔軟な働き方が可能であれば、制度の利用率も上がり、働く側の不安も軽減されます。
制度の「積み重ね」が両立支援を本物にする
この連載では、「育児・介護と仕事の両立」という共通の目標に向けて、4つの柱から制度改正を掘り下げてきました。今回取り上げた「柔軟な働き方の実現」は、そうした柱を支える「土台」ともいえるテーマです。
特に「子の看護休暇」の対象拡大や取得要件の緩和は、これまで制度の枠外に置かれていた家庭にも新たな支援を届ける、大きな一歩となります。また、「所定外労働の制限(残業免除)」の対象が広がったことで、幼児期までの長い育児期間にわたって、働き方そのものの柔軟性が確保されやすくなりました。
これらの見直しは、どちらも日々の生活のなかで直面する育児のリアルに対応したものであり、制度が絵に描いた餅ではなく、実際の暮らしに根ざした使える仕組みへと進化している証といえるでしょう。
制度のひとつひとつが社会の中に積み重なり、やがてそれが「当たり前の支援」として根付いていく。そんな未来を実現するためには、企業、働く人、そして私たち社会保険労務士が、それぞれの立場で制度を整え、活用しやすくしていく努力が欠かせません。
次回はいよいよ連載の大詰めに入ります。
「④企業の対応格差を是正し、育児・介護支援を当たり前に」をテーマに、企業規模や業種による対応の差、義務化される事項などを中心にご紹介します。今回までの内容と重複する部分はあるとは思いますが、ぜひ最後までお付き合いください。

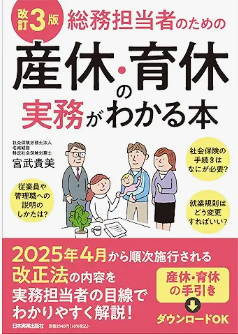
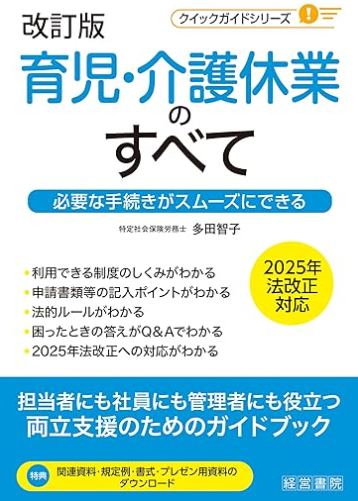


コメント