育児休業の支援体制が整いつつある今、次に社会全体で向き合うべき課題は「介護」です。少子高齢化が進む日本では、40〜50代の働き盛り世代が親の介護に直面し、離職を余儀なくされるケースも少なくありません。
今回のテーマは、2025年法改正で何が変わり、どう介護離職を防ぐのか。企業だけではなく社会全体の対応を見ていきましょう。
日本の高齢化がますます進行する中、仕事と介護の両立は社会全体の重要課題となっています。特に「介護離職」は、個人の生活基盤を脅かすだけでなく、企業にとっても貴重な人材の喪失につながり、深刻な問題となっています。
介護離職の現状とその影響
1:年間約10万人が介護を理由に離職
親や配偶者などの介護を理由に離職する人は年間約9〜10万人。中でも40代〜50代の働き盛りの世代の離職が目立ちます。(総務省統計局『令和4年就業構造基本調査』)企業にとって経験豊富な即戦力である彼らの離職は、業務の停滞や後継者不在など、深刻な影響を与えます。
2:個人にも深刻な影響
介護による離職は、収入やキャリアの喪失にとどまらず、長期的な生活不安や社会的孤立にもつながります。再就職も難しく、心身への負担も大きくなります。
介護と仕事の両立が難しい背景
1:介護の始まりは突然
育児と仕事の両立にはもちろん多くの困難や課題がありますが、介護と仕事の両立にはまた異なる性質の難しさが伴います。多くの場合、親の病気や認知症は予期せぬタイミングで始まり、準備が整わないまま介護に直面します。
2:職場の理解不足と制度の利用しづらさ
制度はあっても「使いづらい」と感じている人は多く、制度利用による評価低下への不安や、同僚への負担を懸念する声が多くあります。
3:情報不足と相談先の不明確さ
介護保険や地域包括支援センターなど、支援制度の情報を把握していない人も多く、適切なサポートを受けられないケースが目立ちます。
2025年 育児・介護休業法 介護に関する改正のポイント
2025年4月の法改正では、「介護と仕事の両立」を支える環境整備が重点強化されました。以下が主なポイントです。
1:介護休業の分割取得がより柔軟に
従来の介護休業の取得は、対象家族1人につき、要介護状態ごとに通算93日・最大3回まで分割取得可能というものでした。
「要介護状態ごとに」と書きましたが、同一の要介護状態の場合は通算93日ということで、対象家族1人に異なる要介護状態が発生した場合はそれぞれに対して、通算93日・最大3回まで分割可能ということです。
2025年法改正後は、本人の状況に応じてさらに柔軟に取得可能となります。もう少し具体的に言いますと、通算93日までの介護休業を、回数無制限で分割取得できるようになりました。
なぜこれが重要かというと、介護は出産や育児のように「ある程度見通しが立てやすいものではない」からです。介護の必要性は、突然やってきます。そして一度きりでは済まない場合がほとんどです。
「一時的な入院」「退院後の在宅介護準備」「要介護度の変化」など、家族の状態に応じて何度も対応が求められます。
このような変化に柔軟に対応するために、「細切れでも休める」「必要なタイミングで都度取得できる」仕組みが必要です。
法改正により、現実のニーズに即した取得スタイルが可能になることは、介護を担う従業員にとって大きな安心材料となるでしょう。
2:介護休暇取得要件の緩和
- 改正前:介護休暇を取得するためには、従業員が継続雇用期間6か月以上であることが条件でした。
- 改正後:この6か月以上の継続雇用期間の要件が廃止され、週の所定労働日数が2日以上の全ての労働者が、雇用形態を問わず介護休暇を取得できるようになりました。
因みにここでいう「介護休暇」と「介護休業」は異なる制度です。
介護休暇
- 目的:介護が必要な家族の世話をするために取得する短期的な休暇
- 取得期間:1年につき最大5日間(1人の対象家族に対して)、複数回に分けて取得可能
- 取得対象者:雇用形態を問わず週の所定労働日数が2日以上である労働者
- 給与の支給:給与の支給は義務ではなく、企業によって異なります。場合によっては無給のこともあります。
- 柔軟性:短期的な介護が必要な場合に、比較的柔軟に取得できる制度です。
介護休業
- 目的:長期間にわたって介護が必要な家族を介護するために取得する休業
- 取得期間:1人の対象家族について、最長93日間まで取得可能
- 取得対象者:原則として、日雇い労働者を除く、すべて労働者(週所定労働日数が2日以上の方など)
- 給与の支給:原則として、雇用保険の介護休業給付金が支給されます。
- 柔軟性:通常は、長期的な介護を担う場合に利用されますが、分割して取得できるなどの柔軟性があります。
3:テレワーク・短時間勤務の推進
企業には、「3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク選択肢の提供」と同じで、介護中の従業員へのテレワークや時差出勤、短時間勤務などを利用できるよう、環境整備の努力義務が課されます。
両立支援に向けた企業の環境整備義務
これまでに、両立支援を取り巻く背景や現状、そして法改正のポイントについて見てきました。そうした中で今、企業には従業員一人ひとりが安心して働き続けられるよう、職場環境の整備が強く求められています。ここでは、企業が取り組むべき具体的な両立支援の内容について述べていきます。
1:就業規則への明記
2025年の育児・介護休業法改正において、企業には両立支援に関する制度を就業規則に明記することが義務付けられました。
これは、従業員が育児や介護の休業制度を利用する際、企業としての支援体制を明確に示し、従業員が自分の権利を適切に理解し、利用しやすくするための重要なステップです。
具体的には、次の内容を就業規則に明記する必要があります
- 介護休業の取得条件
- 取得可能な期間や回数
- 休業中の給与の取り決め
- 復職後の勤務条件やキャリア形成の支援
企業がこれらを明確に規定することで、従業員は自分が利用できる支援策について事前に理解し、迷わず活用することができます。
また、これによって企業内部で一貫した制度運用が保証されるため、従業員間の公平性も保たれることになります。
2:相談体制の整備
介護や育児を理由に仕事との両立が難しいと感じている従業員にとって、相談できる窓口の設置は非常に重要です。
改正法では、企業に対して両立支援に関する相談体制の整備が求められています。これは、従業員が不安や疑問を感じた際に、迅速に対応できる体制を整えることを意味します。
相談体制の整備において企業が行うべきこと
- 介護や育児に関する専門的な相談窓口を設置する
- 人事部門や健康管理部門など、複数の部門で対応できる体制を作る
- 相談窓口を広報し、従業員がアクセスしやすいようにする
- 個別の状況に応じた柔軟な対応ができるよう、スタッフのトレーニングを行う
企業内で専任の担当者やチームを設けることで、従業員は自分の介護や育児に関する悩みや不安を解消しやすくなり、安心して休業制度を利用できるようになります。
3:情報提供の強化 周知・意向確認
もう一つ重要なポイントは、従業員に対する情報提供の強化です。
制度自体が複雑であったり、利用方法が不明確だと、従業員はその制度を使うことをためらうことがあります。そこで、企業は制度についての積極的な情報提供を行う義務があります。
企業が行うべき情報提供の方法
- 定期的な社内研修を実施し、従業員に両立支援制度を周知する
- 社内ポータルサイトやイントラネットを利用して、常に最新の制度情報を提供する
- パンフレットやQ&A資料を作成し、従業員が簡単に制度内容を理解できるようにする
- 個別のケースに基づくアドバイスを行い、制度の利用方法を具体的に示す
特に、情報提供を強化することで、従業員は自分の状況に合った支援を受けることができ、制度の活用率が向上します。企業も円滑な制度利用を促進することで、従業員の負担軽減やモチベーション向上を図ることができます。
4:企業の長期的な視点での支援
これらの就業規則の明記、相談体制の整備、情報提供の強化といった義務は、短期的な対応だけではなく、長期的に継続されるべきものです。
企業が両立支援の体制を整えたとしても、従業員が活用しやすい状況を維持することが重要です。これには、制度の運用を定期的に見直し、時代に応じた改善を行うことが求められます。
企業の長期的な支援が重要な理由
- 介護の負担は急に大きくなることがあり、柔軟な対応が求められる場面が多くあります。
- 従業員が制度を適切に利用できることで、職場でのストレスや不安が減少し、生産性の向上にも繋がります。
- 長期的に両立支援を行うことで、企業のブランドイメージ向上にも寄与し、優秀な人材の定着や採用にも好影響を与えます。
社会全体で介護離職を防ぐには
ここでは、介護離職を防ぐために必要な、国・企業・個人のそれぞれの役割・備えについて箇条書きにて記しておきます。
1:国の役割
- 制度の柔軟化と情報発信
- 両立支援助成金の拡充
- 地域との連携強化(包括支援センターなど)
2:企業の役割
- 「使いやすい制度」づくり
- 社内文化の整備と周知
- 定期的な職場ヒアリング
3:個人の備え
- 家族との話し合い(介護の方向性)
- 地域資源・制度の情報収集
- 社内制度や相談窓口の確認
介護離職を「なくす」ための未来づくり
2025年の法改正は、制度的な後押しとともに、社会全体の意識変革を促す一歩です。企業が制度と文化を整え、従業員が備えと情報を持つことで、「介護離職 防止」という社会的課題に立ち向かうことができます。
高齢社会において、経験豊かな人材が安心して働き続けられる社会づくりは、企業の未来、地域の活力、そして私たち一人ひとりの安心にもつながります。
日本社会は今、かつてないスピードで少子化と高齢化が進んでいます。
その影響を大きく受けているのが「労働力人口」です。働く世代の減少は、企業の人材確保に直結する深刻な課題となっています。
そんな中、介護を理由に離職するケースが毎年のように発生している現実は、見過ごせません。
とくに、「会社の中核を担う40代〜50代の世代が、親や家族の介護を理由に仕事を手放してしまう。」これは、国家にとっても企業にとっても、そして個人にとっても大きな「損失」と言えるのではないでしょうか。
介護離職の防止は、個人の生活やキャリアを守るだけでなく、「貴重な労働力を社会にとどめる」ことにもつながる重要なテーマです。
2025年の育児・介護休業法の改正が、こうした課題への突破口となることが期待されています。

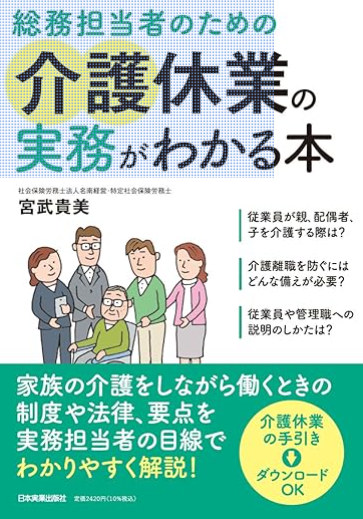



コメント