これまでの育児休業制度は「制度としてはあるけれど、実際には使いにくい」と感じていた人も多いのではないでしょうか。特に男性やキャリアの途中にある人にとっては、「まとまった期間の休業」はなかなかハードルが高いものでした。
2025年の育児・介護休業法改正では、より柔軟に・より現実的に育児休業が取得できるよう、制度の運用や意識改革を促す内容が盛り込まれています。
ここでは、そんな「柔軟な育児休業取得の促進」について、具体的な制度内容やメリット、企業と従業員それぞれの視点から解説していきます。
なぜ今「柔軟な育児休業取得」が必要なのか?
育児休業制度そのものは以前から存在しているにもかかわらず、実際に活用されているかというと、まだまだ理想と現実にギャップがあるのが現状です。特に男性の育児休業取得率は、年々上昇しているものの、依然として「空気を読む文化」や「職場の理解不足」により、利用しづらさが残っています。
では、なぜ今「柔軟な取得」が求められているのでしょうか?
画一的な制度では、現実に対応しきれない
これまでの育児休業制度は、どちらかというと「長期で休む」ことを前提とした内容が主でした。しかし、実際の育児は予測不能です。たとえば以下のようなケースでは、従来の制度だけでは対応が難しいこともあります。
- 出産直後は休めたが、その後子どもが体調を崩したため、また別のタイミングでもう一度休みたい。
- 妻と交代で休みたいが、制度上、うまくタイミングを合わせづらい。
- 1か月も休むのは職場への影響が大きすぎて不安。数週間単位で分けて休みたい。
こうしたリアルなライフスタイルや職場事情に対応できる柔軟性が、今、求められています。
男性育休の「空気の壁」を打ち破るには
政府も掲げる「男性育休取得率50%」(2025年目標)という目標に対して、現状はまだ30%前後にとどまっています。その背景には、制度があることを知っていても、
- 「長期で休むのは気まずい」
- 「代替要員がいないから迷惑をかける」
- 「復帰後のキャリアに悪影響があるかもしれない」
といった心理的ハードルが存在します。
ここで重要なのが、「柔軟に休みが取れる仕組み」です。たとえば「2週間だけ」「1か月を2回に分けて」「夫婦で交代しながら」といった選択肢があれば、「これなら取れそう」と感じる人が増えるのは自然な流れです。
社会の変化と働き方の多様化
かつては「子育て=母親の役割」という前提で制度が作られていましたが、今や共働き世帯が主流です。さらにコロナ禍を経てリモートワークやフレックスタイムなど、働き方の柔軟性も一気に拡がりました。
育児においても同様に、「こうでなければならない」という考えから脱却し、それぞれの家族や職場に合った形で支援ができるようにすることが求められています。
離職防止と人材確保の観点からも
若い世代を中心に「家庭との両立を重視したい」という価値観が広がるなか、育児と仕事が両立できる環境があるかどうかは、企業選びや離職の判断にも直結します。
柔軟な育児休業制度は、「長く働きたいと思える会社」の条件のひとつになってきており、企業側にとっても人材確保・定着のカギとなります。
これからの育児休業制度には、「制度の有無」だけでなく、「どれだけ使いやすいか」「どれくらいの選択肢があるか」が問われます。
働き方が多様化する今、育児休業の取得も多様であってしかるべきです。柔軟性のある制度設計と、それを実際に「使える」文化をつくることが、これからの企業・社会にとって重要なステップになります。
柔軟な育児休業取得とは?2022年・2025年の法改正ポイントを整理
ここでは2022年改正で実現した柔軟な制度と、2025年から加わる新たな制度を、それぞれ簡潔に整理して見ていきます。
2022年法改正で制度化されたポイント
①育児休業の分割取得(最大2回まで)
- 従来は1回しか取得できなかった育児休業が、原則2回に分けて取得可能になります。
- たとえば「生後すぐに1回目」「育児が落ち着いた頃に2回目」といった使い方が可能です。
➁産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 子の出生後8週間以内に、最大4週間の育休を別枠で取得可能になります。
- 分割取得(2回まで)もOKです。
- 通常の育児休業とは別に取得できるため、特に男性の育休取得のを後押ししてくれます。
➂申出期限の柔軟化(2週間前でもOK)
- 「産後パパ育休」に関しては、労使協定があれば、2週間前の申出でも取得可能です。
- 急な出産や状況の変化にも対応しやすくなりました。
2025年法改正で新たに加わるポイント
出生後休業支援給付の創設
- 最大28日間の育児休業に対して、手取りをほぼ減らさず取得できる給付制度が新設されます。
- 対象は、子の出生後8週間以内に育児休業を取得する被保険者(男女ともに対象)です。
- 給付率は賃金の100%相当(社会保険料免除と併せて実質100%近く)になります。
- これにより、特に男性が経済的不安なく育休を取得しやすくなります。
2022年の改正で育休の「取り方」が広がり、2025年の改正では「取りやすさ(給付の充実)」がさらに強化されます。
これらの制度を活用することで、育児とキャリアを両立しやすい環境が着実に整いつつあります。
柔軟な育児休業取得によるメリットとは?
従業員・企業それぞれに期待される効果
育児休業制度が進化し、「分割取得」や「産後パパ育休」など、より柔軟に休める制度が整ってきました。
では、こうした柔軟な取得が実現することで、どんなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、従業員側・企業側それぞれの立場から、期待される効果を整理して見ていきましょう。
従業員側のメリット
① 家族との時間がしっかり確保できる
分割取得や短期休業が可能になることで、「生まれたての子としっかり関わる時間」を持ちやすくなります。
出産直後、育児の大変な時期を夫婦で支え合うことが可能になります。
② キャリアへの影響を最小限に
一度に長期間離れるのではなく、仕事と育児のバランスを取りながら休むスタイルが選べるようになります。
復職後のブランク感や業務キャッチアップの不安も軽減されます。
③ 心理的ハードルが下がる
「育休=長期離脱で迷惑をかける」といったプレッシャーが減り、「少しだけ取る」という選択肢が当たり前になります。
初めて育休を取る男性社員の心理的負担も大きく軽くなります。
企業側のメリット
① 離職の防止・エンゲージメントの向上
柔軟な取得スタイルを許容することで、「働き続けられる」という安心感が生まれます。
結果として、人材の定着率やモチベーションの向上につながります。
② 多様な働き方に対応できる企業としてのアピールに
「柔軟な育児支援制度あり」は、採用市場でも強みになります。
特にZ世代以降では「家庭も大切にできる会社か」は重視されがちです。
企業イメージやブランディング向上にも貢献します。
③ 女性活躍の推進だけでなく、「男性育休の常識化」に
女性だけでなく男性も積極的に育休を取得する文化が根付けば、育児=女性という固定観念の払拭にもつながります。
育休は「制度」から「戦略」へ
柔軟な育児休業制度は、単なる「福利厚生」ではなく、従業員の満足度・企業の持続的成長に直結する「戦略ツール」です。
「取れる」ではなく、「取りやすい」「取りたくなる」制度へ。これからの時代、企業と従業員がともに成長するために、柔軟な育休制度の活用は欠かせないカギとなるでしょう。
柔軟な育児休業取得を促すために企業ができること
「取れる」だけでなく「取りやすい」環境づくりのポイント
育児休業制度が柔軟化しても、実際に取得するかどうかは職場の環境次第です。
制度があっても「なんとなく取りづらい」と感じてしまうケースも少なくありません。
では、企業として「柔軟な育児休業取得」を促すには、何をすべきなのでしょうか?
ここでは、具体策として3つ取り上げたいと思います。
① 社内制度の整備
取得の仕方・手順をわかりやすく
- 育休の取得方法や手続きの流れを、明文化・見える化することが第一歩です。
- 「どのタイミングで誰に言えばいいのか?」が明確であれば、不安なく申請できます。
- 社内イントラやマニュアルで、図解やQ&A形式にするのが推奨されます。
ポイント
「分割取得はどうするの?」「産後パパ育休との違いは?」など、よくある疑問をあらかじめ解消しておくことで、取得率はぐっと上がります。
② 上司・同僚の理解を促す研修や情報共有
「なんとなく迷惑をかける」という空気をなくす
- 上司が制度を理解していなければ、部下は育休を申し出づらくなります。
- 管理職向けの育休制度研修や成功事例の共有会を定期的に実施することで、上司・同僚の理解が促深まります。
- チーム内でも、「〇〇さんが育休を取る予定です」とオープンに共有・応援できる雰囲気づくりが大切です。
ポイント
育休は「個人の問題」ではなく「組織全体で支えるべきライフイベント」であり、この認識を共有することが重要です。
③ フォロー体制と復職後の安心づくり
休んでも「戻れる」安心感を
- 育休中の情報共有や、復職時の面談制度など、スムーズな職場復帰のサポート体制を整えることはとても重要です。
- チームメンバー間での引継ぎやサポート体制も事前に設計しておきましょう。
- 復職後は、自分のライフスタイルや状況に合わせて柔軟な働き方を選択できると理想的です。
ポイント
「育休を取ったらキャリアが止まる」と思わせない環境を整えることで、安心して制度を利用できるようになります。
企業の取り組みが柔軟取得のカギになる
| やるべきこと | 目的 |
|---|---|
| 制度の整備 | 取得時の不安をなくす |
| 理解の促進 | チーム全体で支える意識づくり |
| フォロー体制 | 安心して戻ってこられる環境 |
これからの時代、人が集まる会社は「人が休める会社」と言っても過言ではありません。それを可能にする制度を整えるのが第一歩です。しかし、せっかく作ったその制度を活かすも殺すも、現場の文化と運用次第です。柔軟な育休取得を当たり前にするには、企業側の積極的な後押しが欠かせません。
育児休業制度は、単なる法律上の義務ではなく、従業員のモチベーションや企業の持続的成長を支える重要なツールです。
柔軟に活用できる制度が整っていれば、従業員はより安心して仕事に取り組むことができ、企業も生産性の向上に繋がります。
私たち社会保険労務士は、企業が育児休業制度を効果的に運用できるようサポートしています。
もし貴社でも「育児休業を取りやすくするためにはどうしたら良いか?」とお悩みであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
共に、より良い職場環境を作り上げていきましょう。
今回で「男性の育児休業取得編」は終了です。
次回からは「介護離職を防ぐ」というテーマで記事を書きます。
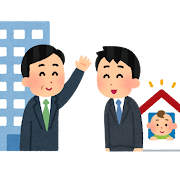
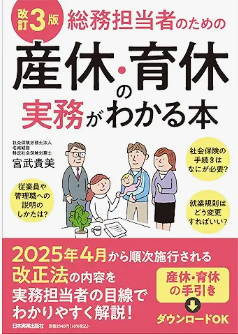
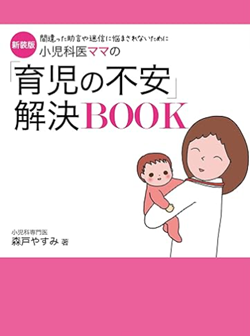
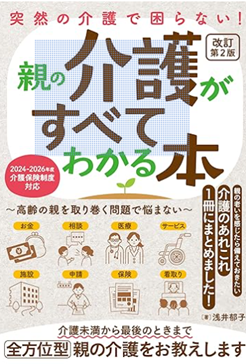


コメント