「仕事と育児・介護の両立、あなたの会社ではどこまで対応できていますか?」
近年、少子高齢化の進行に伴い、仕事と家庭の両立支援がより重要視されています。特に、男性の育児休業取得の促進や、介護離職を防ぐための環境整備は、企業にとって避けて通れない課題となっています。
こうした背景のもと、2025年4月1日、10月1日と段階的に改正育児・介護休業法が施行されることになります。今回の改正では、育児休業・介護休業の柔軟な取得や企業の義務強化など、大きな変更が加えられています。
本記事では、改正のポイントをわかりやすく解説し、企業と従業員にとってどのような影響があるのかを詳しくご紹介します。ぜひ最後までご覧ください!
育児・介護休業法の成立
まずは、育児・介護休業法成立の過程を見てみます。
- 育児・介護休業法の制定前 日本では、1980年代後半から少子化が進行し、共働き世帯の増加に伴い、育児と仕事の両立支援が社会的課題となりました。また、高齢化が進み、介護と仕事の両立も重要な問題として認識されるようになりました。
- 1991年:育児休業法の制定 1991年に「育児休業法」が成立します。この法律では、労働者が1歳未満の子どもを養育するために休業できる制度が初めて法制化されます。ただし、当初は企業に義務付けるものではなく、努力義務でした。
- 1995年:育児・介護休業法へ改正 1995年に法律が改正され、「育児休業法」から「育児・介護休業法」へ名称が変更されます。この改正により、介護休業制度が新設され、家族の介護のために休業を取得できるようになりました。
以上のように「育児・介護休業法」が成立し、その後は幾度かの法改正が加えられ、最近では2022年に法改正がされております。
育児休業法成立から30年、積み重ねてきた成果と課題
1991年に「育児休業法」が成立してから30年以上が経過してます。この間、日本の労働環境や社会の価値観は大きく変化し、育児と仕事の両立を支援する制度も段階的に整備されてきています。
特に、2009年の改正育児・介護休業法では、育児休業の対象範囲が広がり、父母ともに育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」制度が導入され、その後も、2021年の改正では「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されるなど、男性の育児参加を促す仕組みが強化されています。
こうした法整備の積み重ねにより、男性の育休取得率1996年の0.12%から、2023年には30.1%まで上昇し、女性の育休取得率も高い水準を維持しています。また、企業の意識改革も進み、育児支援制度を充実させる企業が増加しました。
しかしながら、依然として男性の育休取得率は政府目標(2025年50%)には届かず、企業によっては制度が整っていても利用しづらい現状もあります。今回の2025年改正では、育休取得をより促進するための義務が強化され、柔軟な働き方の選択肢も拡充される予定です。
一方で介護休業法に関してはどうでしょうか?
1995年に成立した「介護休業法」は、仕事と介護の両立を支援するための第一歩として重要な役割を果たしてきました。
この法律の施行により、従業員が一定期間仕事を離れて介護に専念できる制度が整備され、介護離職の防止に寄与しました。2009年の改正では、介護休業の分割取得が可能となり、2016年の改正では介護のための短時間勤務制度が拡充されるなど、働きながら介護を続ける選択肢が広がりました。
その結果、介護離職者数は一時的に減少傾向を見せ、企業の介護支援策も徐々に進展しました。しかし、依然として年間約10万人が介護離職しており、制度があっても「利用しづらい」職場環境が課題となっています。
育児休業法の成立から30年が経ち、一定の成果を上げてきたものの、真のワークライフバランス実現に向けて、さらなる制度の充実と職場文化の変革が求められています。
2025年4月・10月の育児・介護休業法改正の狙いとは?
今回の法改正は、単なる制度の拡充ではなく、育児・介護と仕事の両立をより現実的なものとし、少子化対策や労働力確保につなげることを目的としています。その狙いを大きく4つに分けると以下のようになります。
- 男性の育児休業取得を促進し、育児の負担を分散
- 介護離職を防ぎ、経験豊富な労働力の確保
- 仕事と家庭を両立しやすい柔軟な働き方の実現
- 企業の対応格差を是正し、育児・介護支援を当たり前に
2025年の改正育児・介護休業法は、これまでの流れをより強化し、実効性を高めることが目的です。これまでの法律でも、育児や介護を支援するための基本的な枠組みは整備されていましたが、実際には制度の利用がしづらかったり、企業の対応にばらつきがあったりしました。今回の改正法では、これらの課題を解決し、特に男性の育児休業取得促進や介護離職の防止に向けた措置が強化され、柔軟な働き方の推進が進みます。つまり、従来の支援策をさらに実効性のあるものにし、仕事と家庭を両立しやすい環境を提供するという点で、より一層強化された形となっています。
次回の記事から上記の4つの狙いについて深堀していきます。

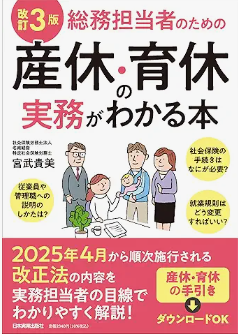

コメント