計画を立てる
資格試験の勉強法について書かれた記事等を読むと、たいてい「まずは学習計画を立てましょう」っていうアドバイスが出てきますよね。確かにその通りだと思うんですが、最初からカチッとしたスケジュールを組むと、スケジュール通りにいかなかったときのダメージが気になります。
そこで私は、「この時期までにここまでは終わらせる」みたいな大まかな目安を決めようと思いました。
社労士試験に合格するには、よく「トータルで1000時間の勉強が必要」と言われています。私が本格的に勉強を始めたのは年明けの1月。試験本番の8月までは、ざっくり8か月弱。じゃあ1000時間ってどうやって確保するのか?と、まずは計算してみました。
1000時間を8か月で割ると、1か月あたり約125時間。これを日割りにすると、1日あたり4時間ちょっと。うーん、こうして見るとなかなかのボリュームですよね…。
でも、ちょっと工夫すれば現実的かも?と思い直して、週休2日として考えてみました。私は水曜日・日曜日が休みなのでそれぞれ10時間ずつ勉強すれば、この2日だけで20時間。残りの平日5日であと8時間を割ると、1日あたり約1時間半強。これならなんとかいけそうかな?と、最初はそんな感じで計画を立てていました。
まぁ、こうしてみると若干「捕らぬ狸の皮算用」感は否めませんが(笑)、とりあえず「勉強時間」の面ではこんな感じでやっていこう、という目処は立ちました(というか、強引に立てました)。
次に考えるべきは、「じゃあ具体的に、どうやって進めていくか?」というところですよね。時間は確保できても、やり方がズレていたら意味がない。そんなわけで、ここからは勉強の進め方についても、少しずつ形を整えていくことにしました。
前回のブログにも書いた通り、いきなり問題集に取りかかるのはちょっと無理があるな…と感じたので、他の人はどうしてるんだろう?と、ネットでいろいろ調べてみました。
その中でよく見かけたのが、「勉強期間を3つに分けて考える」という方法。
いわゆる「インプット期」「アウトプット期」「直前の総仕上げ期」といった流れです。
確かに、まずはテキストをひと通り読まないと、土台ができないよなと納得。さらに情報を集めてみると、
・4月くらいまではインプット中心(テキストを読む・理解する)
・5月〜6月はアウトプット期(問題演習で問題を解きまくる)
・7月〜8月は全科目を横断しながら総仕上げ(総復習・苦手克服)
という流れが王道パターンのようです。
いずれにしても購入したテキストの読み込みから入ります。
一発合格
当時の私は49歳。その時の心境をひと言で表すと、「一発で合格したい」というものでした。
もちろん、受験生であれば誰しもそう考えるとは思いますが、私の場合、もう何か月後かに50代突入、しかもつい先日大病を患ったばかり、いつ死ぬかわからない、という事情もあったので、「1回落ちても来年また」というイメージは正直、あまり持てませんでした。
実のところ、最初に学習計画を立てた段階では、そこまで強く「一発で」という意識はなかったのですが、以前のブログでも触れたとおり、2020年3月の年度末の「係長⇒主任」降格事件があった後は強烈に「一発合格」を意識しました。
この出来事をきっかけに、「合格すれば、これまで一度も考えたこともなかった違った未来があるのではないか」という思いや、50代に入る前に病気をしたことで、「自分の人生は、それほど多くの時間は残されていないのではないか」という感覚が芽生え、一撃で突破したいという気持ちが強くなっていきました。
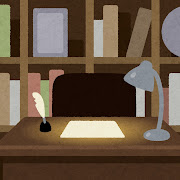
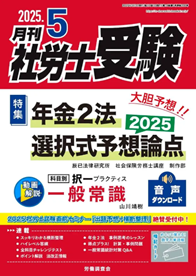



コメント